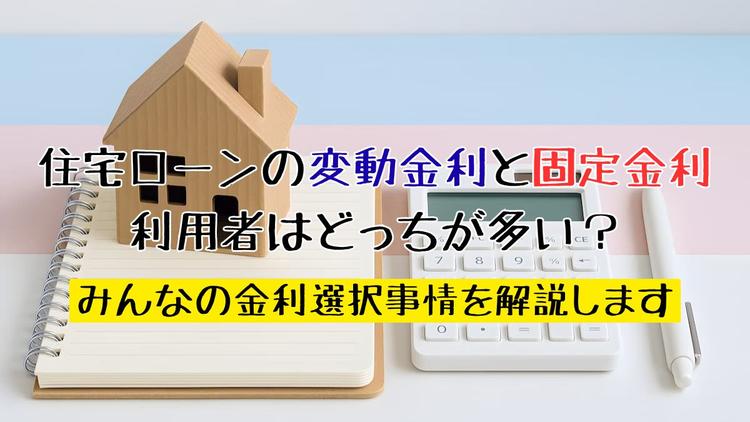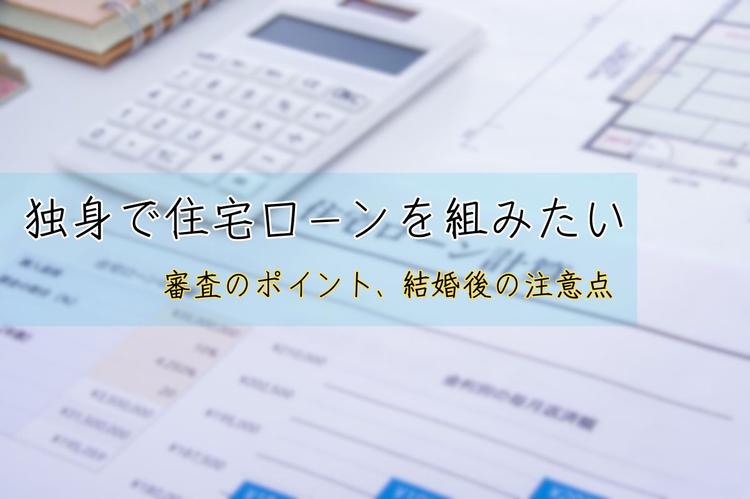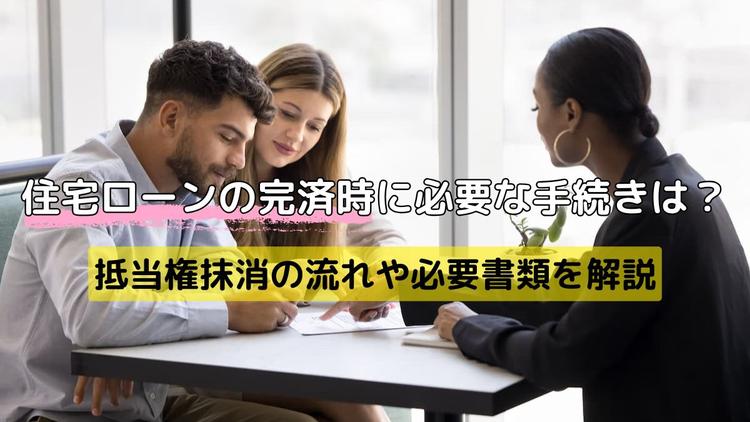「住宅ローンは変動金利と固定金利どっちがいいだろうか?」
そのようなお悩みを抱えている方もいるでしょう。
変動金利には金利の安さ、固定金利には金利上昇リスクを避けられるという魅力があります。
しかし、どちらにもデメリットはあり、返済の負担にも大きく関わってくるので、自分に合ったタイプを選ぶことが重要です。
とはいえ、他の人がどちらを利用しているかは気になるところでしょう。
この記事では、変動金利と固定金利のどちらが多いかやそれぞれのメリット、デメリットについて分かりやすく解説します。
住宅ローンは変動金利と固定金利どっちが多い?
住宅ローンの金利タイプは、大きく「変動型」と「固定型」の2種類に分かれます。
変動型とは、借入後定期的に金利が変動するタイプです。
一方、固定型は借り入れ当初で金利が決まり、返済期間中変動しないタイプをいいます。
まずは、住宅ローン利用者はどちらのタイプを選んでいるのかをみていきましょう。
変動金利が断続的に増えている
国土交通省の調査による金利タイプ別割合では、全期間固定型+証券化ローン(フラット35等)が6.1%に対し、変動金利型が84.3%と変動型が多ことが分かります。
さらに、変動型は令和1年度が63.1%に対して令和5年度が84.3%と年々上昇傾向にあります。
また、住宅金融支援機構の「住宅ローン利用者実態調査(2024年10月調査)」 においても、変動型が77.4%に対し全期間固定型が9.0%です。
このことから、住宅ローンを利用する多くの人が変動型を選んでいることが分かります。
固定期間選択型金利・全期間固定金利共に縮小傾向
固定期間選択型金利とは、当初から5年や10年といった一定期間が固定期間となる金利タイプをいいます。
固定期間終了後は固定型か変動型を選��べるのが一般的です。
前述した国土交通省の調査によると、全期間固定金利は令和1年度が4.6%に対し、令和5年度で2.1%に減少しています。
固定期間選択型についても、令和元年度が19.9%、令和5年度が9.0%と減少傾向です。
変動型の利用割合が年々上昇しているのに対し、固定期間選択型、全期間固定金利は年々減少傾向にあることが分かります。
住宅ローンで変動金利を選ぶメリット・デメリット
ここでは、変動金利のメリット・デメリットをみていきましょう。
メリット
メリットとしては、以下が挙げられます。
- 金利が安い
- 金利が下がれば返済の負担が軽減できる
変動金利の大きなメリットが、他の金利タイプと比べて最も金利が安いという点です。
全期間固定金利タイプであるフラット35の2025年7月最頻金利は1.840%であるのに対し、変動金利は0.5~1.0%前後で推移しています。
2025年7月の主要銀行の変動金利は以下のとおりです。
| みずほ銀行 | 0.525% |
| 三菱UFJ銀行 | 0.595%~ |
| 三井住友銀行 | 0.595%~ |
| りそな銀行 | 0.640%~ |
| auじぶん銀行 | 0.834% |
| 住信SBIネット銀行 | 0.698%~ |
| SBI新生銀行 | 0.590%~ |
| 楽天銀行 | 1.005~1.655% |
| ソニー銀行 | 0.897% |
住宅ローンは長期間返済するため、金利が1.0%変わるだけでも返済総額が大きく異なります。
たとえば、3,000万円を35年で借りる場合 、金利0.5%と1.5%では返済額が以下のように変わってきます。
| 金利0.5% | 金利1.5% | |
| 毎月の返済額 | 77,875円 | 91,855円 |
| 返済総額 | 32,707,500円 | 38,579,100 円 |
金利が最も低い変動金利であれば、返済の負担を大きく軽減できる可能性があるでしょう。
また、金利見直しのタイミングで金利下がれば、返済をより軽減できる可能性がある点もメリットといえます。
デメリット
デメリットとしては、以下が挙げられます。
- 金利上昇リスクがある
- 返済計画を立てにくい
変動金利は、一般的に4月と10月の半年ごとに金利が見直されます。
このタイミングで金利が下がれば返済の負担が軽減できる反面、金利が上がると返済の負担が大きくなる可能性もあるので注意が必要です。
しかし、変動金利は5年ルール・125%ルールが設けられているので、いきなり返済額が大きく増えることはありません。
- 5年ルール:5年間は返済額が変わらない
- 125%ルール:返済額が変わる場合でも前回の返済額の125%以上には上がらない
ただし、返済額は変わらなくても返済額に占める元本と利息の内訳が変動しているため、元本の減りが悪くなり返済総額が上がる可能性がある点には注意しましょう。
また、5年ルール・125%ルールが必ず適用されるわけではないので、契約時に適用されるかの確認が必要です。
変動金利は定期的に金利が見直されるので、将来の返済額が当初の見込みと変わっている可能性があります。
将来の返済額が正確に分からないので、長期的な返済計画が立てにくい点にも注意しましょう。
住宅ローンで固定金利を選ぶメリット・デメリット
次に、固定金利のメリット・デメリットをみていきましょう。
メリット
固定金利のメリットとしては、以下が挙げられます。
- 金利上昇リスクを避けられる
- 返済計画を立てやすい
固定金利は、契約時に金利が決めれば返済期間に金利が変動することはありません。
たとえ、金利が上昇しても影響を受けないので、金利上昇リスクを気にしなくていいのは大きなメリットといえるでしょう。
将来の金利がいくらになっているかは正確に見通すことはできません。
そのため、変動金利では定期的な金利チェックや金利上昇リスクに備えた対策が必要です。
その点、固定金利であれば小まめな金利チェックや対策を講じる必要はないので、金利の変動を心配したくないという人に適しています。
また、借入当初で最終返済までの返済額も決まります。
返済額が変動することがないので、長期的な返済計画を明確に立てられるのもメリットといえます。
デメリット
デメリットとしては以下が挙げられます。
- 金利が高い
- 金利が下がっても恩恵を受けられない
前述のとおり、固定金利は変動金利に比べ1.0%以上高いのが一般的です。
そのため、金利が上昇しないのであれば変動金利よりも毎月の返済額・返済総額は大きくなります。
仮に、固定金利の金利が下がってもすでに返済中であれば金利が下がることはなく、�返済の負担を軽減することもできません。
固定金利は金利上昇局面ではメリットがありますが、金利が変わらないもしくは下降局面ではデメリットが大きい点には注意しましょう。
変動金利を選ぶ人が多い理由は?
変動金利を選ぶ人が多い理由には、以下の3つが考えられます。
- 金利が低いから
- フラット35と比べて手数料などを抑えて利用できるケースが多いから
- 金利が上昇しても返済額の上昇は一定に抑えられるルールがあるから
それぞれ見ていきましょう。
金利が低いから
変動金利の大きな魅力が金利の低さです。
2025年8月現在は、変動金利であれば0.6%程度から借り入れできるのに対して、フラット35の全期間固定金利は1.8%程度の水準です。
例えば、3,000万円を35年返済で借り入れる場合、金利0.6%(変動金利)と1.8%(固定金利)では、月々の返済額と総返済額に以下のような差が生じます。
| 金利 | 月々の返済額 (元利均等) | 総返済額 | 金利総負担額 |
| 0.6%(変動) | 約79,300円 | 約3,333万円 | 約333万円 |
| 1.8%(固定) | 約91,600円 | 約3,856万円 | 約856万円 |
金利の低さは返済総額や毎月の返済額の負担軽減につながるため、金利の低い住宅ローンを選ぶ人は多い傾向にあります。
住宅金融支援機構の「住宅ローン利用者実態調査(2024年10月調査)」 を見ても、変動金利の住宅ローンを選んだ理由は「金利の低さ」が62.6%と最も多くなります。
フラット35と比べて手数料などを抑えて利用できるケースが多いから
フラット35では借入時に以下のような手数料が必要です。
- 融資手数料
- 印紙税
- 火災保険料
- 物件検査手数料
たとえば、融資手数料は定額型と定率型に分かれ、定額型では3~5万円、定率型で借入額の1~2%が目安です。
仮に、定率型2%で3,000万円借り入れる場合、融資手数料として60万円かかります。
また、フラット35では住宅金融支援機構の定める技術基準(住宅の品質)を満たすことが必要となり、そのための物件検査が必須となります。
物件検査費用は検査機関によっても異なりますが、5~10万円が目安です。
融資手数料は変動金利でもかかりますが、物件検査費用はかからないケースが多いため、手間や費用を避けて変動金利を選ぶケースも多いと考えられるでしょう。
金利が上昇しても返済額の上昇は一定に抑えられるルールがあるから
変動金利では5年ルール・125%ルールがあります。
たとえば、金利が上昇しても今の返済額が5年間据え置かれ、上がる場合でも上限は125%にとどまります。
金利�が上昇しても急激に返済額が上がる心配がないことも選びやすい理由と言えるでしょう。
ただし、先述したように返済額が変わらなくても内訳は変わります。
金利上昇幅によっては返済額に占める利息部分が多くなり、元本が減らない・返済期間が終了しても未払利息が残るリスクがある点には注意が必要です。
変動金利では返済額自体は変わらなくても、内訳が変わっていないか・返済計画が変わっていないかまでチェックする必要があります。
変動金利の今後の見通しは?
変動金利を選ぶかどうかは、今度の金利の見通しも重要なポイントです。
ここでは、今後の変動金利についてみていきましょう。
利上げにより変動金利は上昇傾向
変動金利は政策金利の影響を受けます。
基本的に政策金利が上がると変動金利が上がり、政策金利が下がると変動金利も下がるというように連動しているのです。
マイナス金利政策以降低い水準を維持していた変動金利ですが、2024年のマイナス金利政策解除以降上昇傾向がみられます。
日銀は2024年3月にマイナス金利政策を解除して以降、同年7月、2025年1月に利上げを実施しています。
それを受け、2024年10月、2025年4月に変動金利の基準金利を引き上げた金融機関も多くあったのです。
今後も変動金利が上昇する可能性がある
2025年6月の金融政策決定会合では、さらなる利上げは見送られました。
�しかし、世界的なインフレや円安状況によっては追加利上げが行われる可能性は十分あります。
追加利上げが行われると変動金利に影響が出る可能性もあるので、今後の政策金利や変動金利の動向には注視しておきましょう。
変動金利が上がるときにはすでに固定金利が高くなっているケースが多い点に注意
「変動金利が固定金利より高くなったら、固定金利に借り換えればいい」そう思っている方もいるでしょう。
しかし、一般的に固定金利は変動金利よりも先に上がると言われており、変動金利が上がる事には固定金利が上がっている可能性があります。
実際、令和1年4月1.270~1.960%に対し、令和5年4月は1.760~3.070% と上昇傾向です1。
そのため、変動金利が上がったら固定金利に借り換えという対策はおすすめできません。
変動金利を検討する場合は、繰り上げ返済や一括返済用の資金を貯えておくなど、別の対策を講じておくとよいでしょう。
ただし、今度の金利がどうなるかの見通しは正確にできません。
変動金利が引き続き低い水準で推移する、固定金利以上に上昇しないのであれば、もっともお得な選択肢であるのも事実です。
とはいえ、どの金利タイプが自分に適しているかは個人の状況や返済スタイルの希望などによって異なります。
まずは、不動産会社やFPなどのプロに相談しながら検討することをおすすめします。
▼関連記事:住宅ローンの変動金利は一気に上がる?
まとめ
住宅ローンの変動金利は金利の低さという魅力から、利用者の8割以上が選んでおり利用割合も上昇傾向にあります。
ただし、変動金利には金利上昇リスクがあるため、選ぶ際には金利上昇リスク対策も欠かせません。
反対に、固定金利は金利上昇リスクの心配はありませんが、金利が高いというデメリットがあります。
どのタイプが適しているかは個々の状況によって異なるので、長期的なシミュレーションを踏まえプロに相談しながら自分にぴったりのタイプを選ぶようにしましょう。