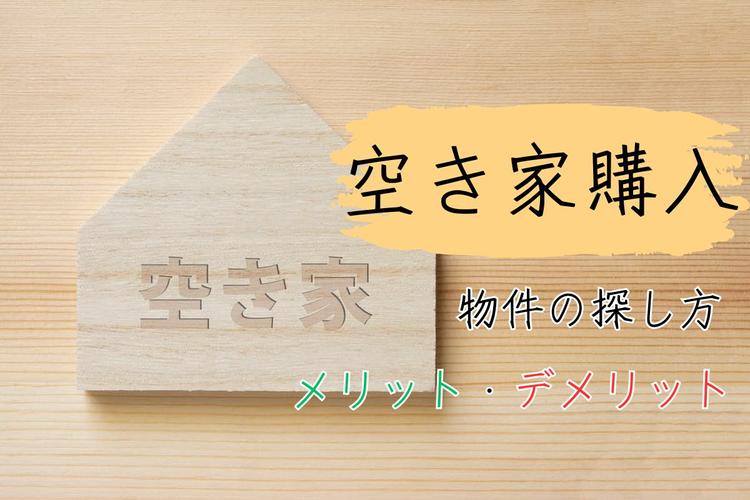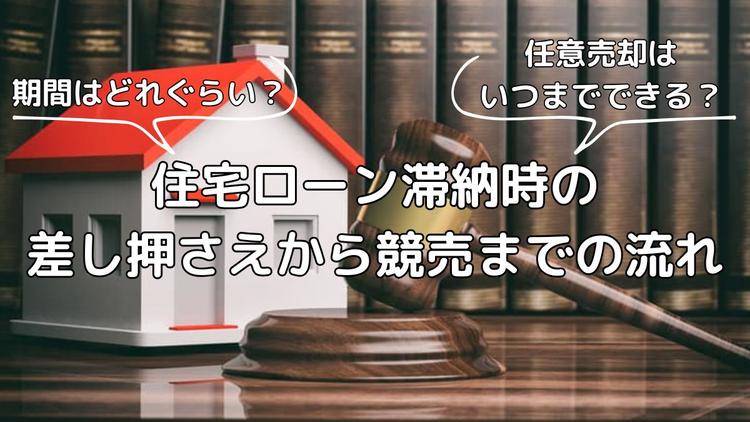住宅ローンについて調べていると「優遇金利」という言葉を目にする機会が多いのではないでしょうか。
一見すると金利の面で何らかのメリットが得られる制度のように見えますが、詳しく知らない人も多いはずです。
そこで当記事では、住宅ローンで利用できる優遇金利の仕組みや、適用される条件、利用する際の注意点について初心者にも分かりやすく解説します。
住宅ローンの優遇金利とは?
住宅ローンを検討していると、頻繁に目にすることになる「優遇金利」。どのような意味があるのかは分からなくても、なんとなく利用者にメリットがあるように思えますよね。
しかし、なにを優遇してもらえるのか、仕組みや内容を知らないまま利用することに不安を感じる人もいるはずです。
その不安を取り除くために、以下では優遇金利の仕組みや店頭金利・適用金利との違いについて詳しく解説します。
優遇金利の基本と仕組み
住宅ローンについて調べていると「優遇金利」のほかに「店頭金利」や「適用金利」といった言葉が並ぶため、混乱する人も多いはずです。
優遇金利を解説するうえで、まず店頭金利と適用金利について理解しておきましょう。
店頭金利とは、金融機関が提示している金利で「基準金利」とも言われています。店頭金利は商品などで言う所の「定価」のようなものです。
一方、実際に住宅ローンを借りる時には、店頭金利から一定の割引が適用されます。この割引分のことを「優遇幅」と呼びます。
つまり、優遇金利、店頭金利、適用金利は次のような関係になります。
例えば、店頭金利が2.4%、優遇幅が1.5%の場合、実際に適用される優遇金利(適用金利)は0.9%になります。
例えば、以下の条件で住宅ローンを借りたとしましょう。
- 借入金額:3,000万円
- 返済期間:35年
- 店頭金利:2.4%
- 優遇幅:1.5%
- 優遇金利(適用金利):0.9%
この条件で住宅ローンを借りた場合、優遇ありとなしでは月々の返済で2万円以上、ローンを35年返済し続けると約900万円近い差が生じます。
優遇金利の種類
住宅ローンの優遇金利には「当初期間優遇」と「全期間優遇」の2つの種類があります。
当初期間優遇は、住宅ローンを借りた直後から一定期間だけ、店頭金利から割り引かれた金利が適用されるタイプです。
住宅ローンの返済を始めた当初の負担を抑えたい人にピッタリです。しかし、優遇期間が終了した後は金利が上昇するため注意が必要です。
一方の全期間優遇は、住宅ローンの借入期間中、一定の優遇幅がずっと適用されるタイプです。
優遇金利が適用される条件
住宅ローンの優遇金利を受けるためには、金融機関が定める条件を満たす必要があります。
条件は各金融機関によって異なりますが、住宅ローンを借り入れる金融機関の口座を開設し、次のような取引を行うことが求められます。
- 毎月の給与が振り込まれるように指定する
- 公共料金やクレジットカードの引き落とし口座に指定する
- 定期預金や投資信託などの金融商品を一定金額以上保有する
- 勤務先、年収、勤続年数、信用情報などに問題がない
これらはあくまで一例で、条件は金融機関によって異なります。優遇金利を受けられる条件を詳しく知りたい場合は、事前に各金融機関に確認しておきましょう。
優遇金利は場合によって取�り消される
住宅ローンで優遇金利を利用する際に、特に気をつけたいのが優遇金利の取り消しです。優遇金利は一度適用されたらずっと続くと思われがちです。しかし、実際には取り消しになるケースもあるのです。
優遇金利が取り消される主な理由は次の通りです。
- 優遇金利の適用条件を満たしていない
- 住宅ローンの返済を遅延・延滞した
- 住宅ローンの契約内容を変更した
- 金融機関側の方針変更による見直し
例えば、給与振込や公共料金の引き落とし口座を、住宅ローンを組む金融機関で作ることで優遇金利が適用されるのが一般的です。
それなのに、口座を解約して他行に変更するなどした場合、優遇条件を満たしていないとして金利を元に戻されることがあります。
また、住宅ローンの返済を延滞した場合も、優遇金利が打ち切られる可能性があります。金融機関によっては、1回でも延滞・遅延をしただけで取り消される場合もあるため注意しましょう。
金利は少しでも上がると総返済額に大きく影響します。借入期間によっては総返済額が100万円単位で増えてしまう恐れもあります。
優遇金利を長く活用するためにも、契約時に提示された適用条件をしっかり把握しておきましょう。同時に、優遇金利が取り消される条件についても金融機関に確認しておくことをお勧めします。
優遇金利を上手に利用するポイント
住宅ローンの優遇金利を上手に利用する��ためには、金利の低さだけで選ぶのはNGです。
なぜなら優遇金利は大きいと宣伝しているのに、その条件を維持するのが難しかったり、手数料や保険料などが高額なケースもあるからです。
そこで以下では、優遇金利を上手に活用するために押さえておきたい具体的なポイントを詳しく解説します。
複数の金融機関の優遇金利を比較する
「優遇金利はどの銀行も同じでしょ?」と考えがちですが、各金融機関ごとに優遇金利を受けられる条件や内容は異なります。
例えば、金利が0.1%違うだけでも、借入の期間や金額次第で数十万円以上もの差が生じることも珍しくありません。
住宅ローンの返済が楽になるかは、優遇金利を上手に活用できるかがカギになります。無理なく安定した返済を続けるためにも、複数の金融機関の優遇金利を比較しましょう。
各金融機関の金利等を比較したい場合は「モゲチェック(PR)」が便利です。
条件を維持し続けられるかを検討する
優遇金利を受けるには「給与振込口座の指定」「カードローンの契約」「定期預金を一定額預け入れる」など、金融機関で定めている条件を満たす必要があります。
さらに優遇を受けた後は、その状態を維持しなければいけません。例えば、給与振込を途中で他行に変更した場合、金利優遇がなくなり金利が上がる恐れもあります。
こういったリスクを避けるために、優遇条件を長期間維持することができるかを慎重に検討しましょう。
もし、生活環境の変化などで維持が難しいと感じたら、他の金融機関の優遇制度を利用することをお勧めします。
金利優遇の期間や終了後の金利を確認する
優遇金利には「当初期間優遇」と「全期間優遇」の2種類があります。全期間優遇であれば、住宅ローンを完済するまで低金利を維持することは難しくありません。
しかし、当初期間優遇のように、住宅ローンを契約して数年間のみ金利を優遇するタイプでは、期間が過ぎると金利が上昇するリスクがあります。
優遇期間が過ぎた後に住宅ローンの返済が困難にならないように、期間終了後にどれだけ金利が上がるのかを事前にチェックしておきましょう。
トータルコストで判断する
住宅ローンを選ぶ際、ついつい金利だけに目が行きがちです。しかし、金利以外にも「事務手数料」「保証料」「保険料」といった諸費用もかかることを忘れてはいけません。
いくら金利が低くても、諸費用が高額であれば総支払額が予想以上に高くなることがあります。
逆に、金利が若干高くても諸費用が低ければ、トータルコストが抑えられるケースもあるのです。
金利が低い住宅ローンを選ぶのは大事なことです。しかし、金利だけで判断せず、総返済額や諸費用を含めたトータルコストで金融機関を比較することで、結果として返済が楽になることもあります。
▼関連記事:住宅ローンの利用でかかる諸費用を解説
定期的な繰上返済を検討する
せっかく優遇金利を活用して低金利で住宅ローンを組めたとしても、返済が長期にわたれば返済額も大きくなるものです。
そこで、優遇金利を上手に活用するために繰上返済を検討しましょう。繰上返済とは、毎月の返済とは別に、余剰資金を使ってローンの一部または全額を返済する方法をいいます。
定期的に繰上返済を行うことで返済期間が短縮、または元金が減るスピードが早くなるため、結果として総返済額を軽減することができます。
ただし、金融機関やローン商品によっては繰上返済時に手数料がかかるケースもあります。
無駄な出費を省くためにも、手数料がかからず少額からでも繰上返済ができるローン商品を選ぶようにしましょう。
借り換えで金利の見直しを視野に入れる
「住宅ローンは一度組んだら返済を続けるだけ」と考える人は少なくありません。しかし、金利が現在よりも低いローン商品があるなら、そちらに借り換えることで総返済額を減らすことができます。
当初期間優遇の場合、期間が終了すると金利は上昇します。そのままでは高い金利の状態で返済を続けなければいけません。
そこで、期間が終わるタイミングで他の金融機関をチェックして、今よりも良い条件のローン商品を探しましょう。
借り換えを検討して条件が良い金融機関に乗り換えることで、総返済額を大きく抑えることもできます。
優遇金利を受ける際の注意点
住宅ローンの優遇金利は、利用者にとって多くのメリットがあります。しかし、内容を理解しないまま契約すると、思わぬトラブルが生じる恐れもあります
後々になって後悔しないためにも、適用条件や優遇の仕組みをしっかりと理解して、失敗の原因となる注意点を押さえておきましょう。
以下では、優遇金��利を利用する際に特に注意したいポイントを解説します。
優遇金利は場合によって取り消される
優遇金利は、各金融機関で設定している一定の条件を満たすことで適用されます。代表的な条件として、給与振込口座の設定、公共料金やクレジットカード利用代金の引き落とし、インターネットバンキングの利用などがあります。
しかし、優遇金利は一度適用されればずっと適用されるわけではありません。
例えば、住宅ローンの返済中に延滞したり、金融機関からの催促を無視していると、優遇金利が取り消されて金利が引き上げられてしまうことがあるのです。
審査の結果次第では引き下げ幅が小さくなる
優遇金利は誰にでも同じように適用されるわけではない点に注意してください。金融機関の窓口やホームページなどで提示している優遇金利の引き下げ幅は、あくまで参考でしかありません。
実際の引き下げ幅は、申込者の審査結果によって決まります。例えば年収が少ない、勤続年数が短い、他に借り入れがあるなど、返済能力に不安要素があると判断された場合は、優遇幅が縮小されることがあります。
反対に、収入が安定している、勤続年数が長い、信用情報に問題がないなど、信用力が高い人ほど金利面などで有利になりやすい傾向にあります。
「ネットで見た時よりも金利が高い!」とならないよう、どの程度優遇してもらえるかを事前に金融機関に確認しましょう。
優遇期間終了後は金利が上昇する
当初期間優遇の住宅ローンは、契約から一定の期間にわたって大幅な金利引き下げが適用されるのが最大の魅力。しかし、この優遇はあくまで期間が決められている点に注意が必要です。
例えば、10年間は年0.6%の優遇金利を受けられるとしましょう。11年目以降は優遇がなくなり、金利が1.5%に引き上がるといったケースがあります。
金利は0.1%増えただけで毎月数千円、総返済額では100万円以上も差が生じることもあるのです。
優遇期間が終了した後に、金利が上がって返済額が高くなると普段の生活にも支障が出かねません。金利の上昇に備えて、借り換えや繰上返済も視野に入れた計画を立てておきましょう。
まとめ
最後までお読みいただきありがとうございます。今回は、住宅ローンで適用される優遇金利について解説しました。
住宅ローンの優遇金利は、金利面で大きなメリットがあります。しかし、優遇金利の仕組みや優遇を受けるための条件を正しく理解しないと、かえって不利になることもあります。
例えば、当初期間優遇は、契約した当初は金利が大幅に引き下げられます。ですが、期間が終了すると金利が上昇するといったデメリットもあります。
金利が僅かでも上昇すると、総返済額が大幅に上がり家計にも多大な影響を与えるでしょう。
また、金利の低さだけで選ぶのではなく、総返済額や諸費用、借り換えや繰上返済のしやすさなどを視野に入れて住宅ローンを選ぶ必要があります。
しかし、住宅ローンは専門的な知識がなければ判断が難しい部分も多々あります。もし、不明点や不安がある場合は、金融機関の担当者に直接相談したり、住宅ローンに詳しいファイナンシャルプランナーからアドバイスをもらいましょう。