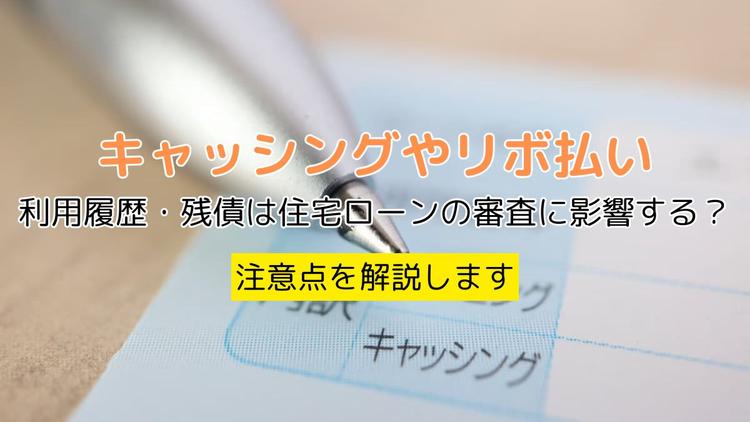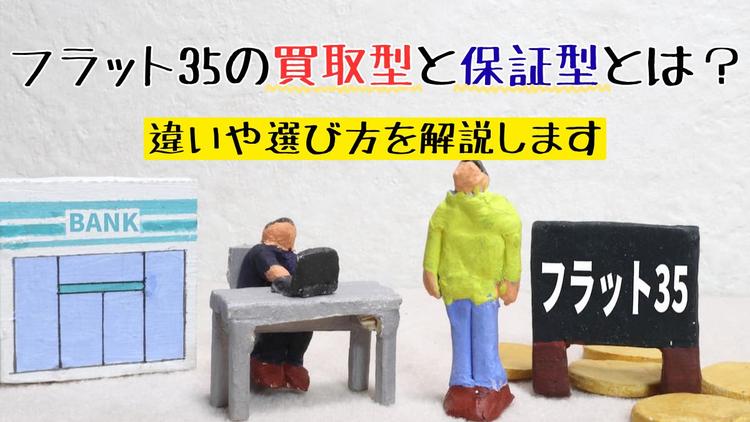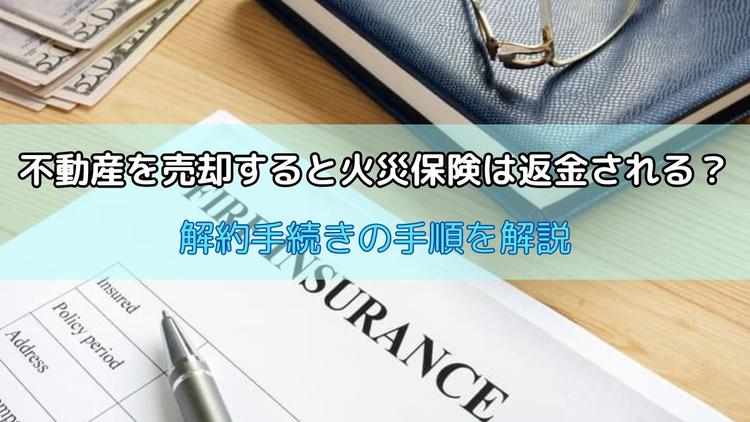火災や地震による災害時は速やかに罹災証明書を取得しましょう。
罹災証明書を取得することで、税金の減免や仮住まいの提供を受けられるため、早急な立て直しが可能となります。
特に、被災直後は住む場所や金銭面で不安になるケースが多いですが、罹災証明書を取得すれば、これらの不安も解消できます。
本記事では、火災による罹災証明書の取得方法や手順、受けられる支援などを詳しく解説します。
火災の被害に遭った方、もしくは災害に備えたい方は、ぜひ参考にしてみてください。
火災に関係する罹災証明とは
罹災証明書とはどのような書類なのか解説します。
罹災証明書が必要になる人や申請方法などを確認しましょう。
- 災害状況を証明する書類
- 罹災証明書の対象者
災害状況を証明する書類
罹災証明書とは、市区町村が発行する公式な書類で、災害状況を証明するための必要な書類です。
具体的には、住宅の損壊度合いや家財の被害状況などが記載され、被害の程度に応じて「全壊」「半壊」などの判定が行われます。
災害状況を証明することで、各種支援や保険金の請求ができるようになります。
罹災証明書の対象者
罹災証明書は、被災した住宅の居住者や所有者が対象です。
具体的には、被災した家屋に住んでいる世帯主や家屋の所有者が該当します。
同じ住所で複数の世帯が暮らしている場合、それぞれの世帯主が個別に申請できます。
また、賃貸住宅の場合でも、居住者である世帯主が申請可能です。
火災や地震による罹災証明書を受け取る手順
火災や地震による罹災証明書を受け取るためには以下の手順で進めます。
- 被害状況を記録する
- 申請書類を準備する
- 管轄の窓口へ申請書を提出する
- 現地調査による認定を受ける
- 罹災証明書が発行される
それぞれの手順を詳しく解説します。
STEP①:被害状況を記録する
被害の程度を証明するために、以下の点を記録しておきましょう。
| 記録方法 | 詳細 |
| 写真撮影 | 被害箇所をさまざまな角度から撮影する 外観だけでなく、内部の損傷も詳細に記録する |
| メモの作成 | 被害を受けた日時、場所、状況を具体的に書き留める |
| リストの作成 | 損傷した物品や設備の一覧を作り、可能であれば購入時期や価格も記載する |
これらの記録は、罹災証明書の申請時や保険金の請求時に役立ちます。
特に写真は、被害の程度を客観的に示す証拠となるため、できるだけ多く撮影しておきましょう。
被災直後は混乱しがちですが、冷静に対応し、しっかりと記録を残すことが大切です。
STEP②:申請書類を準備する
記録を残したら、次に以下の申請書類を準備しましょう。
| 必要書類 | 詳細 |
| 罹災証明書交付申請書 | 火災→地域の消防署で入手できる 地震→市町村役場で入手できる 氏名、住所、連絡先、建物の所在地、発生日時、被害状況などを記入する |
| 本人確認書類 | 運転免許証やマイナンバーカードなどの身分証明書が必要 代理人が申請する場合は、委任状と代理人の本人確認書類も必要 |
| 被害状況を示す写真 | 被災場所を撮影した写真が必要 |
| 印鑑 | 申請書類に押印が必要な場合があるため |
書類準備に時間がかかる場合もあるため、早めに行動することが大切です。
STEP③:申請書を提出する
申請書類を準備したら、郵送または窓口で申請書を提出します。
火災の場合は消防署、地震等の場合は市町村役場が提出先になりますが、地震によって火災が発生した場合などは役所に提出先を確認するのがよいでしょう。
STEP④:現地調査による認定を受け��る
申請書類を提出した後は、自治体の職員が被災した住まいを訪れ、外観や内部の損傷状況を詳しく確認します。
具体的には、建物の傾き、壁や天井のひび割れ、床の損傷、台所や浴室などの設備の被害状況を調べます。
この調査に基づき、被害の程度が「全壊」「半壊」などと判定され、罹災証明書の内容が決まります。
STEP⑤:罹災証明書が発行される
現地調査による認定を受けると罹災証明書が発行されます。
発行までの期間は、通常は1週間から2週間程度ですが、大規模な災害が起こった際は発行までに時間がかかることもあります。
発行された証明書は、今後の各種手続きで必要となるため、複数枚取得して大切に保管しましょう。
また、被害認定に納得がいかない場合は、再調査を依頼できます。
以上が火災や地震によって家が壊れた際に罹災証明書を取得する流れです。
罹災証明書の申請時のポイント
罹災証明書は、申請前後においていくつかのポイントがあります。
スムーズに申請するためにも、すべてのポイントを理解しておきましょう。
申請前のポイント
罹災証明書を申請する前に以下のポイントを押さえておきましょう。
- 自分で被害状況を撮影しておく
- 必要書類は余裕を持って準備しておく
- 早めの申請を心がける
自分で災害状況を撮影しておく
被災した際、すぐに修復や片付けを行わず、まずは災害状況を撮影しましょう。
災害状況を記録することで、申請時に被害状況を証明できるからです。
建物の外観や室内状況などを�さまざまな角度から撮影し、申請時にまとめて提出します。
必要書類は余裕を持って準備しておく
前述のとおり、罹災証明書を申請するには、いくつかの書類が必要です。
しかし、必要書類を揃えるのには時間がかかる場合があります。
そのため、準備する際はできるだけ余裕を持ったスケジュールで進めることが大切です。
必要書類が不備の場合は申請できないケースもあり、さらに時間がかかってしまうかもしれません。
早めの申請を心がける
申告書の提出後、調査員が現地を確認し、被害の程度を評価します。
その後、罹災証明書が発行されますが、発行までに時間がかかる場合があります。
特に大規模な災害時には、1ヶ月以上要するケースもあるため、早めの申請が重要です。
また、申請期限が設けられている場合もあるため、被災後は速やかに手続きを進めましょう。
申請後のポイント
罹災証明書を申請した後は以下のポイントを押さえて行動しましょう。
- 税金の減免申請ができないか確認する
- 仮住まいの手配をする
- リフォームや修繕の見積もりを取る
税金の減免申請ができないか確認する
火災や自然災害による被害を受けた場合、所得税や固定資産税などの減免措置を受けられる場合があります。
建物を所有している場合、本来であれば固定資産税を支払う必要がありますが、被災した場合は税額が少なくなったり、場合によっては免除されたりするケースもあります。
税金の減免については、国税庁「災害減免法による所得税の軽減免除」を参考にしたり、お住まいの市区町村の税務担当部署に問い合わせたりしてください。
仮住まいの手配をする
被災した家に住み続けるのが難しい場合、早急に新しい住まいを確保する必要があります。
まず、自治体の公営住宅や民間の賃貸物件を検討しましょう。
自治体によっては、罹災証明書を提示することで公営住宅への入居が優先される場合があります。
また、火災保険や地震保険に加入している場合、保険金の一部で仮住まいの費用を賄えることもあります。
保険会社に連絡し、適用範囲を確認しましょう。
さらに、家族や知人の協力を得て、一時的な住まいを提供してもらうのも一つの方法です。
リフォームや修繕の見積もりを取る
被災した建物に住むのが難しい場合はリフォームや修繕が必要です。
これらを行う場合、まずは信頼できるリフォーム業者を選び、被害状況を詳しく伝えて見積もりを依頼しましょう。
この際、複数の業者から見積もりを取ることで費用や工事内容を比較し、最適な選択ができます。
また、火災保険を利用する場合、保険会社に見積もり内容を提出し、適用範囲や補償額を確認しましょう。
罹災証明書を取得した後に受けられる支援
罹災証明書を取得すると、以下の支援を受けられる場合があります。
- 税金の減税
- ごみ処理費用の減免
- 災害援護資金の貸付
- 仮設住宅の提供
- 保険金の請求
それぞれの支援を理解して、被災後の生活に役立てましょう。
税金の減税
罹災証明書を取得した後、所得税の減免措置を受けられる場合があります。
具体的には、「災害減免法」に基づき、被災した年の所得税が軽減または免除される制度です。
所得税については災害減免法により、被害額が住宅や家財の価値の2分の1以上で、かつその年の所得金額が1,000万円以下の場合、所得税の軽減や免除が適用されます。
具体的には、所得金額が500万円以下の場合は所得税が全額免除、500万円超〜750万円以下の場合は半額免除、750万円超〜1,000万円以下の場合は4分の1が免除されます。
この減免を受けるためには、確定申告書に被害の状況や損害金額を記載し�、所轄の税務署に提出する必要があります。
詳しくは国税庁「災害減免法による所得税の軽減免除」をご覧ください。
ごみ処理費用の減免
火災や自然災害によって発生した一般廃棄物を市の廃棄物処理施設に搬入する際、処理手数料が免除される場合があります。
例えば、横浜市では、火災により生じた一般廃棄物を市の廃棄物処理施設に搬入する場合、1キログラムあたり13円の処理手数料が免除されます1。
この減免制度を利用するためには、被害を受けた場所の行政区の資源循環局収集事務所などへの事前申請が必要です。
申請時には、罹災証明書の提出が求められます。また、申請は被災後90日以内に行う必要がある場合もあります。
災害援護資金の貸付
災害援護資金の貸付とは、災害で負傷したり住居や家財に被害を受けたりした方が対象となる制度です。
貸付金額は最大で350万円で、被害の程度に応じて異なります。
例えば、住居が全壊した場��合は250万円、半壊の場合は170万円が上限となります。また、世帯主が1ヶ月以上の負傷を負った場合は150万円が上限です。
さらに、家財の3分の1以上の損害を受けた場合も150万円が上限となります。これらの条件が重なる場合、合計で最大350万円までの貸付が可能です。
申請期限は災害発生から3ヶ月以内とされていますが、自治体によって異なる場合があるため、早めの確認と手続きが重要です。
詳しくは厚生労働省「災害弔慰金・災害援護資金などの支援について」をご覧ください。
仮設住宅の提供
仮設住宅は、災害で住まいを失った方々に一時的な住居を提供する制度です。
自治体が民間の賃貸住宅を借り上げて提供する場合や新たに建設される場合があります。
入居を希望する際は罹災証明書を持参し、お住まいの市区町村に申請します。
詳しくは、内閣府防災情報「被災者の住まいに関する現行制度」をご覧ください。
保険金の請求
火災や地震で保険金を請求するには、ご自身が加入している火災保険・地震保険の契約内容を確認し、補償範囲や請求手続きの詳細を把握しましょう。
次に、保険会社に連絡して被害状況を伝えます。この際に罹災証明書が必要となる場合が多いので、事前に用意しておくとスムーズです。
保険会社からは、被害の程度を確認するために調査員が派遣される場合があります。
調査結果と罹災証明書の内容をもとに、保険金の支払額が決定されます。
手続きの際は、被害の写真や修理の見積書など、必要な書類を揃えておくとよいでしょう。
罹災証明に関するよくある質問
罹災証明に関するよくある質問をご紹介します。
罹災証明書の書き方は?
罹災証明書を貰う際の申告書には以下の内容を記入しましょう。
- 被災者の氏名
- 住所
- 連絡先
- 被害を受けた場所の詳細
- 被害の程度
- 火災発生日時
- 被害状況
これらをできるだけ具体的に記入します。
記入例は、東京消防庁「り災申告書」のページ内からダウンロードできるので参考にしてみましょう。
罹災証明書に申請期限はありますか?
罹災証明書の申請期限は自治体によって異なりますが、一般的に災害発生から1ヶ月以内、3ヶ月以内、6ヶ月以内などと設定されています。
申請期限を過ぎると証明書の発行が受けられない場合があるため、早めの手続きが重要です。
また、罹災証明書の有効期限も存在し、保険金請求や各種支援を受ける際に、3ヶ月以内に取得したものが求められることが多いです。
どの程度の火災で申請が通りますか?
罹災証明書の申請が通るかどうかは、被害の程度によって異なります。
具体的には、建物の損壊状況が「全焼」「半焼」「部分焼」「ぼや」などに分類され、それぞれの被害程度に応じて申請が可能です。
例えば、「全焼」は建物全体が焼失した場合、「半焼」は建物の半分以上が焼損した場合を指します。
被害の程度が軽微であっても罹災証明書の発行が認められるケースもあります。
ただし、具体的な基準は自治体によって異なるため、詳細はお住まいの市区町村や消防署に確認しましょう。
まとめ
火災や地震で被害を受けた際の罹災証明書の取得方法を解説しました。
罹災証明書は火災であれば消防署、地震・台風等の自然災害であれば役所で申請・取得でき、税金の減免や仮住まいの提供を受けられる場合があります。
また、災害によるごみ処理費用の減免や災害援護資金の貸付なども受けられるため、被災者にとっては非常に助かる制度です。
災害に巻き込まれ、すぐにでも生活を立て直したい方は、なるべく早く罹災証明書を申請することが大切です。
罹災証明書の申請方法や手順を理解して、スムーズ且つ確実に支援を受けましょう。