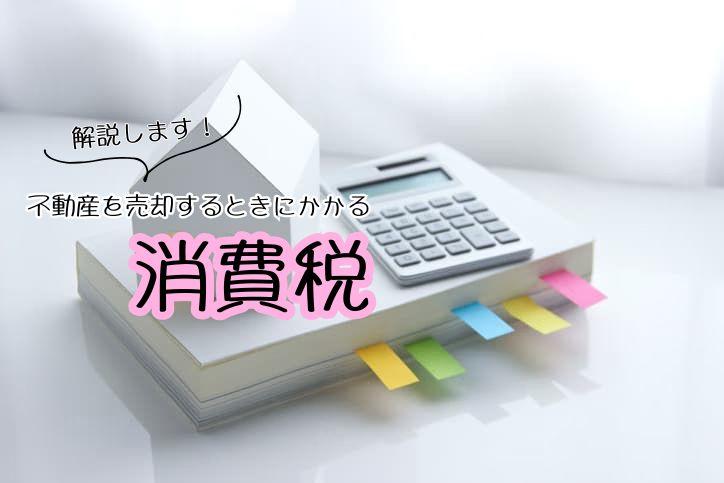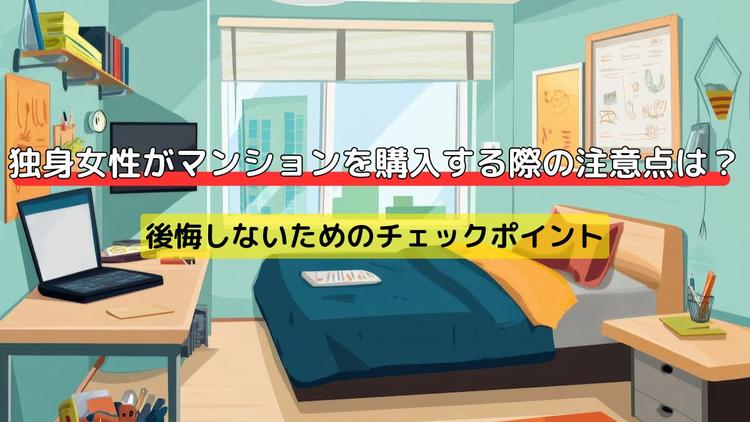2019年10月に消費税が8%から10%に増税されました。不動産の購入においては、住宅ローン控除の拡充によりむしろお得となるケースもありますが、不動産本体部分以外にかかる消費税について考慮する必要があります。
消費税は何かを購入するときにかかるものですが、不動産を売却するときにも、解体費用や仲介手数料、司法書士報酬などに対して消費税が課税されます。
本記事では、不動産売却時の消費税について、どんな消費税がかかるのか、シミュレーションを交えながら解説していきたいと思います。
不動産売却で消費税が課税されることがある?
消費税は普段の生活の中でよく目にするものなので、イメージしやすいのではないでしょうか。
一般的にはモノを購入するときに支払う消費税ですが、不動産を売却したときにも支払う必要があるのでしょうか?
そもそも消費税とは?
そもそも、消費税とは「モノ」や「サービス」を購入したときに、その購入価格に消費税率を掛けた額を支払う必要がある税金です。
モノとは食料品や衣料品など、一般的なお店で購入できるものをイメージするとよいでしょう。
一方、サービスとは例えば塾に支払う月謝などが該当します。
消費税を受け取った事業者がまとめて税金を納めるため、支払う人と納税者が異なる「間接税」に分類されます。
なお、ご存知かと思いますが2019年10月から消費税は10%に増税されています。
土地は非課税
消費税はモノやサービスを購入するときに課される税金ですが、不動産の売買ではどうなるのでしょうか。
実は、不動産の内、土地については消費税は非課税とされています。
土地が非課税な理由としては「土地の売買はモノやサービスの消費ではなく資本の移転だから」ということになっています。
建物も個人間売買なら非課税
一方、不動産のうち建物部分は消費税の課税対象となります。
ただし、売主が一般の個人など、「免税事業者」に該当する場合は建物部分も非課税です。
一方、工務店やハウスメーカーから建売住宅を購入する場合、売主が個人で賃貸事業に取り組んでおり、年間売上1,000万円以上の「課税事業者」に該当する場合は建物部分に消費税が課されることになります(個人の課税事業者が所有する不動産でも、居住用の住居は非課税)。
一般的には、中古住宅を「仲介」による方法で個人から購入した場合は消費税は非課税と考えてよいでしょう。
不動産会社がリフォームした物件を再販するようなケースや、工務店やハウスメーカーから建売住宅を購入する場合、注文住宅を契約する場合は建物部分について消費税がかかると考えておけば、大きく外れることはありません。
その他経費の部分で消費税がかかる
上記は不動産を購入するときに消費税がかかるかどうか…という問題でしたが、不動産を売却する場合でも消費税がかかることがあります。
それは、仲介手数料や司法書士報酬、土地の整地や建物の解体など、不動産本体部分の売買以外の各種経費についてです。
不動産売却時に課税される消費税
先述の通り、不動産売却時に消費税が課税される可能性のあるものとして、以下のようなものが挙げられます。
- 仲介手数料
- 司法書士報酬
- 解体費用
- 整地費用
それぞれについて見ていきましょう。
仲介手数料
まずは仲介手数料です。
不動産会社に仲介を依頼し、不動産会社の案内により売買が成立した場合、仲介手数料を支払う必要があり、消費税を含めて支払います。
仲介手数料の上限額は、法律により以下のように定められています。
例えば、3,000万円の売買であれば仲介手数料96万円に対して、消費税9.6万円が加えられ合計105.6万円を支払います。
司法書士報酬
不動産の売買では、売主から買主への所有権移転登記や、売主側の抵当権抹消登記など手続きする必要があり、登録免許税とは別に司法書士に対して司法書士報酬を支払う必要があります。
一般的に、所有権移転登記費用は買主側が負担することとなっており、売主側が負担する可能性のある登記費用としては以下のようなものがあります。
- 抵当権抹消登記
- 売渡証書作成費用
- 住所/氏名変更登記
上記3つの登記について、いくらの司法書士報酬を支払う必要があ�るかは、依頼する司法書士にもよりますが、概ね、それぞれについて0.5万円~1.5万円程度が相場です。
仮にいずれも1万円だった場合、1万円×3登記分=3万円に対して、消費税が0.3万円課されることになります。
解体費用
不動産売却時に、建物を解体して更地として売却する場合、解体費用に対して消費税が課されます。
解体費用も、どの解体業者に依頼するかや、解体する内容により価格が変わりますが、概ね構造毎の相場は以下のようになっています。
- 木造建物の解体・・・3万円~4万円/坪
- 鉄骨造建物の解体・・・5~6万円/坪
- RC造建物の解体・・・7~8万円/坪
例えば、30坪の木造戸建て住宅を解体する場合、解体費用として100万円程度、消費税が10万円程かかると考えておくとよいでしょう。
整地費用
不動産売却時に建物を解体する場合や、土地として売却する場合に土地に段差があったり、多数の木が植えられていたりするケースでは、事前に整地する必要があります。
整地の費用は単に地面をならすだけでよいのかや、木の抜根等の必要があるかどうか、ブロックなど積む必要があるかどうかなどによって変わります。
例えば、地ならしと木の抜根をし、隣地との境界線にブロックを積んで150万円の費用がかかった場合、消費税は15万円になります。
不動産売却時の消費税の額をシミュレーション
ここでは、一般的な不動産売却を2つ想定し、それぞれについてかかる消費税の総額を確認しましょう。
100万円かけて3,000万円の一戸建てを解体する場合
まずは、3,000万円の一戸建てを売却する場合で、売却前に100万円かけて解体するケースを見ていきましょう。
- 仲介手数料:3,000万円×3%+6万円×10%(消費税)=9.6万円
- 司法書士報酬(抵当権抹消登記/売渡証書作成):(1万円+1万円)×10%(消費税)=0.2万円
- 解体費用:100万円×10%(消費税)=10万円
- 合計:9.6万円+0.2万円+10万円=19.8万円
このケースでの消費税の総額は19.8万円となりました。
500万円かけて7,000万円の一戸建てを解体・整地する場合
次に、7,000万円のRC造の建物を解体するにあたり、500万円かけて解体・整地するケースです。
- 仲介手数料:7,000万円×3%+6万円×10%(消費税)=21.6万円
- 司法書士報酬(抵当権抹消登記/売渡証書作成)」:(1万円+1万円)×10%(消費税)=0.2万円
- 解体・整地費用:500万円×10%(消費税)=50万円
- 合計:21.6万円+0.2万円+50万円=71.8万円
このケースでの消費税の総額は71.8万円です。
特に解体・整地費用の負担額が大きくなっていることが分かります。
【番外編】不動産売却時の譲渡所得における消費税の計算
ここでは、番外編として不動産売却時の譲渡所得における消費税の計算を見ていきたいと思います。
不動産を売却して利益があると、その利益額に対して譲渡所得として所得税と住民税が課されます。
譲渡所得の計算上、建物の取得費から減価償却費を差し引く必要があるの��ですが、売買契約書が土地と建物で分かれて表記されていない場合は消費税の額で判断することがあります。
ここでは、その方法について見ていきましょう。
譲渡所得の計算方法
まず、譲渡所得は以下の計算式で求めます。
税額=課税譲渡所得×税率
問題となるのは、この中の取得費です。
減価償却費を割り出すために消費税を計算する必要がある
取得費とは、売却した不動産を購入したときの額を計上できるもので、建物部分については購入から現在までの分について減価償却を差し引く必要があります。
つまり、3,000万円で不動産を購入した場合、その内2,000万円分が建物価格だった場合、2,000万円分だけについて減価償却します。
しかし、古い売買契約書の中には、建物と土地が分けて表示されていないことがあります。
この場合、土地は非課税、建物は課税という特徴を理解して、消費税額から建物価格を割り出すことがあります。
消費税と本体価格が分かれている場合
一般的な売買契約書では、不動産の価格について以下のように表記されています。
- 土地価格:1,000万円
- 建物価格:2,000万円
- 消費税:200万円
- 合計:3,200万円
古い売買契約書で土地と建物が分けて表記されていない場合は
- 売買価格:3,000万円
- 消費税:200万円
- 合計:3,200万円
このように消費税の額を見ることで建物価格がいくらかを見分けることができます。
消費税が200万円かかっているのだから、建物価格が2,000万円だという計算です(消費税10%の場合)。
なお、売買契約日により消費税率は当然異なります。
日本において、消費税�は過去以下のように変わってきました。
- 1989年4月1日:消費税導入(3%)
- 1997年4月1日:消費税5%へ増税
- 2014年4月1日:消費税8%へ増税
- 2019年10月1日:消費税10%へ増税
消費税と本体価格が分かれていない場合
消費税と本体価格が分かれていない場合や、消費税が導入される前の売買契約だった場合、上記の判別方法は使えません。
こうした場合、建物の標準建築価格で算出することになっています1。
覚えておくとよいでしょう。
【番外編】消費税増税に対する不動産に関する政策
2019年10月に消費税は8%から10%へ増税されましたが、不動産は売買価格が大きいこともあり、消費税増税の影響を強く受けます。
そこで、不動産の買い控えに備え、政府は消費税増税に合わせてそれを緩和するための政策を実施しています2。
この内容が非常に手厚くなっており、消費税増税前に住宅を購入するより、消費税増税後に住宅を購入した方がお得になったという方も少なくありません。
以下、具体的な内容について見ていきましょう。
住宅ローン控除の拡充
まずは住宅ローン控除の拡充です。
住宅ローン控除とは、住宅ローン年末残高の0.7%について、10年間所得税と住民税から控除を受けられるというものです。
最大毎年35万円、合計455万円もの控除を受けられる、効果の高い控除となっていますが、消費税増税後に購入した不動産については3年間延長され、13年間控除を受けられることになっています。
なお、2025年現在、住宅ローン控除を13年間に延長できるのは特定の省エネ基準を満たす住宅を購入した場合のみで、規格に満たない一般住宅では適用可能期間が10年間に留まります。
すまい給付金の拡充(現在は終了)
すまい給付金とは、住宅取得者に対して、年収に応じて給付金を受け取れるというものです。
消費税8%増税への対策として導入され、当初は最大30万円の給付額でしたが、消費税10%増税後の取得については最大50万円の給付を受けられることになっています。
なお、すまい給付金は2024年7月で新規の申し込みが打ち切られており、代わりに「子育てエコホーム支援事業」等が利用できる場合があります。
次世代住宅ポイント制度(現在は終了)
次世代住宅ポイント制度とは、一定以上の省エネ性能を持つ等、要件を満たした住宅取得者に対し、最大35万円相当のポイントが付与されるというものです。
消費税10%が適用される住宅で、かつ2020年3月末までに契約を結ぶ必要があります。
贈与税非課税枠の拡充
最後に、父母や祖父母など直系尊属から住宅取得のための資金として贈与を受ける場合、一定額が非課税になる制度について、増税前の非課税枠が1,200万円だったのに対し、増税後は最大3,000万円まで非課税枠を利用できるようになりました。
しかし、現在では省エネ住宅は1000万円、それ以外の住宅は500万円まで非課税枠の規模が縮小されています。
まとめ
不動産売却時の消費税についてお伝えしました。
消費税はモノやサービスを購入するときに課される税金ですが、不動産売却時には、不動産の売買以外にも不動産会社による仲介や司法書士による登記など、いくつかのサービスを利用するのが一般的です。
不動産売却そのものには消費税が課されないものの、それらサービスの利用に消費税が課されることを覚えておくようにしましょう。