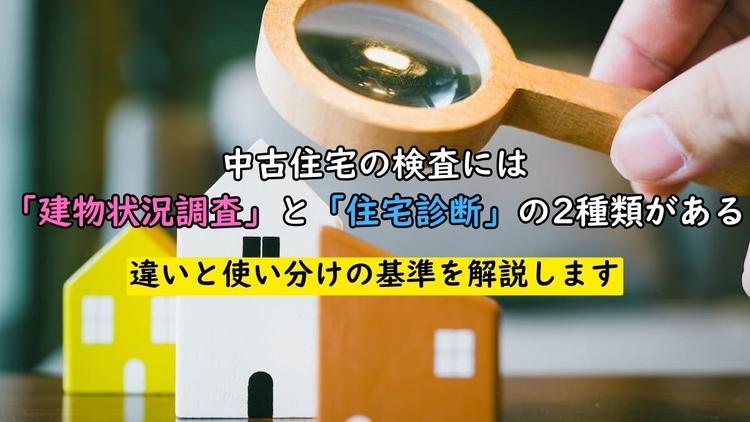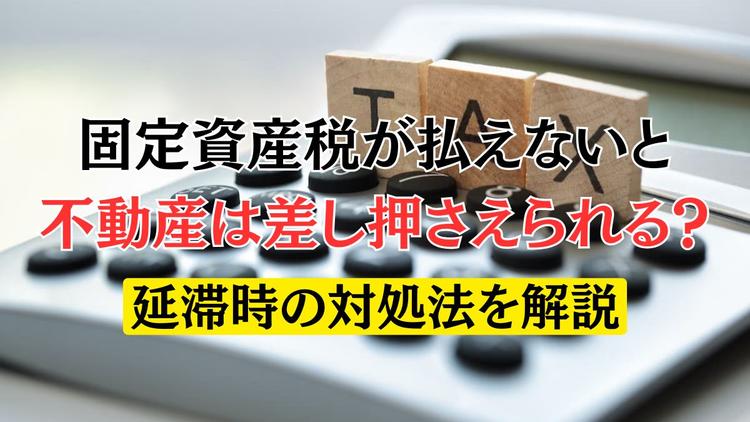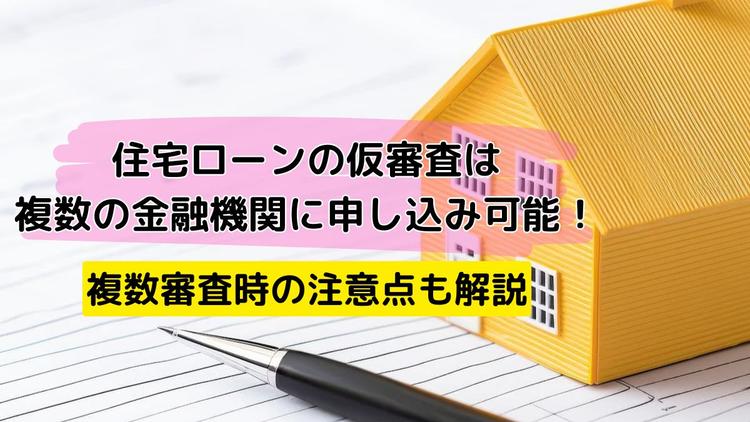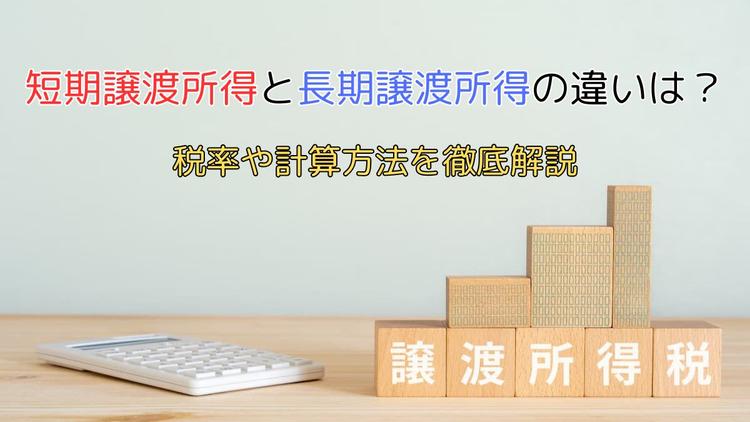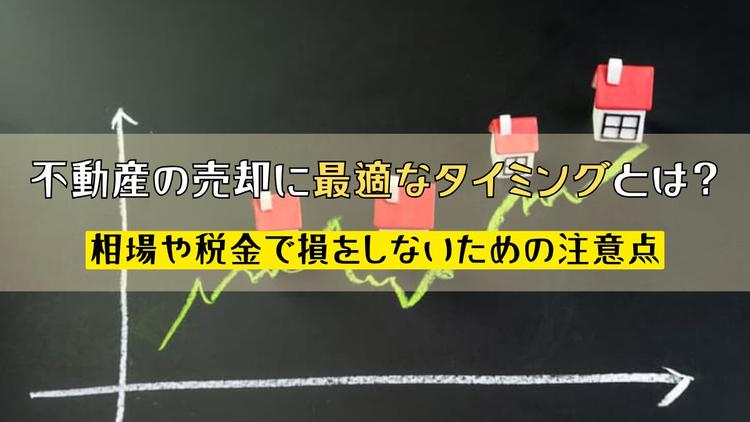住宅ローンを組む際、多くの人は返済年数の設定で悩むはず。「短期間で返済して借金から解放されたい」「月々の支払いを抑えて生活に余裕を持たせたい」など、各家庭の状況によって理由は異なります。
この記事では、住宅ローンの平均的な返済年数について詳しく解説します。
一般的な返済年数は30〜35年が多い
住宅ローンの返済年数は、一般的に35年が多いと言われています。これは、住宅ローン商品の多くが最長35年まで返済期間を設定できるためです。
日本の平均的な住宅ローン返済期間は以下の通りです。
短期ローン(20年以下):約10%
長期ローン(35年以上):約60%
参考:住宅金融支援機構【住宅ローン利用者調査(2024年4月調査)】
20年以下で組む人が10%に留まるのに対して、最長の35年で利用する人が6割であることが確認できます。
住宅ローンは他の金融商品に比べて圧倒的に金利が低いため、できるだけ長期間借入することで月々の支払いを抑え、家計にゆとりを持たせたいという背景があります。
返済年数30〜35年が多い理由
住宅ローンの返済期間として30~35年を選ぶ人が多いのには、主に3つの理由があります。
まず、多くの金融機関が最長期間を35年に設定しているため、この範囲でローンを組むのが一般的です。
次に、返済期間を長くすることで月々の返済額が抑えられ、無理のない返済計画が立てやすくなります。
さらに、月々の負担が軽くなることで、家計管理がしやすくなるのも理由の1つです。返済額が減れば、生活費や医療費など他の支出にまわす余裕が生まれます。
無理のない返済プランを立てるコツ
住宅ローンを組む際には、返済が家計を圧迫しないように慎重に計画を立てる必要があります。
無理のない返済計画を立てれば、毎月の支払いを安定させつつ他の支出に備えることが可能です。
以下では、返済負担を抑えるためのポイントとして、月々の支払額の設定方法、金利タイプの選び方、繰り上げ返済の活用法を解説します。
毎月無理なく返済するには
住宅ローンを無理なく返済するために、月々の返済額を手取り収入の25%以内に抑えましょう。
これを超えると家計に大きな負担が生じてしまい、突然の出費や生活費の増加に対応しにくくなります。
例えば、手取り月収が30万円の場合、返済額は7万5,000円以下に設定すると、普段の生活も安定しやすくなります。
また、ボーナスに頼らず、毎月の収入だけで返済できるような計画を立てることも重要です。ボーナス払いは月々の負担が減る一方で、総負担額が増えるといったデメリットもあるためです。
さらに、返済期間を長めに設定して月々の支払いを軽くする方法も効果的です。返済額が減れば他の支出にまわす余裕も生まれるため、無理なく返済が可能になります。
どの金利タイプを選ぶべき?
金利タイプごとのメリット・デメリットを確認しておきましょう。
金利タイプには「全期間固定金利」「固定期間選択型」「変動金利」の3種類があります。
全期間固定金利は、借入時の金利が返済終了まで変わらないため、毎月の返済額が一定で計画が立てやすいのが特徴です。ただし、変動金利に比べて金利がやや高めに設定されることが多く、初期の返済額が高くなる傾向があります。
固定期間選択型は、5年や10年など一定期間は固定金利、その後は変動金利に移行する仕組みです。安定した返済と金利に合わせて変更できる柔軟性が特徴です。
変動金利は、半年ごとに金利が見直されるタイプです。固定金利に比べて、借入時の金利が低いのが特徴です。ただし、将来的に金利が上昇すると、月々の返済額が増えるリスクもあります。
どの金利タイプを選ぶかは、家計や収入の状況、現在の金利を踏まえて検討する必要があります。金利は返済期間が長くなるほど影響も大きくなるため、自分に合ったプランを金融機関の専門家と相談しながら選択することをおすすめします。
繰り上げ返済を上手に活用しよう
繰り上げ返済とは、まとまった金額を返済にあてて総返済額を減らす方法です。繰り上げ返済には「期間短縮型」と「返済額軽減型」の2種類があります。
期間短縮型は、毎月の返済額は変えずに返済期間を短縮する方法です。返済期間が短くなる分、支払う利息の総額が減ります。
一方、返済額軽減型は、返済期間をそのままにして毎月の返済額を減らす方法です。家計に余裕を持たせたい場合や貯�蓄などを考えている場合に適しています。
ただし、無理をして繰り上げ返済を行なうと、生活に必要な費用や突発的なトラブルでかかる出費に対応できない可能性もあります。これらの出費を考慮した上で、計画的に利用しましょう。
住宅ローンは何歳までに完済するべき?
住宅ローンの返済は長期にわたるため、何歳までに完済すれば良いかを知りたい人は多いはずです。
以下では、何歳まで完済すれば家計に負担をかけずに済むか、完済が遅れた場合の対策についても解説します。
定年退職までに終わらせるのが安心
多くの企業では60~65歳を定年退職の年齢と定めています。住宅ローンは、定年退職までに完済するのが理想的です。
退職後は、年金を主な収入源とするケースが一般的です。現役時代のような収入が期待できない中で住宅ローンの返済を続けると、生活費や医療費など老後にかかる費用が不足する恐れがあります。
例えば、40歳で35年ローンを組んだ場合、完済時期は75歳となります。その間に金利が上昇したり、予期せぬ出費が発生したりすると、生活が厳しくなる可能性があります。
65歳までに完済するために、借入時の返済年数を短めに設定するか、繰り上げ返済を利用して早めに完済できる段取りができると良いでしょう。
また、退職金を一括返済にあてる方法もあります。ただし、退職金を使いすぎると老後の資金が不足するリスクもあるため注意が必要です。
定年後にローンが残った場合の対策
定年後も住宅ローンが残っている場合、いくつかの方法で対策が可能です。
まず、月々の返済額を減らすために、金融機関に返済期間の延長を相談してみましょう。延長が認められて月々の返済額が減れば、老後の生活費に余裕を持たせることができます。
また、前述の通り退職金の一部を繰り上げ返済にあてて、早期完済を目指すのも効果的です。
もう一つの選択肢として、自宅に住み続けながら資金を確保できるリバースモーゲージを活用する方法があります。自宅を担保に金融機関から資金を借り入れ、生活費やローン返済にあてられます。
リバースモーゲージは、利用者が亡くなった後に担保にとった不動産を売却する方法であり、相続財産として引き継ぐことができないといったデメリットもあります。
また、リバースモーゲージの融資限度額は不動産評価額の50~70%程度に留まるのが一般的です。そのため、自宅の価格変動によっては借り入れできる金額が安くなってしまう点に注意してください。
これを回避する方法として、住み替えも検討しましょう。現在の家を売却して手頃な物件や賃貸住宅に移ることで、返済の負担を抑えることができます。
住宅ローンの借入額の目安
住宅ローンを検討する際、いくら借りるかも重要なポイントとなります。
借入額が多すぎると家計に大きな負担をかける可能性があります。しかし、少なすぎると希望する住宅を購入できないかもしれません。
適切な借入額を知ることは、無理のない返済計画を立てる上で欠かせません。以下では、住宅ローンの平均的な借入額と、自分の家計に合った借入額を計算する方法を詳しく解説します。
平均的な借入額はどれくらい?
住宅ローンの平均借入額は、地域や収入状況などにより差が生じますが、約3,000万円といわれています。
ただし、首都圏などの都市部では収入・地価も高い傾向にあるため、住宅ローンの借入額も高めです。
また、頭金の有無や購入する物件の種類(新築・中古、マンション・戸建て)によっても必要な借入額は変動します。
物件価格の20〜30%程度を頭金として準備し、残りをローンで補うのが一般的です1。
ただし、こうした平均値はあくまでも全体の傾向ですので、自分の家計に適した数値になるかは全く別物です。
借入額や頭金の額、借入年数などは、他人の事例や平均値にとらわれず、自身の状況を確認した上で意思決定することを推奨します。
無理のない借入額を計算する方法
無理のない借入額を計算する目安として、住宅ローンの借入額は年収の5〜7倍以内が推奨されています。これを超えると返済負担が大きくなり、生活費などに影響を及ぼす可能性があります。
年収500万円の場合を例とした場合、以下が借入額の目安です。
また、借入額を決める際は、月々の返済額も重要。月々の返済額は、手取り収入の25%以内に収めるのが理想的とされています。
例えば、手取り月収が30万円の場合、毎月の返済額は7万5,000円以下に設定することで、無理のない返済計画が立てられるでしょう。
住宅ローンを借りる際の注意点
住宅ローンは、多くの人にとって人生で最大額の借り入れとなるはずです。そのためにも、後々後悔しないために慎重に計画を立てる必要があります。
以下では、住宅ローンを借りる際に注意すべき3つのポイントを詳しく解説します。
審査でチェックされるポイント
住宅ローンの審査では、主に以下の項目がチェックされます。
- 返済負担率:年収に対する年間返済額の割合が重視されます。一般的に、返済負担率が25〜35%以下であれば��審査に通りやすいとされています。
- 年収:安定した収入があり、無理なく返済できるかが判断基準となります。雇用形態や勤続年数も審査に影響します。
- 信用情報:過去の借り入れやクレジットカードの利用状況が確認されます。延滞や未払い履歴があると、審査が厳しくなる場合があります。
審査を通過するためには、ローンを申し込む前に自身の信用情報を確認し、返済負担率を抑えた借り入れを計画することが重要です。
また、過剰な借り入れを避けるために、無理のない返済額を設定するように心がけましょう。
金利上昇のリスクを理解する
住宅ローンを組む際、金利タイプによって将来の返済額が大きく変わる可能性があります。
特に変動金利を選ぶ場合は、将来的に金利が上昇するリスクを十分に理解しておくことが重要です。
変動金利は、借入当初の金利が低いのが魅力で、住宅ローン利用者のうち6割程度の方が選択しています2。しかし、金利が上昇すると月々の返済額も増えてしまいます。
例えば、金利が1%上昇すると、月々の返済額が数万円単位で増加する可能性があります。
一方で、固定金利は借入時の金利は変動金利よりも高いものの、一定期間もしくは返済終了まで金利が変わらないため、安定して返済できるでしょう。
また、固定金利は審査の上でも「審査時の金利が実行金利と同じ」という特徴があり、比較的年収が低い方は固定金利の方が借入額を大きくできるメリットもあるのです。
金利タイプを選ぶ際は、家計の状況はもちろん、市場の動きや金利の上昇をチェックすることを推奨します。
また、変動金利を選ぶ場合は、金利上昇に備えて貯蓄をしたり、まとまった資金があるなら繰り上げ返済を検討することで、金利上昇のリスクを回避できます。
収入の減少に備えて貯蓄する
住宅ローンの返済は長期にわたるため、、病気や失業、収入減少といった不測の事態に備えることは必要不可欠。
収入が減った場合でも返済を続けられるよう、事前に十分な貯蓄を確保しておくことが重要です。
生活費の3〜6ヶ月分を目安に資金を準備しておくと安心です。
また、団体信用生命保険(団信)に加入することで、病気や死亡といった場合にローンの返済がカバーされます。
計画的に繰り上げ返済を行うことで、住宅ローンの負担を軽減することが可能です。手元資金に余裕がある場合は、無理のない範囲でローン残高を減らし、返済額を抑えることを目指しましょう。
まとめ
住宅ローンの借り入れは、夢のマイホームを手に入れるために欠かすことが出来ません。しかし、返済は長期間に及ぶため、返済年数の平均である30~35年を参考にして、無理のない返済計画を建てる必要があります。
また、住宅ローンは65歳までに完済することを目標にし、不測の事態に備えてあらかじめ貯蓄しておくことをおすすめします。
初めての借�り入れでは、分からないことがたくさんあると思います。そのような場合は、専門家の意見を取り入れながら自分に最適な住宅ローン計画を立ててください。
無理のない返済プランを選ぶことで、普段の生活を圧迫することなく安定して返済を続けられます。