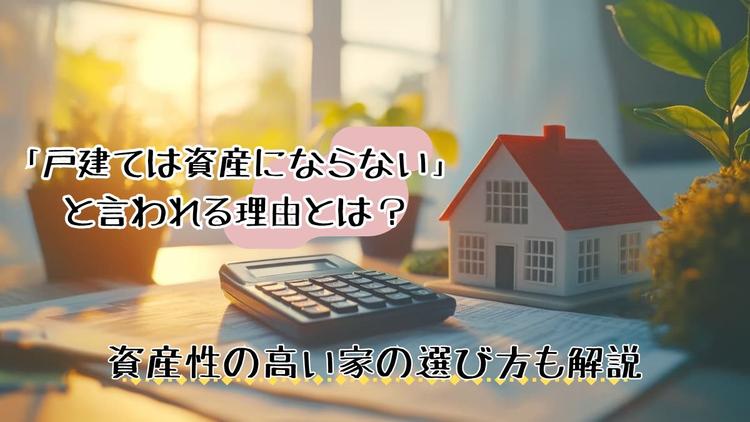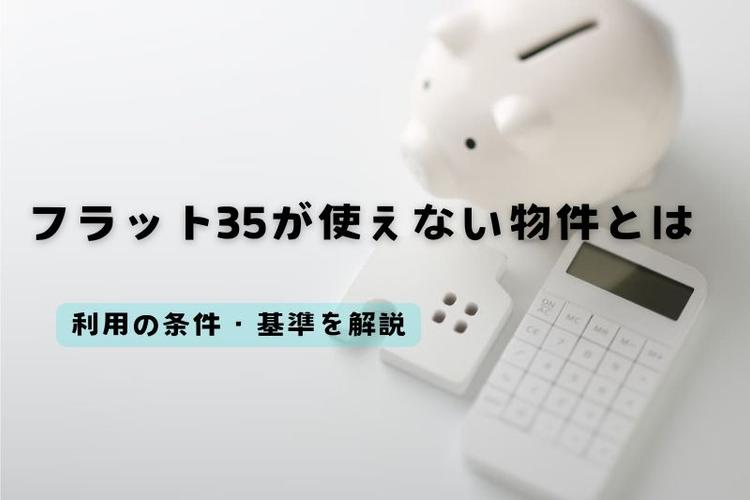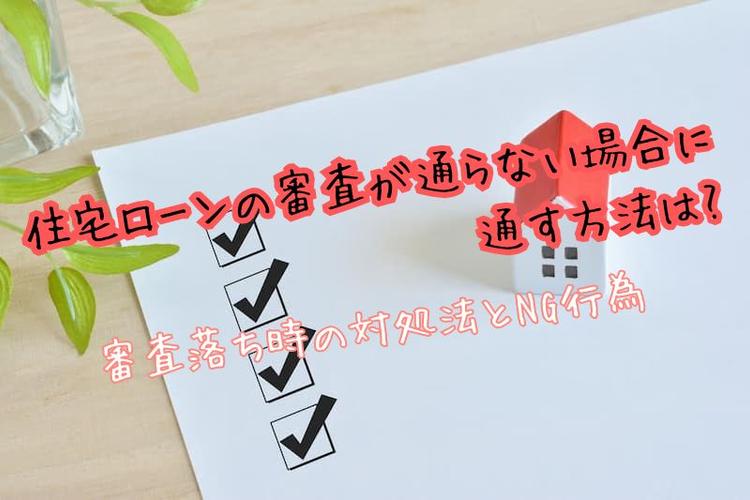住んでいない家でも売却して利益が出ると、譲渡所得税と呼ばれる税金がかかります。
ただし、譲渡所得税がかかる場合でも、控除の適用で節税できるので、計算方法や控除について理解しておくことが重要です。
この記事では、住んでいない家の売却でかかる税金の計算方法や、利用できる控除、譲渡所得税以外で課税される税金などを解説します。
住んでいない家を売却すると利益に応じて税金がかかる
家を売却して利益が出ると、譲渡所得税と呼ばれる税金がかかります。
これは、売却した家に住んでいる・いないは関係なく、利益が出たかどうかで課税が判断されます。
そのため、住んでいない家であっても売却して利益が出れば課税の対象となるのです。
譲渡所得税は利益や所有期間に応じて税額が異なり、ケースによっては税額が高額になる可能性があります。
ただし、譲渡所得税には控除の特例がいくつか用意されており、住んでいない家にも適用できる特例があるため、節税が可能です。
住んでいない家の売却を検討する際には、税金の計算方法や節税方法についても理解しておくようにしましょう。
住んでいない家を売却したときの税金の計算方法
住んでいない家を売却し利益が出ると、譲渡所得税の対象になります。
まずは、譲渡所得税の計算方法を押さえていきましょう。
売却時の所得は譲渡所得として計上する
住んでいない家を含め不動産を売却して利益が出ると、その利益は「譲渡所得」という所得に区分され、所得税・住民税の対象になります。
この譲渡所得にかかる所得税・住民税を総称して譲渡所得税と呼びます。
また、不動産の譲渡所得は給与所得と合算せずに税金を計算する、分離課税の対象です。
そのため、売却した人の年収に関わらず、譲渡所得が発生すると納税が必要になります。
譲渡所得にかかる税金は以下の2ステップで求められるので、以下で詳しくみていきましょう。
- 課税譲渡所得を計算する
- 課税譲渡所得に税率を掛けて納税額を算出する
課税譲渡所得を計算する
1ステップ目では、税金の対象となる「課税譲渡所得」を計算します。
課税譲渡所得の計算方法は、以下の通りです。
取得費とは、売却した家を取得した際の費用を指し、家の購入代金だけでなく仲介手数料や不動産取得税などの費用も含まれます。
なお、相続した家のように古くからある家の場合、取得費が明確にならないケースも少なくありません。
その場合は概算の取得費として「売却額×5%」を計上することになります。
減価償却について
また、家の場合、取得費からは経年劣化による資産価値減少分として「減価償却費」を差し引く必要がある点には注意しましょう。
例えば、購入時の費用の総額が4,000万円であっても、減価償却費が2,000万円なら、差し引いた2,000万円を取得費からマイナスすることになるのです。
減価償却費の計算方法は、建物の構造と用途(居住用・事業用)などによって異なり、毎年同じ金額が償却されていきます。
関連記事:不動産売却時の減価償却はどう計算する?
譲渡費用
一方、譲渡費用とは売却時にかかった仲介手数料などの費用を指します。
売却額から、この取得費と譲渡費用を差し引いた額が譲渡所得です。
課税対象となるのは、さらに特別控除などを差し引いた部分になります。
特別控除については後述するので参考にしてください。
課税譲渡所得に税率を掛けて納税額を算出する
特別控除まで差し引いてプラスになれば税金が発生するので、税額を計算します。
譲渡所得にかかる税金の計算方法は以下の通りです。
課税譲渡所得に税率を乗じるだけのシンプルな計算で求められます。
ただし、税率は所有期間に応じて以下の2種類に区別されるので注意しましょう。
| 所有期間 | 所得税・復興特別所得税 | 住民税 | 合計税率 | |
| 短期譲渡所得 | 5年以下 | 30.63% | 9% | 39.63% |
| 長期譲渡所得 | 5年超 | 15.315% | 5% | 20.315% |
所有期間5年以下の短期譲渡所得は、所有期間5年超の長期譲渡所得の2倍近い税率です。
また、2037年までは東日本大震災への復興資源となる復興特別所得税も徴収されます。
なお相続の場合の所有期間は、前の所有者の所有期間からの通算です。
例えば、相続後の所有期間は1年でも被相続人(故人)の所有期間が10年なら、通算の所有期間は11年となり長期譲渡所得の対象となります。
住んでいない家の売却で利用できる特別控除
譲渡所得からは特別控除を差し引けるので、適用できる控除は積極的に活用することが大切です。
住んでいない家の場合、以下の2つのケースで特例の適用が検討できます。
- 相続した空き家の売却
- 住まなくなった日から3年以内のマイホームの売却
親から相続した実家を空き家で売却した場合、「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」の適用が可能です。
この特例を適用することで、相続空き家の売却の譲渡所得を最大3,000万円控除できます1。
例えば、譲渡所得が4,000万円であれば特例の適用で4,000万円-3,000万円=1,000万円が譲渡所得税の対象となるのです。
ただし、この特例を適用するには以下のような要件を満たす必要があります。
- 昭和56年5月31日以前に建築された戸建であること
- 相続開始時に被相続人以外に住んでいる人がいなかった
- 相続開始から売却まで活用していない
- 相続の開始にあった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までの売却
- 売却代金が1億円以下
- 売主と買主が夫婦など特別な関係でない
また、売却する際には解体して更地にするか、建物を耐震補強することが求められます。
適用要件のハードルが高いですが、適用できれば大きな節税が見込めるので、国税庁のホームページで細かい要件をチェックしてみるとよいでしょう。
今は住んでいない家であっても直前までマイホームとして利用していた家の場合、一定の条件を満たすこと売却時に適用できる可能性があります。
マイホームとして特例を適用する場合は、複数の特例の検討が可能です。
以下で詳しく解説するので、参考にしてください。
住まなくなってから3年以内であれば住んでいる家と同様の特別控除を受けられる
現在住んでいない家であっても、それまでマイホームとして利用していた場合、一定の条件を満たすことでマイホームの売却として特例の適用が可能です。
過去に居住していたマイホームとして特例を受ける場合は、以下の2つの要件を満たすことが前提となります。
- 自分が所有者として住んで�いた家屋であること
- 自分が住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに家屋または家屋・敷地の売却
過去居住していたマイホームに該当する場合、以下のような特例の適用が検討できます2。
- マイホームを売却したときの3,000万円特別控除
- 所有期間10年超の軽減税率
- 特定のマイホームを買い換えたときの特例
- マイホームを買い換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
- 特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
なお、特例を適用する際にはそれぞれの特例の適用要件を満たす必要があります。
さらに、特例によっては併用できるもの・できないものもあるので、シミュレーションしながら適切な特例を適用することが大切です。
以下で、それぞれの特例を詳しく解説します。
マイホームを売却したときの3,000万円特別控除
マイホームの売却で適用できる代表的な特例が「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」です。
この特例では、譲渡所得から最大3,000万円を控除できます3。
例えば、譲渡所得が4,000万円の場合、この特例を適用することで、4,000万円-3,000万円=1,000万円が課税の対象となるのです。
譲渡所得3,000万円未満であれば特例の適用で税金が発生しなくなるため、大きな節税につながるでしょう。
この特例を適用するには、前述した要件以外にも「他の特例を適用していない」「親子や夫婦などの特別な関係での売却でない」などのいくつか要件があります。
また、3,000万円特別控除は住宅ローン控除との併用ができないので、住み替えによる売却の場合はどちらを適用するかを慎重に判断することが大切です。
詳しい要件は国税庁のホームページに記載されているので、チェックして検討するとよいでしょう。
所有期間10年超の軽減税率
所有期間が10年を超えるマイホームを売却した場合、譲渡所得にかかる税金の税率を引き下げる特例です4。
特例を適用することで、譲渡所得6,000万円以下の部分の税率を14.21%(所得税・復興特別所得税・住民税の合計)まで引き下げられます。
この特例は、マイホームの3,000万円特別控除と併用�ができるので、より節税効果を高めることが可能です。
特定のマイホームを買い換えたときの特例
マイホーム買換えに伴う売却時に適用できる特例が、「特定の居住用財産の買換えの特例」です5。
この特例では、売却益の課税を「買い換えた住居を将来売却するとき」まで繰延できます。
例えば、買い換えの利益が3,000万円のとき、この特例を適用することで今回の売却の税金を発生させないようにできます。
しかし、買い換えで購入した住居を将来売却した際、新居の課税分に繰延した3,000万円の課税分が加算されるのです。
この特例は、3,000万円特別控除のように税金がかからなくなるのではなく、あくまで将来に繰り延べするだけです。
将来住居を売却しないなら大きな節税が見込める反面、売却した場合は税負担が大きくなる恐れがあります。
この特例を検討する際には、将来の売却まで視野に入れて3,000万円特別控除とどちらがお得かを判断するようにしましょう。
マイホームを買い換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
譲渡所得がマイナスの場合は税金が発生しないので、確定申告は必要ありません。
しかし、マイナスの場合でも適用することで節税につながる特例が用意されています。
そのうちの1つが�、「マイホームを買い換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」です6。
この特例では買い替えに伴う売却で損失が出た場合、一定の要件を満たすことで損失分を給与所得など他の所得から控除(損益通算)できます。
例えば、売却で500万円の赤字があり給与所得が400万円の場合、控除することで給与所得が0円となるため給与所得にかかる所得税・住民税の節税につながるのです。
また、この特例ではその年で控除しきれない分を翌年以降3年間控除できます。
特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
譲渡所得がマイナスになった場合に検討できるもう1つの特例が、「特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」です7。
この特例では、住宅ローン残債のある家を売却し損失が出た場合に、損失分を給与所得などから控除できます。
また、その年では控除しきれない分は、翌年以降3年間は控除が可能です。
譲渡所得以外に住んでいない家の売却でかかる可能性がある税金
住んでいない家の売却では、譲渡所得にかかる税金以外にも、以下のような税金が発生します。
- 消費税
- 印紙税
- 登録免許税
消費税
個人がマイホームを売却する場合、売却額は消費税の対象とはなりません。
また、そもそも土地取引は消費税の対象外です。
さらに、個人事業主などであっても免税業者であれば消費税は発生しません。
そのため、基本的に個人が住まない家を売却しても消費税は発生しないでしょう。
ただし、以下のような取引は消費税を支払う必要があります。
- 不動産会社の仲介手数料
- 司法書士報酬
- リフォームや解体を依頼した場合の業者への支払い
印紙税
印紙税とは、課税対象の書類を作成した際にかかる税金です。
不動産売却の場合、売買契約書が印紙税の対象となるので、契約書に収入印紙を貼付・消印して納税する必要があります。
印紙税の税額は、契約書に記載の金額(売買金額)に応じて異なり、主な不動産取引の価格帯での税額は以下の通りです。
| 契約金額 | 本則税率 | 軽減後の税率 |
| 500万円超1,000万円以下 | 1万円 | 5,000円 |
| 1,000万円超5,000万円以下 | 2万円 | 1万円 |
| 5,000万円超1億円以下 | 6万円 | 3万円 |
令和9年3月31日までは軽減後の税率が適用されます。
なお、売買契約書は2通作成し、売主・買主が保管するため、それぞれの保管分の税額を負担するのが一般的です。
また、電子契約での契約なら印紙税の対象外となるため、収入印紙は必要ありません。
売主・買主のどちらが負担するか、電子契約にできるかなどは不動産会社に確認するようにしましょう。
登録免許税
登録免許税とは、不動産登記を作成・変更する際にかかる税金です。
不動産売却の場合、以下の2つの登記で登録免許税が発生します。
- 所有権移転登記:所有者を売主から買主に変更する登記
- 抵当権抹消登記:設定されている抵当権を抹消する登記
基本的に所有権移転登記は買主が負担するため、売主に負担はありません。
また、抵当権抹消登記は売却時に住宅ローンを完済するか、すでに完済していたが抵当権の抹消ができていなかったという場合で必要です。
この場合、抵当権抹消登記の登録免許税として不動産個数×1,000円が必要になります。
さらに、登記手続きは司法書士に依頼するのが一般的なので、司法書士報酬も発生する点に注意しましょう。
なお、すでに抵当権が抹消されている場合は、抵当権抹消登記の登録免許税は発生しません。
住んでいない家を売却したときの税金に関するシミュレーション
�ここでは、住んでいない家を売却した際の税金を具体的にシミュレーションしていきましょう。
条件は以下の通りです。
- 売却額:1,500万円
- 所有期間:20年(相続で取得)
- 取得費用:不明
- 譲渡費用:200万円
- 抵当権抹消登記:不要
なお、今回は建物の減価償却費は考慮せず、譲渡所得税・印紙税を計算していきます。
印紙税は、3,000万円の売買契約書なので軽減適用の場合で1万円です。
譲渡所得にかかる税金の計算は以下のようになります。
取得費が不明なので、概算取得費として3,000万円×5%=150万円を計上し、課税譲渡所得を算出します。
所有期間20年は長期譲渡所得に区分されるため、税額は以下の通りです。
なお、相続で取得し空き家として売却した場合は「相続空き家の3,000万円特別控除」、相続をマイホームとして活用してからの活用であれば「マイホームの3,000万円特別控除」の適用が検討できます。
いずれかの特例を適用した場合、譲渡所得が0円となるので税金は発生しません。
住んでいない家を売却したときの税金に関するよくある質問
最後に、住んでいない家を売却したときの税金に関するよくある質問をみていきましょう。
住んでいない家に固定資産税はかかる?
住んでいない家であっても不動産の所有者である以上、固定資産税が課税されます。
また、地域によっては都�市計画税も課税の対象です。
ただし、住んでいない家であっても居住用の建物が建築されている場合、土地の固定資産税に軽減措置が適用され、税額は最大6分の1に軽減されます。
しかし、家を解体してしまうと軽減措置が適用されなくなるので、本来の高い税額に戻ります。
住んでいない家の管理ができずに自治体から「特定空き家」に指定された場合も、軽減措置が適用できないので注意しましょう。
セカンドハウスを売却したときに税金はかかる?
セカンドハウスを売却した場合も、通常の不動産の売却時と同様に譲渡所得に税金が課税されます。
さらに、セカンドハウスは基本的に3,000万円特別控除の対象外である点に注意しましょう。
3,000万円特別控除は、2つ以上居住用建物を所有している場合は、主として住んでいる物件のみに適用されるため、セカンドハウスでは適用できません。
また、別荘や投資用不動産でも適用不可となります。
ただし、単身赴任などで一時的に離れて暮らしている家などでは適用できるケースもあるので、要件を確認するようにしましょう。
まとめ
住んでいない家であっても売却して利益が出れば、譲渡所得にかかる税金が課税されます。
ただし、住んでいない家でも相続空き家の3,000万円特別控除や、マイホームの3,000万円特別控除の適用で節税できる可能性があります。
譲渡所得にかかる税金の計算方法や活用できる特例について理解し、満足いく売却ができるようにしましょう。