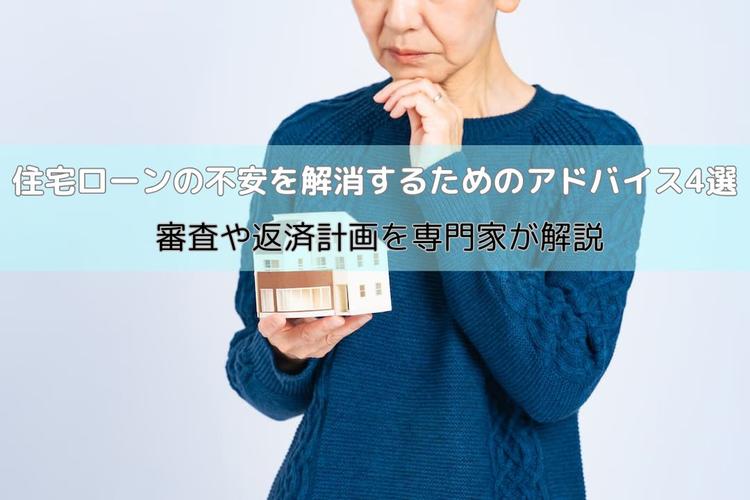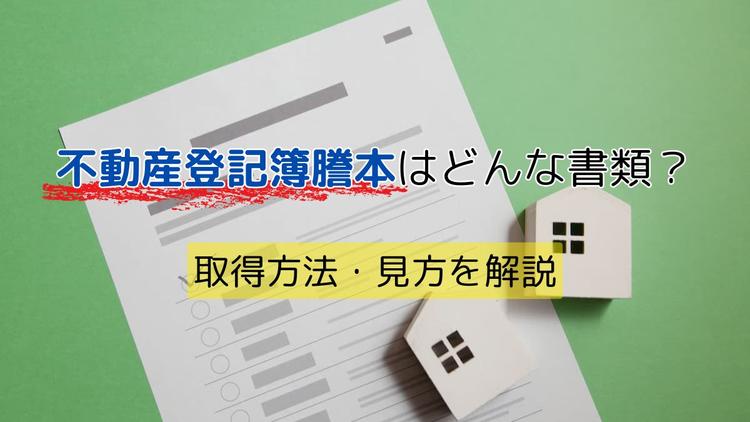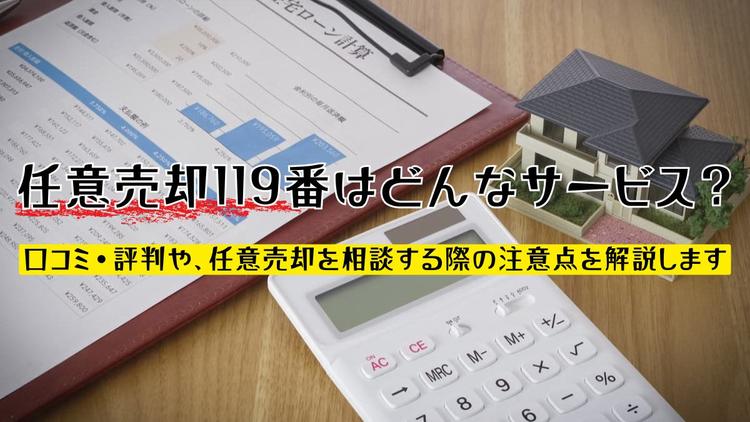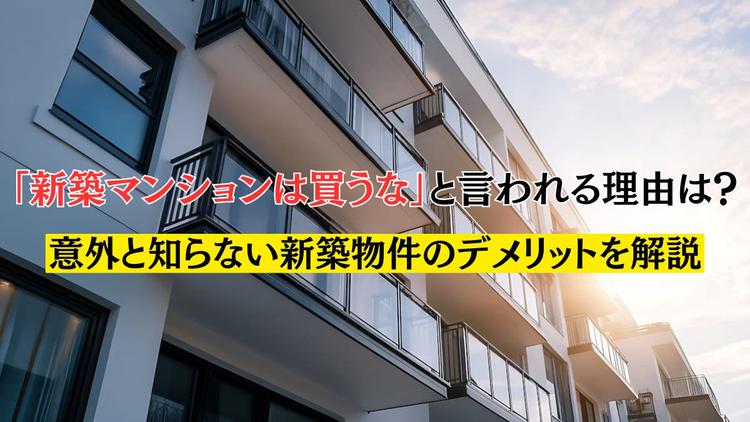住宅ローンは高額な借入になるうえ、20年や30年と返済期間も長期に渡ります。
「自分の年収で審査に通るだろうか」「そんな先まで返済し続けられるだろうか」と不安を感じる人も少なくないでしょう。
住宅ローンを借り入れる際には、そのような不安を解消しておくことが大切です。
この記事では、住宅ローンでよくある4つの不安と、それを解消するためのアドバイスを、専門家が解説します。
この記事を参考に、住宅ローンの不安を解消して満足いく家を購入できるようにしてください。
住宅ローンに関するよくある4つの不安
住宅ローンの検討段階ではマイホームの購入に胸が弾む一方、ローンへの不安を抱く方も多いものです。
何に不安を抱くかは人それぞれですが、よくある不安として以下の4つが挙げられます。
- 審査に通るか不安
- 返済できるか不安
- 将来金利が上がらないか不安
- 老後の金銭面が不安
それぞれ見ていきましょう。
審査に通るか不安
住宅ローンは誰でも借入できるわけではなく、金融機関の審査に通る必要があります。
審査の結果によっては、借入できなかったり、審査に通ったものの希望額を借入できない(減額)というケースも珍しくありません。
住宅ローンが利用できなければ、マイホームの購入を諦めなければならないでしょう。
住宅ローン審査に通るかはマイホーム購入の前提ともなるので、審査を不安に感じる人も多いのです。
返済できるか不安
住宅ローンを借入できても、借りたお金は返さなければなりません。
住宅ローンの返済期間は30年以上かかるケースが一般的です。
今の収入では問題なくでも、いつ収入が減少するか、また教育費などの支出が増えるかは分かりません。
2020年~2022年ごろの新型コロナウイルスの感染拡大など、予測できない事態に陥る可能性もゼロではありません。
住宅ローンの支払いができなくなると、最悪競売で家を手放す��だけでなく自己破産しなければならないケースもあります。
完済までの長い期間、毎月返済を続けられるかのプレッシャーに不安を感じる人も多いのです。
将来金利が上がらないか不安
住宅ローンは高額な借入かつ長期に渡る返済のため、返済額が金利に大きく左右されます。
わずか数%金利が上がっただけでも、返済額が数百万円変わってくるのです。
例えば、3,000万円を30年間金利1.0%で借入れた場合の毎月の返済額、総返済額は以下のようになります。
- 毎月の返済額:96,491円
- 総返済額:34,736,760円(利息分4,736,760円)
これが、15年目で金利が1.5%に上がると残り期間の毎月の返済額と返済総額は以下のように変わるのです。
- 毎月の返済額:100,079円
- 総返済額:35,382,600円(利息分5,382,600円)
毎月の返済額は約4,000円アップし、総返済額は70万円のアップになっています。
金利の上り幅やタイミングによっては、これ以上の負担になるケースもあるでしょう。
2024年10月に基準金利の引き上げを実施した金融機関も多く、住宅ローンの金利がいつ上がってもおかしくない状況です。
20年後、30年後の金利がどうなっているか分からないため、将来の返済に不安を抱く人も少なくないでしょう。
老後の金銭面が不安
住宅ローンの返済は老後の生活費にも大きな影響を与えます。
仮に、35歳で35年ローンを組み、繰り上げ返済せず順調に返済した場合、完済は70歳になります。
この時、もし65歳で定年退職していると�、残り5年を年金収入や預貯金でカバーする必要が出てきます。
65歳の時に退職金で残債を一括返済するにしても、自己資金が大きく減少することになります。
定年退職後の年金や預貯金、退職金は、老後生活するうえでの重要な資金です。
特に30代後半以降で長期のローンを組むと、その影響は大きくなります。
住宅ローンの返済が老後資金に影響することで、老後の生活に不安を覚える方もいるでしょう。
以下では、これら4つの不安を解消するためのアドバイスを詳しく紹介するので、ぜひ役立ててください。
住宅ローンの審査に関する不安を解消するアドバイス
まずは、住宅ローンの審査に関する不安についての解消法をみていきましょう。
結論:仕組みを理解して複数の手段を検討しよう
住宅ローンの審査に不安を感じるのは、審査基準など住宅ローン審査の仕組みを理解していないことが要因として挙げられるでしょう。
住宅ローン審査の仕組みを理解することで、事前にしっかり対策でき不安を解消できます。
また、住宅ローン審査に落ちてしまった場合の対処法まで理解しておくと、より安心して住宅ローン審査に進みやすくなるでしょう。
住宅ローン審査の仕組み
住宅ローン審査は、一般的に事前審査(仮審査)と本審査の2種類があります。
事前審査では主に申告内容などを精査し、本審査ではより詳しい申告内容や提出書類などをチェックした上で、融資の可否が判断されます。
事前審査と本審査では審査項目や提出書類は異なりますが、基本的にどちらも「�この人に融資しても大丈夫か」「いくらまで融資できるか」が審査されます。
審査基準
審査基準については金融機関ごとに異なり、明確な基準は公表されていません。
とはいえ、審査される項目は基本的に共通しており、主に以下の項目が審査されます。
- 年齢(申込時・完済時)
- 年収
- 勤務先・勤続年数
- 他の借入状況
- 健康状況
- 担保価値
- 家族構成など
年齢や年収・勤続年数などで収入の安定性・長期間返済できるのかがチェックされます。
返済比率
住宅ローンの借入可能額は金融機関ごとに異なりますが、基本的には個人の年収や他の借入額などから算出される返済比率をもとに計算されます。
返済比率とは、年収に占める年間の返済額の割合です。
そのため、他の借入を返済したり、借入希望額を下げるなどして返済比率を下げる方が、審査に通りやすくなります。
また、審査に落ちやすい要因として、クレジットカードなどの個人信用情報に延滞などの記録があるケースもあるので、信用情報に不安がある人は事前に取り寄せて確認することもおすすめです。
住宅ローン審査に通らないときの対策
仮に、住宅ローンの審査に落ちてしまったからといって、すぐに住宅購入を諦める必要はありません。
以下のような対策をして再度申し込むと、住宅ローンに通る可能性があります。
- 自己資金を高める(親にお金を借りるなど)
- 収入が足りない場合は親子リレーローンや夫婦収入合算を検討する
- 別の金融機関に申し込む
- 個人信用情報にキズがある方でも積極的に融資してくれる金融機関を探す
住宅ローンの審査基準は金融機関ごとに異なるため、同じ条件であっても一方が落ち、一方が通ることは珍しくありません。
なかには個人信用情報にキズがある状態でも、キズの理由や、その後の貯蓄の計画性などを証証明できれば、融資してくれるケースもあるので、自分の条件に合った金融機関を見つけるとよいでしょう。
ただし、自己破産の情報が登録されている場合は、基本的にどの金融機関でも難しいため、自己破産情報が抹消されるまで期間を空けるか、配偶者や親で申込むなどを検討するとよいでしょう。
住宅ローンの返済に関する不安を解消するアドバイス
次に、住宅ローンの返済に関する不安の解消法をみていきましょう。
結論:実際の金の流れをシミュレーションする
住宅ローンの返済に不安を感じるのは、長期的で詳細な返済計画がないことも要因の一つです。
現状の資金状況や収支だけでなく、将来のライフプランまで含めた長期的な返済計画を立てることで、返済の流れが明確になり不安も解消しやすくなるでしょう。
長期的な返済計画を立てると、検討している住宅ローンが適しているかも分かりやすくなり、借入額や金利などの判断材料にもなります。
返済比率20~25%程度がおすすめ
先述したように、返済比率とは年収に占める年間の返済額の割合です。
例えば、年収600万円で年間の返済額が180万円なら、返済比率は「180万円÷600万円×100=30%」となります。
一般的に金融機関では、審査の際に返済比率を30~35%以下として、借入可能額を算出します。
ただ、返済比率30~35%は借入できる額の目安ではありますが、返済に無理がない額とは異なってきます。
理想的な返済比率は20~25%以下と言われているので、返済比率20~25%を目安としてシミュレーションしてみるとよいでしょう。
FPなど専門家にプランニングしてもらう
返済比率20~25%はあくまで一つの目安であり、適切な比率は資産状況や家族構成などによっても異なります。
しかし、ライフプランまで踏まえた長期的で詳細な返済計画を自分で立てるのは容易ではありません。
そのため、FPなどの専門家に相談しながらプランニングしてもらうことで、より現実的なプランができるでしょう。
第三者のアドバイスを受けることで、適切な住宅ローンも判断しやすくなります。
住宅ローンの金利に関する不安を解消するアドバイ��ス
住宅ローンの金利に関する不安の解消法をみていきましょう。
結論:将来不安なら全期間固定金利がおすすめ
20年後・30年後の住宅ローンの金利状態を正確に見通すことは不可能です。
そのため、金利上昇リスクに備えて対策しておくことは欠かせません。
金利上昇リスクを避けたいなら、全期間固定金利タイプの住宅ローンを選ぶのも一つの選択肢です。
住宅ローンの3つの金利タイプ
住宅ローンは、以下の3つの金利タイプから選択することになります。
- 全期間固定金利:返済期間中の金利が固定されている
- 変動金利:定期的に金利が見直される
- 固定期間選択型金利:一定期間は固定期間となりその後は固定か変動かを選ぶ
それぞれの金利タイプごとにメリット・デメリットが異なるので、自分の返済スタイルに合った方法を選ぶことが大切です。
| 金利タイプ | メリット | デメリット |
| 全期間固定金利 | ・金利上昇リスクを避けられる ・長期的な返済計画を立てやすい | ・3つの中で最も金利が高い ・金利が下がっても返済額が変わらない |
| 変動金利 | ・3つの中で最も金利が低い ・金利が下がれば返済額も下がる | ・金利上昇リスクがある |
| 固定期間選択型金利 | ・一定期間の返済を固定できる ・固定期間終了後金利が下がれば返済額も下がる | ・金利上昇リスクがある ・変動金利の5年ルールや125%ルールが適用されないケースが多い |
※5年ルール:金利が見直されても返済額は5年間据え置かれる
※125%ルール:返済額が変動する場合でもそれまでの返済額の125%を超えない
なお、金融機関によっては借入額のうちの半分を変動金利、半分を固定金利にするといった商品が用意されているケースもあります。
全期間固定金利なら返済�完了までの返済額が確定する
全期間固定金利では、融資実行時に金利が決定するとその金利が最終返済まで固定されます。
期間中に金利が変動しないため、金利上昇リスクがありません。
さらに、融資時に最終返済までの額が確定するので、長期的な返済計画が立てやすいというメリットもあります。
ただし、全期間固定金利は他の金利タイプよりも金利が高くなります。
例えば、全期間固定金利であるフラット35の2024年10月の最頻金利が1.82%なのに対し、変動金利ではネットバンクで0.4%前後で借りられる住宅ローンも多くあります。
変動金利は金利上昇時に繰り上げ返済できる資金があれば不安になりにくい
変動金利は金利の低さが魅力ですが、金利が上がってしまうと返済の負担が大きくなる恐れがあります。
変動金利を選ぶ場合は、金利上昇リスクに備えておくことが大切です。
小まめに繰り上げ返済する、自己資金を蓄えておくなどして、金利上昇時には一括返済できるようにしておくと安心でしょう。
金利上昇時に固定金利への借り換えを検討する人もいますが、一般的に変動金利は固定金利が上がってから上昇するため、変動金利が上がる頃には固定金利も上がっている可能性が高くなります。
そのため、借り換えを検討しつつも返済資金の余力を貯えておくことが重要になるのです。
老後の住宅ローンに関する不安を解消するアドバイス
最後に、老後の住宅ローンに関する不安の解消法をみていきましょう。
結論:退職前に住宅ローンを完済する計画を立てる
住宅ローンの返済が退職後にも続くと老後資金を大きく圧迫します。
これを解決するには、退職前に住宅ローンを完済する計画を立てることが重要です。
多くの金融機関では、住宅ローンの完済時年齢を75歳~80歳に設定しています。
条件だけで考えれば、45歳で35年ローンを組むことも可能です。
とはいえ、80歳まで返済するローンの場合、70歳で定年となれば、残りの10年は収入減少のなか年金や預貯金で返済する必要があり、現実的には厳しいと言えるでしょう。
そのため、定年退職後も返済が続くローンを借りる場合、定年前に完済できるように計画を立てておくことが重要なのです。
繰り上げ返済の時期と金額を決めて資金を積み立てる
定年前に完済できるような条件で住宅ローンを組めれば問題ありませんが、すでに申し込んでいたり、年齢が高い、毎月の返済額を抑えたいなどで定年前に完済するプランが難しい場合もあるでしょう。
その場合は、無理なく返済できる期間で住宅ローンを組み、返済期間中に小まめに繰り上げ返済していくことが必要です。
繰り上げ返済は、金融機関によっては1万円ほどからでも受け付けているので、子どもが小さく教育資金がかからない期間など、余裕のある時期に活用していくとよいでしょう。
ただし、繰り上げ返済時には手数料がかかります。
あまりに小まめに繰り上げ返済すると手数料分損する恐れもあるので、時期や金額をあらかじめ決めて計画的に返済していくことをおすすめします。
住宅ローンの返済とは別に老後資金を貯めておくことも大切
繰り上げ返済も重要ですが、退職金で一括返済するなど、老後資金に大きく影響する返済の仕方には注意が必要です。
2019年に金融庁の金融審議会「市場ワーキング・グループ」が公表した報告書を発端とした「老後資金2000万円問題」が話題となりましたが、近年では老後に必要な資金は夫婦で5000万円に上るとも言われています。
住宅ローン返済を重視しすぎて老後資金が不足しないように、両方の資金を計画立てていくようにしましょう。
まとめ
住宅ローンに関するよくある不安の「審査」「返済」「金利」「老後」について、解消のアドバイスを解説しました。
審査の不安は審査基準を理解すること、返済の不安は長期的なシミュレーション、金利の不安は固定金利を検討すること、老後の不安は退職前に完済することで解消できる可能性があります。
住宅ローンの不安を解消したうえで、満足いくマイホームが購入できるようにしてください。