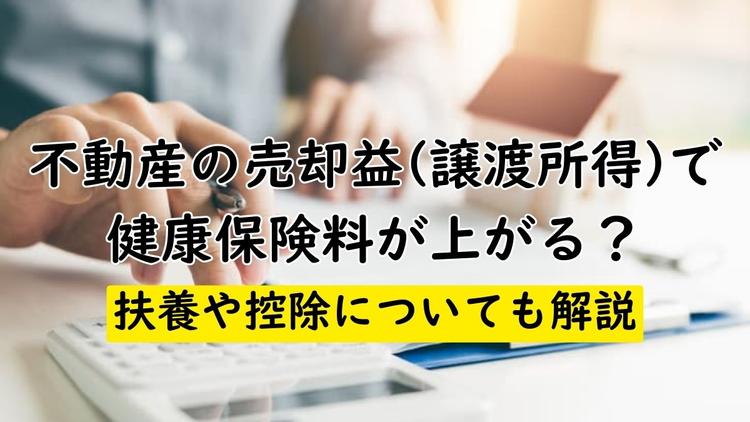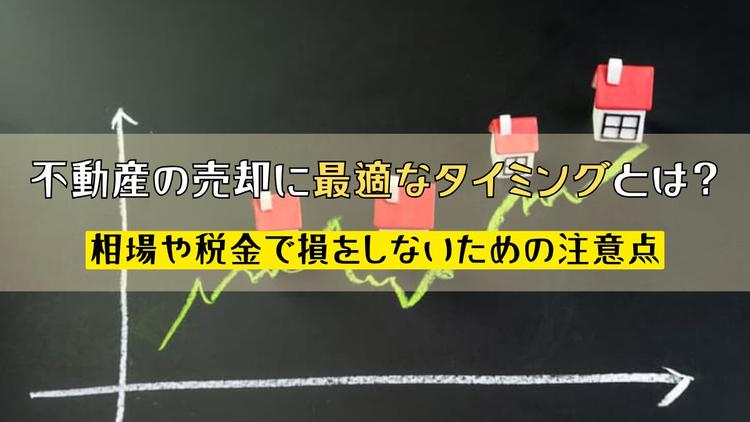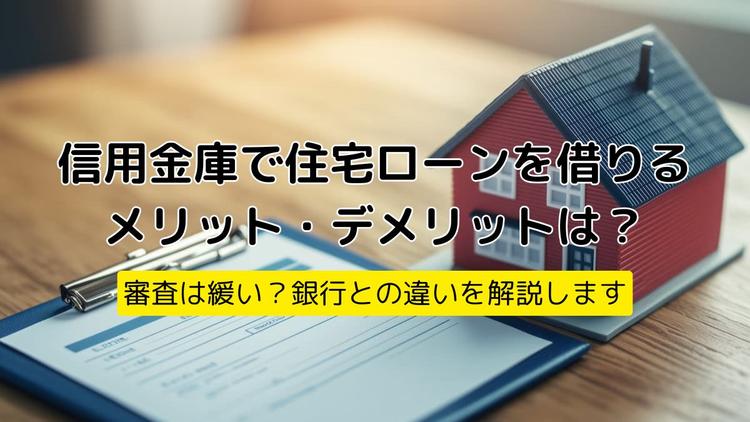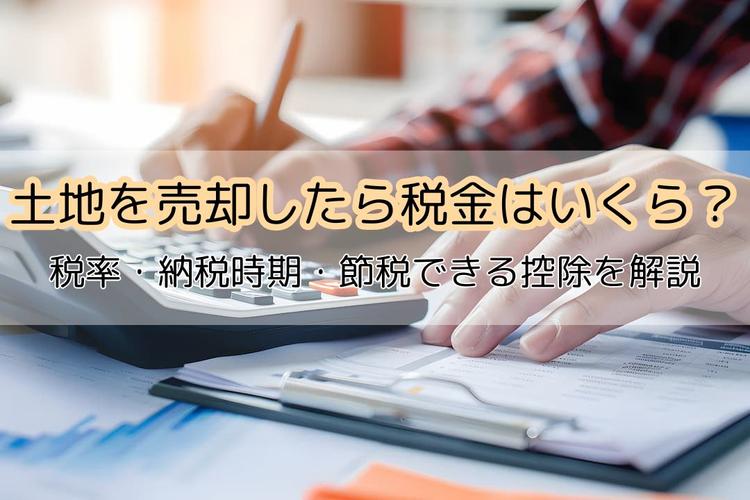不動産の売却で譲渡所得(売却益・譲渡益)があった場合、それに応じて所得税がアップすることは広く知られています。しかし、その影響が健康保険の保険料にまで及ぶことは意外と知られていません。
特に、国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入している個人事業主や自営業の方は、譲渡所得があると翌年の保険料が大きく増える可能性があります。
一方、会社員の場合は勤務先の健康保険組合が加入先となるため、本人の保険料が直接増えるケースは多くありません(ただし扶養の家族に影響する場合はあります)。
この記事では、不動産の譲渡所得が健康保険料にどのように影響するのかを解説し、会社員の方にも関係する控除制度や注意点について詳しく見ていきます。
健康保険料は何を根拠に保険料を定めているのか
不動産の売却益が本当に健康保険料に影響するのかを確認するには、そもそも保険料が何を根拠に定めているのかを知る必要があります。健康保険の種類ごとの保険料の算定根拠をみていきましょう。
健康保険の種類は3種類
健康保険は、大きく次の3種類に分類することができます。
- 健康保険……会社員が加入
- 共済保険……公務員が加入
- 国民健康保険……自営業者や団体に所属していない人が加入
保険料の算定根拠は何か
このうち、健康保険と共済保険は給与額に応じで保険料を定めていますから、不動産の売却による利益=譲渡所得があっても、保険料にはまったく影響しません。
つまり、会社勤めのサラリーマンの方は不動産の売却益が出ても、健康保険の自己負担額が上がる心配はありません(後述しますが、扶養家族に譲渡所得が出た場合には注意が必要です)。
一方、国民健康保険は所得額に応じて保険料が決められますから、不動産の譲渡所得も大きく関わってきます。
不動産の譲渡所得とは何か
それでは次に、不動産の譲渡所得とは何かを押さえておきましょう。
不動産の譲渡所得とは、不動産の売却によって得た利益のことです。次の計算式から算出します。
「取得費」とは、対象の不動産をかつて購入した時に要した費用のことです。「譲渡費用」とは、今回の売却で要した経費(仲介手数料や印紙税、登記手続きの費用など)のことです。
たとえば、かつて3,000万円で購入した不動産が今回5,000万円で売却でき、そのために200万円の費用を要したとすれば、譲渡所得は次のように計算します。
これにより譲渡所得は1,800万円となります。
取得費・譲渡費用として計上できる経費の詳細は、タックスアンサーを確認しましょう1。
なお、相続で自分名義になった物件など、取得費の正確な計算が難しい場合は、売却価格の5%を概算取得費として計上できます。
国民健康保険の保険料はどのように決まるのか
それでは、国民健康保険の保険料がどのように決められるのかについてみていくことにしましょう。
国民健康保険の保険料は基準総所得金額が基本
国民健康保険の保険料は、基礎分、支援金分、介護分に分かれています。設定金額は各都市ごとに異なりますが、ここでは参考までに、兵庫県神戸市の保険料算定基準を利用しています(料率は2025年度のもので記載)2。
| 区分 | 基礎分 | 支援金分 | 介護分 |
| 所得割 | 基準総所得額×7.74% | 基準総所得額×3.02% | 基準総所得額×2.67% |
| 均等割 | 被保険者1人につき 34,400円 | 被保険者1人につき 13,230円 | 被保険者1人につき 13,960円 |
| 平等割 | 1世帯につき 22,230円 | 1世帯につき 8,550円 | 1世帯につき 260,000円 |
| 最高限度額 | 66万円 | 26万円 | 17万円 |
このように保険料は、所得割、均等割、平均割の三階層から構成されています。このうち均等割と平均割は所得に関係なく、一定の金額を負担します。
一方で�所得割は「基準総所得金額」に保険料率を乗じます。このため、所得が増えると保険料が増える仕組みになっているのです。
基準総所得金額
基準総所得金額とは、前年の総所得金額等から基礎控除額(43万円)を差し引いた金額です。
総所得金額等には、給与所得や公的年金等の所得、事業所得、譲渡所得、一時所得などが含まれます(損失繰越控除適用前の金額で計算します)。
不動産売却で得た利益は「譲渡所得」に分類されます。
そのため、不動産を売却した翌年の確定申告では、次のように記入することになります。
- 個人事業主:事業所得+譲渡所得
- 会社員:給与所得+譲渡所得
→国民健康保険は会社員で社保に加入している方には関係ない内容ですが、不動産売却で利益が出た場合には会社員も確定申告が必要です。
▼関連記事:不動産の売却後に確定申告しないとどうなる?申告不要なケースや注意点を解説
譲渡所得は分離課税では?
ここで確定申告の経験のある人なら「不動産の譲渡所得は分離課税だから、事業所得とはリンクしないのではないか」と考える人もいるかもしれません。
たしかに確定申告書では、不動産の譲渡所得があった場合、通常提出する第一表、第二表に加えて第三表を提出して、税金は分けて算出をします。一般の所得税と合わせて計算をしてしまうと、累進課税を適用している現在の税制度では、一時的に膨大な税金が課せられることになるからです。
ところが、税金面では不動産の一時所得に対する配慮がなされているのですが、健康保険の保険料は、この税金の仕組みには一切連動しません。
次に示すのは、確定申告書Bの所得金額の欄です。
確定申告書B 所得金額
この合計金額が、総所得金額であり、ここから基礎控除の43万円を差し引いたものが、国民健康保険料の算定根拠となる基準総所得金額です。
不動産の売却により譲渡所得を得た場合は、「⑧総合譲渡・一時」に所得金額を記入します。これにより基準総所得金額が上がるため、ダイレクトに保険料に反映されるのです。
譲渡所得の保険料への影響をシミュレーションする
それでは、不動産で譲渡所得があった場合、どれくらい保険料に影響がでるのかシミュレーションをしてみましょう。
200万円の所得があった個人事業主が、500万円の課税譲渡所得があった場合、どれくらい保険料がアップするのかを検証します。
200万円の事業所得のみの場合
→ 医療:178,148円 + 支援分:69,194円 + 介護分:62,619円
→ 年間合計:約309,961円
→ 月額換算:約25,830円
→ 医療:178,148円 + 支援分:69,194円
→ 年間合計:約247,342円
→ 月額換算:約20,600円
事業所得+500万円の譲渡所得があった場合
医療分 565,028円 + 支援分 220,194円 + 介護分 196,119円
→ 年間合計:約981,341円
→ 月額:約81,778円
医療分 565,028円 + 支援分 220,194円
→ 年間合計:約785,222円
→ 月額:約65,435円
500万円の譲渡所得があると、翌年の国民健康保険料は大きく跳ね上がります。
しかし、自宅や相続した家の売却であれば、特例控除を使える場合が多く、譲渡所得がゼロ、または大幅に減額されるケースもあります。
この場合、国保料の増額もゼロ、またはわずかで済みます。
譲渡所得があった会社員の注意点
会社員の健康保険の保険料は、不動産の譲渡所得とはまったく連動しません。
しかし、扶養家族である配偶者が所有する不動産を売却して譲渡所得があった場合は、影響があるので注意が必要です。
扶養家族から外れることも
扶養家族の具体的な取り扱いは、各健康保険組合によって異なりますが、一般的には、
- 1年間の見込み年収が130万円以上(60歳未満の場合)
- 180万円以上(60歳以上または一定の障害がある場合)
- 被保険者の収入の2分の1以上
である場合、扶養から外れます。
一時的な収入増加であれば継続して扶養認定される場合もありますが、これは組合の判断によります。
翌年に再び扶養になるには、条件を満たしたうえで改めて申請が必要です。
国民健康保険に加入することになる場合もあり、その際は保険料の負担が発生します。
国民健康保険に加入することに
扶養家族から外れた期間は、市町村で国民健康保険の加入手続きをする必要があります。
前述の通り、保険料は譲渡所得を含めた基準で算定されますから、特例控除などを適用しない場合はかなりの高額負担になる可能性があるのです。
3000万円特別控除を活用しよう
いくら譲渡所得があったとはいえ、新たに保険料が発生すれば、家計にとって大きな負担となります。
そこで大きな力になるのが「居住用不動産の譲渡にかかる3000万円の特別控除」です。
マイホームを売却した場合であれば、譲渡所得からに3,000万円を控除することができますから、一�般的な住宅であれば、ほとんどの場合、譲渡所得はゼロ円になります。
これにより会社員の扶養家族を外れることはなくなります。また個人事業主においても、前年と大きく健康保険料が変わる事態を避けることが可能になります。
ただし、この制度はマイホームに限定されており、別荘や遠隔地の親が住んでいた不動産には適用されませんので注意が必要です。
▼関連記事:マイホーム売却時の特例「3000万円控除」とは?
年金の減額や支給停止はない
不動産売却時の譲渡所得によって収入が発生しても、国民年金や厚生年金の支給が停止されることはありません。
ただし、障害年金と後期高齢者の国民保険料に影響することがあります。
3,000万円の特例控除を利用すれば社会保険料の増額等を回避できることがあるので、年金受給中で家の売却を検討している方は、税理士などの専門家に相談してみましょう。
▼関連記事:不動産売却で利益が出ても年金支給の停止や減額はないけど、社会保険料の増額等の影響が及ぶ可能性あり
まとめ
不動産の売却による譲渡所得は、所得税の算出においては、分離課税とすることで大きく軽減されていますが、保険料の算出においては、譲渡所得がそのまま反映されることになります。
そのため、翌年の保険料が大幅にアップして、家計を圧迫する事態も十分に想定できます。不動産の売却に際しては、所得税ばかりでなく、保険料への影響も十分考慮して必要になる資金を確保しておくことが重要です。
また、マイホームを売却して譲渡所得が出た場合は「居住用不動産の譲渡にかかる3000万円の特別控除」を活用することで、保険料への影響を回避することができます。
不動産の売却に際しては、保険料への影響も事前に確認しておきましょう。
▼関連記事:不動産売却時にかかる税金について解説