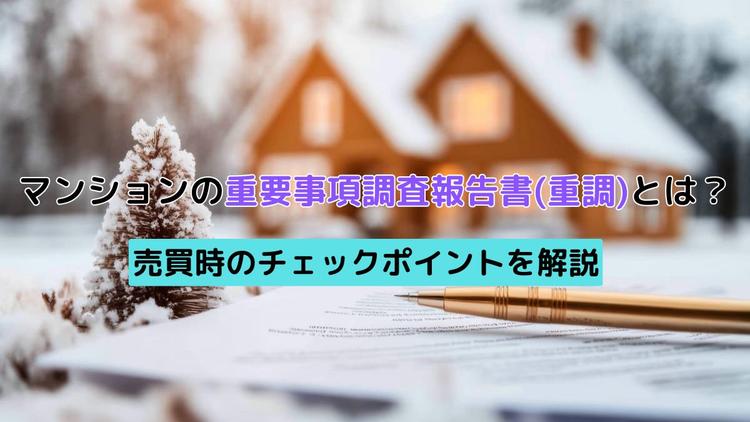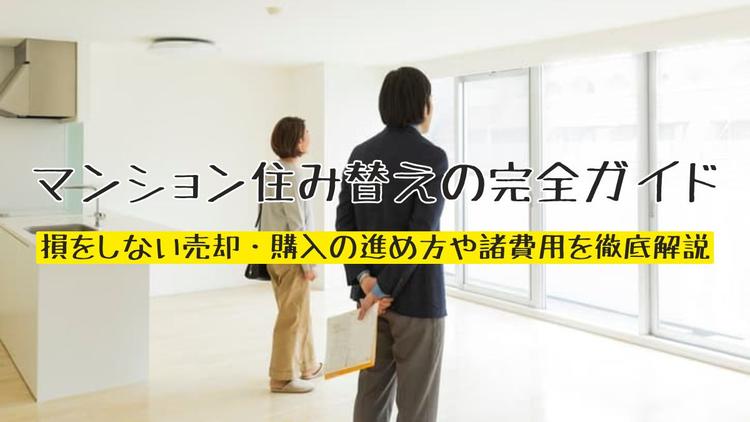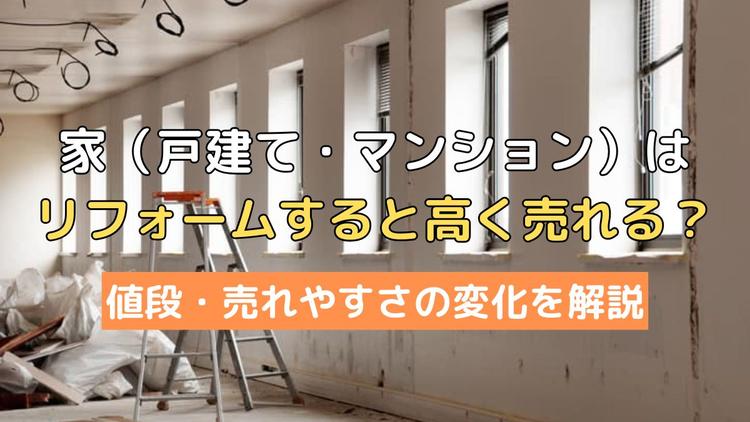「空き部屋を民泊として運営したい」と思ったとき、最初に立ちはだかる壁が「分譲マンションであること」です。
民泊を始めるには、「住宅宿泊事業法(いわゆる民泊新法)」「旅館業法」「特区民泊」のいずれかの制度をクリアする必要があります。
ただし、それ以前にマンションの管理規約と管理組合の同意を得なければ、民泊の手続きは一歩も進められません。
この記事では、分譲マンションで民泊を運営するにあたり、必要な許可や、管理組合や行政に確認すべきポイントについてを解説します。
民泊とは何か
民泊とは「住宅を使って旅行者を短期的に受け入れる有償の宿泊サービス」です。
2018年に施行された住宅宿泊事業法(いわゆる民泊新法)により制度化され、年間180日以内の営業なら、許可ではなく届出だけで運営できます。
民泊は「住宅を前提」とする点が、365日営業できるホテルや旅館(旅館業法)と大きく異なります。
また、通常の賃貸借契約では借主が長期居住することが前提ですが、民泊は数日だけ滞在する不特定多数が出入りするため、騒音・ごみ・セキュリティなど、住民との間でトラブルが起こりやすいのが特徴です。
民泊を運営できる3つの制度
民泊を始めたいと思ったとき、まず知っておくべきなのが「民泊は1つの制度ではない」という点です。
日本には、民泊に該当する仕組みが複数存在しており、それぞれ法律上の根拠や運営条件、行政への手続きが異なります。
ここでは、民泊を合法的に運営するための主な制度を3つに分類し、それぞれの特徴を解説します。
住宅宿泊事業(民泊新法)
最も一般的な制度が、2018年に施行された住宅宿泊事業法、いわゆる「民泊新法」です。
この法律により、住宅を活用した宿泊サービスが届出制で認められ、誰でも比較的簡単に参入できるようになりました。
この制度では、個人や法人が都道府県(または政令指定都市・中核市など)の行政窓口に対し、住宅宿泊事業の届出を行うことで営業が可能になります。
ただし、年間の営業日数は180日以内に制限されており、「週末だけ」「長期休暇中だけ」といった副業的な運営に向いています。
届出にあたっては、建物の用途や構造、消防法への適合、近隣住戸への事前説明など、いくつかの条件をクリアする必要があります。加えて、2カ月ごとに宿泊実績を報告する義務もあり、「簡易な制度」とはいえ、継続的な管理が欠かせません。
なお、マンションなどの共同住宅で運営する場合は、「管理規約との整合性」も重要な確認事項となります。
管理組合が民泊を禁止している場合、たとえ行政の届出が受理されたとしても、実際の運営ができないことに注意が必要です。
旅館業法に基づく許可制民泊(簡易宿所・ホテル営業)
2つ目の制度は、旅館業法に基づいて「簡易宿所」や「ホテル・旅館営業」の形で民泊を行う方法です。
この方法では、構造基準や消防設備、玄関帳場(フロント)の設置など、厳格な要件を満たす必要があるため、分譲マンションの一室では物理的にも制度的にも対応が困難です。
さらに、こうした営業形態はほとんどのマンションの管理規約に違反しており、管理組合の承認もまず得られません。
制度上は申請可能でも、実務上はほぼ不可能であり、一般的な分譲マンションでは選択肢から除外すべき運営形態といえるでしょう。
国家戦略特区による特区民泊
3つ目の制度は、特定の地域でのみ導入されている「特区民泊」です。
これは、国家戦略特区として指定された区域内で、各自治体が独自の条例を設けて民泊を認めるものです。代表的な地域としては、東京都大田区や大阪市、大阪府の一部区域などがあります。
特区民泊の大きな特徴は、自治体ごとに営業日数やその他の要件を柔軟に定められる点です。たとえば、大田区では当初「最低2泊以上」といったルールが設けられていましたが、条例改正によって見直しが進んでいます。
このように、特区の中では、住宅宿泊事業法とは別のローカルルールが適用されるため、該当区域での運営を検討している場合には、自治体の窓口で詳細を確認することが不可欠です。
分譲マンションならではのハードル~管理組合への確認
民泊の制度や法令を理解したうえで、いざ自分の所有するマンションの一室で民泊を始めようとすると、次にぶつかるのが「分譲マンション特有の規制や合意形成の難しさ」です。
戸建住宅や一棟所有のアパートとは違い、分譲マンションは多数の区分所有者が共用部分を共同で管理しているため、民泊の運営が他の住民の生活に直接的な影響を与えることになります。
この章では、分譲マンションで民泊を運営する際に生じる主なハードルについて解説します。
「住宅専用」の管理規約
まず確認すべきは、管理規約の中にある「用途制限」の条項です。多くの分譲マンションでは、「専有部分は専ら住宅として使用するものとする」といった記載があります。
この「専ら住宅として使用」という文言は、弁護士や判例の解釈��においても、「一時的な宿泊を反復継続的に提供する民泊」はこの用途に含まれないとされています。つまり、事務所や宿泊施設として使うことを原則として認めないという意味です。
この条項がある限り、民泊は規約違反にあたる可能性が極めて高く、たとえ行政に届出を行っても、マンション内での営業は困難です。民泊を正式に認めてもらうには、規約そのものの改正が必要になります。
規約改正のハードル
管理規約の変更には、区分所有法で定められた「特別決議」が必要で、これは所有者の人数および議決権(持分)の「各4分の3以上」の賛成が求められます。
単に人数の多さだけでなく、持分割合も考慮されるため、非常に厳しい条件なのです。
また、たとえ民泊を容認する空気が一部にあったとしても、住民から「見知らぬ人が日々出入りするのは不安」「治安や騒音が心配」という声が上がることも少なくありません。
マンションの居住者は家族や高齢者も多く、全体の理解を得るには時間と丁寧な説明が不可欠です。
理事会・総会での説明義務と調整
民泊を検討している場合、まずは管理組合の理事会に事前相談するのが一般的な流れです。
その後、理事会が議案を整理し、総会において説明と審議が行われます。
- 理事会:管理組合の中から選ばれた少人数の理事が集まり、日常的な運営や議案の事前検討などを行う機関です。
- 総会:すべての区分所有者が参加する場で、重要な事項の最終決定を行う最高意思決定機関です。
民泊のように管理規約の変更や新たなルール策定を伴う内容は、まず理事会で検討・整理され、その後、総会で正式に審議・決議されるという流れになります。
とくに、管理規約の改正や運営ルールの策定には、次のようなステップが必要になります。
- 民泊の営業形態(住宅宿泊事業・旅館業許可など)を明示すること
- 衛生・防災・セキュリティ対策を具体的に提示すること
- ゴミ出しや騒音防止など、居住者への配慮を明文化した運用ルール(ハウスルール)を示すこと
- 緊急連絡先や管理責任者の設置など、事故やトラブル発生時の対応体制を整備すること
このように、単に「やりたい」と表明するだけでは到底認められません。
理事会や総会で住民の納得を得るには、民泊の社会的意義や地域への波及効果だけでなく、具体的なリスク対策を文書で示し、粘り強く説明することが求められます。
共用部利用に関する制限
民泊運営では、来訪者が建物のエントランス、エレベーター、共用廊下といった共有スペースを日常的に通行することになります。
こうした共用部分の利用については、たとえ専有部分の使用が認められたとしても、別途のルール作成や理事会の承認が必要になるケースがあるでしょう。
また、オートロックの開錠方法や鍵の受け渡し、監視カメラの運用方針など、防犯上の配慮も不可欠です。場合によっては、共用部にスマートロックや監視機器を新�設する必要があり、その際には管理組合による承認と費用負担の議論が発生します。
管理会社との契約条項
マンションによっては、管理組合と管理会社の間で締結された契約書に「宿泊施設としての利用は禁止」と明記されている場合があります。
管理会社は、共用部分の清掃や防犯対応、トラブル時の一次対応などを担っているため、民泊利用が増えるとその負担が大きくなると考えられがちです。
このような契約上の制限が、民泊運営にとっては壁となります。そのため、民泊を始める前には管理会社の意向も含め、事前に確認しておくことが重要です。
▼関連記事:空き部屋のマンションはどう活用できる?事例を紹介します
行政に確認すべきポイント
分譲マンションで民泊を始めるにあたり、管理規約や組合の承認と並んで重要なのが、行政への事前確認です。
民泊新法(住宅宿泊事業法)では「届出制」が採用されていますが、形式的に届出を出せば誰でも営業できるというわけではありません。
地域ごとに異なる条例、消防法や建築基準法の適合性など、場所と建物の状況に応じた個別の確認事項があります。
ここでは、実際に民泊の届出を行う前に、行政に確認すべき代表的な項目を紹介します。
所在地の所管窓口と条例の有無
民泊の届出先は、原則として物件所在地を管轄する都道府県です。
しかし、政令指定都市や中核市などの人口が多く大きい都市では、市区町村が窓口になるケースがあります。
まずは、自分の物件所在地の担当窓口がどこかを確認し、可能であれば事前相談の予約を取りましょう。
あわせて、自治体が独自に定める「上乗せ条例」の有無を確認することが不可欠です。
たとえば、
- 営業日や曜日の制限(例:住居専用地域では平日の営業不可)
- 最低宿泊日数(例:2泊以上からのみ可)
- 周知義務の強化(例:全階住戸への事前説明を義務化)
といった内容が自治体によって異なり、国の制度とは別に制限されていることがあります。
上乗せ条例が厳しいエリアでは、実質的に民泊運営が困難な場合もあるため、制度上可能でも、地域的に不可能なケースがあることを念頭に置いておきましょう。
建物の用途地域と建築基準法の適�合
民泊は「住宅を使った宿泊サービス」であるため、住宅地として認められている地域(用途地域)でなければ営業が制限されることがあります。
たとえば、第一種低層住居専用地域では、民泊を全面的に禁止する自治体もあります。商業地域や準住居地域などでは比較的柔軟ですが、用途変更が必要な場合もあります。
また、建物そのものが「共同住宅」として建築確認を受けているか、「寄宿舎」や「簡易宿所」としての利用に適合しているかどうかを、建築指導課で事前確認しておくと安心です。
200平方メートルを超える規模になれば、建築確認申請(用途変更)が必要となる可能性があります。
消防法令の適合と必要設備
民泊を始めるには、管轄の消防署による法令適合確認が必要です。
宿泊施設とみなされる以上、住宅よりも厳しい防火基準が適用されます。
具体的には、次のような対応が必要になります。
- 火災報知器の設置
- 避難経路図の掲示
- 誘導灯・消火器の設置
- 非常口の確保と照明
これらは物件の構造や規模によって異なるため、消防署への事前相談は必須です。相談の際は、建物の図面や部屋のレイアウトを持参すると、より正確な指導が受けられます。
なお、消防法令適合通知書は、届出時に添付書類として求められるケースが多いため、行政手続きの前提条件のひとつと考えてください。
騒音・苦情対応体制の整備要件
自治体によっては、民泊営業に際して苦情対応の責任者の明示を求めたり、24時間対応可能な連絡体制を整えるよう指導している場合があります。
また、物件周辺で過去にトラブルがあった場合、次のような説明や対応を求められることもあります。
- 管理責任者の名前・電話番号を宿泊者向けに掲示
- 緊急連絡先の自治体への登録
- 近隣住民からの通報受付体制の構築
こうした項目は、届出審査時や営業後の指導で確認されることもあるため、あらかじめ整備しておくとトラブルを防げるでしょう。
近隣住戸への事前説明義務
住宅宿泊事業法では、届出前に「近隣住戸への事前周知」が義務付けられています。
説明対象は、両隣や上下階の住戸、場合によってはフロア全体やマンション全体とされる場合もあり、自治体によって求められる範囲や記録形式が異なります。
説明の際には、民泊の営業内容、対応体制、連絡先などを明記した書面を作成し、配布または掲示するのが一般的です。
さらに、説明の日時・方法・対象者を記録しておき、届出時に提出できるように準備しておくことが重要です。
まとめ
分譲マンションで民泊を始めるには、法律より先に「管理規約」と「管理組合の同意」という大きな壁を越える必要があります。
たとえ住宅宿泊事業法(民泊新法)で届出をすれば営業できる制度であっても、マンションの規約で「住宅以外の用途を禁止」とされていれば、民泊は認められません。
管理規約の改正には、所有者と議決権の各4分の3以上の賛成が必要と、非常に高いハードルです。
行政への届出に関しても、地域によっては条例で営業日や説明範囲が独自に定められており、建築基準法や消防法への適合も求められます。さらに、運営後も騒音、ごみ出し、共用部の使用など、住民トラブルを未然に防ぐための配慮が不可欠です。
民泊は空き部屋の有効活用であると同時に、「共同住宅という生活空間の中で信頼を築く事業」です。
制度と管理ルールの両方を正しく理解し、丁寧に準備を重ねることが成功の鍵となるでしょう。
▼関連記事:マンションは売るか貸すかどっちがお得?