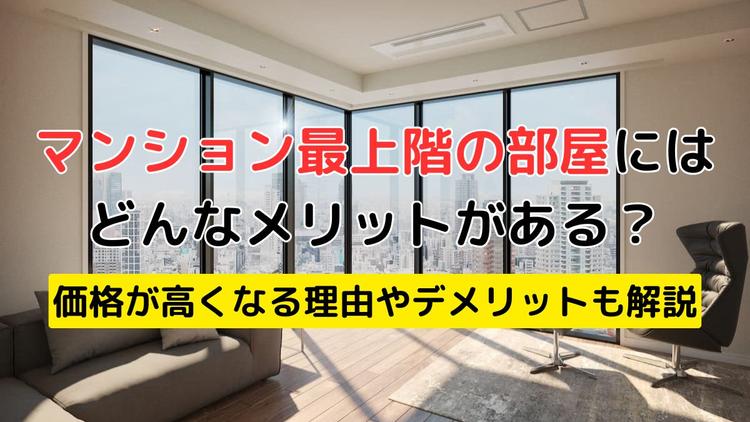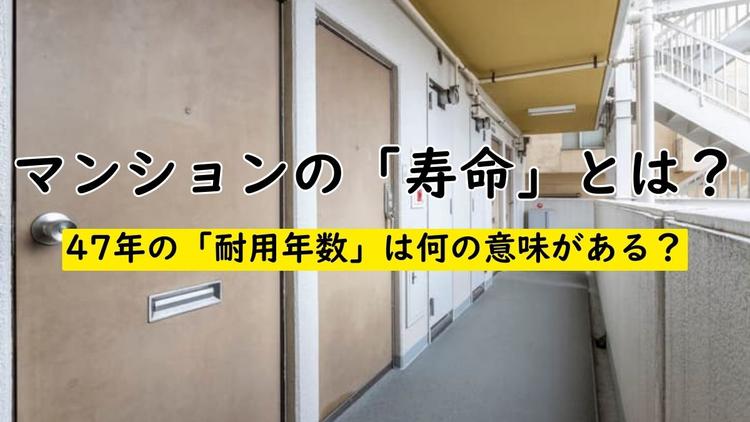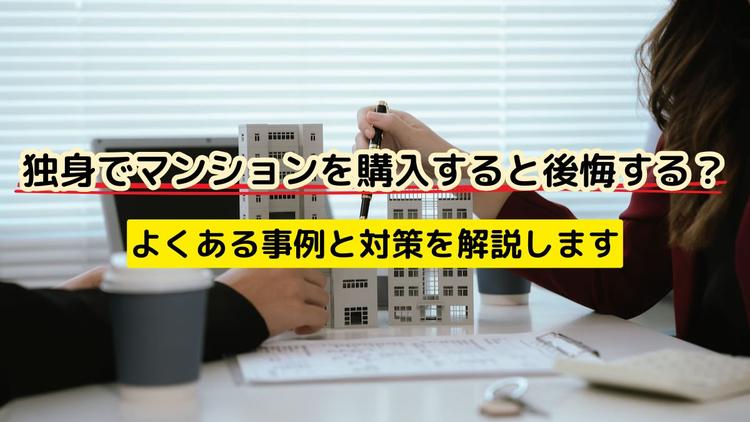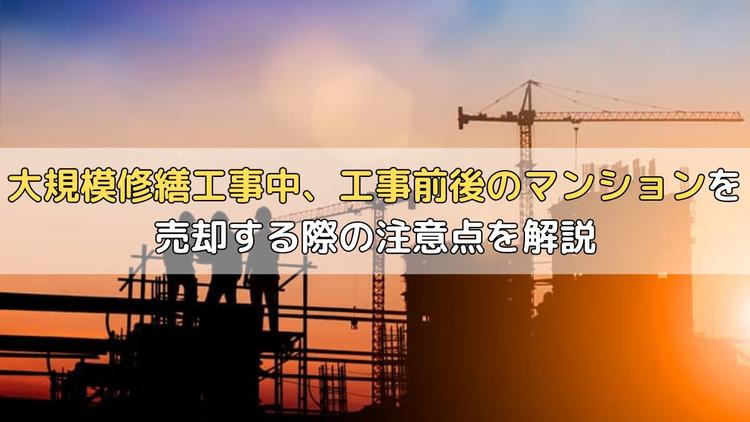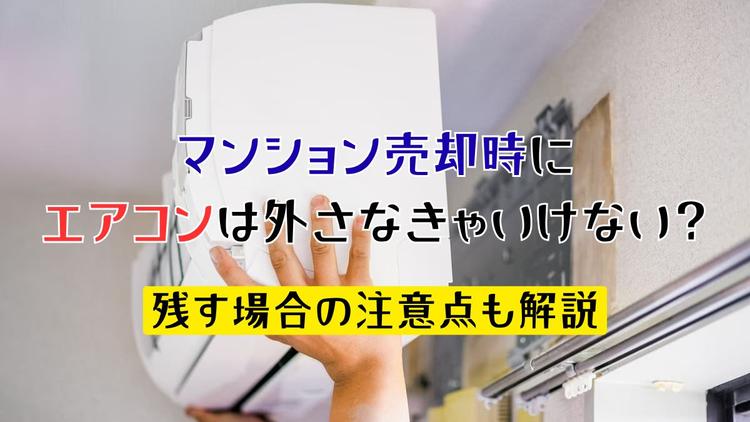マンションの耐震等級とは、大地震に対して耐えられる強度を3段階で等級表示したものです。
マンションの売却においては、耐震等級の有無が価格に大きく影響することもあり、重要な指標のひとつとされています。
この記事では、マンションの耐震等級について詳細を明らかにするとともに、耐震等級の調べ方や耐震基準との違いについて解説します。
耐震等級とは
耐震等級とは、「住宅品質確保促進法(品確法)」が定める「住宅性能表示制度」に基づいて、地震に対する建物の強度(耐震性)を示す指標のひとつです。
法律に基づいて客観的に評価される「住宅性能評価書」の中の10分野のうち、「構造の安定に関すること」の項で、地震の力がどの程度大きくなるまで傷や損傷を発生しないかを等級表示しています。
- 耐震等級1: 現行の建築基準法を満たす最低限の耐震性能で、おおむね震度6強~7程度の大規模な地震でも倒壊・崩壊しない耐震性能
- 耐震等級2: 耐震等級1の1.25倍の耐震性能
- 耐震等級3: 耐震等級1の1.5倍の耐震性能
耐震等級には1~3の段階があり、耐震等級3が最も耐震性能が高い建物です。
耐震等級1
耐震等級1は、建築基準法で定める新耐震基準に適合した建物です。
したがって1981年に建築基準法が改正されていることを踏まえると、現在の新築マンションは全て耐震等級1以上の認定を受けられる耐震性能があります1。
震度6強~7といった大規模な揺れが発生しても、倒壊や崩壊しません。また、それ未満の揺れが発生した際は、構造躯体に損傷を与えない性能を有しています。
耐震等級1であっても、耐震性が劣るわけではなく、通常の生活の範囲において耐震性は十分に確保されています。
耐震等級2
耐震等級2は、数百年に1度といった極めて稀に発生する地震(震度6強~7を想定)による力の1.25倍の力に対して倒��壊や崩壊をしない建物です。また、数十年に1度程度の地震(震度6弱以下を想定)による力の1.25倍の力に対しては、構造躯体に損傷を与えない性能を有しています。
長期優良住宅の認定を受けるためには、耐震等級2以上が条件になります。
耐震等級3
耐震等級3は、数百年に1度といった極めて稀に発生する地震による力の1.5倍の力に対して倒壊や崩壊をしない建物です。また、数十年に1度程度の地震による力の1.5倍の力に対しては、構造躯体に損傷を与えない性能を有しています。
高い耐震性能を有していることから、地震保険の耐震等級割引として50%の割引が適用されます。
マンションの耐震等級の状況
一般社団法人 住宅性能評価・表示協会によると、新築マンションの耐震等級の内訳(令和4年度)2は、次のとおりです。
- 等級1……75,224戸(89.1%)
- 等級2……1,098戸(1.3%)
- 等級3……4,300戸(5.1%)
- 評価対象外……3,810戸(4.5%)
9割近くのマンションが等級1の認定を受けており、それ以上の等級を受けているのは1割に満たないことが分かります。
耐震基準と耐震等級の違いとは
耐震基準は、建築基準法で定めた基準です。地震に対して最低限クリアすべき構造強度を規定しています。耐震基準は何度も改正が繰り返されており、新築するすべてのマンションは最新の建築基準法が定める耐震基準に適合しなければなりません。
耐震基準は、大地震が発生したときに即座に建物が崩落・倒壊して命が奪われることがないようにするための基準です。
地震に遭っても何の影響も受けずそのまま住み続けられることを保証するものではありません。つまり、一定のひび割れや歪みが生じる可能性はあるが、そこに住む人の命を奪うまでの崩落は生じないということです。
一方の耐震等級は、等級1から等級3までの3段階で表され、現行の耐震基準で建てられた建物は耐震等級1とみなされます。
耐震等級は第三者機関の審査を受けることで認定される制度ですが、任意の制度なので認定を受ける義務はありません。
新耐震基準とは
新耐震基準が施行されたのは、1981年(昭和56年)6月1日です。
耐震基準は、1950年の建築基準法施行時にすでに制定されていましたが、大地震が発生するたびに被害の状況を踏まえて見直されてきました。そして、1981年には耐震設計を根本的に塗り替える大きな改正がおこなわれたのです。
1978年の宮城県沖地震の甚大な被害から教訓を得た1981年の改正は、耐震基準の節目ともいえます。耐震設計の考え方が大きく異なることから、一般的に1981年5月31日までの基準を「旧耐震基準」、同年6月1日以降の耐震基準を「新耐震基準」と呼んでいます。
具体的には、建築確認済証の交付が同年5月31日以前であれば旧耐震基準、6月1日以降であれば新耐震基準の建物になります。
新耐震基準が耐えられる地震の強さ
旧耐震基準では、数十年に一度発生するような震度5程度の中規模の地震には耐えられるものの、それ以上の大地震に対しては倒壊する可能性がありました。
一方、1981年に施行された新耐震基準では、震度5程度の中地震では躯体の軽�微なひび割れ程度にとどまり損壊しません。さらに数百年に一度の震度6強程度の大地震であっても倒壊・崩落して人が押しつぶされることなく、命を守れるだけの耐震性を備えるようにしています。
旧耐震基準と新耐震基準の違い
旧耐震基準では中地震への考慮がされていましたが、新耐震基準では、中地震に加えて大地震にも耐えられるよう、一次設計と二次設計の2段階で耐震計算がおこなわれるようになったのが大きな特徴です。
まず一次設計において中地震対策として、家の機能を損なわないよう柱や梁、壁などを強化し変形を抑えます。次に二次設計で大地震対策として、柱や梁などが変形しても倒壊・崩落しない粘り強さを持たせ、人命を保護できる構造になるよう構造計算をします。
現行の耐震基準(2000年基準)とは?
1995年の阪神・淡路大震災を受け、建築基準法は2000年にさらに大きな改正がおこなわれました。この耐震基準は現在の基準であり、「現行の耐震基準」や「2000年基準」と呼ばれています。
現在、建物を新築する場合には、現行の耐震基準(2000年基準)が適用されます。
新耐震基準と現行の耐震基準(2000年基準)の違いは?
現行の耐震基準(2000年基準)では、新耐震基準からさらに規制強化がされています。一次設計の段階から、中程度の地震に柱や梁などの主要構造部が耐えられるように構造計算をします。
そのうえで二次設計では、大地震に対して倒壊・崩落しないよう、建物の構造種別や規模別に3つのルートに分けて構造計算するといった詳細な検討が求められているのです。
これにより現行の耐震基準(2000年基準)で建てられたマンションは、それまでの新耐震基準で建てられたマンションよりも、さらに高い耐震性を有しています。
もちろん従前の新耐震基準でも強力な耐震性能を有しています。実際に、1995年に発生した阪神・淡路大震災(最大震度7)では、被害が多かった建物は旧耐震基準の建物であり、新耐震基準の建物の多くは倒壊等の被害を免れました。
新耐震建物は築25年超でも住宅ローン控除は可能
住宅ローン控除には、築年数に関する要件が定められています。
従前の制度では、住宅ローン控除を適用するには、マンションは築年数が25年以内とされていました。この条件に合わない場合は、耐震基準適合証明書を提出して耐震性能を証明する必要があったのです。
しかし、2022年にこのルールが緩和されて、「登記簿上の建築日付が1982年(昭和 57 年)1月1日以降の家屋」であれば築25年超のマンションでも買主が住宅ローン控除等を利用できるようになっています。
現在は、築25年超のマンションでも1982年以降に建築された物件であれば住宅性能評価書等がなくても住宅ローン控除が適用できるので、中古マンションの売買の活性化が期待できます。
マンションの耐震等級の調べ方・確認方法
耐震等級は住宅性能評価書に表示される指標であることから、耐震等級を知るにはマンション全体で住宅性能評価書を取得していることが前提になります。
住宅性能評価書は新築と中古で調べ方が2種類がありますので、それぞれの調べ方を説明しましょう。
新築マンションの調べ方
新築の場合、マンシ�ョン開発事業者が住宅性能評価書を取得していれば、耐震等級がわかります。住宅性能評価書を取得しているマンションは、販売を促進する効果があるので、ほとんどの物件で分譲パンフレットに耐震等級を記載しています。
中古マンションの調べ方
中古マンションの場合、管理組合が住宅性能評価書を取得していれば、耐震等級を知ることができます。
しかし、マンション全体で住宅性能評価書を取得していないのであれば、耐震等級はわかりません。
国土交通省によると、住宅性能表示制度における設計住宅性能評価書の交付割合は、令和5年度で新設住宅着工戸数に対する32.8%です。
マンションでも住宅性能評価書を取得していないケースが多く、その場合耐震等級はわかりません。
管理組合に確認する
住宅性能評価書を取得しているマンションは、管理組合で住宅性能評価書を保管していることが一般的です。
耐震等級を知りたい場合には、まずは管理組合に住宅性能評価書を取得しているかどうかを確認してください。
耐震等級で受けられるメリット
耐震等級があることで、次の2点の特典を得ることができます。
- 地震保険の耐震等級割引
- フラット35の低金利適用
地震保険の耐震等級割引
地震保険は、耐震等級を有することで次のような割引制度が適用されます。
- 耐震等級1 ……10%
- 耐震等級2…… 30%
- 耐震等級3……50%
- 耐震診断割引(耐震診断または耐震改修の結果、新耐震基準を満たす建物)……10%
割引の適用に際しては、品確法に基づく登録住宅性能評価機関により作成された書類のうち、対象建物の耐震等級を証明した書類(コピー)の提出が求められます。
住宅性能評価書を取得していなくても、1981年6月1日以降に新築されたマンションであれば新耐震基準で設計されているので、住宅性能評価書がなくても耐震等級1と同等として扱われ、10%の割引が適用されます。
フラット35の低金利適用
耐震等級2または3のマンションは、一定期間金利を引き下げる制度であるフラット35Sが利用できます。
フラット35Sの金利プランと適用対象マンションは次のとおりです。
- 耐震等級3の新築マンション……金利プランA
- 耐震等級2の新築マンション……金利プランB
- 耐震等級2以上の中古マンション……金利プランA
金利プランの割引期間と割引利率は、申し込み受付期間によって変動します。2025年3月31日までに申し込みを受け付けた場合、当初5年間は金利の引き下げが適用されます。金利プランAで年0.5%、金利プランBで年0.25%が引き下げられます。
旧耐震基準のマンションはどうする
マンションが新耐震基準なのか、それとも旧耐震基準なのかは、マンションが建てられた経緯を確認することでわかります。
建築確認通知書(1999年5月1日以降は確認済証)の発行日が、1981年6月1日以降であれば新耐震基準で設計されたマンションです。建築確認通知書とは、建築基準法に基づいて申請された建築確認申請書が建築基準法に適合していることを確認した後に交付される書類のことです。
マンションの耐震性能を確認する
旧耐震基準のマンションが新耐震基準で定められた耐震性�能を有しているか否かは、「耐震診断」を行うことで確認できます。耐震診断の結果は、賃貸や売買の取引時に物件の内容や取引条件について説明する重要事項説明の項目に含まれます。
耐震診断の実施は、管理組合で検討したうえで決定します。
実施に際しては、その費用を予算化する必要があります。費用は建物の規模や構造、診断の内容などによって異なるため、事前に見積の取得は欠かせません。
耐震診断の結果、耐震性がないと判断された場合には、資産価値に大きな影響を及ぼすかもしれません。
耐震性の不足が確認された場合、取るべき対策を管理組合で検討することになります。
耐震性が不足することが判明したマンションの対策の選択肢として次の3種類が想定できます。
- 耐震改修を実施する
- 新しいマンションに建替える
- マンション敷地売却制度を利用して売却する
それぞれ具体的にどのようなことなのか説明していきましょう。
耐震改修を実施する
耐震改修は地震の揺れに対して弱い部分を補強することをいいます。
耐震診断を行った結果、マンションの耐震性が脆弱(ぜいじゃく)であると診断された場合に、新耐震基準で建てられた建物と同程度の耐震性を確保するために行います。
耐震性が不足しているマンションにおいても、耐震改修を実施するには、マンション管理組合総会での決議が必要です。
共用部分の耐震改修は、耐震改修促進法(建築物の耐震改修の促進に関する法律)の特例により、特別決議ではなく普通決議で実施可能です。普通決議は過半の賛成で成立します。
ただし、�区分所有法の規定により、特別な影響を受ける区分所有者の承諾が必要になります。耐震改修では、外壁にブレース(筋交い)を設置する方法がよく採用されますが、これをベランダに設置するのであれば、そのベランダの専用使用権がある区分所有者の承諾がないと、工事は実施できません。
新しいマンションに建て替える
耐震性が不足している場合、現在のマンションを解体し、新しいマンションに建て替えることも選択肢のひとつとなります。
マンションの建て替えは、区分所有者の5分の4以上の賛成があれば決定できます。しかし、建て替え工事期間中、居住者は仮住まいへ引越さなければなりません。
しかも住宅ローンが残っている場合、返済と家賃の二重負担になります。そのため、必要な賛意を得ることは容易ではありません。
なお、建替え合意後の進め方として、マンション建替円滑化法による「権利変換方式」と「等価交換方式」があります。それぞれの方式にはメリット・デメリットがあり、管理組合の選択が必要になります。
権利変換方式
現行のマンション所有者が、新築マンションにおける新たな区分所有権を取得する仕組みです。
仕組み
- 旧マンションの区分所有者は、持分に応じて新築マンションの区分所有権を取得
- 持分の評価は、旧マンションの評価額や占有面積、立地条件などを基準に算出
- 現金での追加負担が必要になる場合もあるが、従来の所有権に応じた権利を取得できる
メリット
- 現金負担を抑えつつ新築マンションを取得できる
- 所有者間の公平性が確保されやすい
- 円滑化法に基�づくため、法的手続きが明確
デメリット
- 新築マンションの専有面積や間取りが旧マンションと完全に一致しない場合がある
- 現金負担が発生する可能性がある
- 権利変換の内容や評価方法に不満を抱く所有者がいると合意形成が難しくなる
等価交換方式
マンションの建て替えにあたって、デベロッパーが所有者の建物や土地の権利を取得し、その対価として新築マンションの区分所有権を提供する仕組みです。
仕組み
- 土地や建物の権利を所有者がデベロッパーに提供し、その価値に応じて新築マンションの一部を受け取る
- 土地や建物の評価額に基づき、追加負担なしで新築の住戸を取得できるケースもある
- 不足する価値分については、現金の支払いで調整することもある
メリット
- 建築資金をデベロッパーが負担するため、区分所有者の現金負担が少ない
- デベロッパーの関与により、計画が進みやすい
- 新築マンションの品質や設計において専門性が確保されやすい
デメリット
- 土地や建物の権利を譲渡するため、所有者側の自由度が低くなる
- 新築マンションが完成するまでの間、仮住まいの費用や条件に不安が生じることがある
- デベロッパーとの交渉が複雑になる可能性がある
▼関連記事

マンション敷地売却制度を利用して売却する
マンション敷地売却制度は、総会の決議によって建物と敷地を一括して売却する仕組みです。建替え後の建築計画に制約がないので、マンション以外の建物も建築することが可能です。そのため、マンションへの建替えに比べて、区分所有権の評価が高くなることががあります。
マンション敷地売却制度を利用するには、行政による「特定要除却認定」と「買受計画の認定」を受ける必要があります。耐震性の不足は、認定要件のひとつに含まれています。
その後実施するマンション敷地売却決議は区分所有者、議決権、敷地利用権の持分価格の各5分の4以上の賛成で成立します。
まとめ
耐震等級の取得は義務ではありませんが、耐震等級の表示はマンションの販売に有利になる効果があります。
耐震等級を有するマンションは、地震保険の割引やフラット35の金利割引のメリットがあります。
マンションの売買時には、耐震等級もチェックしておくのが良いでしょう。