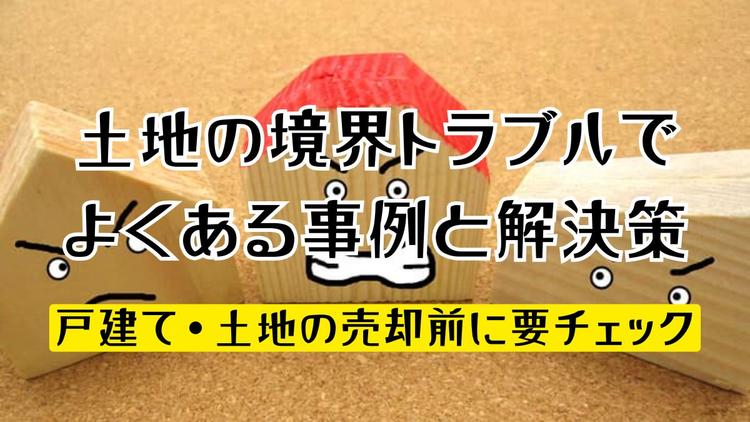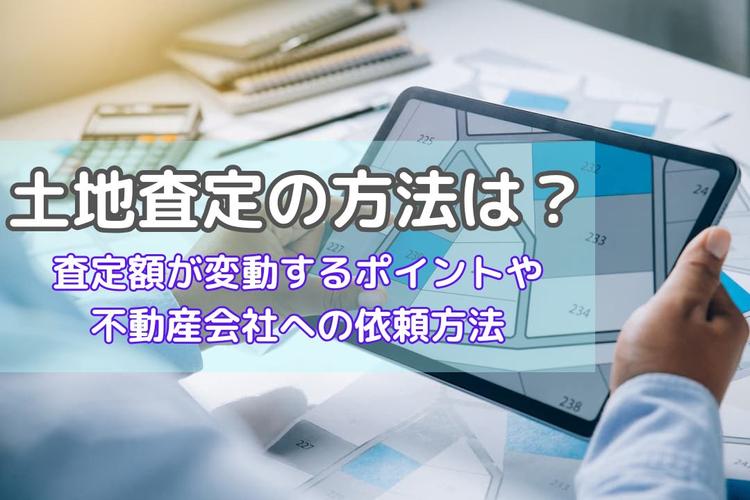土地の境界トラブルの多くは、不動産の売却を検討する段階で発生します。土地を売却する前提として、土地の境界を確定しなければいけないからです。隣地所有者と境界の認識に大きなズレがあれば、解決は難しくなってしまいます。
この記事では、土地の境界トラブルでよくある事例を紹介するとともに、その解決方法について解説をします。
土地の境界トラブルの事例
長年お隣りと平穏な関係を続けていたはずなのに、ある日突然土地の境界トラブルが発生してしまうことがあります。
なぜ、そんな事態になるのかを知るために、土地の境界のトラブルの事例を紹介していきましょう。
塀による境界明示は曖昧
近年では、境界標による境界明示が一般化していますが、ひと昔前の敷地では、塀などの工作物で所有地を明確にしていました。
こうした古くから存在する塀は、これを挟んだ両家にとって慣れ親しんだ存在であり、日常生活においては、なんの支障もありません。
ところが一方の土地が売却される段になると、改めて境界を精査する必要が生じます。
この際に、敷地境界を示す物証が塀のみだと、トラブルの原因になってしまうことがあるのです。
塀が境界となっていた物件でのトラブル事例
隣家とはコンクリートブロック塀で仕切られていますが、父親からは「塀は当家が築造したものであり、境界は塀の外面である」と聞かされていました。
つまりAさんは、隣家の土地とブロック塀が接する面が敷地境界線と認識していたのです。
これを隣地所有者のBさんに確認したところ、「塀は両家が共同出資して築造したものであり、敷地境界線は塀の中心である」との主張をしてきたのです。
お互いにこれらの事実を裏付ける書類は既になく、境界が確定しないまま売却することもできないため、時間だけが経過事態になってしまいました。
境界標を勝手に一時撤去
境界標は半永久的に固定されていることが前提になっていますが、下水道工事や外構工事などの事情により、やむなく境界標を仮移動させる必要が生じることがあります。
この際に、隣地の所有者の立会いの下で、現況の境界標を記録し、再び両者立ち合いで復元をすれば問題は生じません。
しかし施工業者の中には、無断で境界標を一時撤去し、工事後に適当な判断で元の位置と思われる箇所に戻す者もいます。
明らかに境界標を移動させた痕跡があると、境界標そのものの信ぴょう性が大きく損なわれトラブルに発展することになります。
境界標を移設していなかった
隣家同士が古くから懇意にしており、合意によって敷地境界線を変更したのに、境界標を移動しなかったためにトラブルに発展することがあります。
境界標の移設に関するトラブル事例
ところがDさんが土地を売却するために、土地家屋調査士に調査を依頼したところ、大きな問題があることが判明しました。
地積測量図をもとに境界を確認していくと、実際の境界線はCさん宅側に約5メートルも食い込んでいるというのです。
両家の長老的存在の人に聞いたところ、CさんとDさんの父親は従兄弟の関係であり、株の投資で失敗したCさんの父親が、Dさんに資金援助を請い、その見返りに土地を譲ったのではないかという証言を得ました。
しかし、50年ほど前に分筆と合筆をしていたとい�う事実以外に、そこに至る経緯を裏付ける書類は一切存在しておらず、当然のことながら敷地が減少する側のCさんが納得できるものではありません。
Cさんが敷地境界線は境界標が示すとおりであると強く主張したため、境界確定は訴訟にまで持ち込まれることになりました。
土地の境界は取引をした当人同士が納得をしていればいいというものではありません。
世代交代した後世の人々にも納得がいくよう、境界の変更が生じた場合は、同時に境界標を移設させることが大原則なのです。
隣地所有者が納得しない
登記済の地積測量図があり、そのとおりに境界標が存在しているにもかかわらず、境界確定に隣地所有者が納得しないケースがあります。
隣地所有者が境界に納得しないトラブル事例
しかし現況測量図は、相手方が一方的に作成した図面にすぎないため、敷地境界の根拠にはなり得ません。
また隣地所有者のFさんのケースでは、敷地境界が確定した後の自己所有地の面積が、登記上の面積よりも減少することを根拠に土地の境界に対して異議を唱えてきました。
さらに、現地にきちんと施工された境界標があるにもかかわらず、一方的に設置された境界標であり、無効であるとの主張を繰り返したのです。
土地の境界を巡る問題では、客観的データが揃っているのにもかかわらず、相手の一方的な思い込みからトラブルに発展するケースが少なからずありま�す。
建物が越境していた
敷地境界線そのものは双方が納得したものの、確定した敷地境界線を建物の一部が越境していたためにトラブルに発展することがあります。
原則として、所有者に無断で敷地の上空を占有することはできません。
たとえ故意でなくても、建物の軒先などが敷地境界線を越境していれば、これをただす義務が生じます。
上空を他人の建物で占有された土地は、売却するうえで大きな負の遺産となります。
建物を新築する際にも、占有された箇所は建築敷地に含めることができないため実害も発生します。
当然所有者としては、すみやかな撤去を求めることになりますが、占用している部位が容易に撤去できないものだと、解決までに多大な時間を要することになるのです。
接道していなかった
位置指定道路(私道)との接道は、現地の見た目だけではなく、公図や道路位置指定図を確認しないと道路境界が判別できないことがあるので注意が必要です。
未接道のトラブル事例
敷地の目前には、10年前に築造された私道(位置指定道路)があり、これに接道した敷地として建築確認申請をしようと考えていたのです。
ところが、建築を依頼したハウスメーカーの調査によって、当該敷地は位置指定道路との間に5センチメートルの空隙が介在しており、実際には接道していないことが判明したのです。
さらに調査を進めると、とある開発業者が位置指定道路を築造した�際、隣接地所有者であったGさんの祖父に同意を求めたのですが、頑なに拒否されたため、業者がやむなく5センチメートル幅の敷地を分筆することで、ようやく道路の築造に漕ぎ着けたという経緯が判明しました。
Gさんは、分筆された敷地を購入しようとしましたが、相場の十倍以上の価格を要求され、新築計画を断念することになりました。
所有者がそろわない
土地の境界確定に大きな問題がない場合であっても、隣地の所有者が多人数の場合は、多大な労苦を伴うことになります。
土地の境界確定は、土地所有者全員の同意を要します。
このため、隣地の相続手続きが完了していないケースや複数の所有者が遠方に住んでいるといったケースだと、交渉だけで時間と経費を費やすことになります。
土地の境界トラブルの解決法
土地境界のトラブルが発生すれば、当該地所有者と隣地所有者の話し合いによって解決を図るのが基本的な解決方法になります。
しかしお互いの記憶だけを頼りにしていては、土地の境界トラブルを解決することはできません。
土地の境界トラブルを解決するために、どのような準備をすればいいのか、解説をしていきましょう。
隣接地の権利関係を調査する
筆界確認書を作成する際には隣家の居住者ではなく、その土地の所有者が協議対象になりますので、法務局で全部事項証明書を入手して、所有者を正確に把握することが基本です。
地積測量図を確認する
地積測量図は、土地の表示登記の根拠となる測量図です。
法務局に保管されており、客観的資料として活用できます。
ただし登記申請の必要書類となった昭和35年頃のものは、測量精度がそれほど精密でなかったため、しばしば誤差が生じることがあるので注意が必要です。
正確な資料として訴訟にも耐え得るものは、平成18年の座標値の記載が義務化されて以降のものです。
さらに平成20年以降は、世界測地系データで図面が作成されるようになっており、たとえ工事などで一時的に境界標が紛失したとしても、極めて高い精度で再現することが可能です。
地積測量図と境界標を照合する
地積測量図だけでは、隣地の所有者を納得させることはできません。
現地に地積測量図どおりに境界標が存在することを確認することで、土地の境界を確認することが可能になります。
不動産登記規則第77条では「現地に境界標があるときは地積測量図に記録しなければならない」としています。
ここでいう境界標は「筆界点にある永続性のある石杭又は金属標その他これに類する標識」と定義付けられており、具体的な材質としては石、コンクリート、合成樹脂や錆びない鋼製で堅固に埋設されているものとされています。
したがって、木杭や中空のプラスチック杭は境界標としては認められません。
堅固な境界標が現地に存在し、なおかつ地積測量図と一致することで、敷地境界線として説得力を有することになるのです。
事前に境界標を確認しておく
土地の境界立会いをぶっつけ本番で臨むと、トラブルの原因になります。
境界確定の必要性か生じた段階で、事前に地積測量図どおりに境界標が存在していることを確認しておく必要があります。
もし相違が生じていれば、土地家屋調査士と相談をし、その理由をしっかりと押さえたうえで、隣地所有者との協議に臨みましょう。
筆界確認書を作成する
立ち合いで境界が確定したら、土地家屋調査士が作成した「筆界確認書」という書類を2通用意して、当該土地所有者と隣地所有者が記名捺印をしたものをお互い保管します。
ここまで至れば土地の境界トラブルを解決したことになります。
日頃のコミュニケーションも大事
土地の境界トラブルに発展するケースの中には、地積測量図と境界標が一致しているにもかかわらず、根拠のない問題点を指摘して、いつまでも土地所有者が境界の確定に同意しないことがあります。
境界標に正当性があれば最終的には訴訟で解決を図れる目途が立ちますが、そこに至るまでに膨大な時間を要するため、結果として多大な不利益を被ることになります。
隣地所有者が荒唐無稽な主張をするケースの多くは、日常のコミュニケーション不足が原因です。つまらない言いがかりが、土地の売却の足かせにならないよう、日頃のコミュニケーションにも配慮しておくことも大切です。
筆界特定制度で筆界トラブルが解決できる
筆界のトラブルを解決する方法のひとつに筆界特定制度があります。
これは筆界のトラブルを裁判によらずに法務局の手続きによって解決を図る制度です。
どのような制度なのか紹介していきましょう。
筆界調査委員の調査
筆界特定制度では、土地家屋調査士や弁護士などによって構成された筆界調査委員が調査を進めます。
ここで取りまとめられた意見を参考に、最終的には法務局の特定筆界調査官が筆界を特定します。
筆界調査委員は、法務局や自治体に保管されている調査対象の筆界に関する資料を調査及び現地を測量し、さらに当事者からのヒアリングを経たうえで解決の道を探っていきます。
裁判よりも早く解決できる
平成18年にスタートした筆界特定制度が始まるまでは、筆界の問題は裁判によって解決を図っていました。
このため解決までに何年も要し当事者に大きな負担を与えていました。
もちろん筆界特定制度においても短期間に解決できるわけではありませんが、申請から10カ月から1年が平均的な所要日数であり、裁判に比べると早い解決が図れる点がメリットです。
ただし所有権の解決にはならない
筆界特定制度の目的は筆界を確定させることです。
このため、双方の争点が所有権と筆界の食い違いから発生している場合、所有権界を特定できない本制度では、まったく解決の力にはならないことになります。
▼関連記事

まとめ
日常の暮らしの中では、土地の境界が問題になることはありません。
しかし、いったん土地の売却を進めようとすれば、たちまち大きな課題としてクローズアップされることになります。
土地の売却は、いったん進めると待ったなしの状況になります。
そんな中、土地の境界トラブルを抱えてしまうと、早期解決のために不本意ながら、相手の言い分を聞かざるを得ない展開になってしまいます。
つまり土地の境界確定を売却直前に実施すると、土地所有者にとって不利になる可能性が高いのです。
このため、自己所有地の土地の境界に一抹の不安を抱えている場合には、土地の売却が具体的なスケジュールに上っていない段階に、腰を据えてじっくりと解決を図った方が、不本意な妥協を避けることができます。
この機会に、一度、地積測量図と自宅の境界標が一致していることを確認してみてはいかがでしょうか。