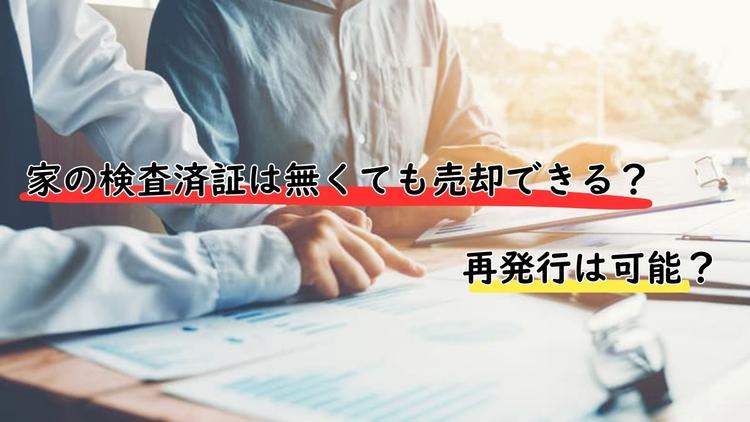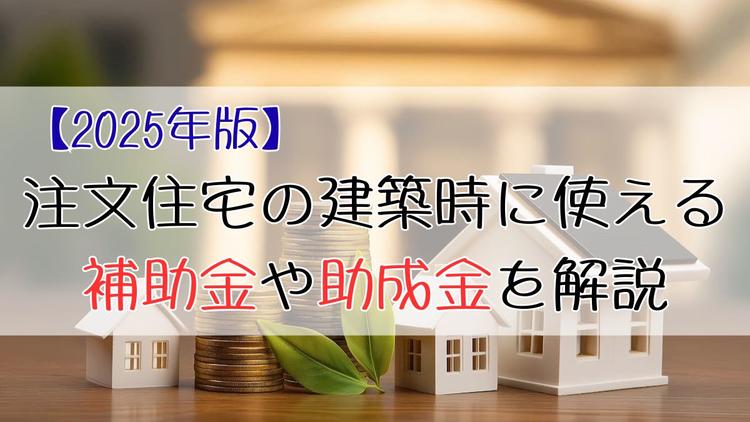庭先や敷地内に物置やガレージを設置するのは、日常生活の利便性を高めるために多くの家庭で検討されることです。
しかし、こうした小規模建築物の設置にも、法的な手続きが必要になるケースがあるのをご存じでしょうか。
特に、「建築確認申請」が必要かどうかは、建築基準法や都市計画法に大きく関わる問題であり、適切な対応をしないと違法建築として扱われる可能性もあります。
この記事では、物置やガレージの設置における建築確認申請の要否、判断基準、設置時の注意点などについて解説します。
物置やガレージは建築物である
一見すると、簡易的に設置される物置やガレージは「建物」としてのイメージが薄いかもしれません。
しかし、建築基準法における「建築物」の定義に照らすと、これらも明確に「建築物」として扱われます。
建築基準法第2条第1号では、「建築物」とは次のように定義されています。
土地に定着する工作物のうち、屋根および柱もしくは壁を有するもの(これに類するものを含む)をいう。
この定義に基づけば、たとえ居住用でなくとも、屋根があり、柱や壁で囲まれ、土地に固定された工作物であれば「建築物」とされるのです。
建築物の定義
たとえば、次のような構造物はすべて建築物に該当します。
- 金属製や樹脂製の既製品物置
- 車庫用プレハブガレージ
- コンクリート基礎付きのカーポート
- 木造の簡易倉庫
- コンテナハウス(電気などのライフラインを引き込み土地に恒久的に固定されたもの)
このため、「小さいから」「人が住まないから」といった理由で建築物でないと誤認してしまうことは大きな落とし穴になります。
建築物に該当すれば、当然ながら建築基準法の遵守の義務が発生し、防火規制・敷地条件・高さ制限など、さまざまな基準をクリアする必要があります。
また、建築物である以上、設置後は固定資産税の課税対象になる可能性もあるため、税務上の管理にも注意が必要です。
カーポートは建築物になる?
カーポートは「屋根があるが壁はない」という特徴から、建築物かどうか迷いやすい構造物ですが、建築基準法上では以下のように扱われます。
固��定式(柱+基礎あり)のカーポート→建築物に該当する
次の条件を満たす場合、法的には「建築物」として扱われます。
- 屋根がある
- 柱で支えられている
- コンクリート基礎などで地面に固定されている
こうしたカーポートは、物置・ガレージと同じく建築確認申請の対象になる場合があります。
簡易式(基礎なし・工具で外せる)のカーポート→建築物に該当しない場合が多い
- DIYで組み立てる簡易カーポート
- 工具1つで取り外せる軽量タイプ
- 土にペグ留めしているだけのタイプ
このようなタイプは「土地への定着性が弱い」ため、建築基準法上の建築物に該当しないと判断されるケースが一般的です。
そのため多くの自治体では、建築確認申請は不要とされ、固定資産税の課税対象外となります。
ただし、自治体によって判断が異なる場合もあるため、設置前に確認しておくと安心です。
建築確認申請とは
建築確認申請とは、建築物を新築・増築・改築・移転する際に必要となる手続きです。
その計画が建築基準法や関連法令に適合しているかを確認するために、所定の行政機関または民間の指定確認検査機関に申請を行います。
申請と異なった建物を建築すると、工事を中止されたり是正指導の対象になったりすることもあります。
都市計画区域内にある場合は要注意
物置やガレージといった「小屋状の建築物」であっても、一定の条件に該当する場合は建築確認申請が必要になります。
建築確認申請の要否をまず分けるのは、その設置場所が都市計画区域内か否かです。都市計画区域内の場合、原則として建築確認申請が必要となる可能性があります。
なお、一般的な市街地や住宅地は多くの場合、都市計画区域に指定されています。自宅の所在地が該当するかどうかは、自分の住んでいる自治体の都市計画課で確認してみましょう。
建築物の規模・構造による判断
設置する物置やガレージの面積によっても、申請の要否が変わります。
都市計画区域内であっても、次の要件をすべて満たす建築物は確認申請が不要です。
- 増築または附属建築物としての設置であり、10平方メートル以下であること
- 防火地域・準防火地域でない地域であること
建物の床面積が10平方メートル以下で建築確認申請が不要とされるのは、「増築」の場合です。
敷地内に他の建物が存在しない場合は、「新築」として扱われるため、建築確認申請が必要です。
なお、建築確認申請が不要であっても、建ぺい率・容積率・高さ制限・斜線制限などの制限は適用されるので、注意が必要です。
たとえば、自宅の敷地に建ぺい率制限一杯に建物が存在していれば、たとえ小規模でも設置することはできません。
確認申請の手続きと必要書類
建築確認申請が必要となる場合、以下の流れで手続きを行います。
申請先
- 建築主事がいる自治体(都道府県または人口10万人程度以上の市)
- 指定確認検査機関(民間機関)
必要書類の例
- 建築確認申請書
- 配置図・平面図・立面図・断面図
申請は、建築士や行政書士などの専門家に依頼するのが一般的です。
特に、構造計算や法的要件を満たす設計が必要な場合は、建築士の専門的知識が不可欠となります。
▼関連記事:建築確認申請とは?手続きの流れや費用、増改築時の注意点を解説します
建築確認申請でよくある誤解とそのリスク
小規模な建築物の場合、あまり深刻に考えることなく設置を先走るケースが多くあります。
しかし、知らないうちに違法行為をしてしまい、行政から思わぬ指導を受ける事例も少なくありません。
ここでは、建築確認申請に関してよくある誤解と、そのリスクについて解説します。
既製品でも建築物
設置者の中には、「簡単な物置だから」「ホームセンターで買ったものだから」といった理由で、建築確認を省略してしまうケースもありますが、これは非常に危険です。
建築基準法上、たとえ小規模でも条件を満たせば明確に建築物とみなされます。
プレハブ建物も建築物
工事現場に設置される仮設建築物(事務所・休憩所など)は、建築基準法第85条に基づく仮設建築物として工事期間中の使用を条件に、建築確認が不要とされています。
しかし、まったく同じ仕様の建物であっても、自宅に設置する場合は、一定の条件(10平方メートル以下の増築等)に該当する場合を除き、建築確認申請が必要です。
申請を怠った場合のリスク
建築確認申請を行わずに設置した結果、次のようなリスクを招くことがあります。
- 行政から是正命令や撤去命令が出される
- 境界トラブルの火種になる
- 固定資産税の課税対象となるが未申告状態になる
- 売却や相続時に「違法建築物」として扱われる
特に「違法建築物」とみなされると、将来的にリフォームや増築の際に建築確認済証が交付されないなど、大きな不利益を被る可能性もあるため、十分な注意が必要です。
小規模建�物に関する確認事項
建築確認申請の有無とは別に、物置やガレージの設置については、様々な確認すべき事項があるので解説していきましょう。
隣地境界からの距離
自治体によっては、隣地や道路からの後退距離(建物との距離)を定めている場合があります。
また、建築基準法による定めがない場合でも、民法第234条第1項で「建物を築造するには、境界線から五十センチメートル以上の距離を保たなければならない」と定められています。
これにより、隣人トラブルを避けるためにも、事前に説明や合意を得ることが望ましいでしょう。
道路後退(セットバック)への配慮
前面道路が狭い場合、建築基準法第42条第2項による「セットバック」が義務づけられているケースもあります。この場合、原則として道路中心線から2メートル以内に建築物を設けることができません。
セットバックとは、前面道路が狭い場合、安全な通行空間を確保するために敷地の一部を後退させること。
また自治体によっては、角地の隅切り部分への建築を禁じていることがありますので注意が必要です。
固定資産税にも注意
物置やガレージの設置を行政が把握すると、翌年から固定資産税の課税対象になる可能性があります。
課税対象となる基準は次のとおりです。
- コンクリート基礎で地面と固定されている
- 屋根と壁があり、三方向以上囲われている
- 恒久的に使用される構造である
課税対象になった場合、税額は建物の材質や床面積によって決まり、評価額に基づいて計算されます。
固定資産税の対象になるかどうかは、市町村の評価基準により判断されます。あらかじめ自治体の資産税課などに相談しておくと安心です。
まとめ
物置やガレージのような小規模な建築物であっても、建築基準法上は「建築物」に該当することが多く、場合によっては建築確認申請が必要となります。
特に都市計画区域内で設置を検討する場合は、その地域が防火地域・準防火地域に該当するかどうか、設置物の面積や構造などを踏まえて慎重に判断する必要があります。
建築確認申請が不要であっても、建ぺい率や高さ制限など他の法規制は適用されるため、油断は禁物です。また、建築確認を怠ると、是正命令や撤去指導を受けるだけでなく、固定資産税の課税対象として申告漏れの問題が生じたり、将来的な売却や相続に支障が出たりするリスクもあります。
既製品や仮設のように見える構造物であっても、「土地に定着し、屋根や壁を有するもの」であれば、基本的に建築物と見なされる点を忘れてはなりません。
物置やガレージの設置を計画する際は、事前に自治体や専門家に相談し、法的な手続きを適切に踏むことが重要です。