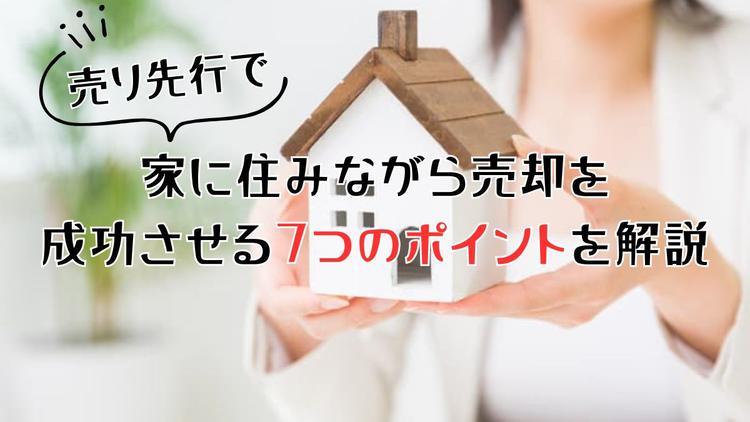「4号特例」とは、小規模建築物で建築確認の審査が一部省略される制度です。建築基準法の改正により、この4号特例が適用される建築物の範囲が縮小されます。
4号特例の縮小は、建築物の安全性確保のために有意義な改正です1。一方で、不動産売買への影響もけっして小さなものではありません。
この記事では、4号特例の縮小について詳細を明らかにするとともに、改正による不動産売買への影響について解説します。
4号特例とは何か
建築基準法の改正により、2025年4月1日から「4号特例」が見直しされます。この見直しは、「4号特例の縮小」あるいは「4号特例の廃止」と表現されることがありますが、いったいどのように「4号特例」が変わるのでしょうか。
「4号特例の縮小」について知るために、そもそも「4号特例」とは何かを押えておきましょう。
4号特例とは
「4号特例」とは、「審査省略制度」とも呼ばれるもので、建築基準法第6条の4に基づき、建築確認の対象となる木造住宅等の小規模建築物において、建築士が設計を行う場合に、構造関係規定等の審査が省略される制度です。
省略対象となる小規模建築物が、同法第6条第1項第4号に規定されている、いわゆる「4号物」と呼ばれる建築物であることから「4号特例」が通称となっています。
4号特例では、建築士が設計する木造住宅で、耐震強度や居室の採光計算を省略することができます。
4号特例を利用することで、建築確認申請の手続きが簡略化され、時間や費用を抑える効果があるのです。また、構造計算書の作成が不要になるため、設計者の負担も軽減されます。
ただし建築士は、省略した事項も建築基準法の規定を遵守して設計する必要があります。
4号特例の対象となる建築物
4号特例の対象となるのは、以下の条件を満たす建築物です。
- 木造2階建て以下
- 延べ面積500平方メートル以下
- 高さ13メートル以下
- 軒高9メートル以下
- 特殊建築物ではない
この要件は、建築基準法第6条第1項第4号に規定されています。
4号特例の縮小とは
4号特例の縮小は、2025年4月1日に施行されます。改正後は、4号特例の対象となる建築物の適用範囲が縮小します。具体的にどのように縮小されるのか、解説していきましょう。
建築物の区分が変わる
「4号特例」の対象とされているのは、建築基準法第6条第1項第4号に規定されている建築物です。改正後は、4号は廃止され、2号と3号に分けられます。
- 新2号:「木造2階建て」か「平屋の200平方メートル超」の建築物です。
- 新3号:「平家の200平方メートル以下」の建築物です。
従前は、鉄筋コンクリート造、鉄骨造、木造などの構造の種類と面積によって、建物が区分されていましたが、改正後は、面積または階数で区分されます。
4号特例の対象は縮小される
建築基準法第6条第1項で1号から4号まで区分されていた建築物は、3号までに変更されます。
4号が廃止されるため、通称としての「4号特例」はなくなりますが、建築士による設計で審査が省略できる制度は、新3号に引き継がれます。
引き続き4号特例が適用されるのは、平家の200平方メートル以下の建築物となるため、適用対象が大幅に縮小されることになるのです。
木造住宅の多くを占める2階建で特例が適用されないため、改正の影響はとても大きいといえます。
建築確認申請の義務化とは
2025年4月1日施行の法改正では、建築基準法第6条第1項第4号に規定されている建物は、改正後は2号と3号に分けられることから、木造一戸建て住宅の大規模なリフォームで建築確認申請の義務化対象が大きく広がります。
大規模なリフォームとは
大規模なリフォームは、建築基準法上「大規模の修繕」または「大規模の模様替え」と呼ばれるもので、建築物の主要構造部(壁、柱、床、はり、屋根または階段)の1種以上について過半の改修等を行うことをいいます。
キッチン、トイレ、浴室等の水回りのみのリフォーム、バリアフリー化のための手すりやスロープの設置工事は、大規模なリフォームには該当しません。
建築確認申請が義務化された大規模なリフォーム
大規模なリフォームで建築確認申請が義務化されるのは、新2号に該当する建築物です。木造2階建て住宅は、法改正前は500平方メートル以下の建物における大規模なリフォームでは、建築確認申請は不要でした。
改正後はすべての木造2階建ての大規模なリフォームは建築確認申請が義務化されます。
4号特例の縮小の背景
4号特例の縮小には、現代を取り巻く環境が影響しています。どのような背景から、4号特例の縮小に至ったのか、解説をしていきましょう。
省エネ基準の厳格化
近年、地球温暖化対策の一環として、住宅を含む建築物の省エネルギー性能の向上が世界的に求められています。日本でも、2050年までのカーボンニュートラル実現に向けて、住宅の省エネ基準が段階的に強化されてきました。
このような状況下で、4号特例の存在は、省エネ基準の厳格化を推進する上で大きな課題となっていました。4号特例は、小規模な木造住宅を対象に、建築確認申請における構造計算や省エネ計算を簡略化する制度です。
4号特例により、簡易な手続きで住宅を建てられる一方、省エネ性能が低い住宅の建設も可能になっていました。4号特例の縮小は、省エネ基準の厳格化を図るためでもあるのです。
大地震対策
4号特例は、小規模な木造住宅を対象に、建築確認申請における構造計算を簡略化する制度です。これにより、簡易な手続きで住宅を建てられる一方、構造計算が十分に行われないまま建設される住宅も存在しました。
このような住宅は、耐震性が低い可能性があり、大地震が発生した場合に倒壊するリスクが高いという問題がありました。特に、2016年の熊本地震では、4号特例で建てられた住宅の多くが倒壊し、多くの犠牲者が出ました。
4号特例の縮小は、構造計算の審査を厳格化するためでもあるのです。
▼関連記事:建築確認申請とは?手続きの流れや費用、増改築時の注意点を��解説します
4号特例の縮小は不動産売買にどんな影響がある?
「4号特例」は、建築確認申請の簡略化制度とも呼ばれ、主に2階建て以下の住宅に対して、構造計算や採光など一部の規定の審査が省略されていました。
4号特例の縮小は、不動産売買に様々な影響を与える可能性があります。具体的にどのような影響が予測されるのか解説をしていきましょう。
家の着工時期が延びる
延べ床面積が200平方メートル規模の木造2階建て住宅は、これまで確認審査の法定審査期間が7日以内でしたが、法改正後は35日以内に延長されます。このため、建築確認済証の交付が、1カ月程度延びることになります。
また、従来不要だった構造計算書の添付が義務化されました。こうした書類の作成に時間を要することから、建築確認申請を提出する時期も、現状より先になる可能性があります。
さらに省エネ基準への適合が義務化されることもあり、施工会社もこれに対応しながら工事を進めていかなければならないため、工期も伸びる可能性があります。
コストが上がる
構造計算の義務化や審査事項の増加などで、設計段階で必要となる作業が増えることから、コストが上昇することが予想されます。
特に、木造2階建て住宅においては、法改正前と作業量の違いが顕著なため、費用が上がる可能性があります。設計費用の増加は、住宅の販売価格も反映されるため、新築住宅の販売価格が上昇する可能性があります。
また、リフォーム時のコストもアップするため、不動産会社が購入後に一定のリフォームを行っ�て再販売される「買取再販住宅」の販売価格も、費用回収のために引き上げざるを得ません。
このことは「不動産会社に買取を依頼した場合、これまでよりも価格が安くなる」といった形で売却価格に影響が出ると考えられます。
再建築不可物件の売却はますます困難に
4号建築物の大規模なリフォームは建築確認申請が不要でした。ただし、大規模なリフォームを行えば、現行法令が適用されるので、再建築不可物件が無条件で大規模なリフォームが行えたわけではありません。
しかし、「建築確認申請が不要なので、大規模なリフォームであれば施工可能」といった、誤った認識が一部で流布されていたために、一定の売買が成立していた実情もあります。
法改正により、木造2階建て住宅は新2号に分類されるため、大規模なリフォームは建築確認申請が義務化されます。これにより、原則として現行法が適用されるという、本来の認識が広まることが期待できるのです。
その一方で、建築確認申請の義務化により、再建築不可物件を敬遠する人が、ますます増えることが予測されます。そのため、老朽化した再建築不可物件の売却価格は大幅に下がる可能性があります。
▼関連記事:再建築不可物件の基準とは|建て替えや売却はできない?
4号特例の縮小で今後注意すべきこと
4号特例が縮小されることで、建物の安全が確保されることが期待できます。しかし、法改正による解釈の違いなどから、様々なトラブルの発生が予測されます。
4号特例の縮小で、どのような��点に注意をすればいいのか解説をしていきましょう。
新3号に引き継がれる特例
「4号特例」と呼ばれていた「審査省略制度」は、新3号に引き継がれます。新3号は200平方メートル以下の平家建てであることから、木造2階建てに比べて、地震に対するリスクは低減されます。
しかし、審査が省略されているからといって、まったく検証が不要なわけではありません。審査省略制度は、建築士の良心に委ねた制度であり、建築士が構造計算を精査したうえで申請することを前提としています。
新3号建築物の設計を依頼する際には、建物の構造計算をどこまで検証しているかを建築士に確認することが重要です。
また審査省略制度では、居室の採光計算も省略されます。建築基準法では、住宅の居室の採光面積は、床面積の1/7以上と定められています(床面照度50lx以上の照明を居室内に設置すれば1/10で可)。
これは、居住者の健康を維持するための最低限の基準です。審査項目から外れているからといって、採光不足が許されるものではありません。設計を依頼した建築士には、必ず各居室の有効採光面積を確認してください。
建築確認不要でも法の適合が求められる
木造2階建て住宅の大規模なリフォームは、建築確認申請が不要であったことから、建築基準法への適合性は求められないという誤った認識が一部で流通していました。
改正後、木造2階建て住宅は、新2号に移行するため、大規模なリフォームであっても、建築確認申請が義務化されます。これにより、本来の正しい認識が広まることが期待できます。しかし��、新3号建物の大規模なリフォームは、建築確認申請が不要なため、引き続き注意が必要です。
たしかに、新3号建物の大規模なリフォームでは、現行法が適用されない項目が多くあります。
たとえば、次の項目は、既存不適格建物であれば、大規模なリフォームを行っても、遡及適用されることはありません。
- 構造耐力
- 容積率
- 建ぺい率
- 高度地区の制限
一方で、次の項目は遡及適用されるため、大規模なリフォームであっても、現行法規に適合させる必要があります。
- 屋根
- 外壁
- 居室の採光・換気
- 準防火地域内の開口部
- 道路内の建築制限
屋根や外壁、開口部の防火性能の向上が求められます。建築確認申請が不要だから、自由に工事が行えるわけではなく、一部の規定には適合させる義務があるのです。
また、既存不適格建築物として屋根の一部が道路に突出していた場合、大規模なリフォームをする際には、突出部分を撤去する必要があります。
▼関連記事:既存不適格建築物をリフォームする際の注意点は?制限や建築確認が必要なケースを解説
再建築不可物件は特に注意
再建築不可物件とは、接道義務(建築基準法第43条第1項)に適合していない敷地をいいます。
改正後、木造2階建て住宅の大規模なリフォームは、建築確認申請が義務化されたため、ルールを無視した工事を未然に防ぐことが期待できます。
一方、建築確認申請の義務化がない新3号建物では引き続き注意が必要です。
複雑なのは、建築基準法第86条の7で、大規模なリフォームにおける「接道義務」規定を適用しないとしている点です。しかし、この条文には「政令で定める範囲」という要件が示されています。
要件とは、「建築物の用途の変更を伴わない大規模の修繕または大規模の模様替であって、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものとする(同施行令137条の12第6項)」というものです。
つまり、新3号建築物の大規模なリフォームがすべて自由に施工できるわけではありません。たとえ建築確認申請が不要な案件であっても、事前に特定行政庁の43条認定または許可手続きが必要なのです。
▼関連記事:43条認定について
まとめ
「4号特例」とは、「審査省略制度」とも呼ばれるもので、木造住宅等の小規模建築物において、建築士が設計を行う場合には、構造関係規定等の審査が省略される制度です。
この4号特例が適用される建築物の範囲が、法改正により縮小されます。引き続き「4号特例」が適用されるのは、新3号に該当する200平方メートル以下の平屋建ての住宅等です。
4号特例の適用範囲が縮小されたことから��、木造2階建て住宅の建築確認の審査期間が7日から35日に延長されます。
また構造計算書の添付など、建築士の負担が増加することから、不動産売買においては新築物件や買取再販物件、購入後に行うリフォーム等のコストがアップするといった影響が考えられるでしょう。