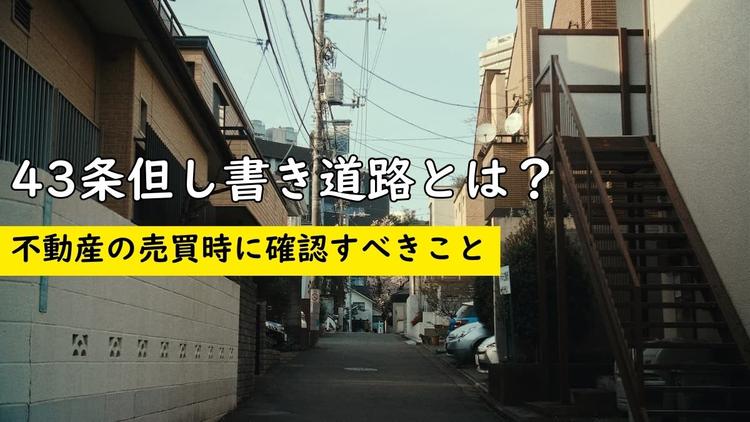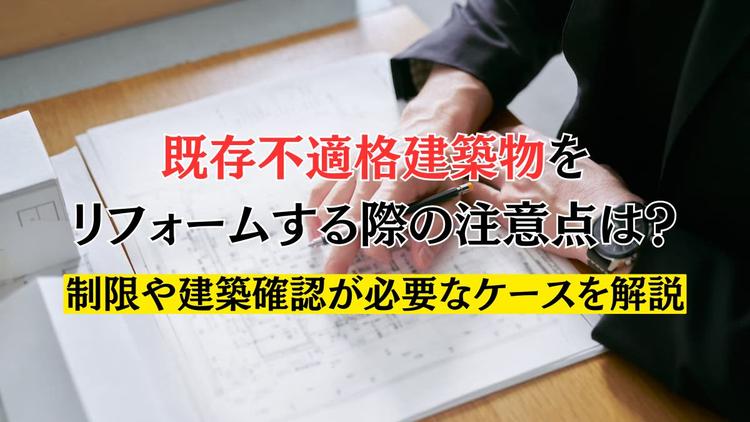建築物は建築基準法上の道路に接していないと建てることができません。
しかし、非道路である通路や広場にしか接していない敷地であっても、「43条但し書き道路」として許可を受けることで、建築が可能になることがあります。
この記事では、43条但し書き道路について、その定義、特徴、不動産売買における注意点などを解説します。
43条但し書き道路とは?
建築基準法第43条では、「建築物の敷地は、幅2メートル以上の道路に接していなければならない」と定められています。
つまり、建築基準法で認められた道路に接していない土地には、原則として建物を建てることができません。
通常、建築基準法上の道路に2m以上接道していない敷地は、建築が制限される(再建築不可物件)。
このルールは、消防車の進入や避難経路の確保を目的としており、防災の観点から非常に重要です。
しかし、例外的に建築が認められるケースがあります。
それが、「43条但し書き道路」と呼ばれるものです。
建築基準法の施行前から建物があった土地や無接道の土地など、特定の条件を満たす敷地について、防災上の安全を確保できる通路や広場に接している場合に、建築を認める制度です。
この制度の活用により、
- 許可を受ければ建て替えが可能
- 更地にして新築もできる(ただし条件は厳しくなる)
といった救済措置が適用されます。
なお、「43条但し書き道路」という呼び方は法改正によって変更され、運用基準も見直されており、以前よりも細かい条件が設定されています。
次に、現在の基準や具体的な許可の条件について確認していきましょう。
今は「43条但し書き道路」とは言わない
「43条但し書き道路」という呼び方は、法改正前の次の条文に由来しています。
第43条 建築物の敷地は、道路に2メートル以上接しなければならない。ただし、その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものについては、この限りでない。
条��文の後半に「ただし……」という形で例外規定を設けて、特例で接道義務を免除していることから「43条但し書き道路」と呼ばれていたのです。
しかし、2018年9月25日施行の法改正で、この但し書きによる特例は43条2項2号に改められました。
これに伴い、条文から但し書きがなくなったため、現在では「43条但し書き道路」と呼ばれることはなくなっています。
「43条認定」と「43条許可」
現在の建築基準法第43条は、次のような規定になっています。
第43条 建築物の敷地は、道路に2メートル以上接しなければならない。
第2項 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。
- その敷地が幅員4メートル以上の道に2メートル以上接する建築物のうち、利用者が少数であるものとしてその用途及び規模に関し国土交通省令で定める基準に適合するもので、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるもの
- その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの
この規定により、無接道で建築できる敷地は次の2種類に分けられました。
- 43条2項1号道路(認定)…… 幅員4メートル以上の通路に2メートル以上接する敷地で、利用者が少数である建築物(主に住宅)が対象となります。
- 43条2項2号道路(許可)……敷地の周囲に広い空地を有する建築物や国土交通省令で定める基準に適合する建築物が対象となります。
以前の「但し書き道路」の規定は、43条2項2号許可として引き継がれ、さらに43条2項1号認定という新たな規定が追加されました。
元々、「43条但し書き道路」は通称ですが、法改正により条文から「但し書き」がなくなったため、現在は「43条認定」「43条許可」といった呼び方が一般的になっています。
43条但し書き道路の認定
但し書き道路の認定(43条2項1号)は、下記の条件に該当する場合、建築審査会の同意を得ることなく建て替えができる制度です。
- 幅員4m以上の通路に2m以上接している
- 利用者が少数の建築物
- 国土交通省や自治体が定める基準に適合している
改正前の43条但し書きでは、接道していない敷地で建て替えを行う際には、すべて建築審査会の同意を得る必要がありました。
しかし、建築審査会の開催日は限定的であり、同意を得るまでに長い時間がかかるのが問題でした。
そこで、2018年の建築基準法の改正によって認定制度が新設され、建築審査会の同意なしで建て替えが可能になったのです。
43条但し書き道路の許可
但し書き道路の許可(43条2項2号)とは、敷地が建築基準法で定められた道路に2m以上接していなくても、許可を受けることで建築ができる制度のことです。
この制度は、改正前の43条但し書き道路の規定を引き継いだ内容になります。
一方で、但し書き道路の認定基準に適合しない場合は許可を受けなければ建築はできません。
但し書き道路の許可を得るには、敷地の周囲に広い空地を有するなど、行政機関が定めている「包括同意基準」や「個別同意基準」を満たす必要があります。
包括同意基準とは
一定の条件(例:周辺環境や安全性の確保など)を満たすものとして、あらかじめ建築審査会から同意を得ている基準に適合している案件のこと。
建築審査会の同意は必要ですが、個別に付議はしないので確実に許可を得られます。
- 敷地に十分な空地・通路幅がある
- 建物の規模や利用者の人数が小規模である
- 消防や救急車両の進入が可能な経路を確保している
個別同意基準とは
包括同意基準を満たさない場合に適用される基準のこと。
個別に付議して同意の可否を審議するため、確実に許可されるわけではありません。
- 建物の構造や規模が大きい場合の防火・避難計画
- 周辺の道路・通路状況や隣接する建物との離隔距離
- 消防活動や避難が十分に確保できるかどうか
43条但し書き道路の事前相談の流れ
43条但し書き道路の許可を受けて建築を行うには、まず事前に許可の可能性があるのかどうかの判断を受ける必要があります。
この判断は、行政機関への事前相談を通して行われます。相談の結果、許可の可能性があると判断された場合のみ、許可申請をすることができるのです。
ここでは、43条但し書き道路の事前相談の流れを解説します。
行政機関へ道路判定の依頼
建築主事が設置されている行政機関(特定行政庁)に相談して、建て替えを予定している敷地と接する通路が建築基準法上の道路に該当するかを判定してもらいます。
建築主事が設置されている行政機関は、都道府県と政令指定の人口25万人以上の市とされています。
しかし、実際には人口10万人程度の市でも建築主事を設けている場合があります。
相談地がこれらの市に属していない場合は、都道府県の特定行政庁に道路判定を依頼しましょう。
相談を受けた行政機関は、すでに判定済の道であれば、その場で「道路」か「非道路」かの回答をします。
未判定の道の場合は、現場調査をしたうえで判定をすることになります。
事前相談書の提出
行政機関から、相談地が接している通路が非道路であると回答された場合は、事前相談書を提出して、43条の認定もしくは許可により建て替えが可能かどうかの判断を委ねます。
行政機関からの回答
事前相談書を提出すると、行政機関から次のいずれかの回答があります。
- 建築不可……認定・許可基準に適合しないので建築できません。
- 43条認定申請可……認定申請をすることで建築が可能になります。
- 43条許可申請可(包括許可)……許可申請をすることで建築が可能になります。
- 43条許可申請可(個別許可)……建築審査会の審議により建築の可否が決まります。
認定申請は建築審査会の同意が不要なので、許可申請と比較して短い期間で建築が可能です。
許可申請には、「包括許可」と「個別許可」があります。「包括許可」は、予め定められた許可基準を満たしているため、申請をすれば確実に許可を受けられます。
しかし、法律の形式上、建築審査会の同意を得る必要があるため、申請後は建築審査会の開催を待つことになり��ます。
一方「個別許可」は、建築審査会の審議によるため、この段階では建て替えが可能か不可なのかの判断はできません。
43条但し書き道路の許可申請の流れ
43条許可申請をすることで建築が可能になる可能性がある案件は、許可申請手続きを行います。
どのような流れで手続きを進めていくのか解説をしていきましょう。
建築審査会への事前相談
「個別許可」と判断された案件は、建築審査会の事前相談で審議が行われます。
許可申請には申請手数料が発生するため、不許可になった場合のトラブルを回避するために、事前に同意が得られるかの有無について審議します。
ここで問題がないと判断された場合は、許可申請が可能です。
また、指摘事項が挙げられた場合でも、それをクリアすることで許可申請が可能になります。
同意見込みがないと判断された場合には、建て替えをすることはできません。
事前相談の必要書類
事前相談では、事前相談書に次の書類を添付します。
- 付近見取図
- 敷地及び空地等の現況写真
- 空地等周辺状況図
- 公図の写し
- 空地等の土地所有者一覧表
- 空地等の土地における登記事項要約書
- 相談敷地の建物及び土地の全部事項証明書
- 配置図、各階平面図、立面図(2面以上)及び断面図(2面以上)
- 面積表(敷地面積、建築面積、延べ面積、各階床面積、建蔽率及び容積率)
- 敷地の土地使用承諾報告書(相談者が相談敷地の土地所有者と異なる場合)
- 土地の高低差がわかる図面(土地の高低差がある場合)
- 道路区域明示図(空地等が認定道路の場合)
許可申請
「包括許可」や建築審査会の事前相談で「同意見込み」とされた案件は、申請書を行政機関に提出します。
申請手数料
建築基準法第43条の許可手数料は、行政機関によって異なります。
たとえば、大阪市や横浜市では33,000円、東京都では36,000円です。
申請に必要な書類
申請には、正本1部、副本1部の合計2部必要となり、受付前に手数料を納付します。
43条許可申請書には、事前相談に提出した書類を改めて添付しますが、その他に次の書類を添付します。
- 申立書
- 同意書(空地等の土地所有者からの同意が必要な場合)
建築審査会での審議
建築審査会は、学識経験者等で構成された組織で、年に3~6回程度開催されます。
43条関連で建築審査会の審議にかけられた案件は、事前相談を経ているので、基本的に否定されることはありません。
しかし、審査会の開催時期によっては、許可が下りるまでに数カ月を要することもあります。
許可書の交付
建築審査会の審議で同意を得ることができれば、行政機関が同意書を受理し、許可書を交付します。
この許可書を添付することで、敷地が道路に接していなくても、建築確認申請が可能です。
不動産の売買時に確認すべきこと
43条但し書き道路に接する不動産を売買する際には、いくつかの注意すべき事柄があります。
売買後のトラブルを避けるためにも、接道をしている一般的な物件以上に注意が必要です。
どのような点に注意をすればいいのか解�説をしていきましょう。
購入前に再建築の可否を確認する
43条但し書き道路に接する既存の建物は、再建築できる場合とできない場合があります。
43条但し書き道路で建築確認済証を交付された物件は、建て替えの際に改めて許可・認定を受けなければ建築ができません。
ここで問題になるのが、法改正前の規定で「建築主事が支障がないと認めるもの」として43条但し書きが適用された物件です。
改正前の建築主事の判断基準と、現在の許可基準が異なることから、建て替えの際に許可も認定も受けられないケースは少なくありません。
購入を希望する物件が建築確認済であっても、43条但し書きで建てられている物件は、直接行政機関に出向いて、再建築が可能か否かを確認することが重要です。
不動産会社に売却の相談や査定依頼をした場合は、代わりに役所調査を実施してもらえるでしょう。
購入の際に必要事項を確認する
43条但し書き道路に接する不動産を購入する際には、売主や不動産会社、あるいは行政機関から、次の事項を確認をしたうえで判断をしてください。
- 道路の状況……幅員、舗装状況、周辺の環境
- 建築規制……建築可能な用途、規模、高さ、防火性能
- 再建築の可否……将来的に建て替えが可能かどうか
- 権利関係……道路の所有権、通行権など
- 周辺環境……日照、通風、騒音、振動など
- 行政の判断……行政機関の過去の許可事例など
これらの事項を確認することで、不動産の価値やリスクを正しく判断することができます。
調査の結果「再建築不可物件」に該当すると判明した場合、査定額の下落に繋がることが多いです。
また、再建築不可でない場合も、私道の通行・掘削承諾書を取得できなければ売却が難しくなるといった問題が発生することもあります。
不動産会社と相談して必要な手続きを進めましょう。
売却の際に重要事項説明書に記載する
43条但し書き道路に接する不動産を売買する際には、重要事項説明書に次の内容を明確に記載する必要があります。
- 道路の種類(43条但し書きによるものであること)
- 再建築の可否
- 既存不適格建築物である場合は、その旨
- その他、建築に関する制限事項
これらの事項を明確に記載することで、将来的なトラブルを予防することができます。
▼関連記事

まとめ
43条但し書き道路は、建築基準法上の道路に該当しないものの、一定の条件を満たせば建築が可能な通路です。建築の可否は、道路の状況、建築物の用途・規模などから、行政機関が判断します。
43条但し書き道路は、過去に建築確認済であっても、再建築ができる保証にはなりません。
43条但し書き道路に接する不動産を売買する際には、再建築の可否、既存不適格建築物の有無、権利関係など、確認すべき事項が数多くあります。
そのため、不動産の購入を検討する際には、専門家に相談するなど、慎重な判断が必要です。