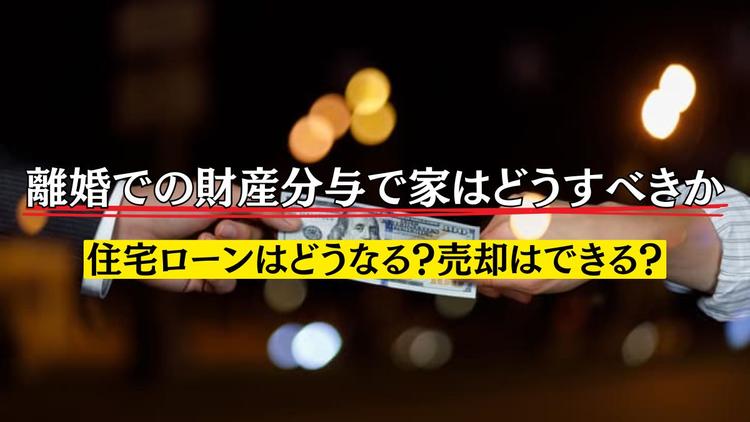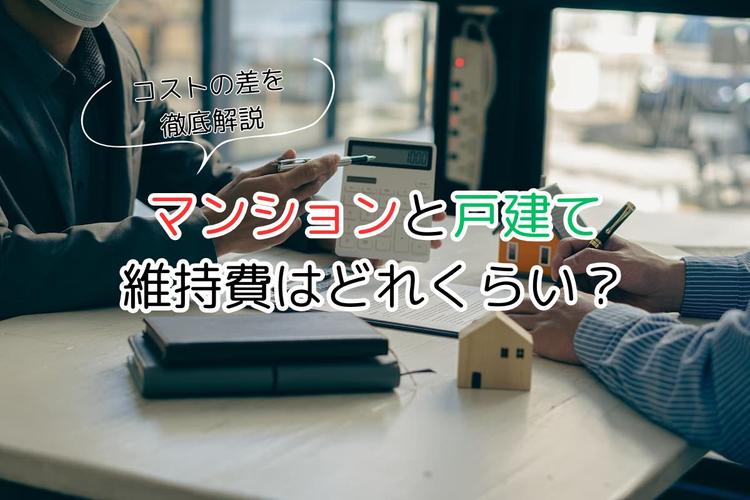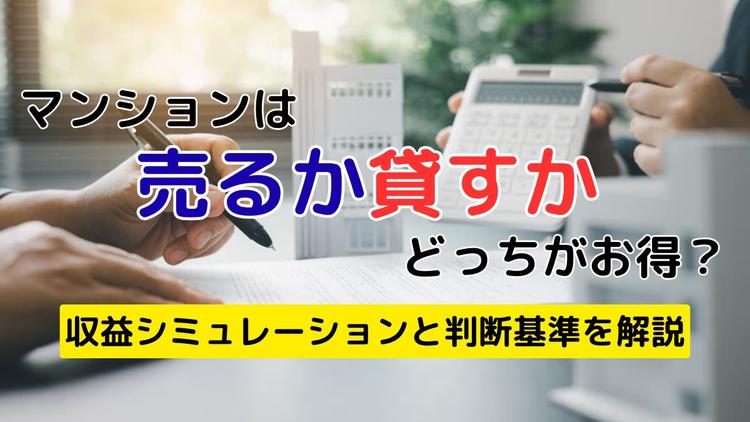リフォーム業者による詐欺は増加傾向にあり深刻な問題となっています。
「自分は悪徳業者に騙されない」と思っていても、巧妙な手口に騙されてしまう可能性は捨てきれません。
悪徳業者に騙されないためには、よくある手口や悪徳業者の特徴を押さえておくことが重要です。
この記事では、悪質なリフォーム業者のよくある手口や悪徳業者の特徴、騙されたときの相談窓口まで詳しく解説します。
悪徳リフォーム業者のよくある手口
国民生活センターの統計によると、訪問販売によるリフォーム工事に対する相談件数 は2023年で11,861件に上ります1。
ちなみに2021年は9,756件であることからも、相談件数が増加傾向にあることが分かります。
消費者庁でも悪質なリフォーム業者への注意喚起が行われており、問題は深刻化しているのです2。
いつ悪徳業者に騙されてもおかしくない状況であることから、自身でもしっかり対策しておく必要があります。
騙されないためにはどのような手口があるかを理解し対策することが重要です。
以下では、悪徳リフォーム業者のよくある手口を紹介するので参考にしてください。
無料点検のはずが費用を請求される
無料点検を謳って点検し、点検後に問題を指摘して高額なリフォーム費用を請求するケースです。
無料点検後の「異常なし」で引き下がる業者なら問題ありませんが、何かしら異常を指摘され、リフォームの必要性を煽ります。
なかには「放置すると家が倒壊する」「このままでは危険」と不安を煽って高額な商品を売りつけるケースもあります。
また、大手企業や役所などの名をかたって、無料点検を装った営業をしているケースもあるので注意しましょう。
相場からかけ離れた金額を請求される
悪徳リフォーム業者の代表的な手口が、相場からかけ離れた高額な請求です。
リフォーム工事を行ったことのない人にとっては、請求される金額が相場に対して適切なのかの判断がつきにくいと思います。
そのことを逆手にとって、相場よりも高額な費用を請求してくるのです。
この場合リフォーム工事についても、そもそもリフォームが必要ない部分や工事の質が粗悪というケースが少なくありません。
リフォーム料金が適切かの判断は難しいですが、契約する前に複数の業者を見比べるなど慎重に契約を検討することが大切です。
わざとキズをつけて修理費用を請求する
リフォームの必要のない箇所に対して、わざとキズをつけてリフォームを勧めるケースです。
屋根や外壁を故意に壊す、配管を傷つけて漏水させるといった手口があります。
とくに、築年数が�古い家や台風などの自然災害後にこのような手口が増えやすいので注意しましょう。
また、キズをつけない場合でも別の家の写真で騙す、どこからか持ってきたシロアリを家で見つけたように装うといった手口もあります。
いずれにせよ、たまたま営業した業者で都合よく不具合が見つかるという時点で、慎重に検討する姿勢が必要でしょう。
手抜き工事をして追加工事を要求する
わざと手抜き工事をして、追加工事の必要性を迫り高額な費用を請求するケースです。
この場合、最初の工事に対しての見積もりはお得な額であるケースが多いでしょう。
そのうえで、追加料金で高額な費用を請求してくるのです。
仮に、追加工事がその場で必要ないケースでも、工事の質が雑ではすぐに修理が必要となるため、余計な費用がかかってきます。
工事中も様子は適宜確認し、必要に応じて写真を残す、完了検査に立ち会うなど雑な工事をされていないかはチェックすることが大切です。
工事中の様子のチェックを嫌がる業者は、怪しい可能性が高いともいえます。
雨漏りを演出する
わざとキズをつけるケースと似ていますが、水を使って雨漏りを演出するケースもあります。
とくに、雨漏りだと家主としても「すぐに対策しないと」となりやすいので、騙されやすい手口といえるでしょう。
それまで雨漏りの気配もなかったのに、いきなり雨漏りを指摘されても信用性はあまり高くありません。
別の業者に再点検してもらう、自分の目で雨漏りの箇所を確認するなど、慎重な判断が求められます。
悪徳リフォ�ーム業者の特徴
悪徳リフォーム業者の手口や特徴はさまざまですが、似通っている点もいくつかあります。
ここでは、悪徳リフォーム業者に共通する特徴を見ていきましょう。
見積書が「一式」だけになっている
見積書が「一式」で記載されていると工事の内容が分からず、後から高額な追加料金が請求される恐れがあります。
一般的な見積もりには、単価や単位・工事の内容・商品番号などが細かく書かれているものです。
一式しか記載がない、見積書の内容がよく分からないという場合は、必ずその場で確認するようにしましょう。
仮に見積もりに対しての質問に答えてくれなかったり、曖昧にはぐらかされる場合はその業者は避ける方が無難です。
そもそも、悪徳業者の中には見積もりなしの口約束で進めようとするケースもあります。
この場合も後から高額な費用を請求されるリスクがあります。
リフォーム工事を行う際には、必ず見積書の確認・契約書での契約を行うことが大切です。
値引き額が異常に大きい
異常な値引きを提案するケースにも注意が必要です。
「今日契約すれば半額になる」「キャンペーン期間中だから○%OFF」などとお得な料金で契約を迫ります。
とくに、「今日しかない」というようにすぐに契約を迫る場合は注意が必要です。
異常な値引きをする場合でも、値引き後の金額が相場より高い可能性があります。
そもそも値引き前の金額の正当性も怪しいところなので、値引きにつられないように気を付けましょう。
施工が雑
リフォームの詐欺とし�ては、高額請求する以外に施工費用を抑えるため、雑な施工をしているケースがあります。
必要な下処理を行わない・品質基準を守らない・事前に提案した内容と異なる施工にするといったケースが挙げられます。
雑に施工されると品質や見た目が悪く、すぐに補修が必要になる恐れもあるでしょう。
より悪質になると施工が雑なうえに高額請求してくる場合もあります。
施行中の様子は写真に撮っておいたり、完了時には細かく施工状況を確認するなどして、施工の質もチェックすることが大切です。
契約書を交付するのを渋る
リフォーム工事のトラブルの多くは、契約書がないことで起きます。
口約束でもリフォームの契約としては有効ですが、契約内容があいまいになり高額請求や提案と異なる工事をされる恐れが高くなります。
契約書がなければ契約内容に違反があってもそれを証明する証拠がなく、不利になりやすい点にも注意が必要です。
口約束でリフォームを進められそうになっても必ず契約書の交付を求めるようにしましょう。
契約書の交付を渋る・施行後に契約書を交付するといった業者の信頼性は高くありません。
仮に、契約書が交付される場合でも内容が適切かのチェックは忘れてはいけません。
業者名や連絡先、契約の内容・金額・支払い方法・クーリングオフについてなど、細かい部分までチェックし納得したうえで契約を交わすようにしましょう。
しつこい営業
何度も訪問する・電話を掛けてくるなど迷惑な営業を行う業者は多いです。
リフォームする気がないならきっぱりと断るようにしましょう。
悪徳リフォーム業者と契約しないための対策
悪徳リフォーム業者と契約すると、高額請求や質の悪い施工など、トラブルにつながります。
契約前には悪徳リフォーム業者でないかしっかりと確認し、慎重に契約を進めることが大切です。
ここでは、悪徳リフォーム業者と契約しないためを対策を2つ紹介します。
リフォーム業者の実績をHPなどで確認する
まずは、HPで会社情報や保有する資格・実績などを確認するようにしましょう。
HPの内容が浅い・そもそもHPがない業者は避けた方が無難です。
また、インターネットでリフォーム業者名を検索し「詐欺」「悪徳」など、マイナスの口コミが多い場合もあまりおすすめできません。
口コミや評判はあくまで目安であり鵜呑みにする必要はありませんが、あまりにマイナスな評価が多い場合は何かしら原因があるといえるでしょう。
工事内容と契約内容を事前にしっかり打ち合わせする
優良なリフォーム業者であれば、契約前��に調査を行い、工事内容や契約書の内容をしっかり説明し、こちらが納得したうえで契約を進めてくれます。
事前の打ち合わせもなく一方的に契約を進めようとする業者は注意が必要です。
「今日契約しないと安くならない」とろくに説明や打ち合わせもせずに契約を迫るような業者はおすすめできません。
家族に相談する・他の業者に見積もりをもらうなどと理由をつくり、いったん冷静になる時間を設けることが大切です。
悪徳リフォーム業者と契約してしまったときの相談窓口
万が一、悪徳リフォーム業者と契約してしまっても、まだ打てる手はあります。
ここでは、契約してしまった時の相談窓口や対処法を紹介するので、1人で抱えずにすぐに相談するようにしましょう。
契約から8日以内であればクーリングオフを検討する
訪問営業によるリフォーム工事であれば、クーリングオフの対象です。
クーリングオフとは、消費者が契約内容を冷静に見直すために設けられた制度であり、期間内に適用すれば全額返金か最低限の手数料で契約解除できます。
契約日から8日以内であれば、クーリングオフを利用して契約を解除するとよいでしょう。
仮に、工事完了後であってもあわてて代金を支払う必要はありません。
とはいえ、工事を着工されるとクーリングオフや返金、契約解除などの手続きが難しくなるので、基本的には契約後すぐの施工は避けることをおすすめします。
業者の中にはクーリングオフの対象外と応じてくれない場合もありますが、訪問営業であれば対象となります。
どうしても対応してもらえない場合は、次に紹介する消費生活センターや法律のプロに相談することをおすすめします。
なお、リフォーム工事であっても自分から業者に出向いて契約した・業者を自分で呼んで契約した場合はクーリングオフの対象外となるので注意しましょう。
消費生活センターに相談する
- 自分で対応が難しい
- どう対応すればいいのか分からない
- 詐欺か判断がつかない
上記のようなケースでは、消費生活センターへの相談をおすすめします。
消費生活センターでは、消費者トラブルに詳しいプロから適切な対応のアドバイスを受けることが可能です。
電話や対面での相談が可能で、「188」の共通ダイヤルに連絡すれば最寄りの消費生活相談窓口の案内を受けられます。
消費生活センターへの相談時には、契約書や見積書などの書類を用意し、情報を整理しておくとスムーズに相談できるでしょう。
悪徳リフォーム業者のリストの調べ方
悪徳リフォーム業者かどうかの判断は容易ではありません。
悪徳リフォーム業者を避けるためには、事前に評判のよくないリフォーム業者を把握しておくのも1つの方法です。
悪徳��リフォーム業者のリスト自体は存在しませんが、悪質な業者を避けるための参考となる情報はいくつかあります。
ここでは、悪徳リフォーム業者の参考として利用できる情報について紹介します。
消費者庁の建設業処分業者一覧
消費者庁では、悪徳な商法などで処分された業者の一覧が公開されています。
「地域名+建設業処分業者一覧」で検索すると、各自治体が公開する処分事業者の一覧をチェックできるので確認してみるとよいでしょう。
消費者庁の特定商取引法ガイド
消費者庁「特定商取引ガイド 」では、国及び都道府県に処分された事業者の名称・処分内容・取引商品・違反行為などが公開されています3。
年度別で執行状況が把握できるのでチェックしてみるとよいでしょう。
国土交通省のネガティブ情報検索サイト
「ネガティブ情報検索サイト」は、国土交通省が管理する(許可している)業者のネガティブな情報を発信するサイトです。
情報開示の透明性を確保するために、過去の行政処分履歴など事業者自身が公開したがらないような不利な情報を公開しています。
事業分野ごとに検索できるので、リフォーム業者の場合は「建築工事」から「建築�業者」を選択し、自治体など必要項目を入力して検索していきましょう。
まとめ
リフォーム業者のなかには悪徳業者も存在し、高額な請求を受ける・雑な施工をされてしまうなどの恐れがあります。
都合よく不具合が見つかり不安をあおって契約を持ち掛ける、大幅な値引きを提案する・契約を急かすといった業者には注意しましょう。
悪徳リフォーム業者の手口はさまざまですが、特徴を理解しておくだけでも意識が変わってきます。
また、騙されたと感じたら1人で悩まずすぐに公的機関などに相談することが大切です。