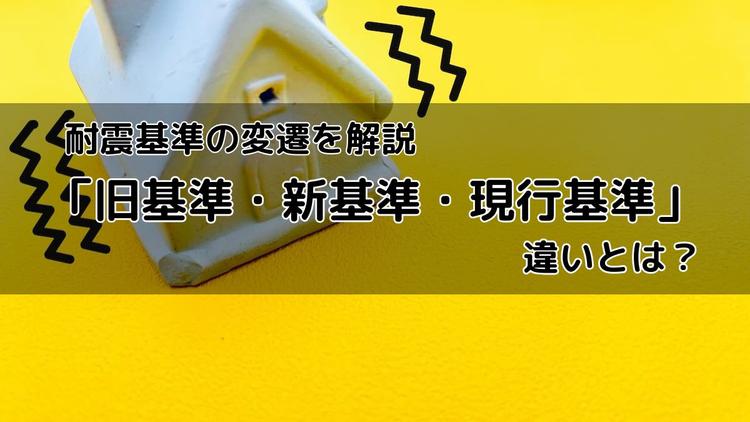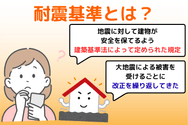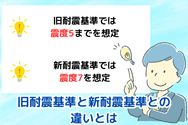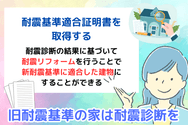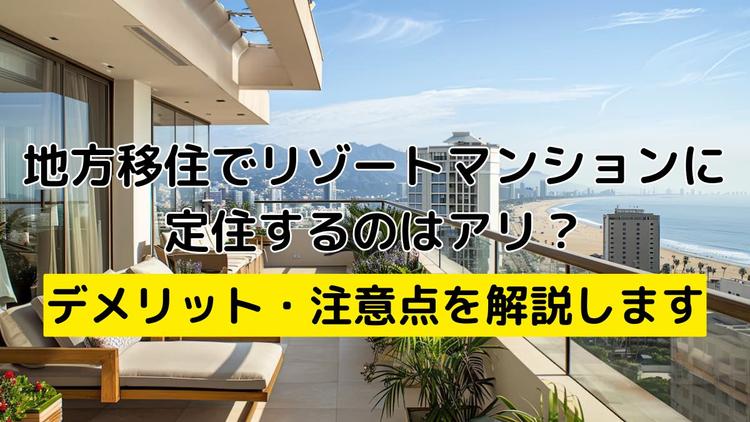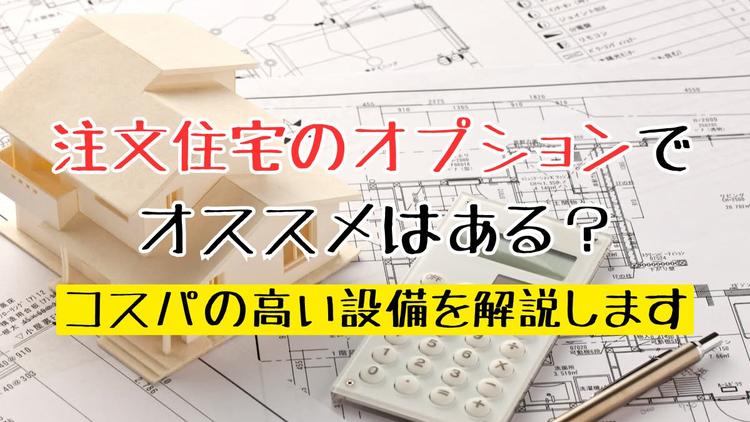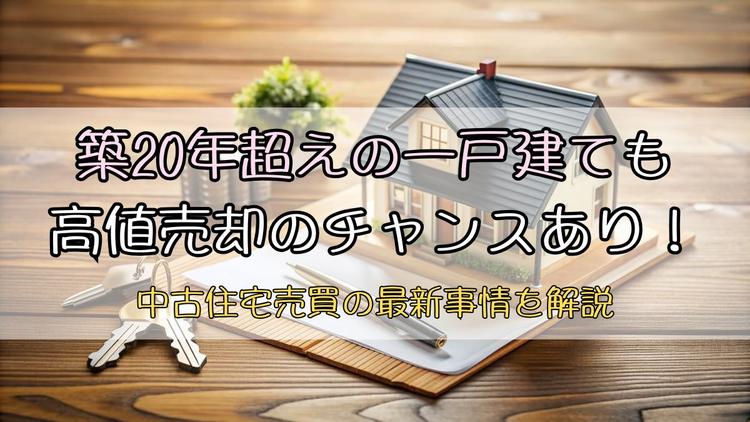耐震基準は地震による建物の崩壊を防ぐための規定です。
過去の地震による被害の教訓から、耐震基準は何度も改正をしてきました。
特に旧耐震基準から新耐震基準への改正は大きな節目とされています。
この記事では、耐震基準の変遷を押さえながら旧基準・新基準・現行基準の違いについて解説します。
耐震基準とは?
耐震基準とは、地震に対して建物が安全を保てるよう建築基準法によって定められた規定です。
耐震基準は、大地震による被害を受けるごとに改正を繰り返してきました。
大きな節目ごとに、次の3種類に分類することができます。
- 旧耐震基準……1950年以降
- 新耐震基準……1981年以降
- 現行耐震基準……2000年以降
現行耐震基準では、耐震性について次のことを目指しています。
- 震度5の地震が起きても建物がほとんど損傷しない
- 震度6〜7の大地震が起きても建物が倒壊しない
震度5の中規模地震は頻発しているため、このクラスの地震では建物はほとんど損傷しないことが求められています。
また、まれに発生する震度6強以上の大地震では、建物自体に損傷があっても、命に危険が及ばない強度が求められています。
耐震基準の変遷の歴史
耐震基準は、実際の地震の被害状況を踏まえて、改正を繰り返してきました。
耐震基準の変遷の歴史を押さえていきましょう。
旧耐震基準(1950年以降)
1923年(大正12年)、関東大震災により建築物に甚大な被害が生じました。
これを受け、その翌年に建築基準法の前身である「市街地建築物法」の基準が改正され、ここで初めて耐震計算の規定が導入されました。
基準では他に、石造やれんが造の建築物の高さ制限、構造種別ごとの規定が耐震性向上のため強化されました。
建築基準法は1950年に施行された法律ですが、耐震基準については「震度5強の地震が起きても建物が倒壊せず、修復が可能である」という、前身の市街地建築物法による基準を引き継いでいます。
以降、何度か基準が見直されることになります。特に大きな改正としては、1968年に発生した十勝沖地震による被害を受けてのものがあります。
この地震では、特に鉄筋コンクリート造の建築物において、柱のせん断破壊(横方向の力で柱が割れる現象)による大きな被害が発生しました。
このため1971年に、その対策として柱をより強くするために、柱内部の帯筋(鉄筋を囲む横方向の補強材)の間隔を狭める規定が導入されました。
新耐震基準(1981年以降)
耐震基準は、1978年の宮城県沖地震を機に1981年に大きく改正されました。
この改正は耐震基準の大きな節目とされており、1981年6月1日の施行日を境に、それまでのものを「旧耐震基準」以降のものを「新耐震基準」と呼んでいます。
この改正では、極めてまれに発生する大地震時において、建築物の倒壊を防止することを目的として、構造計算(二次設計)を主軸とする「新耐震設計法」が導入されました。
これにより、さらに数多くの構造関係規定について見直しが行われました。
現行耐震基準(2000年以降)
1995年に阪神淡路大震災が発生し、甚大な被害が発生しました。
しかしその後の調査によって、新耐震設計法導入(1981年)以降の建築物の被害は比較的軽微だったことが明らかになりました。一方で、多くの木造住宅が倒壊しています。
そのため、2000年には木造建築物の接合部の規定により、新耐震基準をより強化する基準が設けられました。
合わせて、新耐震設計法の導入前に建築された既存建築物の耐震性向上の重要性が認識され、耐震診断や耐震改修を促進するための新たな法制度が設けられるようになりました。
2011年に発生した東日本大震災では、津波による被害を除けば、新耐震設計法導入以降の建築物の被害は比較的軽微でした。ただし、天井の脱落被害が大量に発生したことから、被害の再発防止のための基準の見直しが行われています。
旧耐震基準と新耐震基準との違いとは
中古住宅を購入する場合、新耐震基準で設計された建物であることが、ひとつの選択ポイントとされています。
旧耐震基準と新耐震基準ではどのような点に違いがあるのか解説していきましょう。
旧耐震基準では震度5までを想定
旧耐震基準では「建物の自重の20%に相当する水平力を地震力として作用させた上で許容応力度計算を行う」というものでした。
地震力の定義
地震が発生した際、建物には揺れによって横方向の力(水平力)がかかります。この基準では、建物の「自重(建物そのものの重さ)の20%」を地震による水平力として設定しました。
許容応力度計算
この地震力を建物の構造に加えたときに、柱や梁、基礎などの各部材がその力に耐えられるかを計算します。この計算方法では、材料が壊れない範囲(許容応力度)の中で安全に収まるよう設計することが求められました。
市街地建築物法と建築基準法における設計地震力の違い
建築基準法以前の市街地建築物法では、設計地震力を「建物の自重の10%」と定めていました。
建築基準法では、20%に変更されましたが、部材(柱や梁、床など、建物の骨組みを構成する建築材)の許容応力度も2倍にしたので、実質的な建物の耐震性能は変わりません。
建物の自重の20%とは、10年に一度程度発生することを想定した震度5程度の中規模地震に対して、倒壊あるいは崩壊しないという考えです。
そもそも旧耐震基準では、震度5強よりも大きい地震に対しては想定されていないため、震度6・震度7の大規模地震が発生した際は倒壊する危険があります。
旧耐震基準と新耐震基準では、耐震性能に比較的大きな差があり、大規模な地震が発生した際の被害状況にも顕著な差が見られる。
新耐震基準では震度7を想定
新耐震基準では、震度7の大規模地震でも建物が倒壊・崩壊しないことの検証を2段階で行うことが定められました。
これは、建物の安全性を確保するために、中規模地震と大規模地震の両方に対応することを目的としています。
第一次設計では、震度5の中規模地震に対して、部材の各部が損傷しないことを検証します。
そのうえで第二次設計では、震度7の大地震に対して、建物が倒壊・崩壊しないことを検証します。
大地震で求められる建物の強度は、倒壊・崩壊しないことであり、建物の変形やひび割れまで防ぐものではありません。
つまり、大地震の際にきちんと避難でき、命を守るための空間を確保するという考えに基づいているのです。
現行新耐震基準でさらに強化
1995年に起きた阪神淡路大震災では、多くの木造住宅が倒壊しました。
そのため、同年に「耐震改修促進法」が制定、2000年には建築基準法が改正され、新耐震基準をさらに強化する基準が設けられました。
特に、木材建築物の耐震性強化が重点的に図られています。
地盤調査の義務化
阪神淡路大震災では、地盤の液状化による建物の不同沈下の被害が大量に発生しました。
これを防ぐために、建物を建てる際には構造計算が不要な木造住宅にも地盤調査が義務付けられました。
接合部の金物使用規定
阪神淡路大震災では、壁量計算による基準に適合していながら、柱が土台や梁から抜けたことで倒壊する事例が数多く見られました。
壁量計算とは、建物が地震や風圧による横方向の力に耐えるために必要な「壁の量(耐力壁)」を計算し、設計基準に適合させる方法です。
建物全体のバランスを考えながら、必要な壁量を確保することで横揺れに対する強度を評価します。
阪神淡路大震災の被害を受けて、柱などの接合部に金具を用いて柱の引き抜けを防ぎ、強固にするようになりました。
この新基準を機に、強い衝撃でも柱が梁から抜けないように取り付ける「ホールダウン金物」という補強金物が使用されるようになりました。
耐力壁のバランスを考慮
耐力壁とは、地震の揺れに耐えるために、構造合板や筋交いを取り付けた、構造上非常に重要な役割を担う壁のことです。
木造住宅の旧基準では、直角方向の力に対して、建物全体で必要な耐力壁があればよいという考えでした。
しかし、耐力壁を住宅全体にバランスよく配置することで、耐震性能を高める基準に変更されています。
旧耐震基準と新耐震基準の判別方法
旧耐震基準と新耐震基準の変遷や違いについて解説をしましたが、ここでは売却物件や購入物件の耐震基準がどれに該当するのかを調べる方法について解説します。
建築確認通知書(確認済証)を見る
建築確認通知書とは、新築や増改築を行う際に提出される「建築確認申請書」の内容が建築基準法や条例に適合していることを、建築主事から建築主へ通知する書面のことです。
建物の設計や計画が建築基準法や関連する条例に沿っているかを審査してもらうために提出する書類で、具体的には建物の構造、用途、配置、周辺環境などが記載されています。
この審査を経ることで、計画が適法であるかを確認し、工事を進める許可が得られます。
現在は「確認済証」あるいは「建築確認済証」と呼ばれていますが、1999年4月30日以前は、この書面のことを「建築確認通知書」と呼んでいました。
建築確認通知書(建築確認済証)は、申請から1~3週間程度で発行され、工事期間中は建築士事務所か施工会社が保管しています。
工事が完成したら、建築確認通知書どおりに建物が完成していることを建築主事もしくは指定確認検査機関が検査します。この検査に合格すれば検査済証が発行されます。
建築主(新築物件の買主)は引渡しの際に、建築確認通知書と検査済証を受け取ります。
この2つの書類が揃っていれば適法な建物であることの証となります。
建築確認通知書の発行日で判別する
新耐震基準は、1981年6月1日に施行されました。建築確認通知書(1999年5月1日以降は確認済証)の発行日が1981年6月1日以降であれば、新耐震基準の建物ということになります。
完成日は新耐震基準とは無関係
旧耐震基準か新耐震基準か判別する際に気をつけたいのは、1981年6月1日の直前に建築確認通知書が発行された建物の場合です。
旧耐震基準と新耐震基準では工事費が大きく異なるなるため、この時期に建築費が安くなる旧耐震基準で設計した建物が多く存在しています。
いわゆる「滑り込み」という手法で、1981年5月31日以前に建築確認通知書が発行されるよう急いで建築確認申請をした物件です。
しかし現在では、新耐震基準で設計した建物の方が高く評価されるため、物件の売り込みの際に営業担当者が「この建物は1981年6月1日以降に完成しているので、新耐震基準です」と説明をすることがあります。
1981年5月31日以前に建築確認通知書が発行された建物は、完成日に関係なく旧耐震基準で設計された物件ですので、注意が必要です。
着工日も新耐震基準とは無関係
建築基準法は、工事を始めた時点(着工日)の規定が適用されます。したがって、1981年6月1日以降に着工した建物は、新耐震基準で設計されていなければなりません。
その規定を逆手に取って、「建築確認通知書の発行日は1981年5月ですが、着工したのは6月になってからなので、この建物は新耐震基準の建物です」と売り込む営業担当者がいる可能性があります。
しかし、もしその説明が事実だとしたら、それは違反建築物です。建築確認通�知書が発行されていても、工事着手までの間に改正法が施行されれば、未着工(不適合)の建築確認通知書は無効になるからです。
実際には、こうした大規模改正の施行日には、各行政機関はプロジェクトチームを組んで、管轄内の未着工の工事現場をすべてチェックしますので、そもそもこうした事態はほぼ発生しません。
建築確認通知書の発行日が1981年6月1日以降であることが、新耐震基準で設計された何よりの証なのです。
売却時は建築確認通知書と検査済証を提示する
家の売却では、旧耐震基準建物か新耐震基準建物かによって大きく評価が異なります。売却する家が新耐震基準建物であれば、住宅ローンの融資も通りやすく買手が見つけやすくなります。
仲介する不動産会社が、金融機関に建築確認通知書と検査済証を提示することで、新耐震基準の建物として売り出すことができます。
新耐震基準の建物は旧耐震基準に比べて担保価値が高くなるので、融資額にも有利に働きます。
買主の立場からすれば、住宅ローンの融資額が大きいのは、魅力のひとつです。
もしこれらの書類が見あたらない場合は、市役所(人口10万人程度以上)か都道府県で、交付済証明書を発行してもらえるので、自身の市区町村の役所で確認してみてください。
旧耐震基準の家は耐震診断を
家の耐震性能に不安がある場合は、建築士事務所や地元の工務店に耐震診断を依頼する方法があります。
耐震診断の方法
耐震診断は、日本木造住宅耐震補強事業者協同組合の「一般耐震技術認定者」を取得した技術者が、旧耐震基準で設計された住宅の耐震性能を現在の耐震基準に照らして診断をします。
予備調査によって住宅の築年数、経年による形状変化、使用歴などを確認し、診断レベルを決めます。
耐震診断にかかる費用は、依頼する会社、建物の構造、広さなどの要件によりますが、10万〜40万円程度です。
自治体によっては助成や無料診断を受けられる制度を設けているところもあります。
耐震基準適合証明書を取得する
耐震診断の結果に基づいて耐震リフォームを行うことで、新耐震基準に適合した建物にすることができます。
工事後に建築士に依頼すれば、「耐震基準適合証明書」を発行してもらえます。
発行手数料は、建築士にもよりますが2万〜5万円程度です。
この証明書によって、建物が現在の耐震基準に適合していることを第三者に証明することができます。
中古住宅の買主が住宅ローンを利用する場合、多くの金融機関は新耐震基準を満たしている物件であることを条件としています。
また、住宅ローン控除や不動産取得税の減税措置を受ける際にも、新耐震基準を満たしていることが求められます。
このような状況において、新耐震基準に適合していることを証明するのが「耐震基準適合証明書」です。
まとめ
耐震基準は、大地震による被害を受けるたびに改��正を繰り返してきました。大きな節目としては、次の3種類に分類することができます。
- 旧耐震基準……建築基準法施行時である1950年以降
- 新耐震基準……1981年6月1日以降
- 現行耐震基準……2000年6月1日以降
旧耐震基準では震度5を超える地震を想定していなかったため、震度6以上の大地震に被災すると建物が倒壊するおそれがあります。
新耐震基準の建物は、震度7クラスの大地震で建物が変形する可能性があるものの、倒壊の危険がないよう設計されています。
この記事を参考に、自身が所有、あるいは購入を検討中の不動産の耐震性をチェックし、大規模な地震が起こった際にどれくらいの被害が起こり得るか確認することを推奨します。