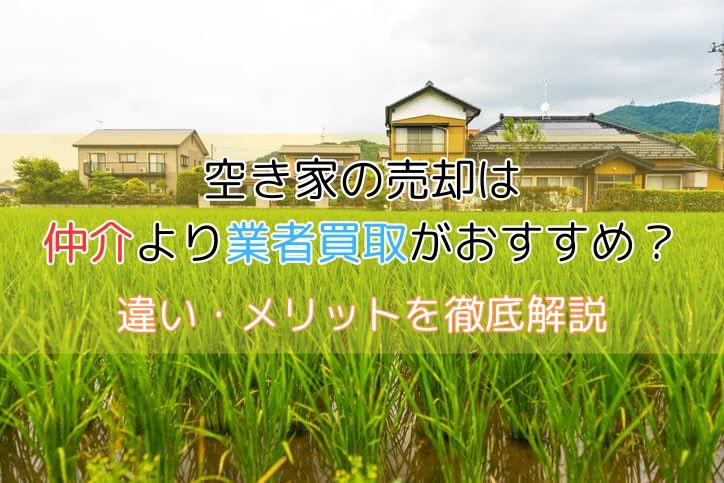高度成長期からバブル景気の時代、不動産が何より堅実な資産として重んじられた「土地神話」は、もはや過去の話となりました。
しかし現代の日本においても、一般のサラリーマンにとって、不動産・住宅購入は一世一代の決心を下す大きな買い物であることに変わりはありません。人口減の時代と言われつつも、今でも利便性の高い立地の不動産は、資産として変わらず機能しています。
その一方で現在では、資産どころか売りたくても売れない、手放したくても捨てることもできない、持っているだけでコストが掛かる、まさに負債としか言いようのない「負動産」の存在も広く語られるようになってきました。
「負動産」の現状
バブル期に1億円で買った不動産が今では1000万円にしかならない、という話ではありません。1000万円の不動産は今でも1000万円の資産です。
ところが昨今話題になる「負動産」は1000万円どころか、そもそも不動産としての価値が低すぎて値段が付かない、売買の仲介に取り組んでくれる不動産会社も見つからないという代物です。
安い物件の売却に苦戦する理由
不動産の特殊性として、価格が安いからと言って売りやすいとは一概に言えないどころか、むしろ安い物件のほうが逆に売るのに苦労するという性質があります。
数千万円の高額の物件は、確かにおいそれと気軽に手を出せる価格ではない反面、多くの方が欲しがる条件のよい商品であるからこその数千万円という価格なので、買い手は探しやすく、仲介業者も進んで取り扱います。
一方で10万円、20万円といった価格の不動産は、仲介に掛かる手間は同じなのに需要が少なく売却まで時間を要するということで、こうした価格帯の物件の仲介に積極的な不動産会社はほとんどありません。
価格が付かない負動産の例
価格が付かない物件として代表的なものが、
- 購入者が農業従事者に限られる農地
- 車両が横付けできないような山林や斜面(崖地)
- 所有しているだけで数千~数万円程の固定資産税や管理費が発生する別荘地やリゾートマンション
などです。
シャッター街と化した地方の小都市の旧市街地の物件も、商業地として需要がないにもかかわらず、建物がRC造で堅牢なために固定資産税や解体費用が高額で、そのために価格が付かなくなっているケースもあります。すべてに共通しているのが、利便性が低く、供給の多さに対して需要が極めて限られている点です。
不動産業者を介さない個人間売買
低価格の物件を手放す場合、仲介業者の手を借りず、自力で売却するという手段もあるにはあります。数年前の話ですが、筆者自身も、所有していた千葉県芝山町の36坪の宅地を、個人売買サイトの「ジモティー」を通じて、個人の方に30万円で売却したことがあります。
広告の写真撮影や文章を自分で書き、問い合わせもすべて自分で応対し、登記も自分で行ったので、手数料を支払う必要もなく、売買代金の30万円がそのまま手元に残りました。
しかしこれは私がその売地の近隣に住んでいたからできたことであり、これが例えば相続した土地で遠方に住んでいたとしたら、どうなるでしょうか。
いくら仲介手数料が発生しなかったとしても、交通費や時間をかけて自力で30万円で売却できたところで、その労力や交通費などを考えれば、はたしてそれは「売れた」と言えるのか微妙な話です。
絶対に誰も買わない、引き取らないとは言い切れない物件であったとしても、売却に至るまでの労力や人件費が物件価格を上回ってしまうようであれば、それはもはや「負動産」と言わざるを得ません。
負動産の有償引取サービスが登場
こうした「負動産」の増加に呼応して、昨今登場した新手のサービスが、「負動産の有償引取サービス」です。従前であれば不動産を手放す方法として、仲介を依頼して買い手を探すか、ある��いは業者に買い取ってもらうかの2通りの手段だったものが、逆に所有者が業者にお金を支払って、「負動産」を引き取ってもらうというサービスです。
遠方在住であったり、また高齢でその余力もないために、その負動産の処分に要する手間暇を、業者にお金を払うことで省略できるという仕組みです。
引取後の物件はどうなる?
では業者はその引き取った「負動産」をどうするかというと、空き家や空き地など、根気良く買い手を探せば売れる可能性があるものについては、一般の不動産同様に自社物件として売りに出しています。ある投資家向け物件サイトでは、100万円以下の低価格帯の売家・売地の広告を出す有償引取業者を頻繁に見かけます。
あるいは自社サイトで売りに出す業者もあれば、ジモティーなどで1万円といった低価格で売りに出すこともあります。引き取りの時点ですでに旧所有者から手数料を受け取っているわけですから、販売価格には頓着がなく、反響が鈍ければどんどん値下げを繰り返して処分を急ぐ会社もあります。
ただそれらは決して売れ筋の不動産ではありませんから、場合によっては不良在庫として長期間抱え持つリスクを孕むものです。買い手が決まるまでの間は維持管理費や固定資産税も要します。
そのため業者は、ある一定期間の所有コストを、元の所有者に肩代わりしてもらう形で有償引取を行っているのです。
お金を払って不動産を処分するという発想は、負動産に縁のない方には分かりにくい感覚かもしれません。しかし、一般の仲介業者に冷たくあしらわれ、手放す手段もわからず、ただ所有コストばかり嵩んでいく負動産の所有者にとっては切実な話です。
ではこの「有償引取サービス」は、今後ますます地価の下落が進行していくであろう地方部や農村の負動産所有者にとって救世主となりうるサービスかと言えば、残念ながら今の時点では一概に歓迎できるものではないというのが実情です。
有償引取サービスの問題点
実はこの有償引取サービスは、その存在が広く知られるようになった当初から、主に以下の2点について重大な懸念を持たれていたものでした。
①不明瞭な根拠で算出される引取価格
有償引取りサービスの業者の存在が最初に広く知られ始めたのは、各地のリゾート地に建つリゾートマンションの所有者の間でした。
新潟県湯沢町が特に有名ですが、バブル期以前に建築されたリゾートマンションは、需要を大きく上回る供給過多の状況が長く続き、10万円程度の価格の売物件が大量に存在する「負動産」の代名詞のような存在です。市場ではほぼ無価値に近い存在でも、鉄筋コンクリート製の高層建築物であるために固定資産税は数万円に及び、さらに毎月の管理費の支払いも要します。
購入したものの高齢になって使わなくなったり、あるいは不本意に相続する羽目になって、その処分に悩む方は少なくありませんでした。そうした消極的な所有者に宛てて、2010年代半ば頃から、「リゾートマンションの買取処分」を謳ったダイレクトメールが頻繁に届くようになっていきました。
売主負担の費用が発生
「買取」とは言っても、ダイレクトメールをよく読むと、買取価格は1��万円。ただし買取の条件として、数年分の固定資産税や管理費、処分のための「引取費用」「手数料」の支払いが必要で、結局売主側が数十~数百万円の費用を負担しなければ引き取ってもらえない旨の記載があり、つまり有償引取の勧誘にすぎないものです。
それ自体は、リゾートマンション市場の現状を考えればやむを得ない面も確かにあるのですが、問題なのは、これらの業者は、売主からは「数年分の管理費」の名目で費用を受け取っているにもかかわらず、いざ所有権を移した後は、一切の管理費を支払うことなく滞納し続けていたことです。
不動産取得税、固定資産税すらも納付せず、標的となったマンションの管理組合には、税務署や自治体からの問い合わせも相次ぐようになりました。
これでは当初ダイレクトメールで呈示していた「引取費用」とはいったい何だったのか、強い疑念が残ります。広告宣伝を介さない二者間の直接取引なので、その売買契約の詳細がオープンになることもなく、「引取費用」の根拠が極めて曖昧なまま、不誠実な有償引取が横行していました。
管理組合が引取業者の利用について注意喚起
同様の手口と思しき会社のダイレクトメールは今でも見かけますが、管理費を滞納される管理組合にとっては災難で、各地のリゾートマンションの管理組合が、組合員に対し、こうした引取業者の勧誘には応じることのないよう、会社の実名を挙げて注意喚起を継続的に行っています。管理組合や管理会社が滞納が続く部屋の差し押さえを申し立て、競売に掛けるケースもあります。
これが仮に真っ当に管理費の支払いを行う事業者であったとしても、自社で収益物件として運用するわけでもない負動産の管理費を、際限なく負担し続けていては事業は成り立ちません。引取業者としても早々にその負動産を手放さなくてはコストが嵩む一方になるわけですが、ではその引取物件を手放すまでにどの程度の時間やコストを要するのかについては、それはもう一般の不動産の査定同様、ケースバイケースとしか言えないものです。
その引取費用を算出する根拠がどこまで客観性のあるものなのか、素人の売主では判断のしようがありません。悪意があればそれこそ前述の業者のように、本当は管理費を払う意思もないのに「数年分の管理費」を要求することもできてしまうわけです。
「普通に売れる物件」を有償引取業者が扱う事例
別の悪質なケースとして、本来は通常の売却が可能な不動産でありながら、旧所有者を言いくるめて逆に「処分費用」を支払わせ、引き取った後は易々と第三者に売却していた、という事例もあります。
実際に引取業者名義の物件の登記には、引取り後のわずか2~3か月後に、さらに別の個人に売却している形跡が見られるものもありました。そもそもダイレクトメールが送られてきているリゾートマンションのすべてが売却不可能な「負動産」というわけでもなく、普通に中古物件としてマンションを購入したオーナーにも同様の勧誘が行われています。
地元業者が仲介で扱うクラスの不動産を有償で引き取る事業が、はたして所有者にとって最善の選択肢と言えるでしょうか。
②出口戦略のない無差別な引き取り
これは有償引取サービスの利用者ではなく、むしろ同業である他の引取業者や一般の不動産業界関係者の間で広がっている懸念ですが、引取業者の中には、その負動産を引き取った後の処分方法や、いわゆる「出口戦略」を深く考慮することなく、目先の手数料だけを目当てに無差別に引き取っているのではないか、との疑念を持たれている事業者があります。
筆者が思い込みだけで疑念を呈しているのではなく、国土交通省不動産・建設経済局不動産業課が2025年2月に発表した『不動産取引に掛かる新たなサービス形態について』においても、
との懸念を示しています。業界関係者の中にはもっと露骨に「引き取るだけ引き取って計画倒産するに違いない」とまで言い切る者もいます。
実際、前項のリゾートマンションを狙い撃ちにした引取業者は、法人登記自体は今も残っているものの既に営業の実態はなく、同じ代表が新たに立ち上げた別名義の法人で、今なお同様の事業を行っています。
これは極めて抑止の難しい課題です。なぜなら法人というものは、誠実に運営していたからと言って必ずしも事業が順調に進むという保証はなく、やむを得ず破綻・解散に至るケースなどいくらでもあるからです。
筆者もこれまで負動産の取材を進める中で、引取業者に限らず、すでに解散、あるいは経営の実�態がない法人名義の不動産を数限りなく目にしてきました。しかし、その法人の解散が意図的なものであったかどうかなど確かめる術はありません。
引取業者の倒産・解散によって負動産が放置されるケースがある
資産を隠したまま自己破産を行えば犯罪ですが、法人が不動産を所有したまま倒産・解散することなどよくあることです。
それが意図的な計画倒産であったとしても、資産隠しが発覚しない限りは刑事責任を問われることもなく、競売に掛ける価値もない、行き場のない負動産が放置されてしまうでしょう。一部の引取業者は、まさにそこに出口を求めているのではないか、という疑念が持たれているのです。
深刻な矛盾点として、まともに管理する意思のない業者ほど負動産の維持コストを下げられる=同業者間の価格競争において優位に立てる、という点も見過ごすことはできません。
解散法人名義の不動産であっても、再び市場に流通させる手段がないわけではないのですが、そもそもお金を払わなければ処分すらできないような負動産を、わざわざ多大なコスト負担と面倒な法的手続きを経て所有権を移すような物好きなど皆無です。誰も管理責任を負わない、相続も発生しない解散法人名義の負動産は、行くあてもなく放置され続けているだけというのが現状です。
有償引取サービスの課題
この有償引取サービスの難しいところは、サービスの利用者である負動産の所有者自身にとっての問題は、引取費用が(その所有者にとって)高額であるかどうかという点が一番重要であり、所有者が納得できる額で、なおかつ確実に所有��権が移転されれば、その後の負動産の行く末についてまで深く思慮する必要がないという点です。
所有権が移ってしまった以上、すでにその負動産の処置に関与する権限もありませんし、散々その処分に悩んだ末の「有償引取」なのに、その先さらに積極的に関与しようとする旧所有者はいないでしょう。お金を支払ったにもかかわらず所有権が移転されなかったという、完全に詐欺としか言いようのない事例も報告されているので、その点の見極めは慎重に行わなくてはなりません。
しかし、今回の記事で述べたような、計画倒産を画策している恐れがあるとか、将来的に管理不全・所有者不明土地が増加する恐れがあるという懸念をいくら負動産の所有者に力説したところで、切実に悩む所有者への抑止力は期待できないであろうというのが筆者の本音です。
有償引取サービスを利用する際に注意すべきこと
そもそも、コストを掛けなければ手放すことができない負動産が存在すること自体は揺るぎない事実ですので、その所有者の苦悩を差し置いて有償引取のリスクについて話を進めても、では他にどんな解決方法があるのだと言われれば、返す言葉もありません。
ですので筆者は個人的には、負動産の所有者に対して、一律に「有償引取業者は利用すべきではない」と述べるつもりは今のところありません。法規制もなく野放し状態の有償引取業界の健全化を掲げた、引取業者5社で運営される任意団体も設立されていますので、国交省の見解も出された今後は、「有償引取業者」としての明確な指針も示されるかもしれません。
しかし現時点ではこの有償引取サービスというビジネスモデルは、その手数料についていまだ明確な基準や指針もなければ、一部業者の不誠実な費用請求を規制する法律もない、倫理観を捨てた方が収益性が高まるという性質を根本的に抱え持つビジネスであるということを念頭に置いたうえで、利用については慎重な判断と見極めを行うべきです。
▼関連記事:「負動産」はどのように利活用されている?