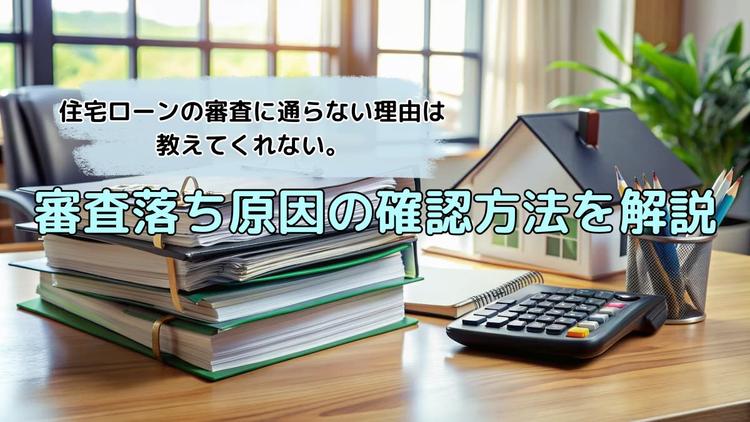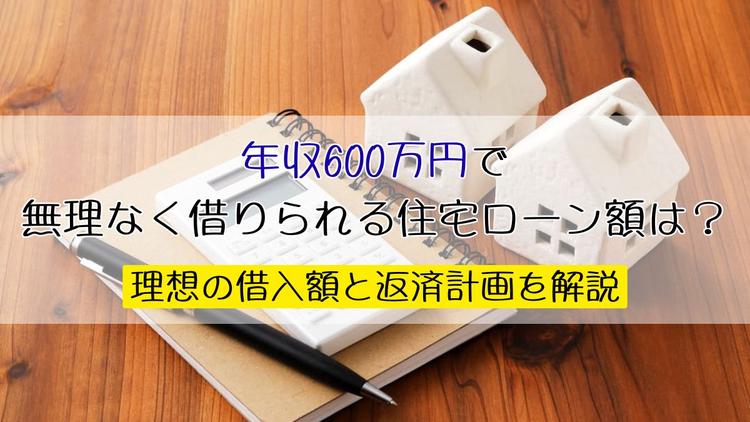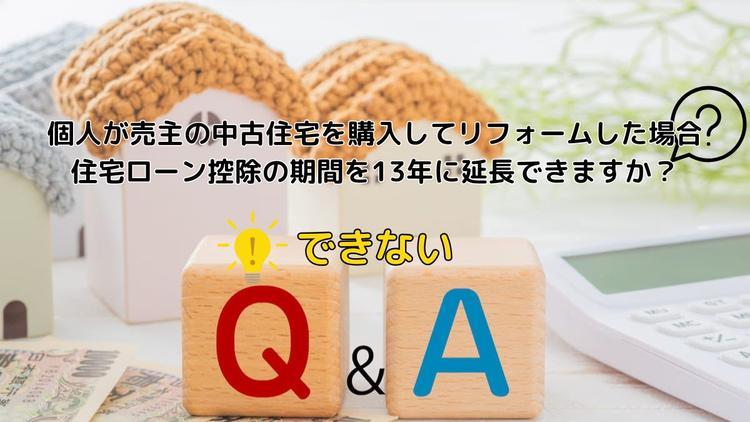不動産取引では、契約締結や引渡しが完了した後に、物件の不具合が発覚することがあります。買主にとっては想定外の損害が生じる一方、売主にとっても、すでに終わったと思っていた契約が再び問題化する事態になりかねません。
こうした場面で重要になるのが「追完請求(ついかんせいきゅう)」です。これは、契約書に記載がない不具合が見つかった「契約不適合」の場面で、買主が売主に対して修補や代替物の引渡し、欠陥部分の補足提供などを求める請求を指します。
この記事では、不動産売買後に追完請求が行われる典型的なケースや、請求の手順、請求をする際の注意点について解説します。
追完請求とは何か?
不動産を購入した後に、雨漏りや排水の詰まり、面積の違いなどの不具合が発覚することがあります。このような場合、買主が売主に対してまず求めるのが「追完請求」です。
追完請求は、引渡された物件が契約の内容に適合していない場合に、その状態を修補・是正するよう求める法的手段となります。2020年の民法改正によって導入された「契約不適合責任」に基づく請求のひとつであり、最初に行使すべき優先的な救済手段と位置づけられています。
たとえば、次のようなケースで適用されます。
- 雨漏りがある → 屋根の修理を求める
- 排水が機能しない → 排水管の修繕を求める
- 契約と異なる面積 → 減額や是正を求める
追完請求が成立するには、「契約内容と異なる不具合」であることに加え、「発見後すみやかに売主へ通知する」ことが必要です。また、契約に免責特約がある場合でも、売主が不具合を故意に隠していた場合は責任を免れない可能性があります。
追完請求は、契約を守るための正当な要求であり、重大な不具合に対しては次の損害賠償や契約解除につながる第一段階となります。
不動産売買後に追完請求が生じる典型的なケース
不動産の売買契約は、多くの書類や専門家の関与を経て慎重に進められていきます。しかし、丁寧に取引が行われたとしても、引渡し後に思わぬ不具合や欠陥が発覚することは少なくありません。こうした場面で買主が売主に対して追完請求を行うことは、法的に認められた正当な権利です。
この章では、実務上よく見られる「追完請求が発生する典型的なケース」について、事例を交えて紹介します。
雨漏り・屋根の不具合
最も多い追完請求の原因のひとつが、引渡し後に発覚する「雨漏り」です。契約締結時や内見時には目立った問題がなくても、実際に住み始めてから雨天が続くことで天井や壁の染み、室内への水の侵入が明らかになることがあります。
売主が雨漏りの存在を知っていたにもかかわらず説明しなかった場合はもちろん、知らなかった場合でも、契約不適合責任を問われる可能性があります。
給排水設備の不具合
排水管の詰まり、逆流、下水の悪臭など、目に見えにくい生活インフラの不具合も追完請求の対象となります。たとえば、次のようなケースです。
- トイレの水がスムーズに流れない
- キッチンのシンクから異臭がする
- 雨水が正しく排水されず、建物基礎部分に溜まっている
これらは「通常の使用に耐えない設備」であり、「契約に適合しない」と判断される余地があります。
シロアリ・腐食による構造材の損傷
購入後に床下や壁内にシロアリの被害が見つかった場合、建物の安全性を損なう重大な欠陥として追完請求の対象となることがあります。
構造体の腐食や蟻害は、表面上は分からず、解体や点検を行って初めて判明することが多いため、売主が説明責任を果たしていなかった場合には特に争いになりやすい分野です。
建物の傾き・基礎の沈下
床にボールを置くと自然に転がる、建具が自然に開閉するなど、建物の傾きや沈下が引渡し後に明らかになる場合もあります。
軽微な�傾きであれば生活に支障がないとされることもありますが、次のような状態であれば、契約不適合と認められる可能性が高くなります。
- 明らかに体感できるレベルの傾き
- 建物の一部が陥没し始めている
- ドアや窓が開閉しない
- 地盤沈下による基礎の亀裂
こうした不具合は、修補に多額の費用がかかることも多いため、追完請求のほか損害賠償や契約解除の争いに発展することもあります。
追完請求の流れと必要な対応
不動産売買後に不具合や欠陥が発覚した場合、買主は契約不適合責任に基づいて「追完請求」を行うことができます。
しかし、請求が認められるかどうかは、単に不具合が存在するだけでなく、発見からの対応の迅速さ・正確さにかかっています。この章では、追完請求を行う際の基本的な流れと、実務上の留意点について解説します。
不具合の発見と証拠の保全
追完請求の出発点は、不具合の発見です。異変を発見したら、まずすべきことは状況の記録と証拠の確保です。後に売主と交渉したり、訴訟など法的手段に進んだりする際に、この初動の対応が重要な判断材料となります。
たとえば次のような対応が有効です。
- 不具合の写真や動画を撮影する(例:雨漏りの染み、シロアリの痕跡など)
- 発覚日時・状況をメモに残す(例:「〇月〇日、雨天時に天井から水が滴った」)
- 専門業者(リフォーム会社、住宅診断士など)に調査を依頼する
- 可能であれば報告書・見積書を取得しておく
第三者の客観的な資料があることで、「買主の主観」ではなく「事実としての不適��合」が明らかになりやすくなります。
売主への通知(相当の期間内)
契約不適合責任に基づく追完請求を行うためには、民法566条に基づき、「相当の期間内に通知する」ことが必要です。
通知のポイントは次のとおりです。
- 一般的には、不具合の発見から2週間~1か月以内が目安
- 書面(特に内容証明郵便)による通知が望ましい
- 単なる口頭連絡やメールのみでは、証拠性が弱い
通知書では、次の内容を明記するのが一般的です。
- 物件の売買契約の概要(契約日、物件所在地など)
- 不具合の具体的内容
- 発見日時と経緯
- 売主に対し、追完(修補・是正)を求める旨
たとえば、「〇年〇月〇日売買契約により取得した建物において、〇月〇日に屋根からの雨漏りが確認されました。よって、当該不適合についての追完(修補)を求めます」といった文面です。
売主との協議と合意形成
通知後は、売主との協議に入ります。売主が追完請求に応じる意思を示した場合、修理内容・範囲・費用負担・期間などの条件を詰める必要があります。
合意にあたっては次のポイントを押えてください。
- 作業内容や実施業者を明確にする(買主が指定する業者か、売主側で手配するか)
- 補修完了までのスケジュールを定める
- 補修にかかる費用負担を文書で確認する
- 応急対応で済ませるのか、本格的に是正するのかを明確にする
合意内容は、できる限り書面化し、双方が署名・押印した合意書を交わすことが理想です。後日のトラブル防止に役立ちます。
修補の実施と��完了確認
合意に基づき修補が行われた後は、買主による完了確認が必要です。工事が不十分であったり、新たな不具合が発生した場合には、再度の追完や損害賠償の検討も必要となるため、慎重にチェックしましょう。
この段階で行うべきことは、次のとおりです。
- 修補内容の確認(修理箇所のビフォーアフターを写真に残す)
- 専門業者が行った場合は報告書を受け取る
- 修理後も問題が再発しないか、一定期間観察する
修補が適切に完了すれば、追完請求は完了となります。
売主が応じない場合の次のステップ
売主が追完請求に応じない場合、あるいは不誠実な対応を取る場合には、次の法的ステップへと進みます。
選択肢は次のとおりです。
- 代金減額請求:補修できないことを前提に、相当額の減額を求める
- 損害賠償請求:補修に要した費用、仮住まい費用などを請求する
- 契約の解除:重大な不適合で契約目的が達せられない場合
これらの請求に進むには、まず売主に対して修補の機会を与える必要があります。
また、こうした段階では法的な争いに発展することもあるため、不動産に詳しい弁護士や専門家への相談が望まれます。
契約書・重要事項説明書との照合も不可欠
追完請求の成否を左右する重要な要素が、「契約書や重要事項説明書に記載されていた内容」との整合性です。
たとえば、次のような場合は追完請求が否定される可能性があります。
- 「本物件は現状有姿で引き渡す」との免責条項がある
- 「〇〇は売主の責任で補修済み」と明記されていた
- 重要事項説明書にて、現状の劣化や不具合について説明され、買主が同意していた
一方で、たとえ免責条項があっても、売主が重要な不具合を知りながら告げなかった場合(=説明義務違反)には、契約不適合責任が認められる余地もあります。
売主が注意すべきポイント
不動産の売買において、買主から追完請求を受けるリスクは決して低くありません。引渡し後に雨漏りや構造上の不具合、越境問題などが発覚した場合、売主は「契約不適合責任」を問われ、修補や損害賠償を求められる可能性があります。
特に個人の売主にとっては、想定外の出費や法的トラブルにつながりかねず、適切な対応が不可欠です。
告知義務を誠実に果たす
売主には、物件に関する既知の事実を正確に開示する義務(告知義務)があります。特に次のような情報は、買主に対して明確に伝える必要があります。
- 過去に雨漏りやシロアリ被害があったこと
- 排水の詰まりや異臭、設備の不調
- 増改築の履歴(確認申請・検査済証の有無)
- 越境・境界に関するトラブルの有無
これらを意図的に隠して売却した場合、たとえ「契約不適合責任免責」の特約があっても、説明義務違反や不法行為責任を問われる可能性があります。
契約書に明確な特約を盛り込む
特に個人売主(一般の個人が自宅を売却する場合)は、引渡し後の責任を限定する目的で、次のような特約を契約書に盛り込むことがあります。
- 「本物件は現状有姿で引き渡し、契約不適合責任を負わない」
- 「売主は建物の状態について調査を行っておらず、その性能を保証しない」
ただし、このような免責条項が有効とされるのは、買主が内容を十分に理解し、納得のうえで合意している場合に限られます。
引渡し前の点検・事前修繕を怠らない
後日のトラブルを防ぐには、引渡し前に設備や��構造の点検を行い、可能な範囲で事前に修繕しておくのが望ましいです。また、売主自らが行った補修や修理についても、履歴を残し、買主に提示しておくことで、信頼性が高まります。
買主が注意すべきポイント
不動産の購入は、人生で最も高額な買い物のひとつです。しかし、見た目や売主の説明だけでは判断できない「隠れた不具合」や「契約内容との食い違い」が、引渡し後に発覚することも少なくありません。
そのようなとき、買主には契約不適合責任に基づく「追完請求」を行う権利がありますが、それを適正に行使するには事前の理解と事後の冷静な対応が欠かせません。
契約内容と説明書を丁寧に確認する
追完請求をする際には、「何が契約内容と食い違っていたのか」が問われます。そのため、契約書や重要事項説明書の記載を事前によく確認しておくことが重要です。
次のような記載がある場合は、追完請求が認められない可能性もあります。
- 現状有姿での引渡し
- 契約不適合責任を免除する特約
- 境界や越境の不明確性についての同意
一見些細に見える条項でも、請求の可否に大きな影響を与えることがあります。
不具合を発見したらすぐに対応する
契約不適合責任を追及するには、「相当の期間内に通知すること」が法律上の要件です。気づいた時点ですぐに売主へ連絡し、証拠を残すことが極めて重要です。
通知の遅れや、日常的な使用で明らかになっていた不具合の放置は、後に「買主にも過失があった」と判断され、請求が棄却されることがあります。
インスペクションや専門家の活用
中古物件では、見えない部分に不具合が潜んでいることがあります。契約前に建物状況調査(インスペクション)を依頼し、客観的な診断を受けておくことは、後の請求の根拠づけにもなります。
また、不具合発見後の対応についても、リフォーム業者や弁護士など専門家に早めに相談することで、感情的な対立を避け、合理的な解決策を探ることができます。
▼関連記事:既存住宅状況調査(インスペクション)とは|検査項目や物件売買時のメリットを解説
まとめ
不動産売買後に不具合が発覚した場合、買主は契約不適合責任に基づいて追完請求を行うことができます。雨漏りや排水不良、シロアリ被害などが典型例であり、速やかな通知と証拠の確保が重要です。
売主は告知義務を誠実に果たし、契約書に免責条項を設けることでリスクを軽減できます。一方、買主は契約内容を正しく理解し、インスペクションや専門家の助言を活用することで不利益を回避できます。
追完請求をめぐるトラブルを防ぐには、取引前後を通じた丁寧な対応が不可欠です。