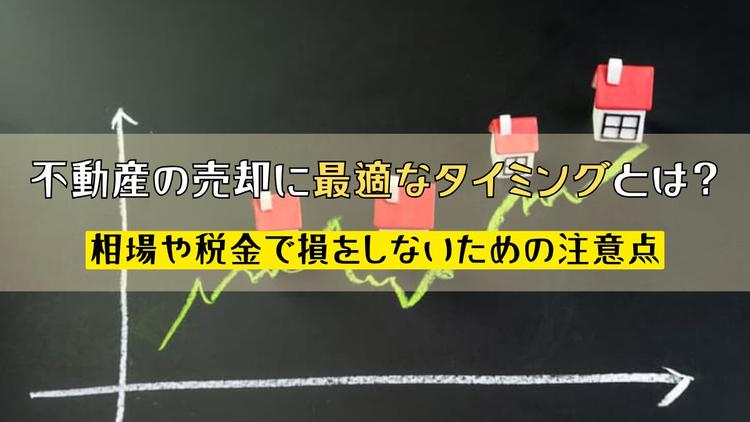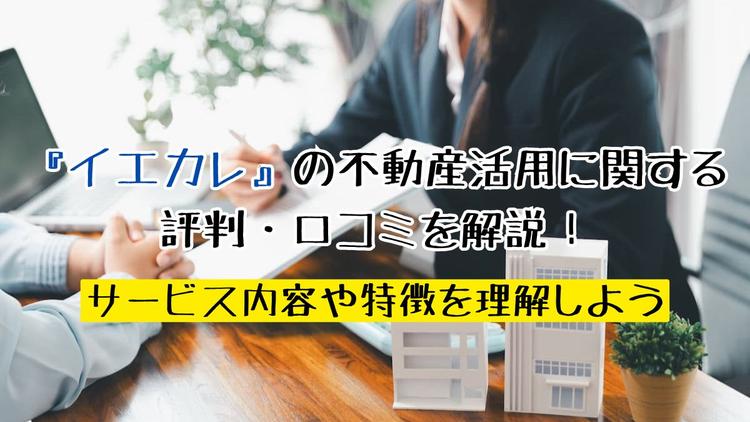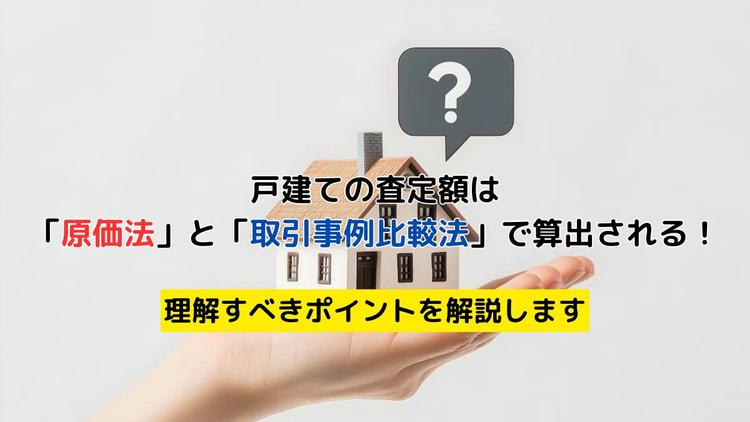不動産の売買を検討する際には、相場の動向をチェックすることも重要です。
不動産価格は常に変動しているので、最新の情報をチェックして将来の予測をたてる必要があります。
とはいえ、不動産相場の変動をどうやって把握すればいいか分からない方もいるでしょう。
そこでこの記事では、不動産相場の変動を予測する際に役立つ指標を分かりやすく解説します。
不動産価格のトレンドを知るのに役立つ指標
不動産価格のトレンドを知るのに役立つ指標としては以下の3つが挙げられます。
- 国土交通省の不動産価格指数
- 民間調査会社が発表する各種不動産価格指数
- 公示地価や路線価などの公的価格
それぞれ見ていきましょう。
国土交通省の不動産価格指数
不動産価格指数とは、年間約30万件の不動産取引価格の情報をもとに価格の動向を指数化したものです。
2010年1月~12月の平均価格を100として、全国・ブロック別・都市県別に毎月公表されています。
2025年の不動産動向指数は以下のとおりです1。
| 住宅総合 | 住宅地 | 戸建住宅 | マンション | |
| 2025/01 | 141.1 | 115.7 | 117.4 | 210.2 |
| 2025/02 | 143.4 | 115.5 | 120.8 | 214.5 |
| 2025/03 | 146.7 | 118.6 | 125.4 | 216.6 |
| 2025/04 | 142.1 | 117.2 | 118.5 | 213.2 |
たとえば、2025年4月の戸建て住宅の指数は118.5となるので、2010年平均の1.18倍になっていることが分かります。
不動産全体で見ても上昇傾向ですが、とくにマンションは2010年の2倍以上と高騰傾向です。
民間調査会社が発表する各種不動産価格指標
不動産の価格指標は国土交通省だけでなく、各民間調査会社なども独自のデータで調査・公表しています。
たとえば、東日本不動産流通機構ではマーケットデータとして取引価格などの各種不動産取引情報を公表しています。
東日本不動産流通機構の「首都圏不動産流通市場の動向(2024年)」によると、首都圏の中古マンション価格は平均4,890万円となり12年連続で上昇しています。
戸建ても3,948万円と4年連続の上昇です。
不動産流通機構は、東日本・中部圏・近畿圏・西日本の4つの地域に分かれているので、所在地の情報をチェックするとよいでしょう。
また、国内最大規模の不動産データベースを構築している東京カンテイでは、中古マンション価格や賃料、戸建価格などのデータのチェックが可能です。
不動産価格の動向を天気図で示した価格天気図など分かりやすいデータもあるので、価格動向のチェックに慣れていない人でも利用しやすいでしょう2
公示地価や路線価などの公的価格
上記のように実際の不動産取引によって決定される市場価格は「実勢価格」と呼ばれます。
それに対し、国や都道府県が公表する不動産の評価額が公的価格です。
公的価格は各種税金などの算出で用いられるだけでなく、不動産価格の動向を知るうえでも役立ちます。
不動産の公的価格としては、以下の4つが挙げられます。
- 公示地価
- 都道府県基準地価
- 路線価
- 固定資産税評価額
それぞれ見ていきましょう。
なお、それぞれ
公示地価
公示地価とは、適正な地価の形成を目的として毎年国土交通省が発表する土地の価格です。
1月1日時点の標準地の価格を3月頃に公表しています。
公示地価は公共事業用地の価値算出や、土地取引の目安として活用されており、実際価格は公示地価の1.1~1.2倍が目安です。
ただし、都市部など立地によっては1.5倍以上になるケースもあるので、エリアの相場などを踏まえて参考にするとよいでしょう。
地価公示のデータは「全国地価マップ」または「不動産情報ライブラリ」の地図データから確認するのが便利です。
都道府県基準地価
都道府県基準地価とは、都道府県が公表する基準地の価格です。
毎年7月1日時点の基準地の価格を9月頃に公表しています。
公示地価は基本的に市街化区域内が対象であるのに対し、基準地価は市街化区域外も対象としています。
また、公示地価とは価格を算出・公表する時期が異なることから、公示地価の補完として活用されるのが一般的です。
基準地価も「全国地価マップ」または「不動産情報ライブラリ」で確認可能です。
路線価
路線価(相続税路線価)とは、主要な道路に面する土地の価格です。
毎年国税庁が発表しており、相続税や贈与税を計算する基となります。
路線価は公示地価の8割ほどになるのが一般的です。
相続税路線価は国税庁のWEBサイトで確認できます。
固定資産税評価額
固定資産税評価額とは、都道府県が算出する土地や建物などの固定資産ごとの評価額です。
固定資産税や都市計画税、各種登録免許税などを算出する際に利用されます。
固定資産税評価額は公示地価の7割ほどになるのが一般的です。
▼関連記事:固定資産税評価証明書の取得方法
過去30年の不動産価格の推移
ここでは、各種データをもとにこれまでの不動産価格の推移をみていきましょう。
国土交通省による2008年から2024年の不動産価格指数の動向は以下のとおりです。
2013年以降すべての不動産で価格が上昇傾向にあり、とくにマンション価格は急騰していることが分かります。
次に、東日本不動産流通機構の「年報マーケットウォッチ2023年・年度」をもとに首都圏の中古マンション・戸建の価格推移をみてみましょう3。
| 中古マンション | 戸建住宅(全体) | |
| 1995年 | 2,679万円 | 4,416万円 |
| 2000年 | 2,052万円 | 3,866万円 |
| 2005年 | 2,107万円 | 3,260万円 |
| 2010年 | 2,566万円 | 3,129万円 |
| 2015年 | 2,892万円 | 3,124万円 |
| 2020年 | 3,599万円 | 3,231万円 |
| 2021年 | 3,869万円 | 3,561万円 |
| 2022年 | 4,276万円 | 3,844万円 |
| 2023年 | 4,575万円 | 3,908万円 |
戸建住宅は1995年以降2015年にかけて下降し、以降上昇傾向にあります。
しかし、2023年では1995年の水準に達していません。
一方、中古マンションは一時期下降していましたが、2005年以降右肩上がりに上昇し、2023年では1995年の倍近い価格になっているのが分かります。
どちらのデータをみても、過去の推移では下降・横ばいも時期もありますが、現在の不動産市場は上昇傾向があるといえるでしょう。
将来の不動産価格の変動を予測するのに使える日経平均株価
日経平均株価とは、プライム市場(旧東証一部)の上場銘柄から選定した225銘柄の平均株価のことです。
日経平均や日系255などとも呼ばれ日本の株式市場の動きを把握するうえで代表的な指標として活用されています。
株価の変動は不動産市場と関係ないように見えますが、日経平均株価は不動産価格とも相関関係にあると考えられており、不動産価格の動向を予測するうえでも重要な指標です。
不動産価格は株価の半年~1年程度遅れてピークを迎える
日経平均と不動産価格は、一般的に日経平均が上がると不動産価格が下がる、日経平均が下がると不動産価格も下がるという関係性があると言われています。
これは、株価が上昇することで投資家の資金が増加し、不動産取引が活発になるからと考えられています。
とくに、マンションは投資対象となりやすいことから、戸建てより強くこの傾向が現れることがあります。
ただし、日経平均が上がれ��ばすぐに不動産価格が上昇するわけではありません。
不動産は購入しようと考えてから実際に購入するまで3ヵ月~半年ほど時間がかかります。
株式に比べて流動性が低いことから、不動産価格は日経平均に遅れて動くのです。
日経平均に必ずしも不動産価格が連動するわけではありませんが、その傾向があるため不動産価格との相関関係が見られる指標として参考の1つにするとよいでしょう。
過去の日経平均株価と不動産価格の推移
過去の日経平均と不動産価格の推移は以下のとおりです。
日経平均にマンション価格が緩やかに連動しているのが分かります。
日経平均は2008年のリーマンショック、2019年からのコロナ禍などの影響により上下はあるものの長期的には上昇傾向にあります。
また、同様にマンション価格も上昇を続けています。
なお、戸建は個別性や地域性が高く、投資よりも居住目的の取引が多い傾向があるため、マンションほど株価の影響は受けないともいわれています。
とくに地方の戸建ては株価とは異なる動きを見せるケースも多いので、地域性などの要素も考慮して価格の動向をチェックするようにしましょう。
不動産価格が上昇している理由
不動産価格はなぜ上昇傾向にあるのでしょうか。
ここでは、不動産価格が上昇する理由として以下の4つを解説します。
- 金融緩和によるインフレ
- 人件費の高騰
- 資材の高騰
- 円安
それぞれ見ていきましょう。
金融緩和によるインフレ
日銀は2010年頃から金融緩和政策を開始し、2013年には大規模な金融緩和政策、2016年にはマイナス金利政策を導入しています。
これにより住宅ローン金利が低くなったことで住宅ローンを組みやすくなり、高額な不動産を買いやすい状況となりました。
とはいえ、不動産の供給量が急激に増えることはないため量は変わらず、不動産にかけるお金だけが増えている状況です。
つまり、お金の価値が下がるインフレとなっていることから、不動産価格が上昇しているように見えていることになります。
2024年にはマイナス金利の解除や利上げの動きもあることから、不動産価格のマイナス要因になる可能性も指摘されています。
▼関連記事:住宅ローン金利の上昇で不動産売却が難しくなる?利上げの影響と売却に苦戦した場合の対処法を解説
人件費の高騰
少子高齢化の進む日本では労働人口も減少していることから、人件費は高騰傾向にあります。
人件費が高騰すれば、新築時の人件費が上がることから新築価格の上昇につながります。
さらに、新築価格が上がると、価格の高い新築を避けて中古の需要が高まることから中古価格の上昇にもつながるのです。
結果として、不動産全体の価格上昇につながっていると考えられます。
資材の高騰
2021年頃から始めったウッドショックと呼ばれる輸入木材の高騰だけでなく、近年は住宅資材や設備が高騰傾向にあります。
また、建築資材だけでなくガソリン代や電気代も高騰傾向です。
人件費同様、これらの住宅をつくるためのコストが高くなることで、不動産全体の価格上昇につながります。
円安
円安が続くことで、近年は割安な日本の不動産を購入する外国人投資家が増えています。
とくに、都心部のマンションや観光地などは多くの外国人投資家に購入されており、価格上昇をけん引している状態です。
また、円安は輸入資材の高騰につながる点も、不動産価格の上昇要因となります。
今後不動産価格が暴落する可能性がある状況とは?
今後の不動産価格は、都市部と地方での価格の二極化や高騰し過ぎた不動産価格の調整が進むと見られています。
そのため、都市部では上昇や安定した推移が進む一方、地方では価格が下がる可能性もあります。
とはいえ、リーマンションやコロナ禍のような市場混乱が起きない限り、短期間で大暴落する可能性は低いと考えられます。
しかし、今後の不動産価格の下落要因もあるので、変動につながる要素を押さえておくことが重要です。
ここでは、不動産価格の下落の可能性についてみていきましょう。
人件費や資材は引き続き高止まりする可能性が高い
高騰傾向の続く人件費や住宅資材は、今後高止まりする可能性があります。
人件費や資材費が高騰を維持すると、建築コストが上昇することで新築価格の上昇、さ��らに新築を避けた中古の需要による価格上昇につながります。
しかし、人件費や資材費の高騰で不動産価格が上昇し過ぎると購入が難しくなることから、買い控えが起き需要減少、価格の下落につながる可能性があるでしょう。
日本国内の景気低迷
インフレが継続することで、日本国内に景気が低迷すると買い控えなどにより不動産価格が下落に転じる可能性があります。
不動産価格は日経平均に遅れて連動する傾向もあるため、景気が低迷し日経平均が大きく下がると遅れて不動産価格も下落する可能性があるでしょう。
不動産に関する税制の変更
不動産に関する税制が変更されると、不動産価格にも影響が出ます。
住宅ローンを利用してマイホームを購入した際に適用できる住宅ローン控除は、現状では2025年末までに入居した人のみが利用可能です。
住宅ローン控除が適用できないと購入者の税制上のメリットが大きく損なわれる為、購入意欲の減退から買い控えが起こり不動産価格の下落に転じる可能性があるでしょう。
ただし、住宅ローン控除は当初の終了予定が延長して2025年末となっており、2026年以降も延長する可能性はあります。
とはいえ、2025年7月末時点では延長について公表されておらず、仮に延長しても今の控除とは条件が異なる可能性がある点には注意しましょう(2022年の税制改正時も、控除できる税額が減少した)。
これから不動産の購入を検討する人だけでなく、売却を予定している人も買い手の資金に影響するため、動向を注視しておくことが大切です。
利上げやトランプ関税などを理由に円高になる
長らく続いた日銀の金融緩和政策は2024年3月に解除されています。
さらに、同年7月、2025年1月には政策金利の引き上げが行われたことで、住宅ローンの変動金利が上昇傾向を見せています。
住宅ローン金利が上昇すると借り手が住宅ローンを利用しにくくなる、借入額が下がることで不動産価格の下落につながる可能性があるのです。
また、日銀の利上げだけでなくトランプ関税などの要素で円安から円高に転じれば、海外投資家からの不動産需要が下がる恐れがあります。
トランプ関税により今後厳しい関税が課されると日経平均に影響が出る点も、不動産価格に影響がでる可能性があります。
不動産相場の予測に関するよくある質問
最後に、不動産相場の予測に関するよくある質問をみていきましょう。
2025年に不動産価格の大暴落はあり得る?
引き続き不動産価格は横ばい、または緩やかに上昇すると見られていますが、下落の可能性がゼロではありません。
とくに地方では価格の二極化により下落の可能性があるので動向には注意しましょう。
ただし、短期間で大暴落する可能性は高くはありません。
とはいえ、将来の価格予測を正確に行うのは不可能であり、インフレや政策金利の状況などのよっては下落の可能性もあります。
今が高いから今後も高いとは限らないので、売却を検討する場合は上昇傾向のある今が売り時と言えるでしょう。
東京の不動産価格は今後どうなる?
都心部の不動産は今後も価格が上昇もしくは維持する可能性が高いでしょう。
た��だし、東京の不動産であってもエリアや不動産種類などによって価格の変動は異なります。
都心部の新築マンションは価格が高騰している一方、郊外のマンションや戸建は価格が下落する恐れもあります。
東京であっても今後の価格の動向を注視しつつ売却判断を行うようにしましょう。
不動産価格や住宅価格は今後下がる?
不透明な部分が多いですが、直近のインフレや資材高騰・円安などの要素により高止まりまたは上昇の可能性が高いと考えられます。
しかし、住宅ローン金利の利上げなど下落要素もあります。
不動産価格は、エリアや物件の種類によっても大きく異なり、経済などの影響も受けるので今後の価格動向はしっかりチェックすることが大切です。
まとめ
不動産価格の動向を把握し、今後の予測を建てることで売却タイミングを見極める一つの材料にできます。
近年は不動産価格は上昇傾向が続いており、今後も上昇が続く可能性があります。
とはいえ、日銀の政策金利による住宅ローン金利の上昇など下落する可能性もゼロではありません。
不動産市場の動向は注視しつつも、売却を検討するなら上昇傾向がある今がベストなタイミングと言えます。
将来を含め、不動産の売却を考えているのであれば、一度イエウリで売却査定してみることをおすすめします。