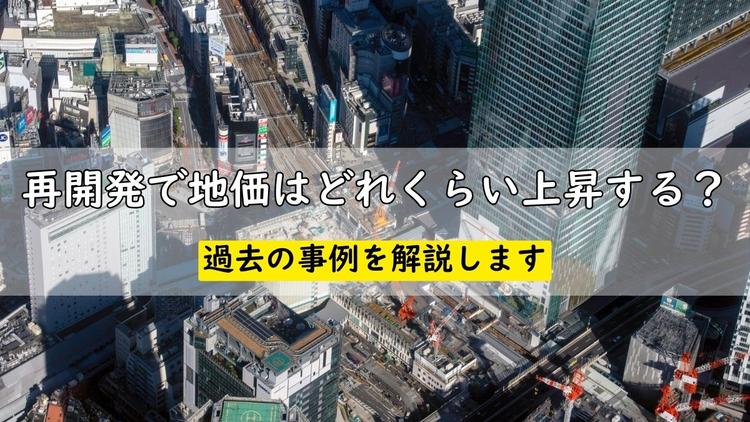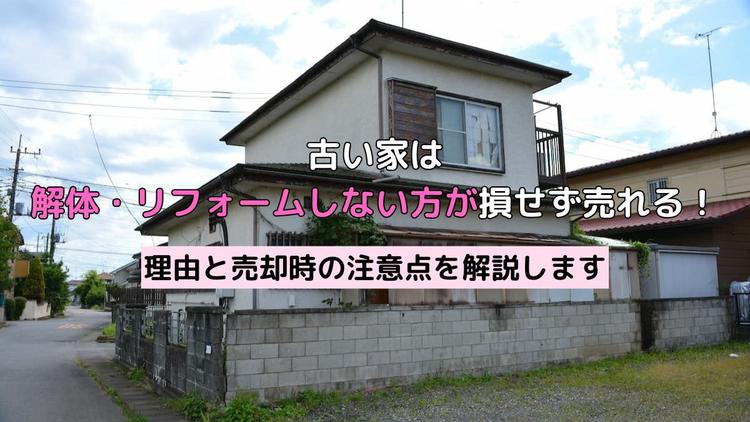がけの上や下に家を建てる際はがけ条例によって規制がかかる可能性があります。
とはいえ、がけ条例がどのような規制か、そもそも敷地が「がけ」に該当するのか分からないという方もいるでしょう。
この記事では、がけ条例の基本や規制内容、がけ条例にかかる土地の注意点を詳しく解説します。
がけ条例とは?
建物を建築する際には、建築基準法などさまざまな法律や条例をクリアする必要があります。
その中の1つが「がけ条例」です。
敷地周辺にがけがあると建物建築時に制限を受ける条例
がけ条例とは、がけの上または下に建物を建てる際の規制です。
がけの上や下に無制限に建物を建てると、地震や大雨でがけとともに流される・押しつぶされるといったリスクがあります。
このようなリスクを回避するために、一定のがけ周囲に建物を建てる際にかかる制限をがけ条例といいます。
「条例」のため自治体ごとに内容が若干異なる
がけ条例は、建築基準法のように国が制定した法律ではなく、自治体ごとに条例として定めているルールです。
そのため、自治体によって制限の内容が異なります。
同じ条件の土地であっても、A自治体なら建物は建築できるけどB自治体では建築できないというケースは珍しくありません。
土地の購入や建築を検討する場合は、所在地の自治体のがけ条例を確認することが大切です。
なお、「がけ条例」というのは通称で正式名称ではありません。
がけ条例の正式名称も自治体によって異なり、たとえば東京都であればがけ条例は「東京都建築安全条例第6条」が正式名称です。
条例を調べる際には正式名称が自治体ごとに異なる点にも注意しましょう。
がけ条例の規制内容
ここでは、がけ条例の具体的な規制内容をみていきましょう。
不動産における「がけ」とは
不動産において「がけ」とは一般的に以下の条件を満たす土地を指します。
- 2mを超える硬岩盤以外の土質
- 傾斜が30°を超える土地
ただし、建築基準法上では「がけ地」についての明確な定義はありません。
各自治体の条例でがけ地は定義されているため、上記とは異なるケースがある点には注意しましょう。
また、コンクリートで基準通り作られた擁壁であればがけに該当しないが、古い石積みや道路との高低差ががけに該当してしまうといったケースもあります。
見かけでは「がけ」のイメージに該当しなくでも条例の対象となるケースもあるので、敷地内に大きな高低差がある場合はがけに該当するか不動産会社などに確認するようにしましょう。
一定の高さ(2mが一般的)を超えるがけがある場合に規制を受ける
がけ地の定義は自治体によって異なりますが、一般的には傾斜30度、高さ2mもしくは3mとがけ地とする自治体が多いため、がけの高さが2mあれば規制を受ける可能性が高いと考えてよいでしょう。
なお、がけの高さとはがけのもっとも低い部分からもっとも高い部分までの垂直距離です。
がけの斜面の距離とは異なるので注意しましょう。
がけの下から「がけの高さの1.5~2倍以上」距離を離す必要がある
がけ条例の対象となる場合、がけの下もしくは上に建物を建築する場合は、がけから一定の距離を離すか擁壁の設置が必要です。
がけから距離を離す場合、一般的には以下の位置には建物の建築が�できません。
- 【がけ下】がけの上端から水平距離ががけの高さの1.5~2倍に相当する位置
- 【がけ上】がけの下端から水平距離ががけの高さの1.5~2倍に相当する位置
たとえば、がけの高さが3mの場合、がけ下なら上端から敷地内に向けた水平距離6m以内、かげ上なら下端から敷地内に向けた6m以内に建物が建築できません。
がけの高さや敷地の広さによっては規制に合わせて建物を建築しようとすると、建物が敷地からはみ出してしまうとなりかねないので注意しましょう。
がけの崩壊に備えてRC造など構造の制限を受ける場合がある
がけ条例では、建物を建築できる範囲だけでなく建物自体の構造に対して制限を設けるケースもあります。
たとえば、東京都では、 一定のがけ下に建物を建築する場合、安全な擁壁の設置が必要です1。
既存擁壁の安全性が確認できないときは、建物の主要構造部を鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造にする必要があります。
擁壁の設置を求められるケースがある
擁壁とは、がけや盛土などの側面から土砂の崩壊を防ぐために設けられる壁上の構造物をいいます。
がけ条例では、建物建築に制限のかかる位置に建物を建てる場合は擁壁の設置が必要です。
なお、擁壁を設置して建物を建てる場合、擁壁が一定の基準を満たしていることが条件となります。
すでにある擁壁でも、安全性の基準を満たさない場合は建物を建てられないので注意しましょう。
仮に、すでにある擁壁が安全性の基準を満たさない場合は建て替えなどが必要です。
しかし、擁壁が隣地をまたいでいるなどで所有権や建て替え費用を巡ってトラブルになるケースもあるので注意が必要です。
▼関連記事:擁壁の安全性を調査すべきケースとは?
東京都のがけ条例
がけ条例は自治体によってがけの定義や制限の内容などが異なるため、条例を確認する際には所在地の自治体のホームページで最新の情報をチェックすることが大切です。
ここでは、一例として東京都のがけ条例をみていきましょう。
東京都建築安全条例では、がけ条例の規制を受ける範囲を以下のように定めています。
(がけ)
第六条2 高さ二メートルを超えるがけの下端からの水平距離ががけ高の二倍以内のところに建築物を建築し、又は建築敷地を造成する場合は、高さ二メートルを超える擁壁を設けなければならない。
つまり、がけの下端からがけ高の2倍以内の距離に建物を建築する際には擁壁の設置が必要です。
ただし、傾斜の勾配が30度以下や斜面が堅固な地盤である、建物の主要構造がRC造りなどであれば擁壁の設置は必要としません。
また、擁壁についても構造や排水措置などの細かい規定が設けられています。
がけ地に建物を建てる場合、さまざまな制限をクリアする必要があるので、事前にハウスメーカーや不動産会社に相談しながら土地の購入や建築を検討することが大切です。
がけ条例に関する注意点
ここでは、がけ条例に関する注意点として以下の3つをみていきましょう。
- がけ条例にかかる場合は売買時に重要事項説明書に記載する必要がある
- 擁壁の設置には数百万円の費用がかかるケースがある
- 自治体の判断で建築確認申請が下りないケースがある
それぞれ解説します。
がけ条例にかかる場合は売買時に重要事項説明書に記載する必要がある
売買の目的となる土地ががけ条例の制限を受ける場合、売買契約前に交付される重要事項説明書に「がけ条例が適用される」といった旨の記載が必要です。
また、擁壁が必要な場合もその旨の記載や説明が必要になります。
がけ条例の制限を受ける土地では、建築に制限がかかる・擁壁の設置で高額なコストがかかるなどが生じることから、買主の購入意思を大きく左右します。
がけ条例が適用されることを知らずに購入すると買主が大きな不利益を被る恐れがあるでしょう。
がけ条例の適用について告知せずに売却すると、契約不適合責任を問われるなど大きなトラブルに発展する恐れがあるので注意が必要です。
▼関連記事:傾斜地・崖地で擁壁がある家、土地を売却する際の注意点を解説
擁壁の設置には数百万円の費用がかかるケースがある
建築するために擁壁が必要、既存の擁壁があるけど建て替えが必要となれば高額な費用がかかります。
擁壁にはさまざまな種類がありますが、がけ地条例で基準を満たす擁壁は主にRC造りまたはコンクリートブロックを積み上げた間知擁壁です。
擁壁の種類や構造によっても費用は異なりますが、たとえばRC造りの場合1㎡あたり3~10万円が目安となります。
仮に、1㎡あたり5万円の擁壁を高さ2m、幅10mで設置すると100万円費用がかかります。
擁壁が必要な土地の場合、建築時には擁壁のコストも含めて購入や建築の判断を行うことが大切です。
なお、自治体によっては擁壁の設置について補助金を設けているケースもあるので、事前に確認することをおすすめします。
自治体の判断で建築確認申請が下りないケースがある
がけがある土地で建築できるかは自治体の判断によっても異なってきます。
擁壁があるから問題ないと思っていても、既存の擁壁が建築申請手続きされていないなどの理由から、がけ条例をクリアできないケースは珍しくありません。
また、建築する位置だけでなく構造や基礎など考慮しなければならない点も多くあります。
土地を購入してから希望の家が建築できない、建築コストが想定以上かかるとなっても購入の取消はできません。
そのため、がけのある土地を売買する際には専門家にしっかり相談しながら取引を進めることが大切です。
がけ条例に関するよくある質問
最後に、がけ条例に関するよくある質問をみていきましょう。
がけ条例にかかる土地を購入することはできる?
購入自体は問題ありません。
しかし、購入後に希望の活用ができるかはがけ条例などによって異なってきます。
法的に問題のない土地かどうかは慎重に調べるようにしましょう。
がけ条例の緩和条件とは?
がけ条例で�は、がけの上と下の一定の範囲内に建物の建築ができません。
しかし、擁壁を設ける、建物の構造の基準を満たすなどで建築範囲の規制が緩和されるケースがあります。
ただし、緩和条件は自治体によって異なるので、所在地の自治体の条例を確認する・ハウスメーカーなどの専門家に相談するようにしましょう。
がけ条例のかかる土地に家を建てることはできる?
がけ条例の基準を満たせば家の建築は可能です。
たとえば、擁壁を設ける、がけから一定の距離を設けることで建築できるケースがあります。
しかし、がけ条例が適用されると建築に制限がかかるだけでなく、建築コストも高くなるといった恐れがあります。
事前に希望の家を建築できるかはしっかり確認するようにしましょう。
まとめ
がけ条例では、高さ2mもしくは3mのがけがある土地ではがけの上と下の一定の範囲内での建物の建築が制限されます。
さらに、建物を建てる際には擁壁が必要、構造や基礎の基準を満たさないといけないなど制限が生じるケースもあるので注意しましょう。
ただし、がけ条例は自治体によって制限の内容が異なります。
検討している土地ががけ条例にかかるか、希望の家が建てられるかは、不動産会社や自治体に確認したうえで判断するようにしましょう。