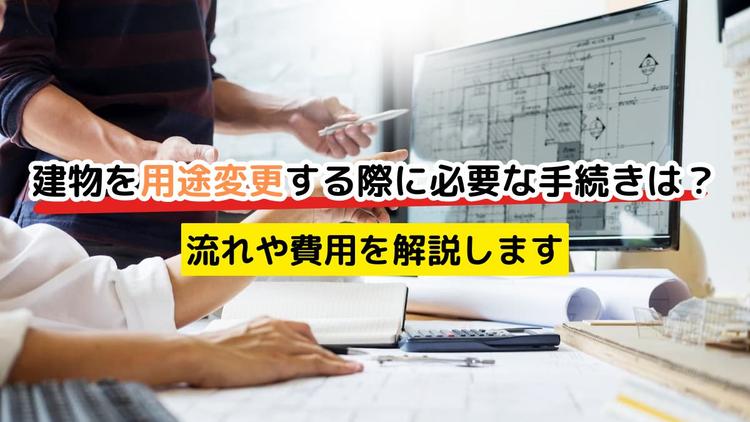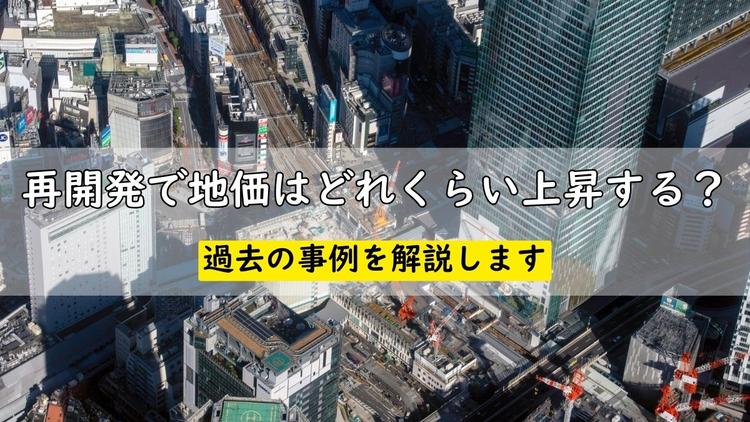土地の売買で重要な確認事項として「都市計画道路予定地」があります。
都市計画道路予定地とは、将来的に道路として使用されることが計画されている土地のことです。
現在は住宅や店舗などとして利用されていても、いずれは道路として整備される可能性があるため、利用や売買に制限が生じることがあります。
この記事では、都市計画道路予定地に該当する不動産の概要や、購入・売却する際の注意点を解説します。
都市計画道路予定地とは何か
都市計画道路予定地とは、都市計画法に基づき、将来道路として整備されることが予定されている土地を指します。
都市計画道路予定地での売買時の注意点を知るために、ここではまず、都市計画道路の基本的な内容を押えておきましょう。
都市計画道路とは
都市計画道路とは、都市計画法に基づいて市区町村などの地方自治体が、将来整備することを想定して定める道路のことです。
道路の種類には、幹線道路、生活道路、バイパスなどさまざまなタイプがあり、都市の機能を支える骨格として重要な役割を果たします。
都市計画道路の整備は、都市の防災、交通の円滑化、環境の改善、市街地整備など、多様な目的のために実施されます。
計画が決定された段階では、まだ工事は始まっていないものの、将来的にその土地が道路として利用される予定です。
このような都市計画道路の指定は、「都市計画」の一環として行われます。
都市計画とは、都市が秩序ある発展を遂げるための長期的なビジョンと方針を定める制度であり、次のような複数の計画要素から構成されています。
たとえば、
- 区域区分(市街化区域・市街化調整区域など):都市の発展を促進すべき区域と、抑制すべき区域を区分する基本方針。
- 地域地区(用途地域、防火地域、風致地区など):土地利用の制限や誘導を通じて、適切な都市機能の配置を図るもの。
- 都市施設(都市計画道路、公園、下水道など):都市機能を支えるインフラ整備に関する計画。
- 市街地開発事業(土地区画整理事業、市街地再開発事業など):実際に街をつくるための事業計画。
- 地区計画:ある特定の地域に対して、建物の形態や用途、道路の配置などを細かく定める計画。
都市計画道路は、これらの中の「都市施設」に位置づけられ、市街地における混雑緩和や防災機能の強化を図るため、一定の長期ビジョンに基づいて設計されます。
また、都市計画審議会などの手続きを経て正式に決定され、「用途地域」や「地区計画」と並ぶ都市整備の重要な方針の一つとなっています。
都市計画道路予定地の調べ方
その土地が都市計画道路予定地はどうかは、登記簿には記載されていません。
確認するには、市区町村が公開している「都市計画図」や「都市計画情報」を閲覧する必要があります。
近年では、インターネットで都市計画情報を公開している自治体も増えており、住所や地番を入力するだけで簡単に確認できる場合もあります。
また、不動産会社を通じて、対象地が都市計画道路に該当するかどうかを調べてもらうことも可能です。
都市計画道路の進行段階
都市計画道路は、都市計画法に基づいて段階的に整備が進められていきます。
各段階によって土地の制限内容が大きく異なるため、自分の不動産がどの段階に該当するかを把握することが非常に重要です。
都市計画決定
都市計画道路は、都市計画審議会の議決を経て、対象地域が将来の道路予定地として指定されます。この段階では、実際の整備工事や用地買収はまだ始まっておらず、「将来的に道路になる予定がある」という状態です。
都市によっては、何十年も事業化されないケースも少なくありません。また、廃止されることもまれにあります。
道路の幅員や通過位置などはすでに概ね決まっており、将来的にどの建物が立ち退き対象となるのか、ある程度予想することが可能です。
ただし、この段階では建物の建築も可能であり、都市計画法第53条に基づく許可1も原則として不要です。構造や階数に関しても特別な制限は設けられていません。
そのため、都市計画決定の段階にある土地では、一般的な建築行為(住宅の新築や増築など)を行うことが可能ですが、将来的に事業決定された際には建築制限を受ける可能性があることは認識しておく必要があります。
また、売却時には、買主にとって心理的な不安要素となる場合もあるため、その点も配慮した方がいいでしょう。
事業決定
都市計画道路の事業決定とは、行政が具体的に整備を進める段階に入ったことを意味します。告示(都市計画法第20条第1項)により都市計画道路の計画が正式に効力を持ち、事業の予算が計上され、用地買収や設計業務が開始されます。
告示後は、都市計画道路予定区域内での建築行為に、都市計画法第53条第1項に基づく都道府�県知事または市長の許可が必要です。新築はもちろん、増築や大規模な修繕、用途変更も制限対象となり、事実上、土地の自由な活用が難しくなります。
また、第53条の許可を得るためには「構造が堅固で、かつ容易に移転または除却することができる建築物であること」などの条件が課され、構造や階数が制限を受けることがあります。
2階建て以下の簡易な建物でなければ許可が下りにくく、鉄筋コンクリート造などの強固な建物は許可されないのが一般的です。
ただし、これらの条件は地域や案件によって異なるため、計画地ごとに市区町村と事前に相談を行うことが不可欠です。
着工~供用開始
用地買収の目処が立つと、道路の造成工事が始まります。既存の建物は立ち退き・解体され、補償手続きなどが進められます。
特に、2年以内に事業の執行が予定されているものは、特定行政庁により建築基準法第42条第4号道路として指定されます。そのため、造成工事中であっても、沿線の土地は接道している敷地として建築が可能です。
道路の造成工事が完了すると、その土地は正式に道路として使用されます。
建築基準法第42条は、建築物を建てるために必要な「道路」の定義を示しており、第4号では次のように規定されています。
道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法、新都市基盤整備法、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法又は密集市街地整備法による新設又は変更の事業計画のある道路で、二年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したもの
つまり、まだ道路として完成していなくても、
- 都市計画で整備が決まっている
- 2年以内に事業執行予定がある
- 幅員や線形が明確で、道路の形状が確保されている
- 行政が「建築基準法上の道路」として指定している
これらの条件を満たせば、「建築基準法上の道路」として取り扱われ、敷地が接道していれば建築許可を取得できるのです。
都市計画道路予定地のリスクと制限とは
都市計画道路予定地に該当する土地を購入・所有する場合、将来の土地利用や資産価値に大きく影響する重要なリスクや制限を理解しておく必要があります。
以下で、具体的なポイントを紹介します。
建築に関する制限がある
都市計画決定の段階では建物の新築や改築は可能ですが、事業決定がなされると都市計画法第53条に基づく建築制限が課されます。道路予定区域内では原則として新たな建物の建築が制限され、建て替えや大規模な改修は許可制となります。
許可を得るためには、建築物が容易に移転・除却できる構造であり、階数は2階以下、構造は軽量鉄骨造や木造などに限定されるのが一般的です。
また、既存建物についても増築や用途変更が認められない場合があります。これにより、将来的なリフォーム計画が制限され、賃貸物件としての柔軟な活用や空室対策が困難になる可能性があります。
資産価値の下落リスクがある
将来的に土地の一部または全部が収用される可能性があることから、不動産としての流動性が低下し、一般市場での評価も低くなる傾向があります。
買い手にとっては「いつ道路になるかわからない」という不確実性がネックとなり、売却価格が下がる原因になることも少なくありません。
特に、将来の整備時期が未定のまま都市計画決定のみされている土地は、実質的に放置されやすく、資産活用の自由度が大きく制限されるというデメリットを抱えます。
立ち退きのリスクがある
事業決定以降は、行政による用地買収が行われ、最終的には土地や建物の収用が進��められることになります。
これに伴い、所有者は立ち退きを余儀なくされる場合があり、補償金が支払われるとはいえ、現在の生活や事業活動に大きな影響を及ぼします。
補償額は時価評価に基づいて算出されるため、必ずしも所有者の希望額が通るとは限りません。場合によっては代替地の確保が困難になるなど、生活再建に苦労するケースもあります。
ローン融資への影響がある
金融機関によっては、都市計画道路予定地に該当する土地について、住宅ローンや融資の審査を厳しく行うことがあります。
担保価値の低下や、将来的に行政に明け渡す必要がある収用のリスクを懸念し、融資額を減額したり、融資そのものが断られたりすることもあるのです。
都市計画道路予定地の売買時の注意点
都市計画道路予定地に該当する土地や建物を売買する際には、いくつかの注意点があります。
特に、将来的な活用に影響を及ぼすリスクが多いため、事前の確認と慎重な判断が不可欠です。
ここでは、都市計画道路予定地を売買する際の注意点について解説します。
都市計画情報を確認する
売買にあたっては、まず対象不動産が都市計画道路予定地に該当しているかどうかを確認しましょう。
これは、「都市計画図」や「都市計画情報」などで調べることができます。自治体の都市計画課や建築指導課、または自治体のホームページでも確認可能です。
不動産会社による重要事項説明書にも、都市計画道路に関する記載が義務づけられていますが、都市計画道路予定地の情報は変更される可能性があるため、自治体で最新情報を直接確認しておくのが確実です。
建築計画への影響がある
都市計画道路予定地では建築に制限があるため、希望する規模や構造の建物が建てられない場合があります。
事業決定の有無や、都市計画法第53条の適用範囲を確認し、建築の可否や構造・階数などの制限の有無を事前にチェックしておきましょう。
また、建築可能であっても、将来的に立ち退きや収用の対象となるリスクが残るため、長期的な住まいや事業用地として活用する場合は、慎重な検討が必要です。
売買価格と資産価値への影響がある
道路予定地であることが明らかになった不動産は、市場での評価が下がる傾向にあります。
買主にとってリスクがあると判断されるため、価格交渉でも不利になりやすいでしょう。
年月の経過とともに売却がさらに難しくなる可能性もあるため、購入の際は都市計画道路予定地に該当しない物件を選ぶ方が安心です。
金融機関へ相談する
住宅ローンを利用して家を建てる場合、都市計画道路予定地にある不動産を担保とすると、金融機関によっては融資を制限することがあります。事前に金融機関に計画の内容を伝え、融資の可否や条件を確認しておくことが大切です。
特に、住宅ローンや不動産投資ローンを利用する場合には、収用リスクや用途制限が担保評価に影響するため、通常の不動産よりも審査が厳しくなる傾向があります。
専門家と連携する
都市計画道路に関する制度は複雑で、自治体によっても対応が異なります。
不動産取引に不慣れな場�合は、建築士や不動産鑑定士、司法書士などの専門家と連携し、契約前にリスクを洗い出し、回避策を講じるようにしましょう。
都市計画道路予定地でのトラブル回避策
都市計画道路予定地は、一般的な不動産とは扱いが異なることが多く、ちょっとした不注意によってトラブルに発展することがあります。
ここでは、都市計画道路予定地でのトラブルを回避する方法について解説します。
不確実なことを安易に説明しない
都市計画道路の事業決定は、行政内で継続的に検討されています。しかし、市民にはその進捗状況が分かりにくいため、現況がいつまでも変わらないと思いがちです。
都市計画道路が決定されてから何十年も経過している場合、買主に対して「いつまでも机上の計画です」と安易に説明すると、数年後に事業決定がされたときに大きなトラブルに発展する可能性があります。
早く土地を売りたいからといって、不確実な情報を買主に伝えることは絶対に避けましょう。
重要事項説明書を詳細にチェックする
都市計画道路予定地であることを隠して売却し、後に買主から損害賠償請求を受けるケースも少なくありません。
たとえ事業化の目処が立っていない場合でも、「将来道路になる可能性がある土地」であることを明示しないと、法的トラブルに発展することがあります。
不動産会社でなくても、売主が「都市計画道路予定地であることを知っていた」場合は、契約不適合責任を問われる可能性があり、知らなかったとしても「調査義務を怠った」と判断されることもあるのです。
売主は、不動産売買契約前に交付される重要事項説明書に都市計画道路の計画状況が正しく記載されているかを確認しましょう。また、買主も重要事項説明書の内容をしっかりチェックして、内容を理解することが重要です。
金融機関の融資条件を早めに確認する
金融機関が担保価値を再評価し、融資金額を引き下げるケースもあります。
都市計画道路予定地であることが担保評価にどう影響するかは、金融機関によって対応が異なり、契約後に住宅ローンの融資が実行されないことが判明すると、大きなトラブルに発展する可能性があるのです。
買主は、金融機関に対象物件が都市計画道路予定地であることを伝え、審査や融資条件に問題がないことを明確にしておくことで、契約後のトラブルを防ぐことができます。
まとめ
都市計画道路予定地は、将来的に公共の道路として整備されることを見越して都市計画上定められるものであり、その進行段階によって建築の自由度や資産価値、取引の可否に大きな影響を及ぼします。
特に「事業決定」以降は都市計画法第53条による厳しい建築制限が課され、建物の構造や階数に制限がかかるほか、用地の収用・立ち退きが現実的なものとなってきます。
また、売買においては価格や融資条件にも影響が出る可能性があるため、購入や建築を検討する段階で、計画の有無や進行状況を正確に把握することが不可欠です。
インターネットや自治体窓口で確認できる都市計画図や、重要事項説明書などの書面からも情報を得ることができますが、判断に迷う場合は必ず建築士や行政書士といった専門家に相談しま��しょう。
都市計画道路予定地の特性を正しく理解し、リスクを把握したうえで行動すれば、将来的なトラブルを未然に防ぎ、安全かつ有効な土地活用につながります。購入・売却・建築のいずれにおいても、慎重な調査と計画が何より重要です。