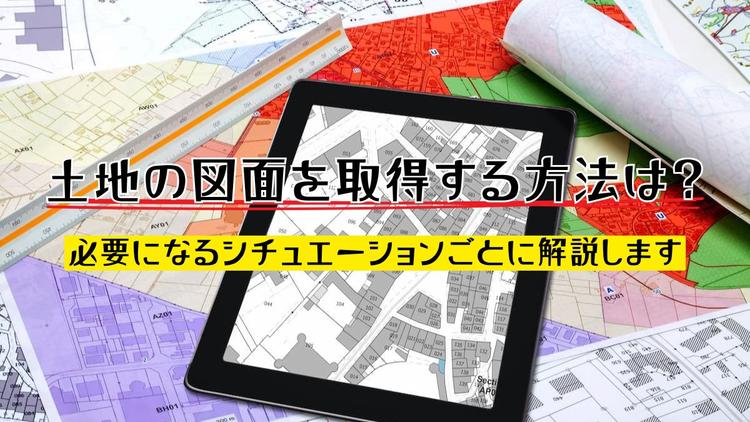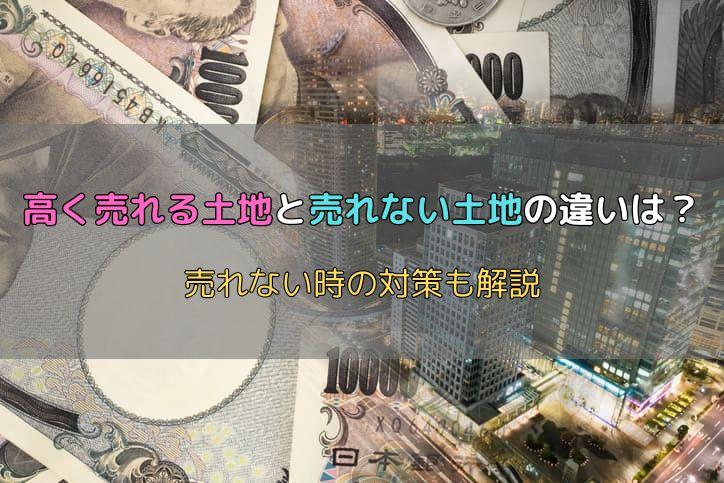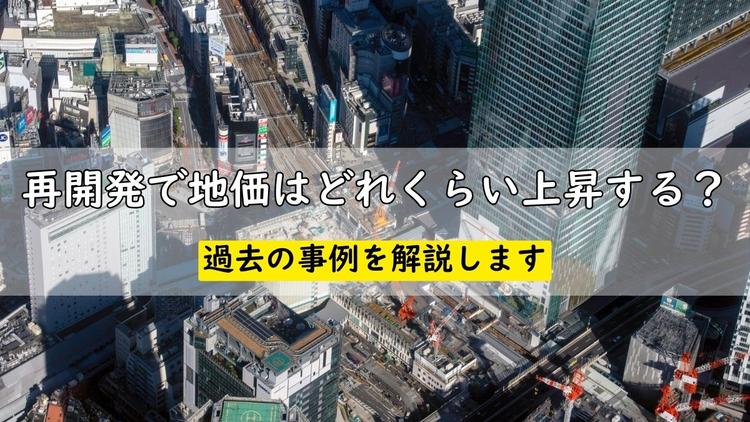「土地の図面が必要だけどどうやって取得すればいい?」
売却や相続・建築などの場面で土地の図面が必要になります。
しかし、土地の図面にもいくつかの種類があり、シチュエーションによって必要な図面と取得方法が異なります。
間違った図面を取得して再取得となれば、費用や手間が余計にかかるので、求められる図面の種類や取得方法を押さえておくことが大切です。
この記事では、土地の図面の種類や取得方法、必要になるシチュエーションなどを分かりやすく解説します。
土地の図面の種類
不動産売却時などで、土地の図面の提出を求められることがあります。
インターネット上で取得した地図でいいのではと考える方もいますが、土地の図面を求められた場合ネット上の地図では代わりになりません。
土地の図面とは、所在地や形状・境界線などが明確にかかれた法的な根拠のある図面で、主に以下の5つの種類があります。
- 法14条地図
- 公図
- 地積測量図
- 現況測量図
- 確定測量図
それぞれどのような図面なのかみていきましょう。
法14条地図
法14条地図とは、法務局に備え付けられている、不動産登記法第14条で定められた地図です。
地籍調査の結果により作成されており、インターネット上の地図よりも土地の面積や形状、距離などの精度が高いという特徴があります。
また、境界線の精度も高く、仮に土地に設けられた境界杭が抜かれたり災害などで境界線が分からなくなったりしても、この地図をもとに復元可能です。
ただし、令和5年4月1日時点で法務局に備え付けられている図面のうち、法14条地図は約58%にとどまります1。
全国的にはまだ作成されていない地域も多く、整備されていない地域では他の図面を利用することになります。
公図
公図も、法務局に備え付けられている図面です。
明治時代に租税徴収を目的として作成された図面で、土地の大まかな位置や形状を記しています。
当時の状況と測量技術を用いているため、法14条地図に比べると精度は低く、実際の状況と矛盾しているケースは多くあります。
ただ、法14条地図は前述のとおり進捗が低く備え付けられていない地域も多いことから、法14条地図に準ずる地図として使用されています。
とはいえ、精度が低く信頼性は低いので法14条地図のように境界を復元することはできません。
また、不動産取引でもおおよその目安としては活用しても、境界線など正確な情報を求められる場面では使用できないケースがほとんどなので注意しましょう。
地積測量図
地積測量図も、法務局に備え付けられている図面です。
これは土地を登記する際に添付される図面で、土地の形状や境界線だけでなく、地積や求積法まで正確に記載されています。
平成20年以降に作成された地積測量図は、GPSによる世界基準の座標で境界線の記載が義務付けられており、精度の高い図面です。
一方、昭和52年以前の地積測量図には境界線の記載義務がなく、面積のみが記載されているケースも多くあります。
また、平成17年の不動産登記法改正以前のものでは、分筆時に分筆部分のみを測量し、残りの面積は引き算で求めていたため、精度に疑問が残ります。
そのため、地積測量図を用い�る場合は、作成時の測量方法や作成年に注意しましょう。
現況測量図
現況測量図とは、土地所有者の依頼により測量し作成した図面です。
土地の面積や形状については正確に測量していますが、境界線については境界杭や所有者の主張などを元に判断しており、隣地の所有者の立ち合いは行っていません。
そのため、正確な境界線が必要というケースでは用いられない場合があるので注意しましょう。
確定測量図
確定測量図とは、隣地の所有者立ち合いのもと境界線を確定した測量図です。
隣地の所有者も確認した正確な境界線が記載されているので、境界線についての信頼性がもっとも高い図面といえます。
ただし、確定測量図は法務局で備え付けられている公的な図面ではなく、個人が所有する図面です。
土地所有者が取得していない、取得したが紛失している場合は、再発行または作成する必要があるので注意しましょう。
土地の図面の取得方法
土地の図面のうち、現況測量図と確定測量図は私的に作成される図面のため、土地所有者が保管しています。
作成していない場合は作成を依頼し、紛失している場合は依頼した測量事務所などに再発行してもらいましょう。
一方、法14条地図・公図・地積測量図は法務局に備え付けられている公的な図面のため、法務局で取得できます。
法務局での取得方法としては、以下の4つがあります。
- 法務局の窓口で申請して取得する
- インターネットで申請して法務局の窓口で取得する
- インターネットで申請して郵送してもらう
- 登記情報提供サービスで図面をダウンロードする
それぞれ見ていきましょう。
法務局の窓口で申請して取得する
法務局に出向いて窓口で申請・取得することができます。
窓口であれば申請方法などを確認しながら手続きできるので、どの図面が必要かなど不安がある方におすすめです。
現在は登記の電子化により全国どこの法務局でも取得できるため、最寄りの法務局で手続きできます。
しかし、古い図面など電子化されていない図面は、不動産を管轄する法務局でなければ取得できないケースがあるので注意しましょう。
インターネットで申請して法務局の窓口で取得する
登記・供託オンライン申請システムで請求手続き、手数料の支払いを行い、申請後に法務局の窓口に出向いて図面を受け取る方法です。
インターネット上の申請手続きは平日21時まででき、窓口での時間も短縮できるので、法務局に行く時間を極力短くしたい場合によいでしょう。
また、後述しますが窓口申請して窓口で受け取るよりも手数料が安くなるというメリットもあります。
なお、登記・供託オンライン申請システムの利用には事前に所有者情報の登録とID・パスワードの取得が必要です。
インターネットで申請して郵送してもらう
登記・供託オンライン申請システムで申請手続き後、図面を郵送し�てもらうこともできます。
郵送であれば窓口に行く必要がないので、時間が取れない方におすすめです。
しかし、郵送は窓口取得よりも時間がかかるので、すぐに図面が必要というケースでは窓口取得が適しています。
登記情報提供サービスで図面をダウンロードする
登記情報提供サービスとは、有料で登記情報のPDFを閲覧できるサービスです。
サイトにアクセスし、図面の請求・手数料の支払いを行えばダウンロードできます。
平日は8時30分から23時、土日祝でも8時30から18時まで利用でき、窓口に行く必要がないので時間がない人でも手軽に図面を取得できるでしょう。
ただし、このサービスで取得した図面には証明文や公印は付加されないため、公的な手続きでは提出できません。
また、古い図面などデータ取得に対応していない図面もあるので注意しましょう。
なお、いずれの方法でも申請時には正確な地番が必要です。
地番は住所と異なるケースもあるので、事前に登記済証や法務局のブルーマップ(住宅地図に地番情報を重ね合わせたもの)などで地番を確認しましょう。
土地の図面取得にかかる手数料
土地図面取得にかかる手数料は、取得方法によって以下のように異なります。
| 取得方法 | 1通あたりの手数料 |
| 法務局の窓口で申請・取得 | 450円 |
| インターネット申請・窓口取得 | 430円 |
| インターネット申請・郵送取得 | 450円 |
| 登記情報提供サービスでダウンロード | 365円 |
登記情報提供サービスで図面をダウンロードする方法がもっとも費用が安くなりますが、対応していない図面もあり公的な手続きには利用できないので、注意しましょう。
初めて図面を取得する、地番が分からないなど不安がある方は、窓口に行った方が確実なので、時間を作って窓口に行くことをおすすめします。
家の売却で土地の図面が必要なシチュエーション
どのような場合で土地の図面が必要になるのでしょうか?
ここでは、図面が必要になるシチュエーションについて解説します。
土地の評価額を調べる
土地の評価額を算出する際には正確な面積や形状が必要となるため、図面が必要になってきます。
評価額は相続税の計算や融資を受ける際などで必要になるので、適切な図面を取得しましょう。
土地を相続する
土地の相続では、相続する土地の把握や相続税の計算・相続登記時などで図面が必要になります。
相続税は、相続財産の総額から基礎控除を除いた部分に課税されます。
土地が相続財産に含まれる場合は、土地の相続税評価額を用いるので、その計算のための図面が必要です。
また、土地の名義を被相続人(死亡した人)から相続人に変更する相続登記や、相続した土地を分筆する際などでも地積測量図が必要になるケースがあるので注意しましょう。
土地を分筆する
土地の分筆とは、土地を分割して新たに登記し直す方法です。
相続人で土地を分ける、広大な土地の一部だけを売却するといったケースで分筆が行われます。
平成17年の不動産登記法改正にともない、土地の分筆登記時には隣地の所有者立ち合いのもと作成された境界確認書が必要です。
そのため、確定測量図が必要になってきます。
土地を売却する
土地を売却する場合、図面がなければ土地の形状や地積・境界線が明確にならずにトラブルになる恐れがあります。
たとえば、境界線が不明確なまま売却すると、買主は購入後に隣地所有者とトラブルになる恐れがあるので買い手がつきにくくなります。
地積が明確でないと、売買契約書に記載した面積と実際の面積が異なりトラブルになってしまうでしょう。
そのため、基本的には確定測量図もしくは法14条地図は必須となってきます。
確定測量図は作成するのに時間がかかるため、ない場合は早い段階で作成依頼するようにしましょう。
土地の図面に関するよくある質問
最後に、土地の図面に関するよくある質問をみていきましょう。
土地の図面は市役所で取得できる?
地積測量図・法14条地図は市役所では取得できません。
公図については市役所によっては閲覧・取得できる場合があります。
しかし、市役所の公図は最新のものでない可能性もあるので、確実に取得するなら法務局が適しているでしょう。
地積測量図はインターネットで取得できる?
地積測量図はインターネットで申請・取得可能です。
登記・供託オンライン申請システムで申請する場合は、取得は窓口か郵送になります。
登記情報提供サービスであれば、申請から取得までオンラインで可�能です。
ただし、登記情報提供サービスで取得した図面は公印が付加されていない点に注意しましょう。
また、古い地積測量図などではオンラインでの取得ができない可能性もあります。
地積測量図と確定測量図の違いとは?
地積測量図と確定測量図は両方とも境界線が確定した図面であり、記載内容はほとんど同じです。
ただし、地積測量図は法務局に備え付けられた図面、確定測量図は依頼主(土地の所有者)のみが保管しているという点が異なります。
地積測量図であれば法務局に行けば誰でも取得できるのに対し、確定測量図は土地所有者しか保管しておらず、紛失すつと再発行が必要になります。
また、平成17年以前の地積測量図は境界が確定していないケースもある点に注意しましょう。
土地の売却であれば基本的に確定測量図が必要です。
まとめ
土地の図面には、法14条地図・公図・地積測量図・現況測量図・確定測量図の5種類があり、それぞれ内容が異なります。
土地売買で正確な境界線・地積が必要なケースでは、確定測量図が必要です。
確定測量図は、法務局ではなく所有者が保管している書類です。作成していない場合は、測量を依頼して作成する必要があります。
作成には隣地所有者の立ち合いが必要になり時間がかかるので、早めに依頼を進めるようにしましょう。
土地の売買でどの図面が必要なのか分からないという場合は、不動産会社に確認すれば解決します。
信頼できる不動産会社であれば、書類の用意や取得方法など、しっかりサポートしてくれるでしょ�う。