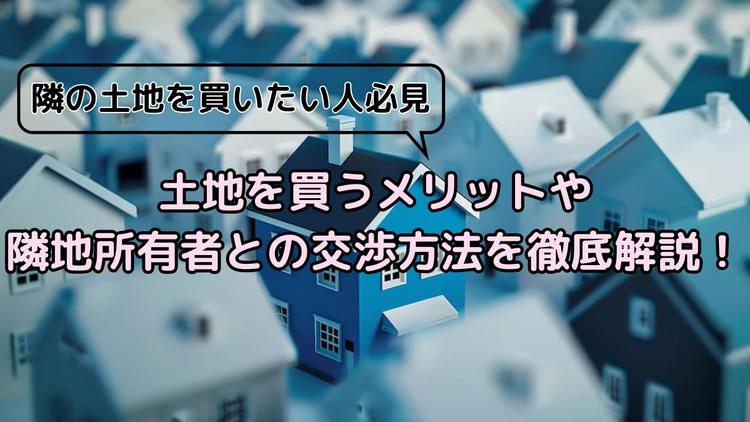近年、環境意識の高まりと共に、土壌汚染に対する関心が大きくなっています。
過去に工場やガソリンスタンド、廃棄物処理場などとして利用されていた土地や、周辺地域で土壌汚染が確認されている土地は、土壌汚染の可能性があるとされています。
これらの土地を売却する際には、買主との間でトラブルが発生しないよう、慎重な対応が求められます。
そこでこの記事では、土壌汚染の可能性がある土地を売却する際に、売主が注意すべき点について解説します。
土壌汚染の可能性のある土地とは
土壌汚染の可能性がある土地とは、過去の土地利用履歴や周辺環境などから、有害物質による汚染が懸念される土地のことを指します。そのような土地は、私たちの健康や環境に悪影響を及ぼす可能性があるため、注意が必要です。
具体的にどのような土地が土壌汚染の可能性が高いのか紹介していきましょう。
過去の土地利用によるもの
過去に特定有害物質使用特定施設が設置されていた次のような土地は、土壌汚染の可能性があります。
- 工場(金属加工、メッキ、化学薬品など)
- ガソリンスタンド
- ドライクリーニング店
- 廃棄物処理施設
また、過去に特定有害物質を扱っていたり、生成していたりした次のような土地も土壌汚染の可能性があります。
- 金属加工工場
- メッキ工場
- 化学薬品工場
- 農薬保管庫
さらに、廃棄物処理場や埋立地として利用されていた土地、鉱山跡地も土壌汚染の可能性があります。
また、農薬を大量に使用していた農地や園芸用地も注意が必要です。
周辺地域からの影響によるもの
周辺地域で土壌汚染が確認されている土地や、過去に有害物質の漏洩事故があった土地は土壌汚染の可能性があります。
土壌汚染による影響
これらの土地では、土壌中に重金属、揮発性有機化合物、農薬などの有害物質が残留している可能��性があり、人体への影響や地下水汚染などが懸念されます。
土地を売却する際には、これらの情報を十分に確認し、必要に応じて専門家による土壌汚染調査を実施することが重要です。
土壌汚染の可能性のある土地を売却するリスク
土壌汚染の可能性がある土地を売却する際には、様々なリスクが伴います。
これらのリスクを事前に把握し、適切な対策を講じることが重要です。想定されるリスクを紹介します。
契約不適合責任を負う
売買契約において、売主は買主に対し、目的物(土地)が契約内容に適合していることを保証する責任(契約不適合責任)を負います。土壌汚染は、この「契約内容への不適合」に該当する可能性があり、売却後に買主から損害賠償や契約解除を求められることがあります。
特に、売主が土壌汚染の可能性を知りながら告知しなかった場合、責任が問われる可能性が高くなります。
土壌汚染対策法による命令を受ける
土壌汚染対策法に基づき、特定の有害物質による土壌汚染が基準値を超えている場合、都道府県知事などから汚染の除去等の措置命令を受けることがあります。
また、売却後であっても、売主が汚染の原因者と特定された場合は、対策費用を負担する責任を問われる可能性があります。
売却が困難になる
汚染の可能性がある場合や、実際に汚染が判明した場合、土地の評価額は大幅に低下します。
汚染除去費用は高額になることが多く、買主はその負担を嫌うため、売却価格を下げざるを得ないケースもあるでしょう。
また、土壌汚染のリスクがある土地は買主が敬遠するため、売却が難航する可能性があります。
特に、住宅地や商業地として利用される予定の土地では、買主がより慎重になる傾向があります。
土地の売却前に土壌汚染調査をすべきケースとは
土地を売却する際、土壌汚染の事前調査が非常に重要な意味をもつケースがあります。
適切な調査を行うことで、売主は法的責任を回避でき、買主も安心して土地を購入できます。
では、どのような土地で事前の土壌汚染調査が必要になるのか、解説していきましょう。
過去の土地利用状況に基づくケース
過去に金属加工、化学薬品製造、メッキ工場など、有害物質を使用する工場や施設があった土地は、土壌汚染のリスクが高くなります。
また、ガソリンや��重油などの石油製品は、土壌汚染の原因となる有害物質を含んでいるため、これらを扱っていた施設があった土地も注意が必要です。
さらに、過去に廃棄物処理場や埋立地として利用されていた土地では、様々な有害物質による汚染が懸念されます。
意外なところでは、農地や園芸用地も土壌汚染調査が必要となる場合があります。
過去に農薬や化学肥料を多量に使用していた場合、土壌汚染のリスクがあるので、調査が必要になります。
法令に基づくケース
3,000平方メートル以上の土地で掘削、盛土、切土などの形質変更を行う場合は、都道府県知事への届出が必要となります(土壌汚染対策法第4条)。
その際、土壌汚染の可能性があると判断された場合には、調査が命じられる事があります。
また、有害物質を使用する特定の施設を廃止する際には、土壌汚染状況調査を行い、都道府県知事へ報告する義務があります(同法第3条)。
有害物質を使用する特定の施設とは、水質汚濁防止法で定められている施設で、ガソリンスタンドなどが該当します。
土地を売却する前の土壌汚染調査とは
土地を売却する前に実施する土壌汚染調査は、土地に有害物質による汚染がないか、またはどの程度汚染されているかを専門家が調査するものです。
この調査は、土地の売買を円滑に進め、売主と買主双方のリスクを軽減するために非常に重要なものとなっています。
調査機関の選定とタイミング
土地の売却を検討し始めた段階で、まず「地歴調査」を行います。
地歴調査とは、過去の土地利用履歴を調査し、汚染の可能性を評価する�ものです。過去の地図、航空写真、登記簿、周辺の聞き取り調査などを参考にします。
地歴調査の結果、汚染の可能性が示唆された場合は、速やかに「土壌汚染状況調査」を行う必要があります。これは、実際に土壌や地下水を採取し、専門機関で分析することで、汚染物質の種類や濃度を特定する調査です。
土壌汚染調査には専門的な知識と技術が必要なため、信頼できる専門業者を選びましょう。環境省が指定する「指定調査機関」に依頼することを推奨します。
調査の流れ
土壌汚染調査は、次のような流れで進めます。
- 地歴調査……過去の土地利用履歴を調査し、汚染の可能性を評価します。過去の地図、航空写真、登記簿、周辺の聞き取り調査などを参考にします。
- 現地調査……地歴調査で汚染の可能性が示唆された場合、現地調査を実施します。土地の状況や周辺環境を目視で確認し、汚染の可能性のある場所を特定します。
- 試料採取……専門の調査員が、土壌や地下水のサンプルを採取します。
- 分析……採取したサンプルを専門機関で分析し、有害物質の種類や濃度を測定します。
- 調査報告書の作成……調査結果をまとめ、報告書を作成します。報告書には、汚染の有無、汚染物質の種類と濃度、汚染範囲、対策の必要性などが記載されます。
土壌汚染調査は、土地売買のリスクを最小限に抑え、安心・安全な取引を行うために非常に重要です。
土��壌汚染調査費用
土壌汚染調査にかかる費用は、調査範囲、調査方法、分析項目、土地の面積、過去の利用履歴等によって大きく変動します。
地歴調査のみであれば、数万円から十数万円程度、土壌汚染状況調査まで行う場合は、数十万円から数百万円以上に及ぶこともあります。
費用を抑えるためのポイントは次のとおりです。
- 事前に見積もりを比較する……複数の専門業者から見積もりを取り、費用と調査内容を比較検討しましょう。
- 調査範囲を適切に設定する……過去の土地利用状況などを踏まえ、重点的に調査すべき範囲を確定することで、無駄な調査を省き、費用を抑えることができます。
- 補助金制度を活用する……地方自治体によっては、土壌汚染調査費用の一部を補助する制度がある場合があります。対象土地の自治体に確認してみましょう。
土壌汚染調査費用は決して安価ではありませんが、将来的な法的リスクや経済的損失を考えると、必要な投資といえます。
土壌汚染が発覚した場合の対応
土地の売却時に土壌汚染が発覚した場合、売主は法的責任や経済的損失など、さまざまな問題に直面する可能性があります。適切な対応を取ることで、これらのリスクを最小限に抑えることが重要です。
契約不適合責任への対応
売買契約において、売主は買主に対し、契約内容に適合した土地を引き渡す義務があります。
土壌汚染は契約不適合に該当する可能性があり、契約内容に記載せずに売却すると、買主から損害賠償や契約解除を請求されることがあります。
契約書の内容を再確認し、自身の責任範��囲を把握しましょう。特に、契約書に土壌汚染に関する条項がどのように記載されているかを確認することが重要です。
土壌汚染対策法への対応
土壌汚染対策法に基づき、汚染状況によっては都道府県知事から措置命令を受ける可能性があります。
専門家(弁護士、土壌汚染対策の専門家など)と相談し、法令に基づいた適切な対応が必要です。
放置すると、法的責任がより大きくなる可能性があります。
買主への対応
土壌汚染に関する情報は、買主に正確に開示しましょう。隠蔽は法的リスクを高めるだけではなく、信頼も失います。調査結果や対策計画、関連資料などを提供し、透明性を確保することが重要です。
汚染除去費用の負担や売却価格の減額については、買主と交渉し、合意による解決を目指します。
交渉の際には、専門家の意見や法的根拠を示すことで、買主の理解を得やすくなります。
交渉が難航する場合は、契約解除も視野に入れる必要があります。その際は、契約解除に関する条項を確認し、適切に進めることが重要です。
汚染除去対策
土地の土壌汚染が判明した場合、土壌汚染対策の専門業者に依頼し、汚染除去を行うのも有力な対策のひとつです。その際、実績と信頼のある会社を選ぶことが、重要なポイントになります。
汚染除去は、主に「掘削除去」と「原位置浄化」という2種類の方法があります。
掘削除去とは、汚染された土壌を場外に搬出して、掘削した跡に汚染されていない土を入れるという工法です。
原位置浄化は、掘削を行わずに、原位置で化学分解などにより浄化させる工法です。
費用は、汚染除去の対象となる範囲によって大きく異なります。広さだけでなく、汚染の深さも費用に影響してきます。目安としては、1立方メートルたり15,000円~25,000円ですが、状況や工法によっては大きく異なるため、見積もり時に作業内容と費用の合計を確認しましょう。
土地を売却する時の注意点
土壌汚染の可能性がある土地を売却する際には、買主とのトラブルを避けるために、いくつかの重要な注意点があります。
情報開示を徹底する
過去の土地利用履歴を調査し、土壌汚染のリスクがないか確認します。特に、工場やガソリンスタンド、廃棄物処理場などがあった土地は注意が必要です。過去の地図や航空写真、登記簿謄本などを調査し、記録を残しましょう。
過去の利用履歴や周辺環境から土壌汚染の可能性がある場合は、専門家による土壌汚染調査を実施します。調査結果を基に、汚染の有無や程度を把握し、適切な対策を検討します。
土壌汚染に関する情報は、買主に正確かつ詳細に開示します。調査結果、汚染状況、対策状況�などを書面で提示し、説明責任を果たしましょう。
契約書に対応を明記する
買主との交渉では、誠実な態度で臨み、信頼関係を築くことが重要です。汚染除去費用の負担や売却価格の減額など、条件について十分に話し合い、合意を目指しましょう。
土壌汚染に関する条項を契約書に明記し、売主と買主の責任範囲を明確にします。契約不適合責任に関する条項も確認し、トラブルを防止することが大切です。
適切な売却価格を設定する
土壌汚染のリスクや除去費用を考慮し、適切な売却価格を設定しましょう。
一般的に宅地として利用する土地の価格設定とは異なることもあるので、不動産鑑定士に依頼し、土地の適正な価値を評価してもらうことも有効です。
売却後も関連資料を保管する
売却後も一定期間、土壌調査報告書や契約書などの関連資料を保管しましょう。
売却後も買主からの問い合わせに対応し、必要に応じて専門家を紹介するなど、誠実な対応が求められます
▼関連記事

まとめ
土壌汚染の可能性がある土地を売却する際には、法的責任と経済的リスクを回避するために、徹底した事前準備と情報開示が不可欠です。
まず、過去の土地利用履歴を詳細に調査し、工場、ガソリンスタンド、廃棄物処理場などの有害物質使用歴がないかを確認します。
次に、専門家による土壌汚染調査を実施し、汚染の有無と程度を把握します。調査結果は買主に正確に開示し、契約書には土壌汚染に関する条項を明記して、売主と買主の責任範囲を明確にしましょう。
汚染が発覚した場合は、契約不適合責任や土壌汚染対策法に基づく措置命令のリスクを考慮し、専門家の助言を得ながら買主との誠実な交渉に努めます。
汚染除去費用の負担や売却価格の減額など、条件について十分に話し合い、合意を目指しましょう。売却後も関連資料を保管し、買主からの問い合わせには丁寧に対応することが、信頼維持とトラブル防止につながります。
土壌汚染のリスクを認識し、適切な対応を取ることで、円滑な土地売却と将来的な法的・経済的リスクの最小化が期待できます。これらの注意点を踏まえ、買主との信頼関係を築きながら、円滑な売却を目指しましょう。