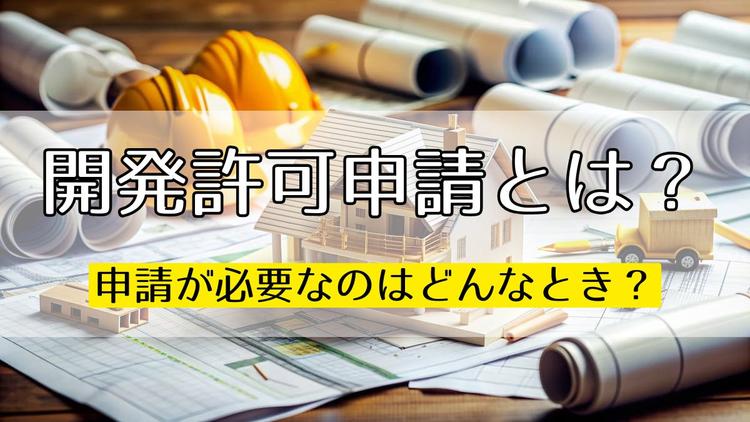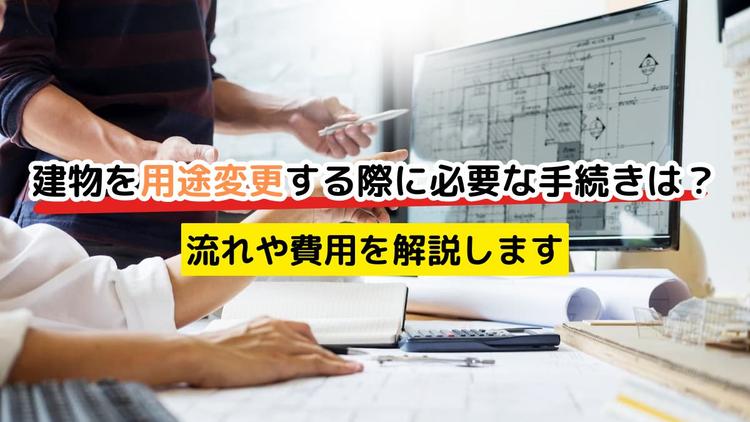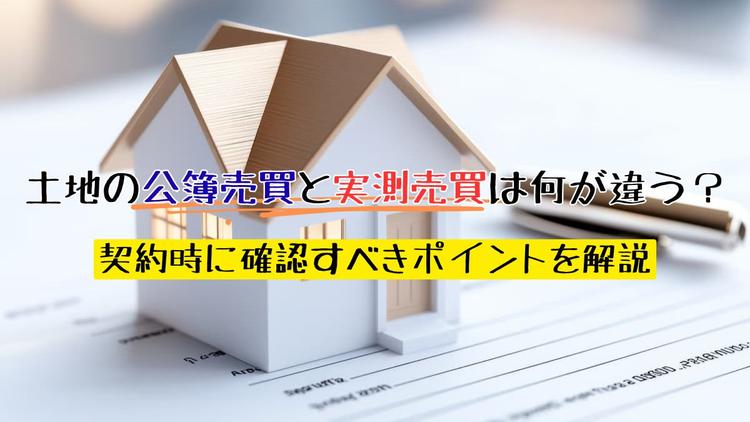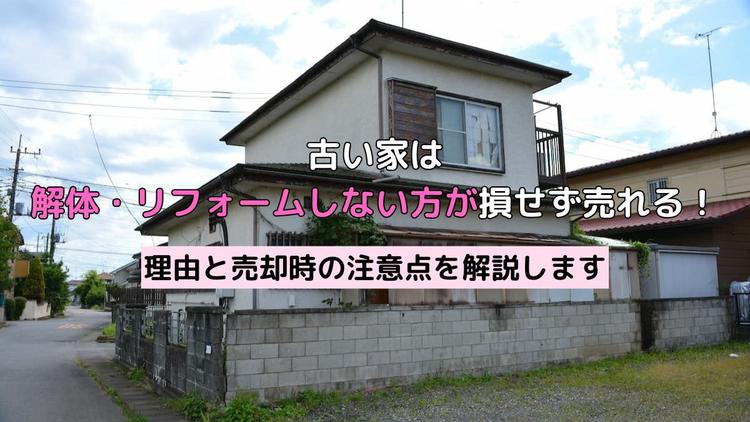住宅分譲地やショッピングセンターなどの大規模な土地の開発を行う場合には、都市計画法に基づく開発許可が必要となります。これは、無秩序な開発を抑制し、計画的なまちづくりを推進するための制度です。
この記事では、どのような開発をする場合に、開発許可申請が必要となるのかについて解説をします。
開発許可制度の概要
開発許可制度は、都市計画法第29条に規定されており、主として良好な市街地の形成や計画的な市街地開発を促進し、安全で快適な都市環境を創造することを目的としています。
開発許可申請について知るために、まず開発許可制度の概要を押えていきましょう。
開発行為とは
開発行為とは「建築物や特定工作物の設置を目的とする土地の区画形質の変更」をいいます。
「建築物や特定工作物の設置を目的とする」としていますので、青空駐車場や露天の資材置き場を築造といったように、建築を目的としない造成は、どんなに対象地が広くても開発行為には該当しません。
「区画形質」は「区画」「形(形状)」「質(性質)」の三要素を合わせて表現していますので、それぞれの要素のうち、いずれかの変更があれば開発行為に該当します。
区画
「区画の変更」とは、ひとつの区画しかなかった土地を複数の区画に分ける場合や、逆に複数の区画をひとつにまとめることをいいます。区画のラインが変われば、区画の変更になります。
形(形状)
「形(形状)の変更」とは、地面に盛土をしたり、反対に切土をしたりする造成工事のことをいいます。
質(性質)
「質(性質)の変更」は非宅地を宅地に変更するケースをいいます。非宅地とは、農地や駐車場などの建物を建てることを目的としていない土地のことです。
開発許可が必要な�区域
開発許可が必要となる区域は、原則として都市計画区域内の市街化区域です。ただし、市街化調整区域や都市計画区域外でも、一定規模以上の開発を行う場合は開発許可が必要となります。
本記事では、最も申請の多い、市街化区域における開発行為を中心に解説をしていきます。
開発許可の規模は1000平方メートル以上
市街化区域において1,000平方メートル以上の開発行為をしようとする者は、あらかじめ都道府県知事(指定都市、中核市においては市長)の許可を取得する必要があります。(都市計画法第29条・同施行令19条)
三大都市圏等は500平方メートル以上
都の区域や市町村が次の区域内にあるものは、500平方メートル以上が開発許可の対象となります(同施行令19条)。
- 首都圏整備法規定する既成市街地または近郊整備地帯
- 近畿圏整備法規定する既成都市区域または近郊整備区域
- 中部圏開発整備法規定する都市整備区域
これらの区域をおおまかに表現すると、東京都を中心とする首都圏、大阪市を中心とする近畿圏、名古屋市を中心とする中部圏が該当します。これらを「三大都市圏の既成市街地等」と表現することもあります。
許可権者
開発許可は、次の者が許可権者になります。
- 都道府県知事
- 政令指定都市の長
- 中核市の長
- 特例市の長
- 地方自治法第252条の17の2の規定に基づく事務処理市町村の長
開発許可申請に添付する書類
開発許可申請は、決められた書類を添付して許可権者に提出します。
- 申請書
- 委任状(代理人による申請の場合)
- 全部事項証明(土地)
- 付近見取り図
- 公図写し
- 敷地現況図
- 建築物又は第1種特定工作物の配置図
- 求積図
- 排水施設計画平面図
- 排水施設構造図
添付書類は一例です。開発許可申請にかかる添付書類は多岐にわたっていますので、詳しくは申請する行政機関が発行する「開発の手引き」を参考にしてください。
開発許可申請が必要なケース
建築物や特定工作物の設置を目的とする土地の区画形質の変更が開発行為ですが、そのすべてが開発許可を要するわけではありません。
具体的にどのような土地の区画形質の変更をすれば、開発許可が必要になるのか、解説をしていきましょう。
建築物の建築
市街化区域において、1000平方メートル(三大都市圏の既成市街地等は500平方メートル)以上の土地に住宅、店舗、工場などの建築物を建てる場合は、開発許可申請が必要です。
ただし、次の建築物の建築は開発許可の対象外となります。
- 建築基準法上の小規模な建築物……延べ面積10平方以以下の物置や車庫など。
- 駅舎、図書館、公民館、変電所等の公益上必要な建築物
- 区画形質の変更を伴わない建築
特定工作物の建設
都市計画法第4条第11項に定める工作物で、周辺地域の環境の悪化をもたらすおそれのある工作物を「第一種特定工作物」、ゴルフコースその他大規模な工作物を「第二種特定工作物」といいます。
次のような工作物を建設する場合、開発許可申請が必要です。
- コンクリートプラント、アスファルトプラント、クラッシ�ャープラントなど
- 危険物の貯蔵又は処理に供する工作物
- ゴルフコース
- 野球場、庭球場、陸上競技場、遊園地、動物園、観光植物園、サーキット、打席が建築物でないゴルフの打ち放し練習場等の運動レジャー施設である工作物でその規模が1ヘクタール以上のもの
区画の変更
区画とは、建築敷地を意味します。建築基準法には「1建物1敷地」の原則があるため、土地の上に2件の一戸建て住宅があれば、その土地には2区画が存在することになります。
この場合、家に付属するガレージや倉庫は、家の付属建物として1建物としてカウントされます。
たとえば、工場があった敷地を10戸が建つ住宅分譲地にする場合が、区画の変更に該当します。反対に10戸の分譲住宅を撤去して、ひとつのホームセンターを建てる場合も区画の変更に該当します。
ただし、次のケースに該当するものは区画の変更とはみなされません。
- 従来の敷地の境界を変更するが、既存塀の除却、設置のみであり、建築行為がなく、建築確認申請上の建築敷地に変更が生じない場合
- 建築基準法第42条第2項に該当する道路(2項道路)に接する敷地内で道路として後退する場合
- 建築計画等で必要な道路のすみ切りのみを整備する行為
形(形状)の変更
形の変更とは、切土、盛土または一体の切盛土を行い、土地の形状を物理的に変更することをいいます。次のいずれかに該当するものが開発許可申請の対象になります。
- 盛土で、土地の部分に高さが1.0mを超える崖を生ずることとなるもの
- 切土で、切土をした土地の部分に高さが2.0mを超える崖を生ずることとなるもの
- 盛土と切土とを同時にする場合で、盛土及び切土をした土地の部分に高さが2.0mを超える崖を生ずることとなるときにおける当該盛土及び切土
- 盛土又は切土であって、当該盛土又は切土をする土地の面積が500平方メートルを超えるもの
この規模未満の切土、盛土であれば、開発許可の対象にはなりません。
質(性質)の変更
質の変更とは、土地の有する性質を変更することで、農地や池沼、山林等の宅地以外の土地を宅地に変更することをいいます。
また開発行為に該当しない運動場、露天資材置場、露天駐車場等で造成された土地に利用目的を変更して建築物を建築するときも質の変更に該当します。
開発許可申請の審査内容
開発許可申請では、計画図などの図面の審査だけでなく、資金面や権利者の同意といった多様な視点から審査が行われます。どのような事柄が審査の対象になるのか解説していきましょう。
宅地の安全性
道路、公園、広場その他の公共の用に供する空地が、環境の保全上、災害の防止上、通行の安全上または事業活動の効率上支障がないような規模や構造で配置されているか。また開発区域内の主要な道路が、開発区域外の幹線道路に接続するように設計が定められていることについて審査します。
前面道路の幅員が基準に満たない場合は、道路を拡張する必要があります。この場合、申請敷地の一部を道路として供用する手法が一般的です。
公共施設管理者の同意
都市計画法第32条の規定より、開発許可の申請者は、あらかじめ、開発行為に関係がある公共施設の管理者と 協議し、その同意を得なければなりません。
公共施設とは道路、公園、下水道、緑地、広場、河川、運河、水路及び消防の用に供する貯水施設を指します。これらの施設が開発区域に接する場合は、管理者の同意が必要になります。
申請者の資力・信用要件
申請者に申請地で開発を行うために必要な資力及び信用、�または能力があるか否かを書類で審査をします。
そのために、法人の登記簿謄本(個人申請の場合は住民票)、事業経歴書、納税証明書の提出が求められます。
工事施行者の能力
開発工事を施工する会社に工事施行者としての能力が有るかについて審査します。そのために、法人の登記簿謄本、事業経歴書、建設業の許可証明書の提出が求められます。
関係権利者の同意
開発行為をしようとする土地やこれに関連する土地の所有権、地上権、抵当権者の同意が必要です。
同意は全員から得ることが望ましいとされていますが、事情がある場合は「大多数の同意」で認められることがあります。同意書に押印するのは実印で、印鑑証明の添付が求められます。
また、開発区域の隣接地の所有者や周辺住民等と調整を行わせることが望ましいと判断される場合においては、承諾書の提出が求められることがあります。承諾書の押印は認印であるのが一般的です。
開発許可不要のときの手続
開発許可申請は、敷地が規定の規模を超えた場合に必ず必要というものではなく、行為の内容によっては、許可を要しないことがあります。
一方で建築確認申請を審査する機関では、開発許可の要不要の判断ができないことから、開発許可が不要な場合には、建築確認申請書に許可不要を証明する書類の添付が必須になります。
開発許可が不要な場合の建築確認申請手続きについて解説します。
60条証明
60条証明とは、都市計画法施行規則第60条に基づいて交付される証明書です。建築物の建築計画が、都市計画��法に適合していることを証明する書面であり、都市計画法に基づく開発許可を要しないことを証明するものです。
敷地の規模が1000平方メートル(三大都市圏の既成市街地等では500平方メートル)を超える規模の敷地で確認申請が提出された場合、建築確認申請を審査する機関では、開発許可を要するのか不要なのかの判断ができません。
この場合は、60条証明の添付が義務づけられています。60条証明の申請には、関係書類の提出が必要です。添付書類には、位置図、公図、登記簿謄本写し、見取り図、平面図、立面図、断面図などがあります。
これらの書類により、土地の区画形質の変更がないことが明らかになれば、60条証明を交付してもらえます。
たとえば、2000平方メートルの工場の跡地にスーパーマーケットを新築するが、切土、盛土は行わないというケースであれば、60条証明が交付されます。
60条証明が交付されないケース
農地転用をしてアパートを建てるようなケースでは、質の変更があるので60条証明は交付されません。
また、工場跡地をいったん露天の駐車場や資材置き場として使用していた場合には、質の変更となるので、60条証明は交付されません。
こうしたケースで、計画を進めたい場合には、開発許可申請が必須となります。
文書照会への回答
60条証明は、申請敷地が200平方メートルといった、そもそも開発許可の規模に該当しない場合にも交付されません。
しかし、申請敷地が小さなものにあっても、元々大きな工場だった敷地を分割したようなケースだと、区画の変更に該当して開発許可が必要になるこ�とがあります。一方で、状況によっては、開発許可を要しないこともあるのです。
この開発許可の要不要は建築確認審査機関では判断ができません。このような場合、自治体によってやり方が異なりますが、建築審査課から開発許可担当部署に文書照会をすることがあります。
開発許可担当部署から「開発行為に該当しない」という旨の回答があれば、建築確認申請の審査が開始されます。
まとめ
開発行為とは「建築物や特定工作物の設置を目的とする土地の区画形質の変更」をいいます。
市街化区域で、1,000平方メートル以上の土地を建築物や特定工作物の設置を目的として、区画形質の変更をする場合は開発許可申請が必要です。
開発許可申請で重要なのが、開発区域及び関連する区域の土地の権利者の同意です。同意書は実印を押印してもらう必要があります。
開発区域が影響する公共施設の管理者との協議が必要で、同意を得る必要があります(32条協議)。
これらの要件を満たすことで、開発許可を取得することができます。