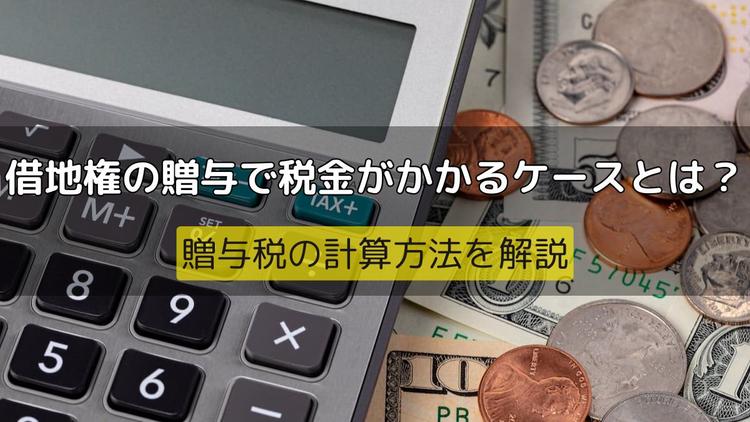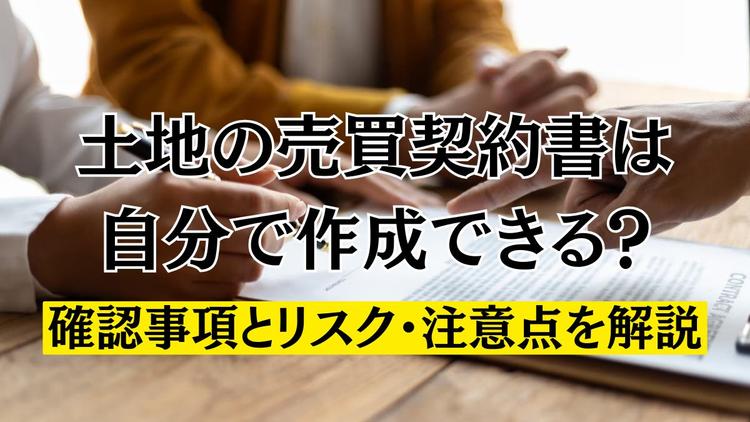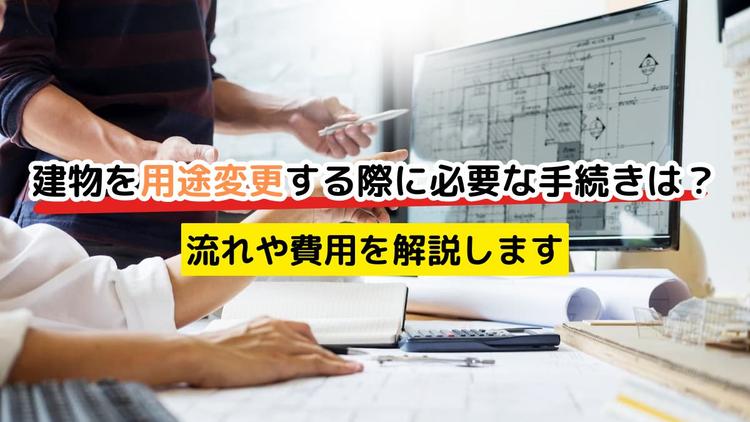「相続する土地を放棄したいけどどうすればいい?」
土地を相続した方の中には、上記のように悩んでいる方もいらっしゃるでしょう。
遠方の土地や田舎の土地など、活用予定のない土地を相続するケースは珍しくありません。
活用予定のない土地であっても相続してしまうと所有者としての責任が生じ、さまざまなリスクを負うことになるので手放すことをおすすめします。
相続予定の土地を手放す方法には、「相続放棄」や「相続土地国庫帰属制度」があるので検討するとよいでしょう。
この記事では、土地を処分しないリスクや手放す方法などを分かりやすく解説します。
土地は放棄できる?いらない土地を処分せずに放置する3つのリスク
相続などで一度土地の所有者となってしまうと、正しい手続きを踏まなければ土地の放棄はできません。
活用予定がない土地であっても、相続した以上所有者として適切に管理または処分する必要があります。
とはいえ、処分するのも手間がかかることから、何もせずに放置しているケースも少なくないでしょう。
しかし、活用しない土地は所有しているだけでも以下のようなリスクが生じるため注意が必要です。
- 維持管理に手間とコストがかかる
- 固定資産税がかかる
- 災害時の二次被害で損害賠償請求される可能性がある
それぞれ解説します。
維持管理に手間とコストがかかる
土地を放置していると、雑草や樹木が生い茂り境界線を越えて近隣の土地に迷惑をかける恐れがあります。
また、荒れ地になることで野生動物や害虫の発生、不法投棄が起こり、近隣とトラブルになるケースもあるでしょう。
土地に建物が建設されている場合は、建物の放置はより深刻な問題になります。
そのため、活用予定のない土地であっても適切な維持管理が必要です。
定期的に除草や掃除が必要になり、建物があれば換気や修繕も必要になってきます。
土地が遠方にあり定期的な訪問が難しければ、管理会社への委託も必要になります。
維持管理するだけでも手間や時間、コストがかかる点は覚悟しておきましょう。
固定資産税がかかる
土地を相続すれば固定資産税の納税義務が生じ、建物がない土地や活用していない土地であっても固定資産税の対象です。
また、土地が都市計画の区域である市街化区域内にあれば、都市計画税も上乗せされます。
固定資産税や都市計画税は、土地を所有し続ける限り毎年発生するコストです。
立地や土地の面積によっては、固定資産税も高額になりかねないので注意しましょう。
事前に、固定資産税がいくらかかるかを把握してから、資金計画を立てておく必要があります。
災害時の二次被害で損害賠償請求される可能性がある
土地を適切に管理せずに、近隣の土地や通行人などへの被害を出すと損害賠償請求されるリスクもあります。
例えば、崖地の土地を放置した結果、台風でがけ崩れが生じて通行人がケガをした、老朽化した建物を放置した結果倒壊し、近隣に被害が出たというケースでは、所有者としての責任を問われる恐れがあるのです。
このように、活用しない土地は収益を生み出すことがないばかりか、支出や手間ばかりかかる負の財産にもなりかねません。
活用予定がないなら早めに手放してしまう方が、コストやリスクから解放されるでしょう。
以下では、相続する土地の手放し方として「相続放棄」「相続土地国庫帰属制度」を詳しく解説します。
相続前の土地なら相続放棄を検討しよう
土地を相続する予定の場合、相続放棄を検討するのも土地を手放す1つの方法です。
相続放棄の手続き自��体は相続発生後ですが、期限があるため相続前から検討しておくことでスムーズに相続放棄できます。
相続放棄とは
相続放棄とは、権利を持つ方が、相続時に財産を承継することを放棄する方法です。
被相続人(亡くなった人)に多額の借金がある、遺産を相続したくないといったケースで選択されます。
相続放棄すれば被相続人の財産を相続できなくなるため、土地も相続することはありません。
相続放棄する手順
相続放棄は家庭裁判所に相続放棄を申立て認めてもらう必要があります。
大まかな手順は以下のとおりです。
- 必要書類の準備
- 家庭裁判所に相続放棄の申立て
- 審査
- 照会書への回答
- 相続放棄申述受理通知書が届く
相続放棄は他の相続人の合意は必要なく、相続人単独で申立てできます。
被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に必要書類を提出し、問題がなければ相続放棄が認められます。
ただし、相続放棄できるのは被相続人の死後であり、生前中の相続放棄はできません。
また、相続放棄できる期限は「相続があることを知った日の翌日から3ヵ月以内」です。
期限を超えると相続放棄できなくなるので注意しましょう。
土地だけ放棄することはできない
相続放棄は、すべての相続財産を放棄することです。
相続放棄することで、相続予定の土地の承継を放棄できますが、土地以外の相続財産も放棄することになるので注意しましょう。
「土地はいらないけど現預金は欲しい」といった選択はできません。
基本的には相続財産が明らかにマイナスになるような場合に選択するため、相続財産をすべて明確にしたうえで相続放棄してもいいかを慎重に検討することが必要です。
また、相続放棄した場合、自分が相続する予定の財産は次の相続順位の人が相続することになります。
このため、相続放棄した場合には次の順位の方に相続放棄したことを伝えることが大切です。
相続後の土地でも放棄できる新制度「相続土地国庫帰属制度」
すでに相続してしまった土地を手放す方法として「相続土地国庫帰属制度」があります。
これまで、土地を手放すチャンスは基本的に相続時の相続放棄だけでしたが、2023年に本制度が始まったことにより、過去に相続した土地を手放せる可能性が出てきました。
とはいえ、土地の要件など細かい規定がある点には注意が必要です。
相続土地国庫帰属制度とは
相続土地国庫帰属制度とは、相続した活用予定のない土地を国に引き渡す(帰属させる)制度です。
相続後に土地が放置されてしまうと、その土地は将来「所有者不明土地」になるリスクがあります。
所有者不明土地は所有者と連絡がつかないため、災害時や公共事業で妨げになるなど、問題となりやすい土地です。
現在、日本ではそうした所有者不明土地の増加が深刻な問題となっており、その解決策の1つとして2023年4月から「相続土地国庫帰属制度」がスタートしました。
相続土地国庫帰属制度の要件
相続土地国庫帰属制度ではどんな土地でも国に引き渡せるわけではありません。
制��度を利用できる人と土地の条件などを満たす必要があります。
主な要件は以下のとおりです。
| 項目 | 内容 |
| 申請できる人 | 相続または遺贈によって土地を取得した人 ※土地が共有の場合は共有者全員申請することにより利用可能 |
| 申請できる土地 | 引き取れない土地の要件に当てはまらない土地 【引き取れない土地の要件】
|
土地の相続人であれば申請することが可能です。
しかし、国が管理・処分するのに多大な費用や手間がかからない土地でなければ申請できません。
申請できる土地の要件のハードルが高い点には注意しましょう。
相続土地国庫帰属制度の費用
相続土地国庫帰属制度を利用する場合、以下の費用がかかります。
- 申請時:1筆の土地につき1.4万円
- 承認後:土地の管理費
審査の際に手数料がかかり、審査の結果利用できない場合でも手数料は返還されません。
さらに、制度の利用が認められた場合、審査の際に算出された10年分の土地管理費相当分の負担金が必要です。
負担金は基本的には1筆ごとに20万円となります。
無料で引き取ってもらえるわけではないので注意しましょう。
相続土地国庫帰��属制度の手続きの流れ
制度と利用する大まかな流れは、以下のとおりです。
- 法務局への相談
- 必要書類の準備
- 法務局に申請
- 負担金の納付
まずは、利用できるか法務局に相談しましょう。
相談の際には登記簿謄本や写真など、土地の状況が正確に分かる資料があるとスムーズに話しを進められます。
申請できると判断した場合は申請書などの必要書類を揃え、その土地を管轄する法務局に提出します。
提出後審査が行われ、制度の利用が決定すれば負担金を納付して手続き完了です。
負担金納付後は国が登記手続きするので、相続人が登記する必要はありません。
なお、負担金には納付期限があり、期限を超えると再度申請から手続きし直す必要があるので注意しましょう。
放棄ではなく売却できる可能性がある土地の特徴
土地によっては相続放棄や相続土地国庫帰属制度を利用しなくても、売却して手放せる場合があります。
売却であれば手放せるだけでなく売却金というまとまった資金を得ることが可能です。
しかし、放棄を考えるような土地なので、そもそも売却は難しいのでは、と考えている方もいらっしゃるでしょう。
そうした土地であっても、以下のような場合には売却を検討できる可能性があります。
- ライフラインが整っている
- 大きい土地は不動産会社が大型分譲地として検討する可能性がある
それぞれ見ていきましょう。
ライフラインが整っている
郊外の土地で、売却が難しくなる土地の条件として、ライフラインが整っていないことが�挙げられます。
例えば、上下水道や電線を引き込む必要がある場合、それらの費用は膨大になることが多いです。
一方、郊外の土地であっても、ライフラインが一通り整っていれば、住宅用地として売却できる可能性があります。
売却できるかどうかを判断する一つの基準として、ライフラインが整っているかどうかをまずは確認するとよいでしょう。
大きい土地は不動産会社が大型分譲地として検討する可能性がある
木が生い茂っているなどして、そのままでは売却が難しい土地であっても、ある程度の土地の広さがあれば、不動産会社が分譲地として買い取ってくれるケースがあります。
こうしたケースでは、不動産会社は買い取った土地をきれいに整地し、ライフラインを整えて、複数の分譲地として販売します。
複数の分譲地でそれぞれ利益を期待できるため、整地にある程度の費用がかかっても問題ないのです。
とはいえ、もちろん分譲地にすれば必ず売れるというわけではなく、価格と立地のバランスなどが重要になります。
この辺りは素人では判断できないところなので、まずは不動産会社に相談するのがおすすめです。
「売れないのでは」と考えていても、プロが見れば売れると判断されるケースもあります。
売却を悩んでいるなら一度プロに相談してみるとよいでしょう。
「イエウリ」であれば、より多くの不動産会社から査定を受けられるので、高値で売却してくれる信頼できる不動産会社と出会える可能性があります。
また、中立の立場のプロへの相談もできるので売却に不安がある方でも安心です。
田舎の土地の成約事例も多数
イエウリ で不動産の無料査定に申し込む
土地の放棄に関するよくある質問
最後に、土地の放棄に関するよくある質問をみていきましょう。
いらない土地を国に返すことはできる?
国に返す方法としては「相続放棄」と「相続土地国庫帰属制度」があります。
相続前の段階であれば、相続放棄を検討するとよいでしょう。
ただし、相続放棄は土地以外のすべての財産を放棄する必要があるため、被相続人(亡くなった方)の財産状況に応じて判断することが大切です。
また、すでに相続してしまった土地を放棄したい場合には「相続土地国家帰属制度」を検討できます。
2023年に始まったばかりの制度なので、これまで悩んでいたという方は利用を検討してみてはいかがでしょうか。
相続土地国庫帰属制度は確実に土地を放棄できるの?
管理の手間やコストがかかると判断される土地は、申請しても承認されません。
建物がある・境界線が確定していない・傾斜や勾配のある土地などでは利用できないので注意しましょう。
なお、2024年10月31日時点の帰属承認率は34%程度と高くはありません1。
スタートして間もない制度であることも理由ですが、約18%は却下・不承認・取り下げとなっており、申請しても承認されない可能性も高い点には注意が必要です。
まとめ
相続した土地を活用せずに放置していると、維持管理の手間やコストがかかり損害賠償請求のリスクも負います。
活用予定のない土地であれば、相続放棄や相続土地国庫帰属制度を利用して放棄することを検討するのも1つの方法です。
また、売却であれば手放してコストやリスクから解放されるだけでなく、まとまった資金を得ることもできるので、相続税などの対応もできるでしょう。
売却できるか悩む場合は、まずはイエウリの一括査定や相談からスタートすることをおすすめします。