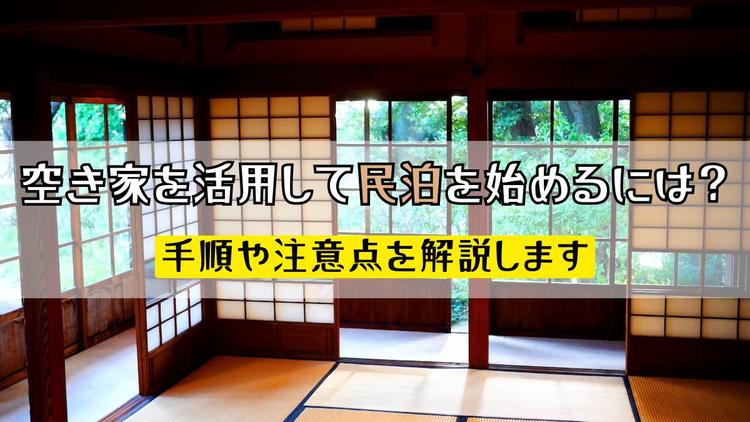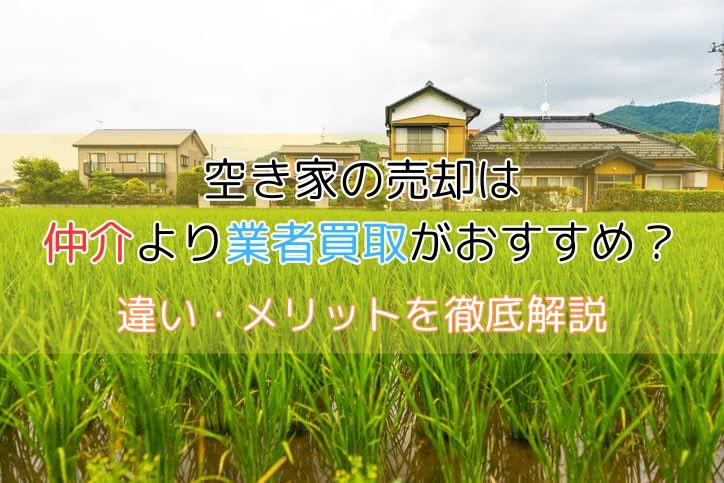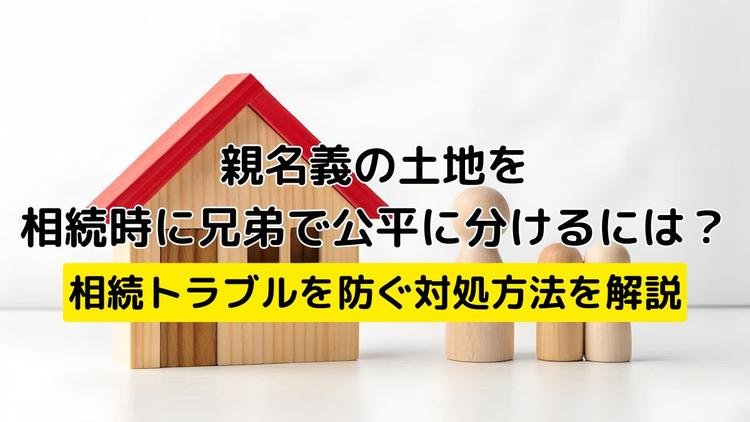日本国内で空き家問題が深刻化していることをニュース等で見たことのある方もいらっしゃるでしょう。
この空き家問題の多くは、実は相続によるものであることをご存知でしょうか。
本記事では日本における空き家問題について解説すると共に、将来ご自分が実家を相続する予定といった方に向けて損をしないために知っておくべきことを解説していきます。
空き家の取得理由の大半は相続
日本国内において空き家問題が深刻化しています。
国土交通省のデータを見てみると、1983年には330万戸だった空き家は2013年に820万戸にまで増えています1。
上記には賃貸併用住宅の空室も含まれていますが、利用者のいないいわゆる「空き家」に該当するものもこの間、125万戸から318万戸と2.5倍程度の上昇割合です。
また、同データにて空き家の取得理由を見てみると2013年における「相続による取得」は全体の56.4%ともっとも大きい割合となっていることが分かります。
都会に出た子どもが実家を相続したものの、活用できず放置されてしまうことが多いです。
空き家はどのくらい増えている?
先程国土交通省のデータに触れましたが、ここでは改めて空き家がどのくらい増えているのか見ていきましょう。
参考:総務省|平成30年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計 結果の概要
上記グラフを見ても分かる通り、1958年2.0%だった空き家率はその後右肩上がりに上昇を続け、2018年には13.6%にまで増えています。
近年では空き家率の上昇は鈍化していますが。一方で空き家数は上昇し続けていることも分かるでしょう。
また、空き家の取得率の半分以上を相続が占めることをお伝えしましたが、日本で高齢化が進んでいることと空き家が増えて続けていることには大きな関連があります。
参考:内閣府 平成30年版高齢社会白書
上記は内閣府による高齢化率(65歳以上人口割合)などを示すグラフですが、先程の空き家のグラフと似た形をしていることが分かるでしょう。
日本の高齢化率は2060年に39.9%まで上昇することが予想されるなど、今後も上昇し続ける見込みで、空き家率も同様に増えていく可能性が高いといえます。
空き家の相続で発生しやすい問題点とは
空き家の相続で発生しやすい問題点にはどのようなことがあるのでしょうか?
ここでは、空き家が地域社会にもたらす問題点と所有者にもたらすデメリットに分けて見ていきます。
空き家が地域社会にもたらす問題とは?
空き家が地域社会にもたらす問題として以下のようなことが挙げられます。
- 問題点①:犯罪のターゲットになる
- 問題点②:老朽化による倒壊の危険性
- 問題点③:景観の悪化
- 問題点④:土地の効率的な利用ができなくなる
問題点①:犯罪のターゲットになる
空き家は犯罪のターゲットになってしまうことがあります。
例えば、よくあるのが放火です。空き家は人の出入りがないため放火のターゲットになってしまいやすいのです。
また、過去に空き家が薬物栽培や特殊詐欺を行うグループのアジトになってしまっていたというケースもあります。
これらは、自分の空き家が犯罪のターゲットになってしまうというデメリットもありますが、それに加えて地域社会にも悪影響を及ぼす事象だといえるでしょう。
問題点②:老朽化による倒壊の危険性
人の住まなくなった家は老朽化しやすく、災害の際など倒壊してしまう危険性があります。
空き家が倒壊してしまうと通行人をケガさせてしまう可能性もあるでしょう。
問題点③:景観の悪化
また、空き家が放置されて老朽化したり倒壊したりすることで景観が悪化してしまうことも地域社会に悪い影響を与えることになります。
景観が悪化すると周辺に住む人の気持ちに悪い影響が及ぶだけでなく、不動産を売買するときにも悪い影響があり、結果として地価が下がるといった可能性もあるでしょう。
問題点④:土地の効率的な利用ができなくなる
空き家があると土地の効率的な利用ができなくなる可能性がありま�す。
例えば、近隣の土地をいくつかまとめてマンションを建てたり駐車場にしたりするようなケースでも、空き家があることで計画が見送られる可能性があるでしょう。
こうしたことが続くと地域社会に与えるマイナスの影響は非常に大きなものになってしまいます。
所有者にも大きなデメリットがある
空き家は所有者にも大きなデメリットをもたらします。
- 問題点⑤:定期的なメンテナンスの必要性ー地方に家がある場合などは大変
- 問題点⑥:火災保険、修繕費、税金などの費用がかかる
- 問題点⑦:メンテナンスを怠り特定空き家に指定された場合は固定資産税が最大6倍になる可能性がある
問題点⑤:定期的なメンテナンスの必要性ー地方に家がある場合などは大変
空き家は老朽化が進みやすく定期的なメンテナンスが求められます。
特に夏場は植物の成長が早く大きな庭があるようなケースでは大変です。
地方に空き家があるなど、住んでいる場所から空き家までの距離が離れていると数カ月に1回程度だとしても足を運ぶのが大変に感じるはずです。
業者を使う方法もありますが、当然ではありますが費用がかかってしまいます。
問題点⑥:火災保険、修繕費、税金などの費用がかかる
上記でも触れていますが、空き家を保有するだけで火災保険や修繕費、税金などの各種費用がかかります。
活用する見込みがないのにこれらの費用を負担しなければならないのです。
問題点⑦:メンテナンスを怠り特定空き家に指定された場合は固定資産税が最大6倍になる可能性がある
空き家は保有しているだけで費用がかかりますが、メンテナンスを怠り、自治体から「特定空き家」に指定されると固定資産税が最大6倍になる点に注意しなければなりません。
不動産は保有していると固定資産税がかかります。これは空き家も同じです。
また、土地の上に建物が建っていると最大6分の1まで固定資産税が軽減される特例があり、例え空き家であってもこの特例の適用を受けることはできます。
ただし、この特例が原因で空き家が解体されないといった問題が起こってしまうことから、2015年に施行された空き家対策特別措置法により自治体が「特定空き家」と指定した空き家は建物が建っていても固定資産税の特例の適用を受けられないことになりました。
この特定空き家に指定される要件に保安上の問題や衛生上の問題があり、長期間メンテナンスしていないとこうした問題に抵触してしまう可能性があります。
メンテナンスには手間や費用がかかりますが、放置して特定空き家に指定されてしまうと固定資産税の負担が非常に大きくなってしまうことになります。
地域社会への悪影響が大きいことも考えると、空き家を保有するのであればしっかりメンテナンスすることが大切です。
特定空き家に登録されないためにやるべきこと
ここでは、特定空き家に登録されないために対策をお伝えしていきます。
特定空き家に登録される物件の要件は以下のようになっています。
- 倒壊等著しく保安上危険となる恐れのある状態
- 著しく衛生上有害となる恐れのある状態
- 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
- その他周辺環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
倒壊等著しく保安上危険となる恐れのある状態
倒壊等著しく保安上危険となる恐れのある状態をさらに細かく分類すると以下のようになります。
- 建物が倒壊するおそれがある
- 屋根や�外壁等が脱落もしくは飛散するおそれがある
- 擁壁が老朽化し危険となるおそれがある
特定空き家に登録されないためには、建物全体が倒壊しないようにするのに加え、屋根や外壁、擁壁にも注意する必要があります。
著しく衛生上有害となる恐れのある状態
著しく衛生上有害となる恐れのある状態を細かく分類すると以下のようになります。
- 石綿(アスベスト)が飛散し暴露する可能性が高い状態
- 浄化槽が破損し異臭や害虫、害獣の発生につながる状態
- ごみの放置により異臭が発生し地域住民の日常生活に支障を及ぼしている状態
- ごみの放置により多数のねずみやはえ、蚊等が発生し地域住民の日常生活に支障を及ぼしている状態
アスベストや浄化槽がある場合はその状態に気を付けると共に、ごみが放置された状態にしないようにすることが大切だといえます。
適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態を細かく分けると以下のようになります。
- 既存の景観に関するルールに著しく該当しない状態
- 汚物や落書き等で外見上大きく傷んだり汚れたまま放置されたりしている状態
- 多数の窓ガラスが割れたまま放置された状態
- 立木などが建築物の前面を覆う程度まで繁茂している状態
- ごみが山積したまま放置されている状態
- 看板が原型を留めず本来の用をなさない程度まで破損、汚損したまま放置されている状態
地域ごとの景観ルールを確認すると共に立木や看板、ごみの処理などに気を付けましょう。
その他周辺環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
その他の条件としては以下のようなことが挙げられます。
- 立木が原因で近隣の道路や敷地に枝葉が大量に散らばっている、もしくは立木の枝により歩行者の運行が妨げられている
- 空き家に住み着いた動物の鳴き声や分等の臭気、毛等が原因で地域住民の日常生活に支障を来たしている
- シロアリが大量に発生して近隣の家屋に飛来し、地域住民の生活環境に悪影響を及ぼすおそれがある
- 門扉が施錠されていない、又は窓ガラスが割れている等不特定の者が容易に侵入できる状態にある
立木やその枝が道路に飛び出していたり、施錠されていなかったりする状態の他、動物やシロアリが見られるようになると問題だといえます。
相続した空き家は相続放棄する?キープする?迷ったときの判断ポイント
空き家は一度相続してしまうと、簡単に手放すことができなくなるため、相続の段階で放棄してしまうのも一つの方法です。
ここは、相続の段階で空き家を引き継ぐのか、放棄するかの判断ポイントについて解説します。
キーポイントはその空き家に「資産価値」があるか
空き家を引き継ぐのか、放棄するかの判断ポイントとして資産価値があるかどうかということが挙げられます。
資産価値があれば、相続した後売却することもできるからです。
資産価値があるかどうかを見分けるためには、一括査定サイトや「イエウリ」を使うことを考えてみるとよいでしょう。
「イエウリ」を使��うことで複数の不動産会社から同時に査定を受ける事が可能です。また、不動産を相続せずに売ることになった場合には速やかに売却を行う必要がありますが、「イエウリ」では買取業者とのマッチングも行っており最短10日で売却を行った実績もあります。
「イエウリ」で不動産買取の無料査定に申し込む
空き家に資産価値がある場合
空き家に資産価値がある場合、以下のような対応が考えられます。
- 売却する
- リフォームして賃貸
- 更地にして売却
- 空き家バンクに登録する
売却する
売却することで固定資産税等の支払いやメンテナンスから解放されると共にまとまった資金を手に入れられます。
先述の通り、相続財産の売却では「イエウリ」の買取マッチングサービスの利用がおすすめです。
相続による相続税の申告は相続開始から10ヶ月以内にする必要があるのに加え、複数の相続人がいる場合、相続財産の処理について相続人全員に逐一状況を報告しなければならず、仲介ではその手間が多くなるためです。
「イエウリ」の買取マッチングであれば業者による直接買取が可能であるため、提示した金額で相続人全員が納得すればすぐに売却に進めることができます。
また、単に不動産会社に直接買取を持ち掛けるのと比べると、「イエウリ」であれば無料でインスペクションを実施できる点や不動産会社による入札形式である点などによって高値で売却しやすくなっていることもおすすめできる理由です。
リフォームして賃貸
資産価値があるのであれば、ひとまずリフォームして賃貸に出すといったことも考えられます。
資産価値のある建物ということは賃貸としても需要がある可能性が高いです。
また、一旦賃貸に出した後、将来的に売却するといった事も考えられます。
賃貸に出してしまえば、その間は固定資産税や修繕費など必要な費用を家賃から補填できるでしょう。
単に人が住むため定期的なメンテナンスも不要になるというメリットもあります。
更地にして売却
土地に価値があれば建物を解体して更地として売却することも考えられるでしょう。
建物の価値はほとんどないけど、立地はよいという物件におすすめです。
なお、建物を解体して更地にしてしまうと固定資産税が高くなってしまうため、できるだけ早期に売却できるようにしましょう。
空き家バンクに登録する
自治体によっては空き家バンク制度がある場合もあります。
空き家バンクに登録すると、郊外にある古い家など、一般的なよくある空き家を探している買主を見つけやすくなるというメリットがあります。
空き家バンク以外にも地域の公民館として活用するなど自治体独自の取り組みをしているケースもあるため、確認しましょう。
空き家に資産価値がない場合
一方、空き家に資産価値がない場合には以下のような対応が考えられます。
- 相続放棄する
- 倉庫としての利用など考える
- 利益なしで不動産会社に買い取ってもらえないか交渉してみる
相続放�棄する
空き家に資産価値がない場合は、相続の段階で放棄することも考えてみましょう。
ただし、相続放棄の場合は空き家だけ放棄することはできず、相続財産全てを放棄する必要があります。
また、仮に相続放棄したとしても国に継承されるまでは管理責任が残り、それまではメンテナンスする必要がある点に注意してください。
倉庫としての利用など考える
空き家の近くに住んでいるケースでは、倉庫や家庭菜園など何らかの方法で活用できないか考えてみるとよいでしょう。
ただし、家を解体してしまうと固定資産税の軽減措置を受けられなくなる点に注意が必要です。
利益なしで不動産会社に買い取ってもらえないか交渉してみる
一般の市場で売りに出しても買い手がつかないようなケースでも、解体費用や処分費用を負担することで不動産会社が引き取ってくれるケースもあります。
郊外の土地であれば固定資産税の負担なども少額です。
不動産会社の場合、こうした土地をいくつかまとめて分譲地にすることがあります。
他には、可能性は低いですが、自治体が公民館に利用するといった目的で引き取ってくれるケースもあります。
空き家を相続する前に確認しておくべきこと
ここでは、空き家を相続する可能性のある人に向けて相続の基本的な確認事項を紹介します。
相続の流れ
まずは相続の流れを見ていきましょう。
死亡してから7日以内には死亡届を出す必要がある他、14日以内に諸手続きを済ませる必要があります。
また、相続の開始を知った日から3カ月以内に相続放棄するかどうかを判断しなければなりません。さらに、亡くなった方に所得があった場合には4カ月以内の準確定申告手続きが必要です。
最後に、10カ月経過するまでに相続税の申告を済ませることになります。
これら相続の手続は遺言書の有無により進め方が大きく変わります。
遺言書がある場合
相続が始まったら、まずは遺言書の有無を確認しましょう。遺言書がある場合、原則として遺言書の内容通りに相続手続きを進めることになります。
遺言書には3つの形式がありますが、この内よく利用されるのが自筆証書遺言か公正証書遺言です。
自筆証書遺言の場合、亡くなった方から遺言書の保管場所を聞いていない場合には相続人が遺言書があるかどうかを探す必要があります(ただし、2020年4月より法務局で保管してくれる制度が始まりました)。
一方、公正証書遺言の場合は公証役場に遺言書が保管されているので、まずは公証役場にいって遺言書の有無を確認しにいくとよいでしょう。
なお、自筆証書遺言の場合、家庭裁判所による検認手続きが必要になるため注意が必要です。
遺言書がない場合
遺言書がない場合、相続人全員が参加する遺産分割協議にて誰がどれだけ遺産を相続するのかを話し合っていくことになります。
なお、相続割合は法律で以下のように法定相続分が定められています。
| 順位 | 続柄 | 配偶者 | 配偶者以外 |
| 第一順位 | 子 | 1/2 | 1/2 |
| 第二順位 | 親 | 2/3 | 1/3 |
| 第三順位 | 兄弟姉妹 | 3/4 | 1/4 |
子がいる家庭では、配偶者と子が法定相続人になり、子がいない場合には配偶者と親、親がいない場合には配偶者と兄弟姉妹という形で順位が決められています。
また、高順位の人が全員相続放棄した場合には次の順位の人が相続の権利を獲得します。
相続方法の確定
法定相続人に該当する人は、相続開始から3カ月以内に以下の3つの内のいずれかの相続方法にするか確定する必要があります。
| 単純承認 | 全て相続する |
| 相続放棄 | 全て相続しない |
| 限定承認 | プラスの財産の範囲でマイナスの財産を引き受ける |
一般的にはプラスの財産が多い場合には単純承認、マイナスの財産が多い場合には相続放棄という形を取ることになるでしょう。
また、相続から3カ月以内の期間ではマイナスの財産がどのくらいあるか分からないといったケースでは限定承認という方法が取られるケースもあります。
プラスの財産が多くとも資産価値の低い不動産が多いようなケースでは相続放棄したほうがよいこともあるでしょう。
遺産分割協議とは?
遺言書がない場合には相続人全員で集まって遺産分割協議を行い、誰がどれだけ財産を相続するか話し合う必要があります。
特に不動産の場合には、現物分割だけではなく換価分割や共有分割、代償分割なども検討したほうがよいでしょう。
相続財産の中に不動産がある場合、相続財産に占める不�動産の割合が高いケースが多いです。
例えば、相続財産が9,000円で、内不動産6,000万円、現金3,000万円を3人で分割する場合、現物分割では均等に配分することができません。
こうしたときに換価分割や共有分割、代償分割といった方法が取られるのです。
- 換価分割:6,000万円の不動産を売却して得られた現金を分割する
- 共有分割:6,000万円の不動産を1/3ずつなど複数の相続人で共同所有する
- 代償分割:Aが6,000万円の不動産を相続する代わりに、BとCに1,500万円ずつ現金で支払う
相続の費用
相続の際には相続税を始めさまざまな費用を支払う必要があります。
ここでは、これら相続費用を見ていきましょう。
まずは、相続税の計算方法を解説します。
正味遺産額の計算
まずは正味遺産額、つまり相続財産がどのくらいあるかを算出します。
正味遺産額の計算方法は以下の通りです。
正味遺産額の計算:不動産や株、現金などの正の資産-借金など負の遺産-葬儀費用
| 現金 | 2,000万円 |
| 不動産 | 1億円 |
| 株式 | 1,000万円 |
| 総遺産額 | 1憶3,000万円 |
| 借金 | △1,000万円 |
| 葬儀費用 | △200万円 |
| 正味遺産額 | 1憶1,800万円 |
なお、土地は相続税路線価(土地の価格の80%程度)、建物は固定資産税評価額(建物の価格の70%程度)で不動産評価額が算出されます。
課税遺産総額の算出
次に、正味遺産額から基礎控除額を差し引いて課税�遺産総額を算出しましょう。
基礎控除額は「3,000万円+(法定相続人の数×600万円)」で求められます。
例えば、配偶者に子2人のケースでは3,000万円+(3人×600万円)=4,800万円です。
先程の正味遺産額から差し引くと、1憶1,800万円-4,800万円=7,000万円が課税遺産総額となります。
なお、法定相続人となっている人が相続放棄をした場合、その人は初めからいなかったものとして基礎控除額を計算します。
相続税の総額を計算
次に、相続税の総額を計算します。
相続税の総額の計算では、最初にそれぞれ法定相続分に分けて計算します。
| 配偶者 | 7,000万円×1/2=3,500万円 |
| 子 | 7,000万円×1/4=1,750万円 |
| 子 | 7,000万円×1/4=1,750万円 |
次に、各人の相続税を計算した後、それを合計します。
| 取得金額 | 税率 |
| 1,000万円以下 | 10% |
| 3,000万円以下 | 15% |
| 5,000万円以下 | 20% |
| 1億円以下 | 30% |
| 2億円以下 | 40% |
| 3億円以下 | 45% |
| 6億円以下 | 50% |
| 6億円超 | 55% |
| 配偶者 | 3,500万円×20%-200万円=500万円 |
| 子 | 1,750万円×15%-50万円=212.5万円 |
| 子 | 1,750万円×15%-50万円=212.5万円 |
| 相続税の総額 | 500万円+212.5万円×2=925万円 |
相続税額の計算
最後に、実際の相続財産の配分に基づいて振り分けて納税額を算出します。
ここでは、配偶者が4割、子がそれぞれ3割ずつ相続するケースを想定すると、それぞれの納税額は以下のようになります。
| 配偶者 | 925万円×40%=370万円 |
| 子 | 925万円×30%=277.5万円 |
| 子 | 925万円×30%=277.5万円 |
相続登記に必要な登録免許税と司法書士報酬の相場
不動産の相続時には相続登記の手続きをする必要があります。
相続登記時には登録免許税を納める必要がある他、登記を司法書士に依頼する場合には司法書士報酬も支払う必要がある点に注意が必要です。
登録免許税は以下の計算式で算出されます。
登録免許税の額=相続不動産の固定資産税評価額×0.4%
また、司法書士報酬の額は依頼する司法書士によって異なりますが、一般的な相場は5~10万円程度となっています。
必要な書類
相続時に必要な書類としては以下のようなものがあります。
| 登記原因証明情報 | ||
| 1 | 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本 | 被相続人の本籍地の市区町村役場 |
| 2 | 被相続人の住民票除票 | 被相続人の最後の住所地の市区町村役場 |
| 3 | 相続人全員の戸籍謄本 | 各相続人の本籍地の市区町村役場 |
| 4 | 相続関係説明図 | 別途作成 |
| 住��所証明情報 | ||
| 1 | 不動産取得者の住民票 | 各相続人の住所地の市区町村役場 |
| 評価証明情報 | ||
| 1 | 対象不動産の固定資産評価証明書 | 都税事務所又は市区町村役場 |
| 登記申請書類 | ||
| 1 | 相続登記申請書 | 法務局HPよりDL |
| 2 | 対象不動産の登記簿謄本 | 法務局 |
| 代理権限証明情報 | ||
| 1 | 委任状 | 司法書士が作成 |
上記通り、相続時にはさまざまな書類が必要になります。
また、戸籍謄本など本籍地の役所で取得しないといけない点、相続人全員の書類が必要な点など、手間と時間がかかる点に注意が必要です。
特に相続時には相続税申告以外にもいろいろな手続きを並行して進める必要があるため、こうした必要書類の準備は早い段階で計画的に進めていくことが大切だといえます。
空き家問題に対する政府の方針は?
冒頭でお伝えした通り、空き家はこれまで上昇し続けており、また今後も高齢化の進む日本ではさらに増えていくことが予想されています。
特に空き家全体に占める「所有者が長期不在など」を理由とする空き家は2013年の318万戸から大きく上昇する見通しで、2025年には400万戸を超える可能性もあるでしょう。
こうした中、政府では空き家問題を解消するためのさまざまな対策を行っています。
例えば、2015年の空き家対策特別措置法の施行もそうですし、空き家バンクなどの自治体の取り組みもそうでしょう。
空き家問題の解消には、現在の新築人気の市場から既存住��宅市場へ転換していくことが求められます。
実際に東京都心においては2016年以降、新築マンションの供給戸数を中古マンションの成約戸数が初めて上回ったというデータがあります。
これは、インバウンド需要増加や都市再開発を理由とする地価の上昇などを背景とする、新築マンション価格の高騰も理由ではありますが、これまでの政府の取り組みが一役買ったとみることもできるでしょう。
まとめ
空き家問題を解説していきました。
空き家問題は個人にとって大きなデメリットがあるだけでなく、地域社旗に対してもさまざまな悪い影響を及ぼします。
本記事の内容を参考に、将来的に空き家を相続する可能性のある方はしっかり対策しておくことをおすすめします。