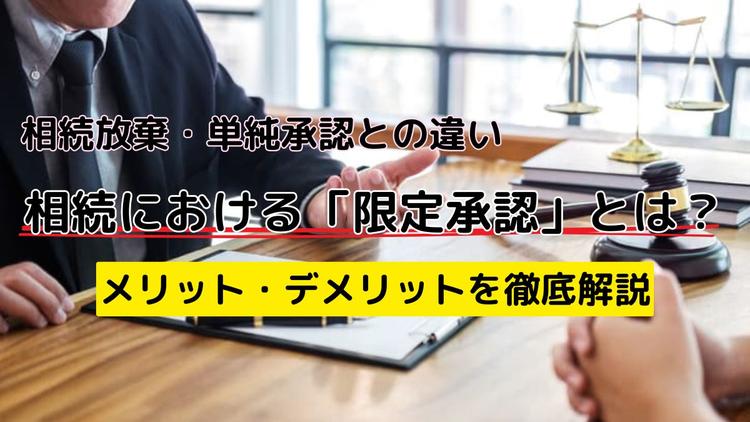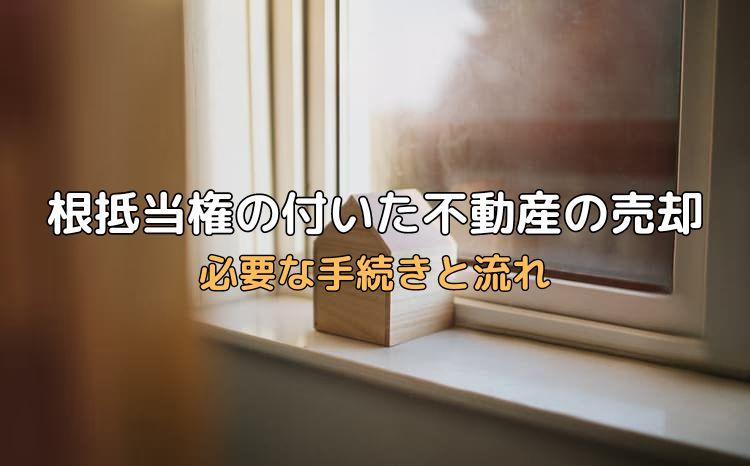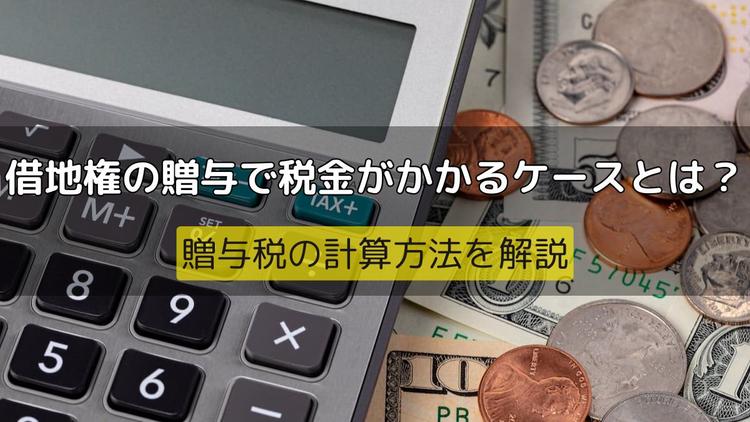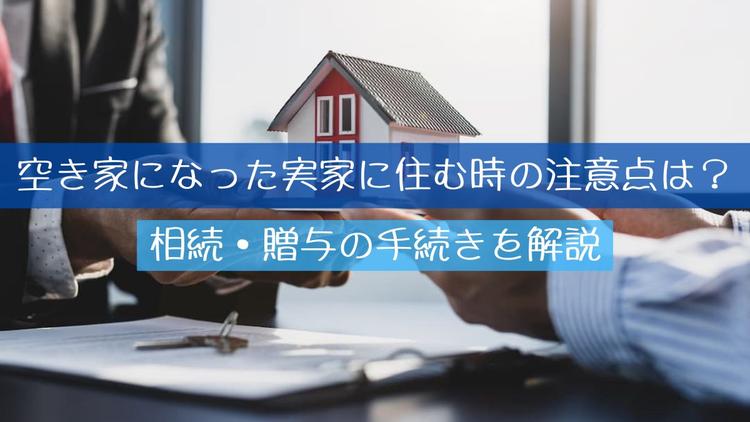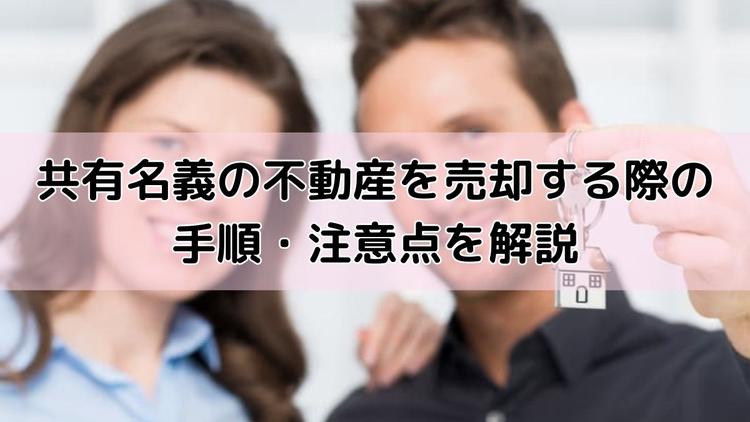親が亡くなったので財産を相続することになったのですが。プラスの財産とマイナスの財産があるので、何をどうやって相続すればいいのか…。
全て相続する方法、相続を放棄する方法の他に、「限定承認」もあります。プラスの財産を限度として、マイナスの財産を相続する形になります。
プラスの財産を限度にする…?うーん、ちょっとイメージがわきにくいですね。
例えば、負債額が把握できないときなどは、後から負債が大きいことがわかって困ることも。そんなときに相続の限度を決める限定承認を選んでおくと安心なのです。
手続きは少し複雑になりそうですが、メリットとデメリットをふまえて、検討してみたいと思います。
この記事では、限定承認の利点や具体的な手続き方法についても説明します。実際の手続きは専門家に代行してもらうことがおすすめですが、ある程度知識は身につけておきましょう!
限定承認についてわかりやすく解説
単純承認とは、プラスの財産もマイナスの財産も全てひっくるめて相続するもので、相続放棄はプラスの財産もマイナスの財産も全て放棄するものです。
上記2つはシンプルで分かりやすいですが、限定承認は「プラスの財産を限度にマイナスの財産を相続すること」と一見すると分かりにくい内容になっています。
この限定承認について理解を進められるよう、まずは制度の概要を見ていきましょう。
相続放棄との違い
相続が発生すると、その相続の発生を知った時から3カ月間の熟慮期間が設けられます。
この期間に、被相続人(亡くなった方)がどのような財産を持っているかを調査し、自分が財産をどのように引き継ぐのかを考える必要があります。
「限定承認」や「相続放棄」するのであれば、熟慮期間中に家庭裁判所に申述する必要があります。
「限定承認」も「相続放棄」も一般的に何らかの借金(債務)があるときに選択されるものです。
相続人全員で申立て
相続放棄は相続人が各人の判断で1人で��申立てすることができますが、限定承認は相続人となった人全員が共同で申立てする必要があります。
また、申立ては3カ月以内にしなければならないため、相続放棄よりも急いで話を進めないといけません。
限定承認を選択するケースとは
「プラスの財産の範囲でマイナスの財産を把握する」とはどういうことなのでしょうか。
結局のところ、プラスとマイナスの合計額が0となるため相続放棄してしまった方が簡単に思えますよね。
限定承認は相続放棄と比べて手続きも煩雑ですが、以下のようなケースでは限定承認が選択されることがあります。
- 負債額が明確でないケース
- 相続したい財産があるケース
それぞれについて詳しく見ていきましょう。
負債額が明確でないケース
限定承認や相続放棄は3カ月の熟慮期間中に手続きしなければなりませんが、3カ月では負債額が明確にならないことがあります。
こうした時に限定承認を選択すると、後の調査で負債の少ないことが分かるとプラスの財産を相続できますし、逆に負債額が大きいことが分かったとしても、プラスの財産以上にマイナスの財産を相続する必要はありません。
これは、熟慮期間が経過してからでは手続きできないため、期間に注意しながら進めていくことが大切です。
相続したい財産があるケース
次に、財産を調査した結果、マイナスの財産が多いことが分かっているような場合でも、相続財産の中に相続したい財産がある場合に限定承認が選ばれます。
①家業を引き継ぐケース
まずはプラスの財産よりマイナスの財産が多い家業を引き継ぐようなケースです。
この場合、家業を引き継ぐ相続人以外が全員相続放棄し、最後に限定承認するとプラスマイナス0の状態から家業を始められます。
②自宅や家宝があるケース
次に、相続財産の中に相続したい自宅や家宝などがある場合、限定承認が選ばれることがあります。
限定承認を選ぶと、相続財産の中から特定の財産を相続したいという時に、その評価額を支払うことができれば相続できるようになっています。
限定承認のメリット
ここでは、改めて限定承認のメリットを見ていきましょう。
メリット①債務を相続しないで済む
限定承認は、プラスの財産よりマイナスの財産が多い場合でも、プラスの財産以上のマイナスの財産(債務)を相続しないでよくなるということが最大のメリットです。
これにより、熟慮期間中に財産の額を把握しきれなかった場合でも安心できます。
また、相続放棄するのと比べるといくらかでも債務者に対して返済するため、心証がよくなるというメリットもあります。
メリット②先買権を利用できる
限定承認を選ぶと、相続人は先買権という制度を利用することができます。
先買権とは相続財産の評価額と同じ額を支払えればその財産を取得できる権利のことで、この制度を使えば先述の通り、相続したい自宅や家宝を取得することができます。
限定承認のデメリット
一方、限定承認にはデメリットもあります。
デメリット①手続きが煩雑
限定承認は単純承認や相続放棄と比べて手続きが煩雑です。
限定承認の手続き自体は、そう大変なことではないのですが、3カ月という短い熟慮期間中に相続人全員の意見をまとめ、書類を揃えて家庭裁判所に申立てしなければなりません。
また、相続放棄であれば被相続人(亡くなった方)の財産状況など特に調査する必要はありませんが、限定承認だと財産状況を調べる手間もかかります。
さらに、家庭裁判所への限定承認の申立て後、5日以内に官報に「2カ月以内に借金などの請求を申し出ること」を公示しなければならず、その手続きや対応もする必要があります。
デメリット②準確定申告が必要
被相続人(亡くなった方)が働いており、収入があるような場合には、その相続人は相続の開始を知った日の翌日から4カ月以内に、被相続人のための確定申告をする必要があります。
このことを準確定申告と呼びます。
相続放棄の場合、初めから相続人でなかったことされるため、原則として準確定申告する必要がないのと比べると手間がかかるのに加えて、税金を支払わなければなりません。
デメリット③含み益に課税される
限定承認で相続した財産については、相続時に売却したこととみなして税金が課されます。
例えば、相続財産に1億円の価値のある不動産があった場合、その不動産の所有期間が5年超であれば20.315%、5年以下であれば39.63%の税金が課されることになります。
これをみなし譲渡所得税と呼び、通常マイホームの売却であれば3,000万円特別控除を活用できますが、みなし譲渡所得ではこうした特別控除を利用することができません。
ただし、限定承認では債務も相続するため、債務と売却益が相殺されて譲渡所得税がかからないことも多いです。
限定承認のその後の手続きは?
限定承認すると、申立てから5日以内に官報に公示する必要があることはすでにお伝えしましたが、他にも申立て後にいくつか手続きをしなければいけません。
相続開始から限定承認の申立て、その後の手続きを並べると以下のようになります。
- 財産の調査と財産目録の作成
- 熟慮期間中に相続人全員の共同で家庭裁判所に申立て
- 5日以内に「2カ月以内に借金などの請求要請」を官報に公示
- 弁済手続きと残余財産の処理
- 相続開始を知った日から4カ月以内に準確定申告(みなし譲渡所得の計算)
それぞれについて見ていきましょう。
1. 財産の調査と財産目録の作成
相続の開始を知ったらまずは被相続人(亡くなった方)にどの位の財産があるのかを確認します。
一般的に、プラスの財産が大きい場合は単純承認、マイナスの財産が大きい時は相続放棄が取られ、熟慮期間中に財産が把握しきれない場合や、どうしても相続した財産があるときに限定承認が選ばれます。
なお、財産の状況については亡くなってから調べるのではなく、亡くなる前から被相続人(亡くなった方)に話を聞いておくことが望ましいでしょう。
2. 熟慮期間中に相続人全員の共同で家庭裁判所に申立て
相続人全員で話し合い、限定承認することが決まったら相続の開始を知った日から3カ月以内(熟慮期間)に共同相続人全員で家庭裁判所に対して申立てします。
共同での申立ての場合、家庭裁判所より相続財産�管理人が選任されます。
3. 申立て後、5日以内に「2カ月以内に借金などの請求要請」を官報に公示
把握している財産以外に債務等がないかを確認するために、申立て後5日以内に官報に「2カ月以内に借金などの請求をしてください」と公示する必要があります。
また、相続人が知っている受遺者や債権者がいれば個別に催告します。
これらの手続きと並行し、以下のような手続きを進めていきます。
- 共同相続の場合、選任された相続財産管理人は清算手続き用の口座を開設
- 被相続人(亡くなった方)の預金口座解約
- 相続財産に不動産がある場合、家庭裁判所に申立てして換価もしくは買取
4. 弁済手続きと残余財産の処理
官報への公示期間が終了したら、公示期間中に申出のあった債権者等に弁済します。
また、弁済手続き後に別の債権者からの申し出があった場合、弁済後の残余財産がある場合のみ弁済を行うこととなります。
さらに相続財産に残余がある場合には、相続人間で配分することができますが、いつ債権者から申し出があるか分からないため、しばらくは手をつけずにとっておくとよいでしょう。
5. 相続開始を知った日から4カ月以内に準確定申告(みなし譲渡所得の計算)
財産の清算手続きと並行して、被相続人(亡くなった方)に収入があった場合には、相続開始を知った日から4カ月以内に準確定申告する必要があります。
限定承認の具体的な手続き方法
最後に、限定承認に必要な書類など具体的な手続きについて見ていきましょう。
限定承認の申立て先
限定承認の申立て先は家庭裁判所ですが、より具体的には「被相続人(亡くなった方)の最後の住所地の家庭裁判所」となります。
限定承認にかかる費用
限定承認の申立てでは、その費用として800円分の収入印紙代を支払う必要があります。
その他、弁護士や司法書士に手続きを代行してもらう場合は別途報酬を支払う必要がありますが、これは財産の規模や依頼する弁護士、司法書士によって異なります。
限定承認の必要書類
限定承認に必要な書類としては以下のようなものがあります。
- 被相続人(亡くなった方)の戸籍謄本や住民票除票
- 申立て人全員の戸籍謄本
- 法定相続人であることを示す書類
- 限定承認に関する申述書
限定承認は自分で手続きできる?
限定承認について、その手続きを司法書士や弁護士に代行してもらうこともできますが、その場合、報酬を支払う必要があります。
自分で手続きすることができれば、司法書士報酬や弁護士報酬を支払う必要はありません。
しかし、限定承認の手続きはかなり手間がかかるため、基本的にはプロに代行してもらうことをおすすめします。
限定承認はできれば避けたい手続き
限定承認は手続きが複雑で相続人にとっても負担が大きいため、できれば避けたい手続きです。
限定承認を選ぶ理由として、相続財産の中に相続した財産があるような場合には他に方法がありません。
ですが、財産の額が分からず仕方なく限定承認を選ぶような場合には、そうならないよう生前から財産の額を把握するなどしておくとよいでしょう。