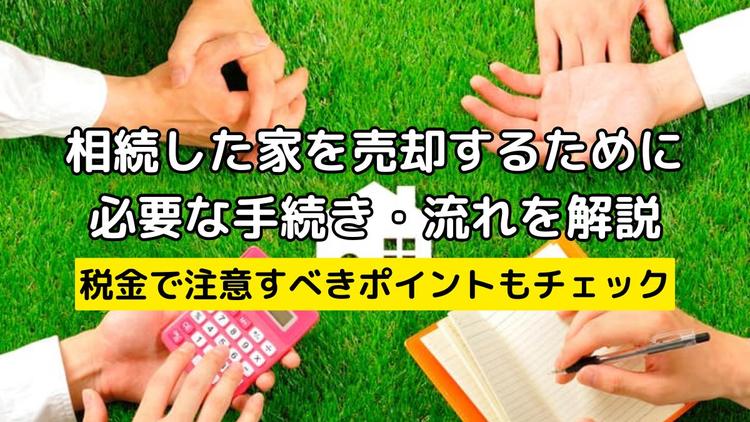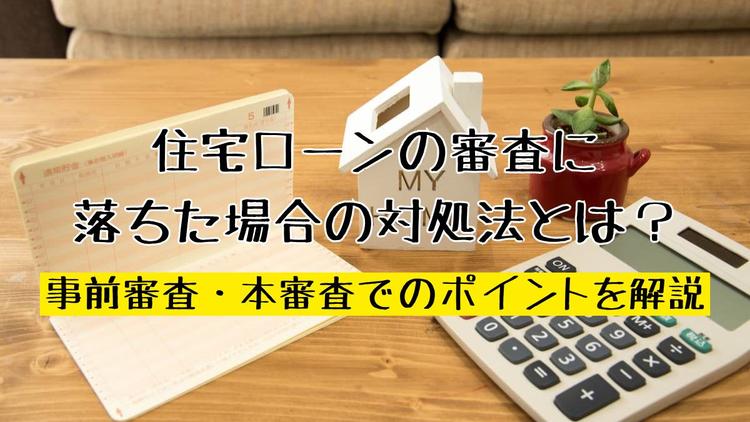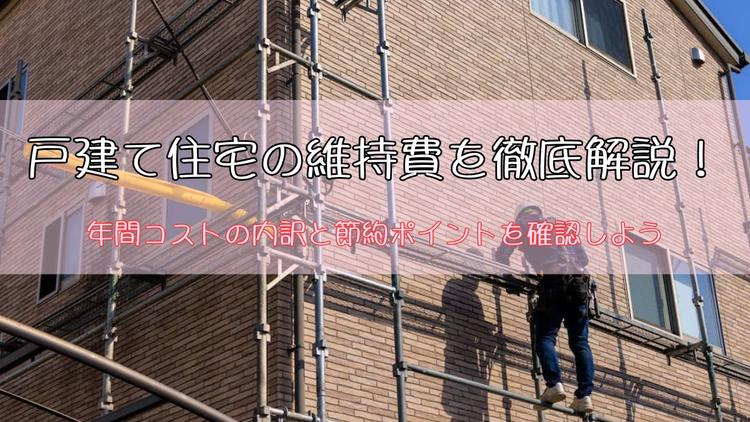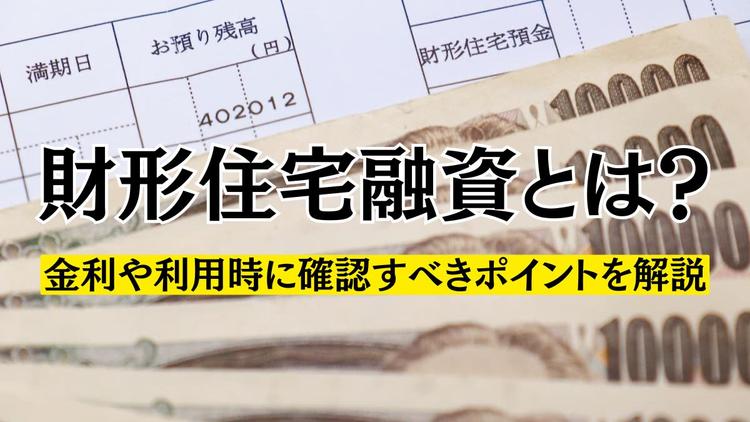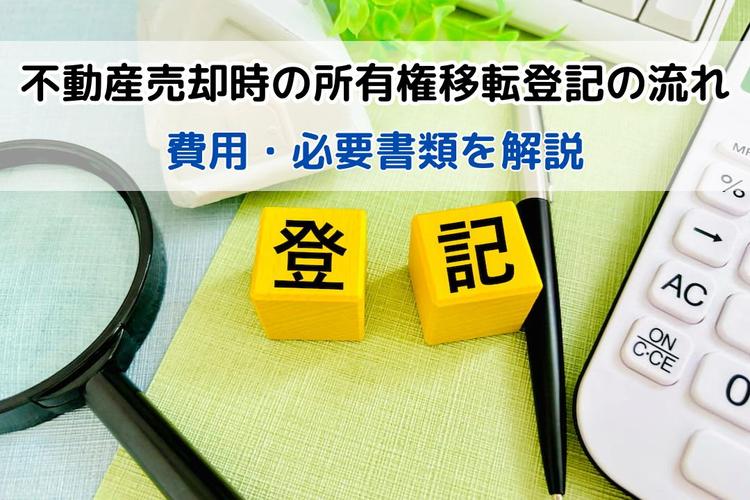相続が始まると、遺産分割協議や相続税の支払いなどの手続きをする必要がありますが、それと合わせて相続した家を売却する場合、どのように手続きしなければならないのでしょうか。
本記事では、相続した家を売却するために必要な手続きや流れに加え、相続税で注意すべきポイントなどお伝えしていきます。
家を相続するまでの流れ
一般的なケースにおける、家を相続するまでの流れは以下の通りです。
- 相続に関して確認する
- 3カ月以内に相続方法を確定する
- 遺産分割協議
- 相続登記
- 10カ月以内に相続税の納付
それぞれ見ていきましょう。
相続に関して確認する
まず、人が亡くなったらその方の相続財産や法定相続人を確認します。
なお、遺言書がある場合は、遺言書の内容に沿って相続を進めていきます。
遺言書の遺し方には3つの方法がありますが、この内一般的に用いられるのは自筆証書遺言か公正証書遺言です。
自筆証書遺言の場合、生前に遺言書をどこに置いてあるか確認しておくことが大切です。
公正証書遺言の場合は、公証役場にいけば遺言書があるか確認してもらうことができるため、遺言書の存在を知らない場合には公証役場に問い合わせてみましょう。
自筆証書遺言の場合、家庭裁判所に検認してもらう必要があるため、発見したとしても勝手に開封してはいけません。
遺言書が存在しない場合には、法定相続人で集まって相続分を決めていくことになります。
なお、法定相続人と相続分は以下のように定められています。
3カ月以内に相続方法を確定する
相続人に該当する方は、相続の開始を知った日から3カ月以内にどのように相続するかを決める必要があります。
相続の方法には「単純承認」と「相続放棄」、「限定承認」の3つがあります。
単純承認とはプラスの財産もマイナスの財産も全て相続すること、相続放棄とは全ての相続財産を相続しないこと、そして限定承認はマイナスの財産の範囲内でプラスの財産を相続することです。
相続放棄か限定承認をするには、上記期限以内にそれぞれ手続きをしなければなりません。
相続放棄の場合は、相続人が単独で申請することができますが、限定承認の場合は相続人全員で申請しなければならない点に注意が必要です。
また、同順位の相続にが全員相続放棄した場合は、次の順位の方が相続人となるため、相続放棄の手続きをしたことを知らせるようにしましょう。
遺産分割協議
相続することを決めた場合、どのように相続財産を分けるかについて、相続人が集まって話し合いをします。
このことを遺産分割協議と呼びます。
相続財産の中に不動産が含まれている場合、不動産の価値が占める割合が高いことがほとんとです。
一方、不動産は現金のように相続人間で均等に分けるといったことがしづらい特性を持ちます。
このため、換価分割と呼ばれる、不動産を売却して得たお金を相続人で分ける方法が取られることが多いです。
不動産を売却したお金を分配する「換価分割」であれば、公平に遺産を分割しやすい。
相続財産の分割方法には、他に相続財産をそのままの形で相続する「現物分割」と、不動産を複数の相続人で共有する「共有分割」、不動産を相続した方が、その価値の差額分を現金で他の相続人に支払う「代償分割」があります。
相続登記
遺産分割協議で不動産の相続人が決まったら、被相続人から相続人に所有権を移転する相続登記を行う必要があります。
なお、2024年に相続登記が義務化されるまでは相続登記には期限がなかったため、相続から数年経っても所有権移転登記されていない不動産がよく見られます。
ただし、相続した家を売却する場合には登記を済ませておかなければなりません。
仮に、相続後すぐに売却しないケースでも、相続後数十年経ってから売却しようとなったときに、他の相続人から書類を集めることに苦労することになる例も多いため、相続時に手続きしておくことをおすすめします。
10カ月以内に相続税の納付
相続があった場合、相続した財産に応じて相続税を納める必要があります。
相続した不動産を売却した資金で相続税を納めることを考えている場合、上記期限内に売却手続きを進めなければなりません。
なお、相続税には「3,000万円+600万円×法定相続人の数」が基礎控除となっており、相続財産の額が左記金額以下であれば相続税を納付する必要はありません。
相続した家を売却する流れ
相続した家を売却する場合、どのような流れで手続きを進める必要があるのでしょうか?
相続した家を売却する流れは、以下の通りです。
- 売却査定~媒介契約
- 不動産会社による売却活動
- 売買契約
- 住宅ローン本申し込み
基本的に通常の方法で家を売却するのと変わりないと考えてよいでしょう。
以下、それぞれについて解説します。
売却査定~媒介契約
まずは不動産会社に売却査定を依頼し、査定額の提示を受けます。
査定額は不動産会社によって変動します。そのため、初めに複数の不動産会社に査定依頼を出し、その中から信頼できる会社を選ぶ事をお勧めします。
一括査定サイトや「イエウリ」を利用すれば、登録した物件に対して複数の不動産会社から査定額を受け取る事が可能です。いちから不動産会社に連絡をする手間が省けるためスムーズに売却活動を始める事ができます。
査定額の提示を受けた後は、気に入った不動産会社と媒介契約を締結します。
不動産会社による売却活動
媒介契約を締結したら、不動産会社がチラシやインターネットに物件情報を掲載し、売却活動を開始します。
売主が内見に立ち会うことも可能ですが、基本的には、この間売主がやることは何もありません。
ただし、内見の日までに家の中をきれいに清掃しておくようにしまし��ょう。
売買契約
売却活動の結果、買い手が現れた場合、売買価格や日取りなどの条件交渉を行います。
条件がまとまったら、売主と買主で売買契約を締結します。
売買契約成立と同時に不動産会社に仲介手数料を支払わなければならないケースもあるため、事前に確認と準備を忘れないようにしましょう。
住宅ローン本申し込み~決済、引き渡し
売買契約後は買主が住宅ローンの本申し込みを行い、住宅ローンの承認を得たら決済、引き渡しとなります。
なお、決済時には登記のために印鑑証明書や権利書(登記識別情報通知)が必要になります。
相続した家を売却した際の譲渡所得税に関する注意点
家を相続すると相続税を納める必要があるのに加え、相続した家を売却すると、その利益額に応じて譲渡所得税を納める必要があります。
ここでは、相続した家を売却したときの譲渡所得税に関する注意点を見ていきたいと思います。
相続した不動産でも譲渡益を申告する必要がある
相続した家の売却では、すでに相続税を納めているのにも関わらず、売却によって利益が生じた場合には譲渡所得税を納める必要があります。
2回に渡って税金を納める必要があることから、多額の税金を支払わなければならないこともある点に注意が必要です。
ただし、相続税を支払った家については、譲渡所得税を軽減できる特例が用意されています。
具体的には、相続で取得した家について、譲渡所得税の計算上、納めた相続税額の内一定額を取得費として計上できるというもので、「取得費加算の特例」と呼ばれます。
譲渡所得税の額は以下の計算式で求められます。
税額=課税譲渡所得×税率
上記計算式の内、「取得費」は売却した家を購入するのに要した費用のことですが、ここに相続税額の一部を計上できます1。
また、被相続人が亡くなった後空き家となっている家については、「昭和56年12月31日以前に建築されていること」などの一定の要件を満たせば、3,000万円の特別控除を受けられる特例もあります2。
譲渡所得の計算上子が同居していた場合に受けられる特例
また、被相続人が亡くなった時点で子が同居していた場合には、「マイホームを売却したときの3,000万円特別控除」や「小規模宅地等の特例」の適用を受けられます。
前者の場合、空き家の特例と同じく一定の要件を満たせば3,000万円分の特別控除を受けられるもので、これは相続した財産でなくともマイホームを売却する場合に受けられる特例です。
また小規模宅地等の特例は、被相続人が亡くなった時点で子である相続人が同居していた場合、その敷地のうち330㎡まで80%分、相続税の減額を受けられるものです。
いずれも非常に節税効果の高い特例となっているので、条件が当てはまるかどうか確認しておくとよいでしょう。
取得の時期は被相続人のものを適用できる
また、先述の通り、譲渡所得税の計算では、売却した家を取得したときの費用を経費として計上できますが、この取得費については、被相続人が取得したときの費用を計上できます。
また、譲渡所得税の税率は、売却する家の所有期間によって以下のように税率が変わるようになっています。
| 所有期間 | 所得税 | 住民税 | 合計 | |
| 短期譲渡所得 | 5年以下 | 30.63% | 9% | 39.63% |
| 長期譲渡所得 | 5年超 | 15.315% | 5% | 20.315% |
上記通り、所有期間が5年超かどうかで税率がほぼ倍変わりますが、相続した家の売却においては、被相続人の所有期間も含めてよいことになっています。
相続した家を売却する際の注意点
ここでは、相続した家を売却する際の注意点をお伝えしていきたいと思います。
相続登記しなければならない
家を相続した際、被相続人から相続人に所有権移転登記することを相続登記と呼びますが、2024年4月1日以降、相続登記が義務化されています3。
従来は相続登記は義務化されておらず、登記費用がかかるため、相続登記されていないままの不動産が現在でも多くあります。
しかし、家を売却する際には相続登記なされていることが条件です。
相続後すぐに売却しないケースで、将来売却することになった場合に、いざ相続登記しようとすると当時の相続人が亡くなっていて、さらにその相続人を探さないといけなくなるといったケースがよくあります。
場合によっては、手続きが煩雑になりすぎて売却できなくなってしまうこともあるため、相続時にしっかり相続登記しておくことが大切です。
売却代金で相続税を支払う場合急いで売却しなければならない
家を相続することになった場合、その相続税の額が高額になってしまうことがあり��ます。
家と一緒に現金も相続できたらいいのですが、他の相続人がいる場合、公平な分割をするとなると、家だけの相続となりやすく、納税資金の準備が必要となります。
しかし、相続は突然やってくるもので、家の売却代金で相続税を支払うこともあります。
こうした場合、相続税の納税期限は相続があったことを知った日から10カ月以内となっているため、この期限までに家の売却を済ませなければなりません。
急いで手続きしたとしても、遺産分割協議が終わるまでに2~3カ月はかかるでしょう。
あまり急いで売却しようとすると、買主に足元を見られて価格交渉の際に不利な条件での売買となってしまうこともある点に注意が必要です。
相続人の意見を合わせることが意外と大変
家の売却で換価分割するようなケースでは、家の売却手続きを進めながら、相続人全員に確認していく作業が生じます。
家の売却価格は、不動産会社の査定額通りになるわけではなく、途中で値引きや値下げを経て最終的な売却価格が決定します。
例えば、家の売却を始めてから2~3カ月経っても買い手が現れないようなケースでは値下げの判断をする必要がありますが、相続人の内の誰かがそれに反対するなど、意見をまとめられないことがあります。
値下げの判断を誤ると、半年~1年以上売れない期間が続くことも珍しくなく、またあまり長く市場に売りに出されていると「売れない家」と認知されてさらに売れにくくなってしまう現象が起こってしまうことがあります。
相続した家の売却では、こうした相続人の意見�をまとめることの大変さもあることに注意が必要です。
相続で家の売却を始める際に重要な2つのこと
ここでは相続で家の売却を始める際にまず検討すべき2つの点を解説します。
仲介にするか買取にするかを決める
売却代金で相続税を支払う場合は10カ月の期限があり、急いで売却しないとなりません。期限までにまだ時間があり、できるだけ高く売却したい場合は仲介での売却がおすすめです。
しかし先述の通り、相続した家を売却する際に仲介による売却を選択すると、意見をまとめるのが大変という注意点があります。
一方、買取を選んだ場合、売却額は仲介の7~8割程度になりますが相続人同士の意見をまとめるのが大変という問題が大幅に軽減されます。
よって期間や手間を考慮してまず初めに仲介にするか買取にするかを選ぶことが重要です。
▼関連記事

複数の不動産業者からの査定を比較しよう
不動産売却をする上で良い不動産業者を選べるかどうかが成功の大きな鍵です。このためにはできるだけ多くの業者からの査定を比較する必要があります。
ここで、一括査定サイトや「イエウリ」を利用すれば1週間程度で一度に複数の業者からの査定を受けることができるため、これら��のサイトを利用する事がおすすめです。
特に、「イエウリ」では査定額や根拠を基に、気に入った業者のみと連絡が取れるシステムであるため一括査定サイトであるような一方的な営業電話を受けずに済みます。
また、「イエウリ」の買取マッチングサービスでは、買取業者による入札形式を導入しているため、買取業者間での入札競争が生まれ、結果として買取であっても高額売却を実現しやすくなっています。
相続した家の売却を検討されている方は、まずは「イエウリ」を利用してみることをおすすめします。
「イエウリ」で物件の無料査定に申し込む
まとめ
相続した家の売却について、相続の流れや家の売却の流れ、税金についての説明などお伝えしました。
相続した家を売却するときの流れ自体は、通常の家の売却の流れと基本的に同じですが、売却したお金で相続税を納付する場合には10カ月の期限内に売却しなければならないといった注意点があります。
文中でお伝えしたとおり、「イエウリ」であればそれら注意点を解消できるということもあり、相続した家の売却では「イエウリ」の利用をおすすめします。
参考:法務省|相続登記の申請義務化に関するQ&A↑