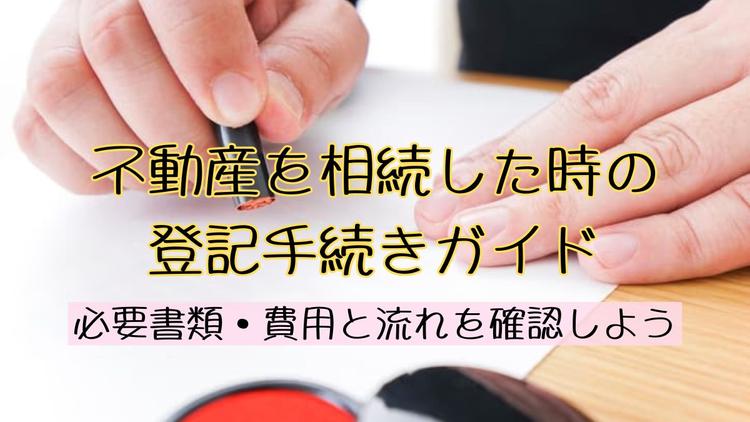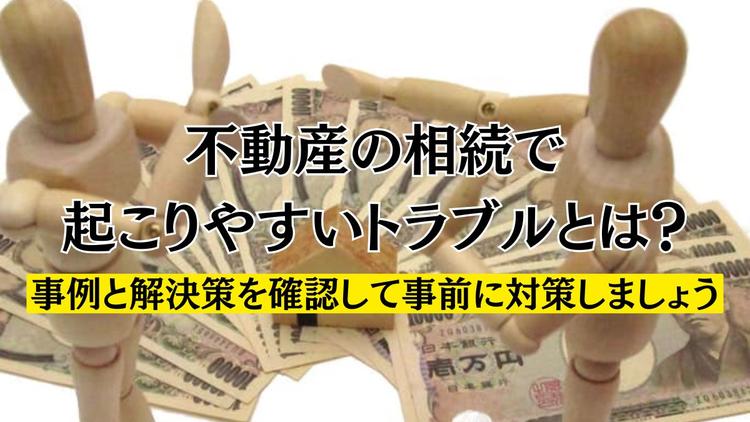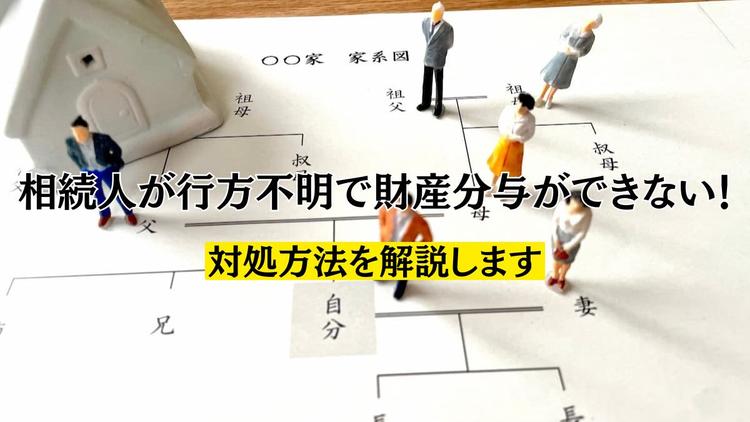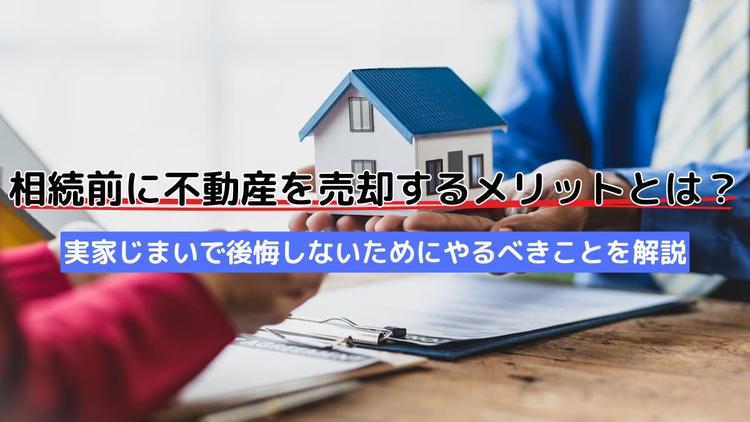家を相続することになったのですが、どんな手続きをすればいいのでしょうか。名義変更などが必要になるイメージがありますが…
はい。家を相続するときは、名義変更の登記を行います。これは義務ではないのですが、済ませておかないと売却や贈与ができなくなります。
あとで家を売ったり、贈与したりする可能性もあるので、名義変更登記はしておくのがベターですね。
登記は司法書士に代行してもらうことも可能です。出費をおさえたい場合は、自分で手続きを行うのもOKです。
自分でたくさんの書類を扱うのは不安ですが…。まずは手続きのパターンや方法について情報収集してみたいと思います。
この記事では、実際の手続きや必要書類、登記費用についてもお伝えします。不動産を相続した方、これから相続する予定のある方はチェックしておいてください。
不動産を相続したらまずは名義変更(相続登記)しよう
遺産分割協議などの手続きを経て、不動産を相続することが決まったら、まずは名義変更登記することが大切です。
この手続きのことを「相続登記」と呼びます。
相続登記は義務化された
2024年4月から、相続登記が義務となりましたが、それ以前は義務ではありませんでした。
相続人は、不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記をすることが法律上の義務になります。正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
また、不動産を相続しても登記を済ませておかないと売却や贈与などをすることはできません。
相続登記せずに放っておくと、権利関係が複雑になり、後々面倒になる可能性もあります。
相続登記をしないことで発生し得るトラブル
相続登記には相続人全員の書類が必要になることから、相続登記を済ませずに放っておいた間に、相続人のうちの誰かが亡くなってしまうと、さらにその相続人の書類が必要になってしまいます。
相続後、数年~数十年放置してしまうと、関係者が数十人規模に膨れ上がってしまうこともあり、最終的に相続登記自体がほぼ不可能という状態になってしまう可能性もあるのです。
こうならないよう、相続後はすぐに登記するようにしましょう。
家を相続した時の登記手続き
家を相続した後の登記手続きに関しては、司法書士に登記を代行してもらうこともできます。
その場合、司法書士から伝えられた必要書類を用意して渡せば手続きは終了です。
一方、司法書士に登記を依頼すると司法書士報酬を支払う必要があるため、自分で登記手続きすると判断することもあるでしょう。
その場合、以下のように手続きを進めていく必要があります。
- 遺産分割協議書を作成する
- 必要書類を取得する
- 登記申請書を作成する
- 法務局で登記申請する
それぞれの手続きについて詳しく見ていきましょう。
①遺産分割協議書を作成する
相続開始後、相続人全員で相続財産をどのように分けるか遺産分割協議で話し合った内容は遺産分割協議書として残しておく必要があります。
また、遺産分割協議書は相続登記の際に必要な書類となります。
遺産分割協議書の書き方には決まりがあるわけではありませんが、相続登記の際に法務局に無効と判断されれば相続登記は完了しません。
②必要書類を取得する
まずは相続登記に必要な書類を取得しましょう。
相続登記の必要書類には法務局で取得する必要のある登記事項証明書や、役所で取得する必要のある住民票、戸籍謄本などがあります。
法務局や市役所は平日しか空いていないため、休みを取るなどして計画的に書類を取得する必要があるでしょう。
ちなみに��、生まれてから亡くなるまでの間に何回も引っ越しているような場合には日本全国から戸籍を集める必要があります。
また、相続人全員の戸籍謄本や印鑑証明書も必要になるため注意しましょう。
③登記申請書を作成する
法務局で受け取れる登記申請書に必要事項を記入します。
内容に関して分からない箇所があれば法務局の窓口で聞きながら記入を進めることもできます。
④法務局で登記申請する
作成した登記申請書、用意した必要書類、遺産分割協議書、登録免許税分の現金を用意したら、法務局の窓口で登記申請しましょう。
その場では簡単なチェックで受理してもらえますが、間違いがあれば後日法務局から連絡が来て、法務局に書類を受け取りに行く必要があります。
修正も済んで、相続登記が完了したら、登記識別情報の発行を受けることができます。
以上で相続登記の手続きは終了です。
相続登記の必要書類
相続登記の必要書類には以下のようなものがあります。
- 対象不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)
- 対象不動産の固定資産評価証明書
- 被相続人(亡くなった方)の住民票除票
- 被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書
- 相続人の住民票
- 遺産分割協議書
それぞれについて詳しく見ていきます。
対象不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)
相続する不動産の登記事項証明書は法務局で取得できます。
対象不動産の固定資産評価証明書
固定資産評価証明書は相続登記の登録免許税の計算に用いられ、役所で取得できます。
被相続人(亡くなった方)の住民票除票
被相続人(亡くなった方)が亡くなったことを証明する書類で、役所で取得できます。
被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍謄本
被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍謄本が必要です。
生前に何回も引っ越しているような場合は、それぞれの役所から戸籍を集める必要があります。
また、生まれたのが大正や明治時代であればその時代の戸籍謄本も集めなければなりません。
相続人全員の戸籍謄本
相続人全員の戸籍謄本です。
相続人それぞれの住所地の役所で取得する必要があります。
相続人全員の印鑑証明書
相続人全員の印鑑証明書についても、相続人それぞれの住所地の役所で取得する必要があります。
なお、役所に届け出た印鑑(実印)は遺産分割協議書に押印しなければなりません。
相続人の住民票
不動産を相続することが決まった登記名義人の住民票が必要です。
役所で取得しましょう。
遺産分割協議書を作成する
相続財産をどのように分けるか話し合った遺産分割協議の結果をまとめた遺産分割協議書も相続登記の際に提出する必要があります。
家を相続した時の登記費用
相続登記の費用は、司法書士に登記を依頼するのと、自分で登記するのとで費用が変わります。
具体的には、自分で登記する際には相続登記に必要な登録免許税だけで済みますが、司法書士に依頼する際には登録免許税に加えて司法書士報酬を支払う必要があります。
相続登記に必要な登録免許税
相続登記に必要な登録免許税は、以下の計算式で求められます。
相続する不動産の固定資産税評価額×0.4%
例えば、相続する不動産の固定資産税評価額が1,000万円の場合、1,000万円×0.4%=4万円となります。
固定資産税評価額については、固定資産評価証明書で確認できます。
相続登記に必要な司法書士報酬の相場
相続登記を司法書士に依頼した場合、司法書士に対して司法書士報酬を支払う必要があります。
司法書士報酬は依頼する司法書士によって金額が変わりますが、一般的な相場は5~10万円となっています。
なお、司法書士に不動産登記費用を支払う際は、登録免許税と司法書士報酬を合わせて支払います。
相続手続きはやることが多いので計画的に
以上、相続登記の流れや必要書類、登記費用についてお伝えしました。
親族が亡くなった後は何かと忙しく、手間もお金もかかる相続登記は後回しになりがちですが、のちのち必要になった時に問題とならないよう、できるだけ早いタイミングで手続き��しておくことをおすすめします。
手間を惜しむのであれば司法書士に登記を依頼すればすぐに手続きが済みますが、費用がかかってしまいます。
相続登記については自分で手続きすることもできるので、手間を取るかお金を取るかで選ぶとよいでしょう。