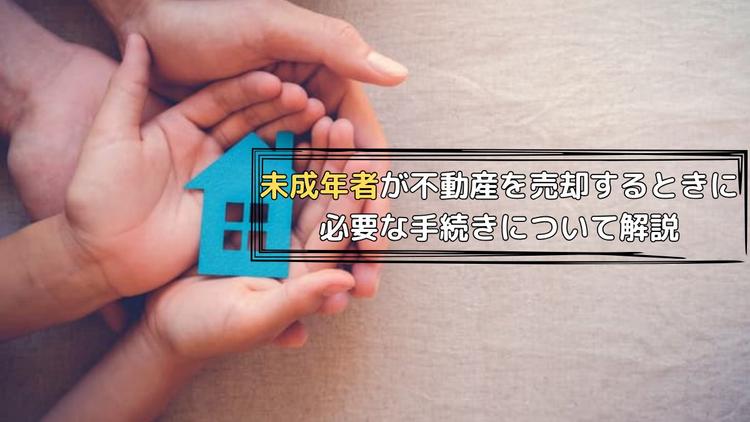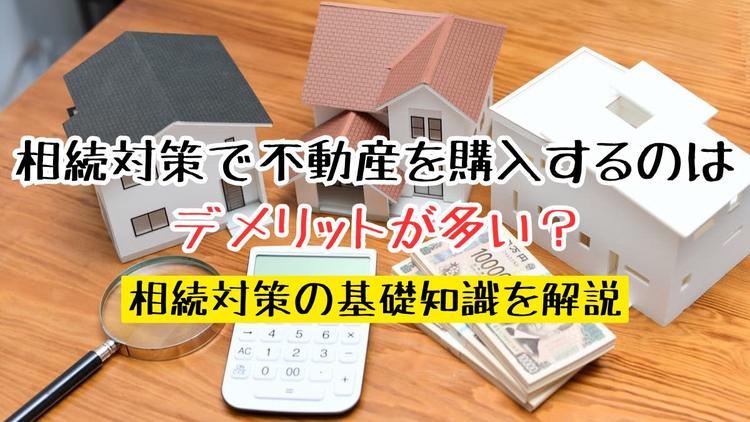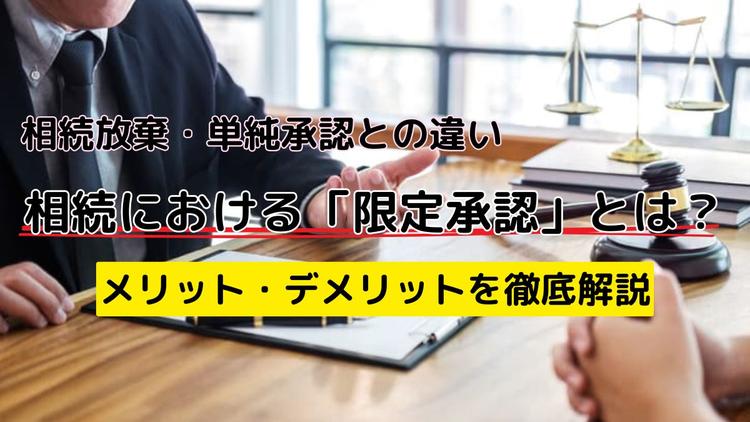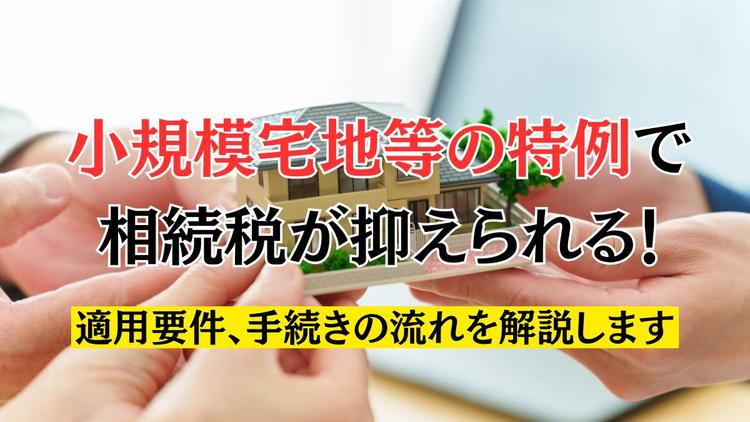未成年者の孫に不動産を相続させたいと考える人は少なからずいます。一方で、未成年者が不動産を維持管理するのはとても困難であり、売却をしたいと考えるケースも多いでしょう。
では、法的に何かと制限が多い未成年者が不動産を売却するには、どのように手続きを進めればいいのでしょうか。この記事ては、未成年者が不動産を売却するときに必要な手続きについて解説していきます。
土地の売却で未成年はどんな制約があるのか
未成年が不動産を所有しているケースで多いのが、祖父母からの相続によるものです。
ところが、その不動産が居住地から離れた地域にあると、維持管理も難しいので、すぐに売却して現金化したいと考える人が少なくありません。
では、不動産の所有者が未成年であっても売却は可能なのでしょうか。
結論から言えば、所有者が未成年であっても不動産の売却は可能です。
しかし、売却に至るまでの過程で様々な制約が付きまといます。
ここではまず、未成年が不動産を売却するに際して、どのような制約があるのかを押さえておきましょう。
未成年者は法律行為ができない
民法では、
未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。(第5条)
と定められています。
この場合の「法律行為」とは、「当事者がした意思表示の内容どおりの法律効果を発生させる法律要件」とされていますが、一般的には契約などが該当します。
つまり、未成年者が不動産の売買契約を締結しようとすれば、法定代理人の同意が必要なのです。
そもそも未成年者とは
基本的な話になりますが、未成年の定義を押さえておきましょう。
民法では
年齢18歳をもって、成年とする。(第4条)
とされていることから、18歳未満が未成年として扱われます。
2022年4月1日から施行された改正民放により、18歳未満が未成年に��なりました。
なお、旧民法では未成年でも婚姻をしていれば成年とみなすことが規定されていましたが、改正民放では女性の婚姻年齢も16歳から18歳に引き上げられているため、男女共通で18歳以上が成年であるという認識で良いでしょう。
法定代理人とは
未成年の法定代理人は、親権者である両親です。
両親の離婚や死亡より、親権者が一人しかいない場合は、法定代理人は一人になります。
また両親ともにいない場合は、家庭裁判所が選任した未成年後見人が、法定代理人になります。
未成年者が不動産を売却する方法
法律行為にいろいろな制約がある未成年が不動産を売却するには、2つの方法があります。
それぞれどのように進めていけばいいのか解説をしていきましょう。
①未成年本人が売主として契約をする方法
未成年が法律行為をする場合は法定代理人の同意が必要です。
未成年の場合、法定代理人は親権者になりますから、両親がこれに該当します。
したがって、売主である未成年者が署名捺印した不動産売買契約書に、父と母がそれぞれ法定代理人として署名捺印をすれば、法的に有効な契約書となります。
離婚や死亡により、親権者が1名しかいない場合は、当該親権者1名の署名捺印で認められます。
②親権者が売主になって契約をする方法
親権者が法定代理人として売主になって、不動産売買契約を締結するという方法もあります。
この場合は、契約書に署名捺印をするのは、両親のみとなり、未成年者の署名捺印は要しません。
両親がいない場合は未成年後見人が法定代理人
親権者が法定代理人になると説明をしてきましたが、死亡などによって両親がいない場合は、未成年後見人が法定代理人になります。
未成年後見人は、本人または親族の申し立てによって家庭裁判所が選任します。
未成年後見人には、祖父母や叔父・叔母といった親族が選ばれるのが一般的です。
ただし、未成年者が多額の財産を所有している場合や、財産管理の方法について親族間で意見が対立している場合は、弁護士や司法書��士などの法律の専門家が選ばれることもあります。
法定代理人と代理人は役割が異なる
法定代理人と代理人は名称がよく似ていますが、役割は大きく異なるので注意が必要です。
不動産の売買において、本人が契約の場に立ち会えないときは、委任状を作成して代理人に手続きを委任することがあります。
この場合の代理人は、委任状に記された範囲の行為しか行うことはできません。
一方、法定代理人は、自分の意思で不動産を売却することができます。
したがって法的にも、法定代理人が示した意思が未成年者の意思であるとみなされます。
未成年が不動産を売却するときの注意点
未成年が不動産を売却する方法を解説しましたが、実際に売却する際には、いくつかの注意点がありますので、押さえていきましょう。
親権者の同意がない契約は取消可能
未成年者が親権者(法定代理人)の同意を得ないまま不動産売買契約を交わした場合、取り消すことができます。
民法第5条第2項では、
前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
としており、親権者の同意がない契約は、親権者あるいは契約者である未成年者自らが、当該契約を取り消すことができます。
取り消された場合、契約は最初から存在しなかったものとして扱われ、売買代金は買主に返却されます。
ただし、民法上、売買代金は現存利益のみを返還すればよいとされているため、取消までの期間に売主である未成年者がお金を使い込んでいれば、その残りの金額しか戻ってきません。
買主にとっては、未成年者からの不動産の購入は、非常にリスクの高い取引になるため、本人確認はもちろんのこと、法定代理人の同意があることをしっかりと確認してください。
追認をすれば契約は確定する
未成年者が法定代理人の同意を得ないまま不動産売買契約を交わした場合は、追認を受けることで、取消されることがない有効な契約とすることができます。
契約をした後で売主が未成年者であることが判明した場合、買主は法定代理人に対して、「契約の取り消し」の意思を確認することができるのです。
追認により取消の意思がないことが分かれば、以後契約が取り消されることはありません。
期限までに回答がなかった場合は、同意したものとみなされて、契約は確定します。
法定代理人の同意がなくても取り消せないことがある
未成年者が単独で交わした契約は、後に取り消すことができると解説をしてきましたが、状況によっては取り消せないことがあるので注意が必要です。
不動産売買の営業を許可された未成年者は、不動産の売却に関しては成人と同等の扱いになります。
このため、法定代理人の同意は必要なく、自分の判断で不動産を売却することができます。
ただし、自己居住用の不動産に関しては営業と無関係であるため、法定代理人の同意が必要です。
さらに、未成年者が年齢を偽ったり、法定代理人の同意書を偽造したうえで行った契約は、買主が事情を承知していた場合を除いて、契約を取り消すことはできません。
親に不動産を売却する場合は特別代理人が選定される
未成年者が不動産を売却する場合、親が法定代理人として同意することで契約が確定しますが、その親に不動産を売却する場合は、取り扱いが異なります。
買主である親が法定代理人だと、利益が相反する立場となり、法定代理人の本来の役割である「本人の利益を優先する」という判断が不可能になるからです。
このような場合、民法では次のように定めています。
親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、そ�の子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。(第826条第1項)
これに基づき、未成年者が親に不動産を売却する場合は、親権者である親は家庭裁判所に対して特別代理人を選任するよう請求することになります。
特別代理人は特別の資格を要しないため、叔父や叔母などの信頼のおける親戚が選ばれるケースが多いです。
未成年者が不動産を売却する際の書類
未成年者が不動産を売却する際の書類は、一般的に行われる手続きの他に用意する書類が必要になります。
どのような書類が必要になるのかみていきましょう。
不動産売却に必要な書類
一般的な不動産売却で必要な書類は次のとおりです。
- 実印・認印
- 印鑑証明書
- 本人確認書類……運転免許証・パスポート等
- 登記済権利証
- 収入印紙
- 住民票……登記上の住所と現住所が異なる場合に必要
- 固定資産評価証明書・固定資産税納税通知書
- 境界確認書・土地測量図
- 建築確認済証・検査済証
未成年者であっても不動産の売買時には実印が必要です。
印鑑登録をしていない場合は、契約の前に市町村役場で印鑑登録の手続きを行う必要があります。
未成年者が不動産売却で必要な書類
未成年者が不動産を売却する際は、上述の書類の他に、次の書類を用意する必要があります。
- 法定代理人(特別代理人)の戸籍謄本
- 法定代理人(特別代理人)の同意書
戸籍謄本は、現在電子化されているため「戸籍の全部事項証明書」と呼ばれています。
法定代理人(親権者)かどうかの関係性は、戸籍を見れば分かります。
また特別代理人の場合は、選任されるとそれが戸籍に記載されます。
同意書は、法定代理人が売主として契約をする場合は不要です。
なお、これらの書類は、所有権移転登記手続きの際にも必要になります。
まとめ
未成年者が不動産を売却する場合、法定代理人の同意が必要です。
両親が健在であれば、法定代理人は、父と母のそれぞれが法定代理人となります。
離婚や死亡によって、親権者が一人しかいない場合は、その親権者の人が単独で法定代理人となります。
未成年者が不動産の売却で何かと制約が多いのは、法律的には、まだまだ未成熟だと考えられているからです。
それだけに法定代理人の責任は重大だといえます。
もし法定代理人の立場になるような機会があれば、その際は、未成年者である我が子の利益を優先した判断が求められることになります。