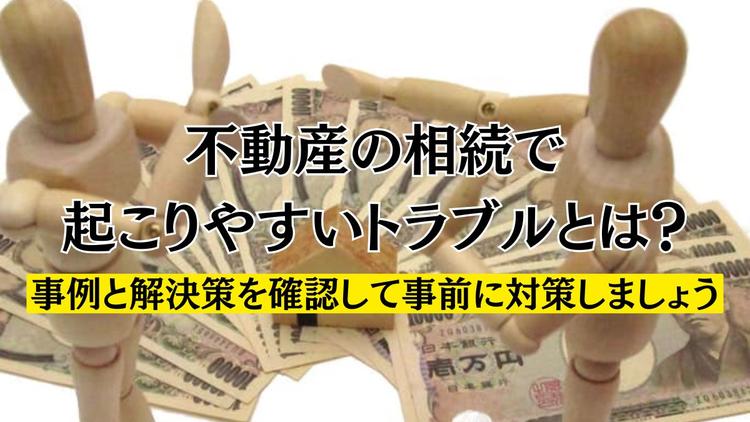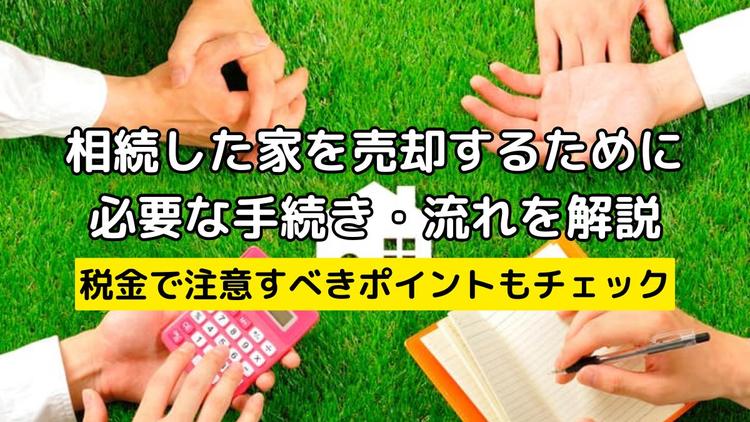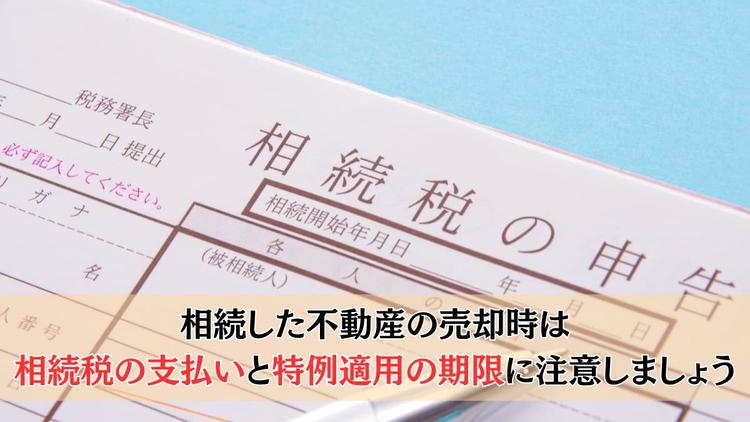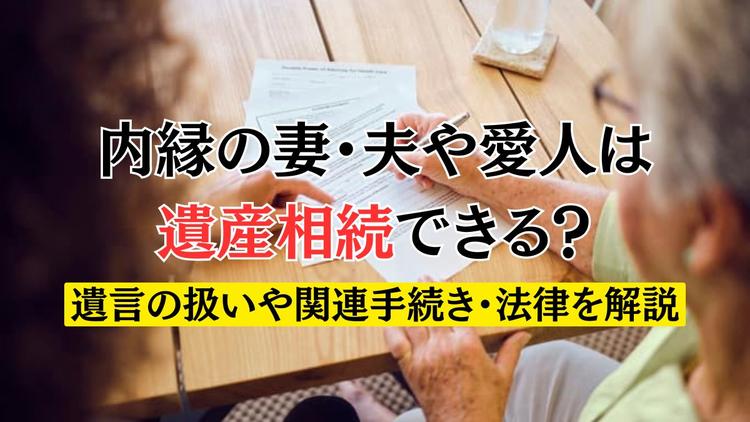相続不動産を売却したいと思っても、「相続登記が必要」「共有者全員の合意が必要」など、思わぬ手続きの壁に直面することがあります。
特に2024年の法改正により相続登記が義務化されたことで、手続きの重要性はますます高まっています。
不動産を相続して売却する際の基本的な手続きやポイントをチェックしましょう。
不動産は相続せずに売却できない
そもそも、不動産は相続せずに売却できません。
ここでは、相続せずに売却できない理由を解説します。相続不動産の売却を検討している方は確認しておきましょう。
相続登記が必要だから
売却できない理由は、相続登記が必要だからです。
そもそも、不動産を売るにはその不動産の名義人である必要があります。
しかし、不動産を相続した場合、所有者は亡くなった被相続人であり、そのままの状態では売却できません。
また、売買契約後の所有権移転も名義人でないと実施できません。
相続した不動産を売却する際には、まず相続登記をおこない、所有者として正式に登録する必要があります。
2024年から相続登記が義務化された
相続登記は、2024年4月1日から義務化されました。法務局でも以下のように記載されています。
令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されました。
相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。
(1)と(2)のいずれについても、正当な理由(※)なく義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ�)の適用対象となります。
不動産を相続した場合「相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内」に相続登記が必要です。
手続きを怠ると10万円以下の過料が科される可能性があります。
相続登記は相続した不動産の所在地を管轄する法務局で手続きできます。
相続不動産を売却したい方は早めに手続きしましょう。
相続不動産を売却する場面
相続不動産を売却する場面は、主に以下のようなケースが想定されるでしょう。
- 相続不動産に住む・利用する予定がない
- 換価分割による遺産分割をしたい
- 被相続人希望の清算型遺贈に従うため
それぞれの場面を詳しく解説します。
相続不動産に住む・利用する予定がない
相続した不動産を使う予定がない場合、早めに売却することをおすすめします。
不動産を相続した場合、住んだり使わなかったりしても所有しているだけで税金が発生するからです。
不動産を所有し続けると、固定資産税や維持管理費がかかります。特に、空き家のまま放置すると劣化が進み、資産価値が下がる恐れがあります。
また、相続した不動産を3年以内に売却すると「取得費加算の特例」や「相続空き家の3,000万円特別控除」といった税制上のメリットを受けられる可能性があります。
これらの優遇措置を受けるためにも、相続不動産に住んだり利用したりする予定がない場合は、早めに売却した方がよいでしょう�。
換価分割による遺産分割をしたい
換価分割による遺産分割をしたい場合も売却した方がよいでしょう。
換価分割とは、相続した不動産を売却して現金化し、そのお金を相続人で分ける方法です。不動産をそのまま分けるのが難しい場合、公平に遺産を分ける手段として有効です。
不動産は価値が高く、物理的に分けるのが難しいため、相続人間での公平な分配が難しくなるケースがあります。
換価分割をおこなうことで不動産を売却して得た現金を相続人で均等に分配でき、納税資金の確保にも役立ちます。
ただし、売却には手間や費用がかかり、譲渡所得税が発生する可能性もあります。
被相続人希望の清算型遺贈に従うため
被相続人が遺言で「清算型遺贈」を希望している場合も売却すべきケースです。
清算型遺贈とは、遺産を売却して得たお金を相続人や受遺者に渡す方法です。
この方法では、不動産などの資産を現金化し、債務を差し引いた残りを分配します。
不動産は管理や維持に手間と費用がかかるため、現金で受け取る方が負担が少なくなります。また、資産の価値は変動するため、現金化することで公平に分配できます。
被相続人が遺言で清算型遺贈の旨を記載している場合、早めに売却して現金を分配しましょう。
相続不動産を売却するうえでのポイント
相続不動産を売却するうえでのポイントは以下の4点です。
- 相続登記を済ませないと売買契約できない
- 相続登記は早めに済ませる
- 売却時期を見極める
- 共有名義の場合は共有者全員の合意が必要
スムーズに売却するためにも理解しておきましょう。
相続登記を済ませないと売買契約できない
不動産を相続した場合、相続登記を済ませないと売買契約できません。
前述のとおり、不動産を売却するには名義人になる必要があり、名義人になるには相続登記が必要です。
また、2024��年から相続登記が義務化され、相続したことを知っているにもかかわらず期間内に登記しない場合はペナルティが課される恐れもあります。
相続不動産をスムーズに売却するためにも相続登記を済ませておきましょう。
相続登記は早めに済ませる
相続登記は早めに済ませましょう。
相続登記を怠ると売却手続きが進められず、買主への名義変更ができません。また、登記を放置すると相続人が増えたり、高齢化による判断能力の低下で手続きが複雑化したりする可能性があります。
相続登記は必要書類を準備する必要もあり、役所などで入手する手間や時間もかかります。
焦って登記しようとすると登記期限が過ぎ、ペナルティが課される可能性もあるため、早めに登記を済ませましょう。
売却時期を見極める
相続不動産を売却する際は、売却時期を慎重に見極めることが重要です。
相続税の納付期限は、相続開始から10カ月以内と定められており、売却を急がないと相続税を納付するための資金が不足する可能性があります。そのため、売却の計画を早めに立てることが大切です。
また、不動産を売却した際には、譲渡所得税が発生する場合があります。譲渡所得税は、売却価格から取得費や譲渡費用を差し引いた利益に課される税金で、売却価格が高いほど税額も増加する可能性があります。
しかし、以下の特例を活用することで、譲渡所得税を軽減可能です。
取得費加算の特例
相続から3年10カ月以内に売却すると、相続税の一部を取得費に加算でき、譲渡所得を減らせます。
参考:国税庁|No.3267 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例
相続財産の3,000万円特別控除
被相続人が居住していた不動産を売却する場合、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる可能性があります。
参考:国税庁|No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例
これらの特例を利用するには、適用条件を事前に確認した上で確定申告が必要です。
相続税の納付や売却時期に関して不安がある場合は、税理士や不動産会社などの専門家に相談し、最適な計画を立てましょう。
共有名義の場合は共有者全員の合意が必要
相続した不動産が複数人の共有物である場合、共有者全員の同意が必要です。
共有物の処分には共有者全員の同意が法律で定められているためです。
各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。次項において同じ。)を加えることができない。
2 共有者が他の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、裁判所は、共有者の請求により、当該他の共有者以外の他の共有者の同意を得て共有物に変更を加えることができる旨の裁判をすることができる。
相続後に不動産を売却する際は、まず相続登記をおこない、所有者��を相続人に変更する必要があります。
その後、共有者全員で売却に関する協議をおこない、全員の同意を得てから売却手続きを進めます。
特に、共有者が多い場合は全員の同意を得るのが難しかったり、同意を得るのに時間がかかったりするため、早めに売却に向けて動き出しましょう。
不動産の相続から売却までの流れ
不動産の相続から売却までは以下の流れで進みます。
- 遺言書の確認
- 相続登記
- 不動産会社へ依頼
- 売買契約
- 決済・引き渡し
それぞれの手順を解説します。
①遺言書の確認
まずは遺言書を確認しましょう。
遺言書があるケースと無いケースでは進め方が異なります。遺言書の有無を確認し、それぞれの手順で進めましょう。
遺言書があれば従う
遺言書があれば内容に従いましょう。
遺言書には、誰がどの財産を受け取るかが明確に記されている場合があります。そのため、遺言書の指示に従って不動産の名義変更をおこない、その後に売却手続きを進めるのが一般的です。
また、遺言書の種類によって手続きが異なります。自筆証書遺言の場合、家庭裁判所での検認が必要です。一方、公正証書遺言であれば検認手続きは不要で、スムーズに手続きを進められます。
遺言書について疑問点があれば、弁護士や司法書士などの専門家へ相談しましょう。
遺言書が無ければ遺産分割協議をする
遺言書がない場合、相続財産を分けるために相続人全員で遺産分割協議をおこないましょう。
遺産分割協議では、誰がどの財産をどのくらい受け取るかを決めます。全員の同意が得られたら、その内容を文書にまとめて全員が署名と押印をおこないます。
これを「遺産分割協議書」と言います。この協議書がないと不動産の名義変更や売却手続きを進められません。そのため、相続不動産を売却したい場合は、まず相続人全員で遺産分割協議をおこない、協議書を作成しましょう。
②相続登記
遺言を確認したら相続登記をしましょう。
相続登記に必要な書類や期限について解説します。
必要書類の確認
相続登記するには以下の書類が必要です。
| 書類 | 取得先 |
| 被相続人の戸籍謄本 | 被相続人の本籍地の市区町村役場 |
| 被相続人の住民票の除票 | 被相続人の最後の住所地の市区町村役場 |
| 相続人全員の戸籍謄本 | 各相続人の本籍地の市区町村役場 |
| 相続人全員の住民票 | 各相続人の住所地の市区町村役場 |
| 遺産分割協議書 | 各相続人で作成(必要に応じて専門家に依頼) |
| 固定資産税評価証明書 | 不動産所在地の市区町村役場(固定資産税課) |
これらの書類を揃えて名義変更する必要があります。
書類によっては市区町村役場で申請するものもあるため、早めに準備しましょう。
期限までに登記
相続登記は期限までに登記しましょう。
期限は、「所有権の取得を知った日から3年以内」であり、この期限を過ぎると10万円以下の罰金が科される可能性があります。
また、手続きを怠ると売却時に手続きが複雑化し、時間や費用が余計にかかることもあります。
相続した不動産を売却する予定がある場合は、早めに名義変更の手続きを完了させましょう。
③不動産会社へ依頼
相続登記が完了したら不動産会社へ売却依頼しましょう。
不動産会社は、適正な価格設定や買い手探し、契約手続きなど、売却に関するサポートを行ってくれます。
不動産会社を選ぶ際は、売却実績や評判などを確認し、本当に信頼できるのか見極めることが大切です。
また、担当者によっても売却価格やスピードなども異なるため、担当者の実績や経験、態度や言動などもよく見ておきましょう。
売却依頼の際は、最初に査定を受け、売却活動を行ってもらうために「媒介契約」を結びます。
司法書士や税理士と連携して、相続の手続きや相続税の納付に関してサポートしてくれる会社もあるため、相続での売却であることを伝えた上で査定を依頼し、信頼できる業者と媒介契約を結びましょう。
④売買契約
不動産会社へ依頼し、買主が見つかれば売買契約を結びます。
売買契約書を不動産会社が作成し、売主・買主の双方が署名・押印をおこないます。
契約書には、売買価格、支払い方法、引き渡し日、契約解除に関する事項など、取引に関する詳細が記載されます。
また、契約時には買主から売買金額の5~10%前後の手付金が支払われるのが一般的です。
契約内容に不備がないか、疑問点がないかなどをすべて確認して契約書にサインしましょう。
⑤決済・引き渡し
売買契約を結んだら、最後に決済と引き渡しです。
決済では、買主から売主へ残りの代金を支払います。手付金を差し引いた残額がここで精算される仕組みです。
このとき、売主は不動産の権利証や登記識別情報など、所有権移転に必要な書類を用意する必要があります。また、不動産会社への仲介手数料や司法書士への報酬などの諸費用も、この段階で清算します(仲介手数料は売買契約時と決済時に半額ずつ支払う場合もある)。
代金の受け渡しが終われば、物件の引き渡しに進みます。具体的には、物件の鍵や関連書類を買主に渡す流れです。
同時に、司法書士が所有権移転の登記手続きを進め、正式に買主の所有となります。
これらの手続きが完了すれば、不動産売却は無事成立となります。
不動産を相続せずに売却することに関するよくある質問
不動産を相続せずに売却することに関するよくある質問をご紹介します。
相続不動産の売却についての疑問や不安を参考にしてみましょう。
相続せずに放置してもいいですか?
放置するとさまざまなリスクが伴うため、早めに売却することを推奨します。
- 所有者不明の土地として扱われ、管理責任が問われる
- 固定資産税の負担が増える
- 未登記のまま放置すると罰則の対象となる
不動産を相続して所有者となった後は、適切に管理しなければなりません。しかし、放置したままだと建物が劣化したり景観が悪くなったりします。
その結果、管理責任を問われるリスクがあります。
また、所有者には固定資産税が課されるため、使用していなかったとしても毎年固定資産税を支払わなければなりません。
さらに、相続登記が義務化されたため、相続人は期限内に登記しなければならず、怠るとペナルティが課される恐れもあります。
相続不動産を放置していると、このようなリスクが伴うため、早めに売却した方がよいでしょう。
相続登記しないと買取もしてもらえない?
不動産買取は、直接不動産会社に買い取ってもらう方法ですが、買い取った後は、一般の買主へ再販するのが一般的です。
しかし、相続登記が完了していない不動産は、売買契約後の「所有権移転」ができないため、契約したとしても買主に引き渡せません。
不動産会社への所有権移転登記もできないため、売買契約も締結しないのが一般的です。
そのため、相続登記が未完了の不動産は基本的に買い取ってもらえないといえます。
相続せずに解体できる?
相続手続きせずに不動産は解体できません。
相続不動産を解体するには相続登記をして、その不動産の所有者になる必要があります。
また、相続人が複数人いる場合は相続人全員の共有物となります。そのため、解体するには相続人全員の同意を得なければなりません。
もし同意を得ずに解体�をおこなうと、他の相続人から損害賠償を請求される可能性や建造物損壊罪に問われるリスクがあります。
安全かつ円滑に解体を進めるためには、まず遺産分割協議をおこない、解体に関する合意を得ることが重要です。
まとめ
相続せずに売却できない理由を解説しました。
相続不動産は相続登記しなければ売却できません。また、相続登記は2024年から義務化され、期間内に手続きしないと10万円以下の罰金を課される可能性があります。
相続不動産を放置すると、固定資産税が余計にかかったり管理責任を問われたりするため、早めに売却すべきです。
不動産の相続は頻繁にあることではなく、実際に相続して扱いに困っている方も少なくありません。
相続不動産でお困りの方は、ぜひこの記事でご紹介した売却のポイントや流れを参考にして、適切に売却を進めましょう。