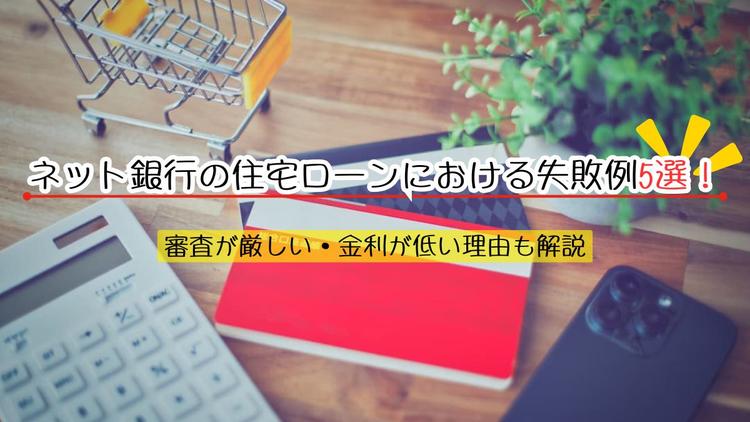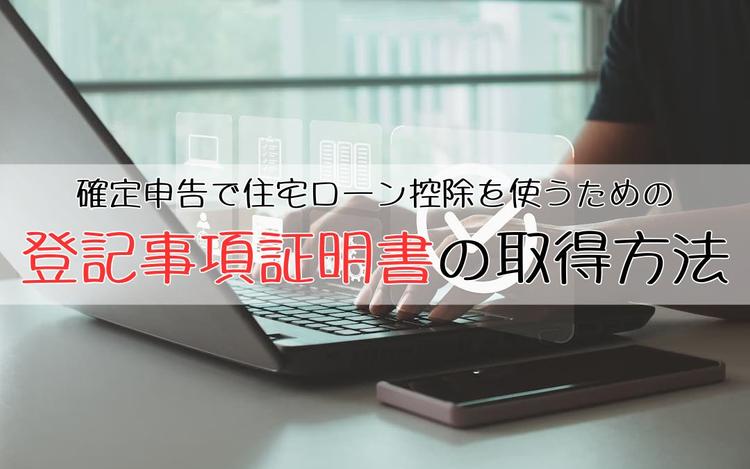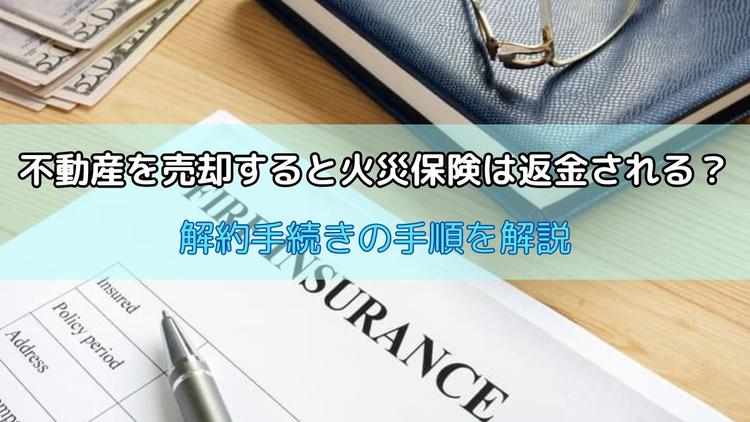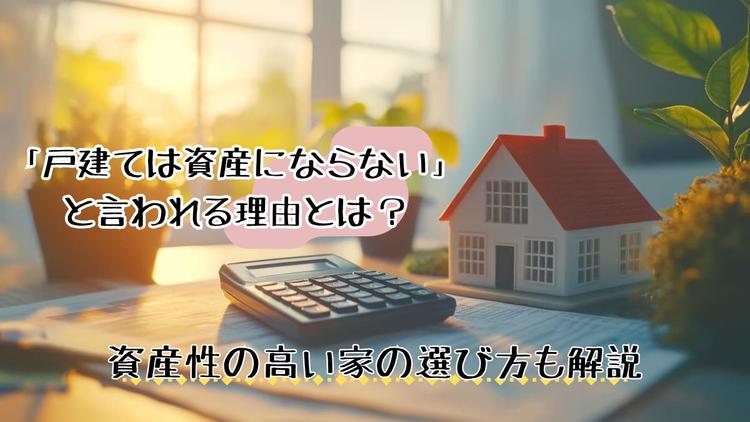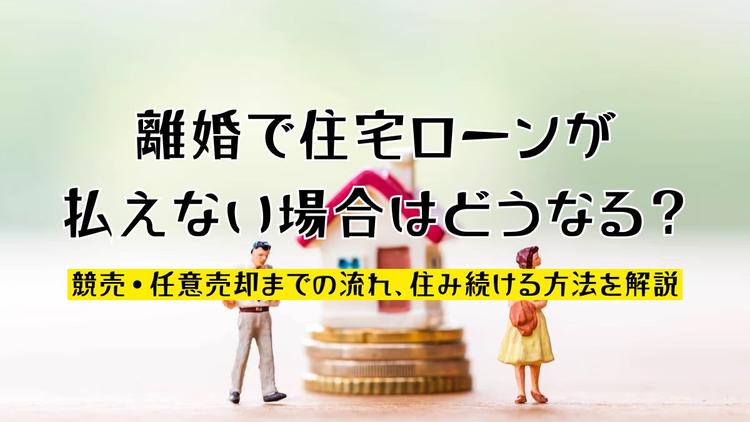相続した土地であっても、売却すれば税金がかかります。
とくに、相続した土地はいくらで購入したか分からず、税額が高くなるケースも少なくないので注意が必要です。
この記事では、相続した土地の売却にかかる税金の種類や計算方法、節税できる特別控除などを詳しく解説します。
相続した土地を売却したときに発生する3つの税金
相続した土地を売却したときに発生する税金は、以下の3つです。
- 譲渡所得税・住民税
- 登録免許税
- 印紙税
印紙税は基本的に必ずかかってくる税金ですが、譲渡所得税・住民税、登録免許税はケースによって課税の有無が異なります。
以下で詳しくみていきましょう。
譲渡所得税・住民税
土地を売却して得た利益は「譲渡所得」と呼ばれる所得に区分され、所得税・住民税の対象です。
また、2037年までは東日本大震災の復興資源となる復興特別所得税も併せて徴収されます。
譲渡所得にかかる税金は、売却で利益が出た場合のみ課税となるため、売却で損失が出れば課税されません。
たとえば、購入した価格よりも高値で売れれば課税され、安値での売却になれば課税されないというイメージです。
ただし、課税されるとなると税額が100万円を超えるケースも珍しくない、高額になりがちな税金でもあります。
売却時に発生する税金の中でも、もっとも多くの割合を占めるのがこの譲渡所得にかかる税金であるため、計算方法などを押さえておくことが大切です。
譲渡所得にかかる税金の計算方法や節税方法は、後ほど詳しく解説するので参考にしてください。
登録免許税
登録免許税とは、不動産登記の手続きの際に法務局に支払う税金です。
土地や建物は、�法務局の登記簿に不動産情報や所有者などが記録されており、新築したり所有者が変更になったりした際には登記内容の新設や変更手続きが必要になります。
この登記の新設、変更をする手続きは不動産登記と呼ばれ、不動産売却では必ず必要な手続きです。
不動産登記は手続きの目的によっていくつか種類が分かれますが、売却時に関わってくるのは以下の2つです。
- 所有権移転登記:所有者を売主から買主に変更する登記
- 抵当権抹消登記:抵当権を抹消する登記
売却により所有者が売主から買主に変更になるため、登記上の所有者を変更する所有権移転登記を行います。
所有権移転登記をすることで、買主は土地の所有者であることを第三者に公的に証明できるようになるのです。
所有権移転登記
ただし、所有権移転登記は一般的に買主負担で行うケースがほとんどであり、売主の負担となることは少ないです。
とはいえ、どちらが負担するかは合意で決まるため、売買契約の際にしっかり確認するようにしましょう。
抵当権抹消登記
一方、抵当権抹消登記とは、土地に設定されている抵当権を抹消する登記です。
住宅ローンで土地を購入した場合、金融機関によって抵当権が設定されます。
抵当権付きの不動産は基本的に売却できないため、売却に伴い住宅ローンを完済し、抵当権を抹消する必要があります。
一般的には、売却金で住宅ローンを完済して、抵当権を抹消するケースが多いでしょう。
また、すでに住宅ローンを完済していても抵当権抹消登記を放置していた場合は、売却前に抵当権�抹消登記が必要になります。
抵当権抹消登記の登録免許税は「不動産個数×1,000円」で、仮に土地が1筆のみの売却なら1,000円、土地と建物セットで売却なら2,000円となります。
抵当権抹消登記は、抵当権が設定されている場合のみ必要です。
もともと抵当権が設定されていない、すでに抹消済みというケースでは必要ありません。
なお、抵当権抹消登記を司法書士に依頼する際の費用は、売主が負担するのが一般的です。
印紙税
印紙税とは、課税対象の文章を作成した際にかかる税金です。
土地の売却では、売買契約書が課税の対象となるため、契約書に収入印紙を貼付・消印して納税します。
印紙税の税額は売買契約書に記載されている金額に応じて異なり、主な土地取引の価格帯での税額は以下のとおりです。
| 契約金額 | 本則税率 | 軽減後の税率(2027年3月31日まで) |
| 100万円超500万円以下 | 2,000円 | 1,000円 |
| 500万円超1,000万円以下 | 1万円 | 5,000円 |
| 1,000万円超5,000万円以下 | 2万円 | 1万円 |
| 5,000万円超1億円以下 | 6万円 | 3万円 |
なお、2027年3月31日までは軽減後の税率が適用されます。
印紙税の納税を怠ると、本来の税額の3倍相当額の過怠税というペナルティが課せられるため、忘れずに納税するようにしましょう。
売買契約書は、売主・買主それぞれが�保管するように2通作成しますが、自分が保管する分のみの負担となるのが一般的です。
譲渡所得税の計算方法
譲渡所得にかかる税金は高額になりがちのため、計算方法を押さえて納税の資金計画を立てておくことが大切です。
譲渡所得にかかる税金は以下の2つのステップで求めます。
- 【ステップ1】課税譲渡所得の計算
- 【ステップ2】課税譲渡所得に税率をかける
以下で、詳しい計算方法をみていきましょう。
課税譲渡所得の計算
課税対象となる譲渡所得は以下の方法で計算します。
取得費は土地の購入にかかった費用であり、土地代だけでなく仲介手数料や印紙税などが含まれます。
一方、譲渡費用は売却時にかかった費用であり、仲介手数料や解体費などがあります。
主な取得費・譲渡費用に含まれる項目は以下のとおりです。
| 取得費 | 譲渡費用 |
|
|
売却額から、上記の費用を差し引いた部分が譲渡所得となります。
例えば、売却額が1,500万円で取得費1,200万円・譲渡費用100万円なら「1,500万円-(1,200万円+100万円)=200万円」が譲渡所得です。
相続した土地の場合、取得費が不明というケースは珍しくありません。
取得費が不明な場合は、売却額の5%を概算取得費として計上します。
また、特別控除が適用できる場合は、さらに特別控除を差し引くことが可能です。
特別控除については、後ほど詳しく説明するので参考にしてください。
特別控除まで差し引いてプラスになった場合、税金が発生するため確定申告での納税が必要です。
反対に、マイナスなら税金は発生しないので確定申告も不要になります。
譲渡所得の税率
税金が発生する場合、以下の計算式で税額を求められます。
課税譲渡所得に税率を乗じるだけのシンプルな計算で税額を計算できます。
ただし、税率は所有期間に応じて以下の2種類に分かれるので注意しましょう。
| 所有期間 | 所得税 復興特別所得税 | 住民税 | 合計税率 | |
| 短期譲渡所得 | 5年以下 | 30.63% | 9% | 39.63% |
| 長期譲渡所得 | 5年超 | 15.315% | 5% | 20.315% |
所有期間5年を境に、短期譲渡所得・長期譲渡所得に区分されます。
短期譲渡所得は長期譲渡所得に比べて税率も高くなるので、注意しましょう。
なお、相続した不動産の場合、相続後の所有期間ではなく、被相続人(故人)の所有期間を含めて所有期間を判断します。
たとえば、被相続人が10年所有し、相続してから1年という場合は、所有期間は11年となるので長期譲渡所得になるのです。
相続した土地を売却するときの税金を安く抑える4つの方法
相続した土地の売却にかかる税金は、以下の4つの方法で安く抑えられる可能性があります。
- 取得費の分かる書類を用意する
- 譲渡費用をできるだけ多く計上する
- ふるさと納税や医療費控除を活用する
- 特例を活用する
それぞれ見ていきましょう。
取得費の分かる書類を用意する
相続した土地の場合、正確な取得費が計上できず利益が大きくなってしまい税額が増えるケースがあります。
先述したように、取得費が証明できない場合は概算取得費として売却額×5%を計上することになります。
概算取得費は、本来の取得費よりも低くなることが多く、利益が大きく出やすいのです。
例えば、次のケースでみてみましょう。
- 売却額:2,000万円
- 取得費:1,500万円
- 譲渡費用:200万円
上記の場合、取得費が証明できれば譲渡所得は「2,000万円-(1,500万円+200万円)=300万円」です。
しかし、概算の取得費で計上するとなると、取得費が「2,000万円×5%=100万円」となるため、譲渡所得は「2,000万円-(100万円+200万円)=1,700万円」となります。
仮に、この時に譲渡所得の税率が20.315%の場合の税額は以下のとおりです。
- 取得費を証明できる場合:300万円×20.315%=約61万円
- 概算取得費の場合:1,700万円×20.315%=約345万円
取得費を証明するには、売買契約書や領収書などの書類が必要です。
被相続人が亡くなってからでは、保管場所が分からず見つからないケースも多いので、できるだけ生前中に確認しておくとよいでしょう。
譲渡費用をできるだけ多く計上する
譲渡所得は、取得費だけでなく譲渡費用を多く計上することでも圧縮でき、節税につながります。
譲渡費用の証明にも領収書などの書類が必要なので、仲介手数料や印紙税などの領収書は大切に保管しておくようにしましょう。
なお、売却時に支払った費用であっても、以下のような費用は譲渡費用として計上できません。
- 抵当権抹消登記の費用
- 遺産分割のための支出
- 土地の維持管理費用 など
譲渡費用とは、売却のための費用です。
修繕費や固定資産税といった土地の維持管理の費用や、直接売却に関わらない費用などは計上できないので注意しましょう。
計上できる費用かどうかの判断に悩む場合は、税理士や税務署に確認することをおすすめします。
ふるさと納税や医療費控除を活用する
ふるさと納税とは、自治体への寄付額のうち2,000円を超えた部分について、所得税の還付と住民税の控除が受けられる制度です。
実質2,000円の自己負担で寄付額に応じて返礼品を得られるというお得さもあり、近年人気が高まっています。
ふるさと納税で控除できる額は、所得額に応じて決まってきます。
譲渡所得もふるさと納税での控除の対象となるため、譲渡所得がある年はふるさと納税の上限額がアップし、より高額な返礼品をもらえる可能性があります。
ふるさと納税の仕組み
なお、ふるさと納税は厳密に言えば所得税・住民税の先払いであり、節税にはつながりません。
とはいえ、税金を支払って返礼品をもらえるというお得さがあるので、検討してみるとよいでしょう。
ただし、ふるさと納税で控除できる金額は年収や譲渡所得額、家族構成などによって大きく異なります。
控除上限額以上を寄付しても無駄になってしまうため、自分の控除上限額を把握したうえでいくら寄付するかを決めるようにしましょう。
医療費控除の仕組み
医療費控除は、年間の医療費が10万円または総所得金額等の5%を超えた場合に、その超過分を所得から控除できる制度です。
医療費控除を含む所得控除は総所得金額等から差し引かれますが、分離課税の所得(譲渡所得など)は対象外です。
そのため、医療費控除が譲渡所得の節税に直接つながることはありませんが、総合所得から控除できるため、その年の所得税や住民税の節税には役立ちます。
医療費をたくさん支払っている人は医療費控除を多く計上できるので、検討してみるとよいでしょう。
特例を活用する
ふるさと納税や所得控除・取得費の計上などで節税できる額は多くありません。
もっとも節税効果が高くなるのは、譲渡所得税における各種特例の適用です。
たとえば、譲渡所得の代表的な控除である「3,000万円特別控除」であれば、譲渡所得から最大3,000万円を差し引けるので、譲渡所得が3,000万円以下なら税金が0円となります。
他にも譲渡所得には節税が見込める控除の特例がいくつか用意されているので、上手に適用することで大幅な節税が可能です。
ただし、特例には細かい適用要件が決められており、どの特例を適用するかによっても節税効果は変わってきます。
自分のケースで適用できる特例の要件を調べ、シミュレーションしたうえで検討することが大切です。
具体的な特例については、次の章で詳しく解説します。
【タイミング別】相続した土地を売却したときに利用できる特例
相続した土地の売却に利用できる特例には、適用できる期間が設けられているケースも少な�くありません。
ここでは、適用できる期間を基準に、タイミング別で利用できる特例を紹介します。
相続してから3年以内の売却で利用できる特例
相続してから3年以内の売却で利用できる代表的な特例は、以下の2つです。
- 取得費加算の特例
- 相続空き家の3,000万円特別控除
取得費加算の特例
取得費加算の特例とは、土地を相続した際に支払った相続税の一部を、譲渡所得税計算の際に取得費に加算できる制度です1。
相続人が、相続のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以降3年を経過する日までの3年以内に売却するなど、要件を満たすことで適用できます。
ただし、相続時に相続税を支払っていることが前提です。
相続税を支払わなかったケースでは適用できないので、注意しましょう。
相続空き家の3,000万円特別控除
また、相続した空き家を解体し土地を売却する場合で検討できるのが「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」です2。
この特例では、譲渡所得から最大3,000万円を差し引くことができます。
家屋だけでなく解体後の更地でも検討できるので、条件に該当するか確認するとよいでしょう。
なお、適用の条件が「昭和56年5月31日以前に建設された家屋」や「相続開始のあった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却」など細かく、ややハードルの高い特例でもあります。
細かい要件については国税庁のホームページで確認するとよいでしょう。
タイミングに関わらず利用できる特例
売却のタイミングに関わらず利用できる主な特例は、以下の2つです。
- 平成21年及び平成22年に取得した土地の1000万円特別控除
- 低未利用土地等の100万円特別控除
「平成21年及び平成22年に取得した土地の1000万円特別控除」とは、平成21年に取得した土地を平成27年以降、平成22年に取得した土地なら平成28年以降に売却した際に、譲渡所得から1,000万円を控除できる特例です3。
相続してからの期間ではなく、取得した年で適用が決まるため、平成21年または平成22年に購入した土地であれば検討する��とよいでしょう。
一方、低未利用土地等の100万円特別控除では、都市計画区域内にある低未利用土地等を売却した場合に、譲渡所得から100万円を控除できます4。
低未利用土地等とは、居住用・事業用などの用途に利用されておらず、同地域内の同じ用途の土地に比べて著しく利用頻度の劣る土地のことです。
また、上記は長期譲渡所得から控除となるため、所有期間5年を超えることも条件となります。
細かい要件については国税庁のホームページを確認するとよいでしょう。
注意点:5年以内の売却は税率が高くなる
譲渡所得にかかる税率は、所有期間5年を境に大きく異なります。
所有期間5年以下で売却すると、5年超で売却した時に比べて倍近くの税率がかけられます。
相続した土地の場合、被相続人の所有期間も通算されるので、短期譲渡所得に区分されるケースは少ないですが、被相続人が直近で購入した土地は注意しなければなりません。
売却の期間に余裕があるなら、5年を超えてから売却するのも一つの手でしょう。
ただし、活用しない土地を所有しているとその期間にも固定資産税や管理費などがかかります。
売却額や特例の適用によっては短期譲渡所得となっても早めに売却したほうがお得になる可能性もあるので、シミュレーションして検討することが大切です。
相続した土地を売却したときの税金のシミュレーション
ここでは、相続した土地の売却にかかる税金を具体的なケース別にシミュレーションしていきます。
なお、今回は譲渡所得にかかる税金のみを計算します。
取得費加算を利用するケース
売却の条件は以下のとおりです。
- 売却額:3,000万円
- 取得費:2,500万円
- 譲渡費用:200万円
- 所有期間:10年
- 相続税:1,000万円を納税済
取得費加算で加算できる相続税は、以下の計算で求められます。
仮に、相続税総額が3,000万円、土地の課税価格が2,500万円、相続した課税価格を合計1.5億円とします。
この場合で加算できる額は以下のとおりです。
加算できる金額:3,000万円×2,500万円/(1.5億円+0円)=500万円
よって、譲渡所得税は以下のようになります。
上記の例では、譲渡所得がマイナスになるため、税金は発生しません。
3,000万円特別控除を利用するケース
条件は以下のとおりです。
- 売却額:2,000万円
- 取得費:1,000万円
- 譲渡費用:100万円
- 所有期間:15年
譲渡所得額は以下のようになります。
さらに、3,000万円特別��控除が適用できるので、課税譲渡所得は0円となり税金は発生しません。
取得費に関する書類が見つからず5%の概算法を活用するケース
条件は以下のとおりです。
- 売却額:4,000万円
- 取得費:不明
- 譲渡費用:200万円
- 所有期間:20年
- 特例の適用なし
概算の取得費は、以下のとおりです。
よって、課税譲渡所得は以下のようになります。
所有期間20年は長期譲渡所得に区分されるため、税額は以下のとおりです。
相続した土地を売却したときの確定申告の流れ
相続した土地を売却し譲渡所得税が発生すると、確定申告での納税が必要です。
確定申告時期は売却した年の翌年2月16日から3月15日となるため、忘れずに確定申告の用意をしましょう。
確定申告の大まかな流れは以下のとおりです。
- 必要書類を準備する
- 譲渡所得の内訳書や確定申告書に必要事項を記入する
- 税務署に書類を提出する
- 期限までに納税する
それぞれ見ていきましょう。
必要書類を準備する
以下が譲渡所得の確定申告における主な必要書類です。
- 確定申告書
- 譲渡所得の内訳書
- 売却した土地を購入した時の売買契約書のコピー
- 売却した土地を購入した時の領収書などのコピー
- 売却した時の売買契約��書のコピー
- 売却した時の領収書などのコピー
- 登記事項証明書
- 本人確認書類
- 特例の適用に必要な書類
確定申告書に加えて、所有期間や取得費・譲渡費用を証明するための書類が必要です。
また、3,000万円特別控除などの特例を適用する場合は、特例ごとの必要書類も加わります。
必要書類は国税庁のホームページで確認して漏れのないように準備しておきましょう。
譲渡所得の内訳書や確定申告書に必要事項を記入する
譲渡所得の内訳書・確定申告書を作成します。
国税庁のホームページでは記入例を記載しているので、チェックしながらミスのないように記入していきましょう。
e-Taxを利用すれば、必要項目に入力するだけで書類の作成が可能です。
記載内容にミスがあると、修正などで時間がかかるため、記入方法に不安がある場合は、自治体の相談コーナーや税理士などに相談するとよいでしょう。
税務署に書類を提出する
申告期限内に、税務署に作成した書類と必要書類を添えて提出します。
提出方法は、「税務署窓口」「郵送」「e-Tax」の3つがあるので、利用しやすい方法を選ぶとよいでしょう。
不安がある場合は窓口で提出すると簡易的なチェックを受けることが可能です。
ただし、申告時期の窓口は混み合うので時間に余裕をもって申告しましょう。
期限までに納税する
所得税の納税期限は、確定申告時期と同じです。
また、住民税は申告した年の5月以降に自治体から送付される納付書で納税します。
確定申告期間に申告できないと、無申告加算税などのペナルティを科せられる恐れもあるので、申告を忘れないように注意しましょう。
相続した土地を売却したときの税金に関するよくある質問
最後に、相続した土地を売却したときの税金に関するよくある質問をみていきましょう。
相続した土地はすぐに売却してもいい?
相続後いつ売却するかは売主の自由です。
ただし、特例によっては売却の期限が設けられているので、特例適用を検討しているなら期限内の売却を目指す必要があります。
また、被相続人からの通算の所有期間が5年以下だと税率が高くなるので、5年を超えてから売却を検討するのも1つの方法です。
相続した土地を売却するタイミングとしておすすめなのは?
相続税を支払っていて、相続空き家の特例を検討できるケースであれば、相続開始後3年以内の売却がおすすめです。
また、特例などを適用しない場合でも、活用しない土地であれば所有期間中もコストがかかるだけなので、早めの売却を検討するとよいでしょう。
共有持ち分がある土地を売却したときの譲渡所得税はどうなる?
共有持ち分のある土地で譲渡所得税が課税される場合、売却額や所得費・譲渡費用などを共有持ち分の割合で按分し、それぞれで税額を計算・確定申告する必要があります。
代表者がまとめて確定申告できるわけではないので、注意しましょう。
なお、共有持ち分の土地の場合、名義人それぞれで控除が適用できます。
たとえば、共有者2名の土地を売却し3,000万円特別控除を適用する場合は、それぞれで3,000万円を控除(最大6,000万円)できる�のです。
ただし、共有持ち分の土地を売却する場合は、名義人全員の合意が必要となり手間も時間もかかります。
自分の持分に合わせて分筆すれば単独での売却も可能ですが、面積が狭くなると売却も難しくなるので注意しましょう。
まとめ
相続した土地の売却では「譲渡所得にかかる税金」「登録免許税」「印紙税」が課税されます。
ただし、譲渡所得にかかる税金と登録免許税は課せられないケースもあるため、自分のケースでは課税されるかを理解することが大切です。
とくに、譲渡所得にかかる税金は高額になりがちなので、税額や適用できる控除を理解し、売却計画を立てるようにしましょう。