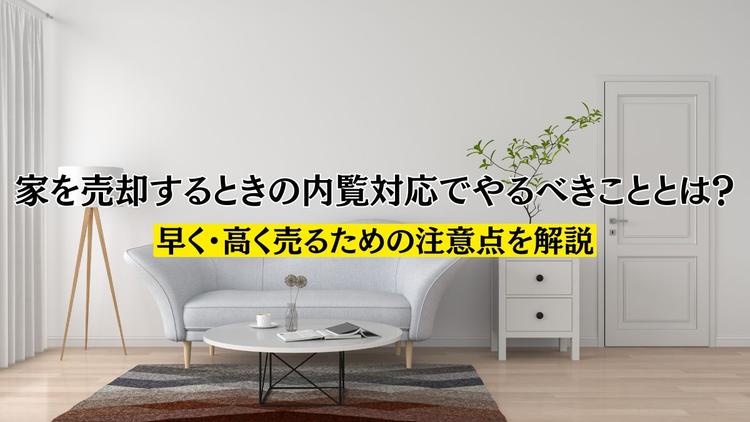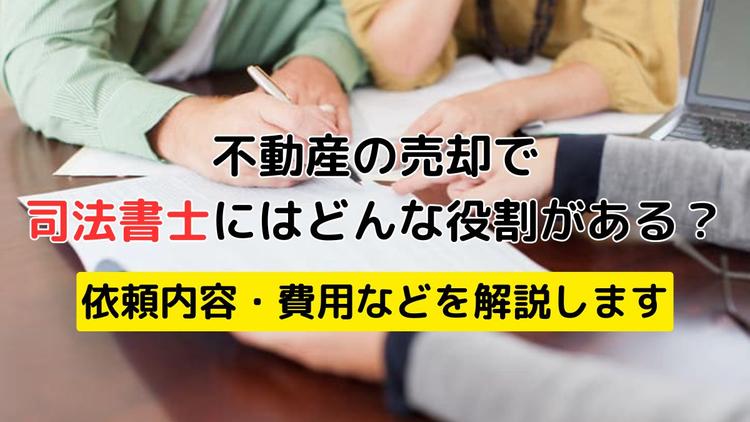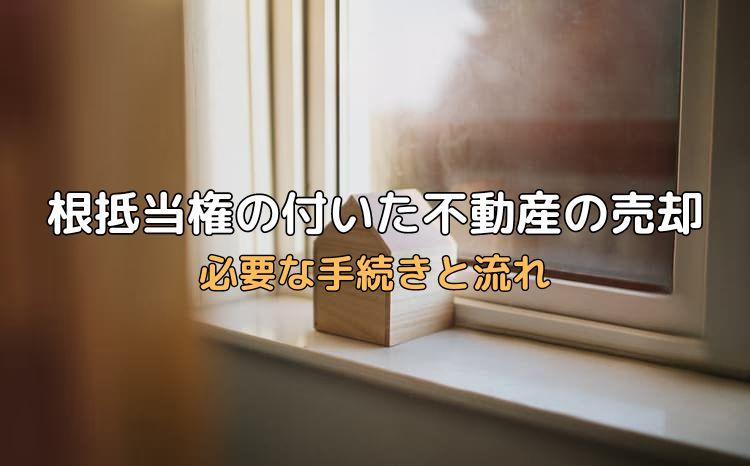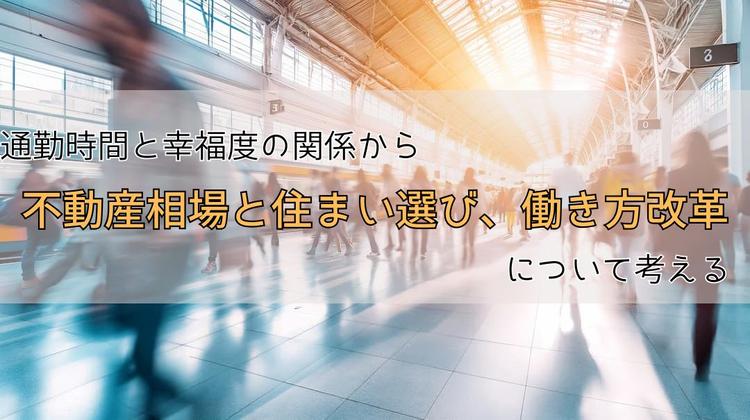事業の見直しで工場の売却を検討することがあります。しかし、工場をスムーズに売却するには、持ち家やマンションにはない、特有のノウハウが必要です。
たとえば、建物を残すのか更地にするのかといった選択だけでも、大きく判断が分かれるところです。この記事では、工場を売却するための手続きの流れや注意点について解説します。
工場売却手続の流れ
工場売却は、次のような流れで進めていきます。
- 事前調査~査定依頼
- 不動産業者との媒介契約
- 売却活動~条件交渉
- 売買契約締結
- 決済~引渡
それぞれどのように進めていくのか解説をしましょう。
1:事前調査~査定依頼
工場を売却する方針が決まれば、複数の不動産会社に査定依頼をします。査定では、各社ごとに異なった数値が出てきますが、4~5社から査定してもらうことで、相場の価額を掴むことができます。
工場の不動産としての価値が分かれば、売却方法や売却条件などを検討します。
2:不動産業者との媒介契約
売却に際しては、不動産会社と媒介契約を結び、売却の仲介を依頼します。ただし不動産会社の選定では、査定額は参考になりません。高い査定をした不動産会社に仲介を依頼したからといって、その価格で売却できる保証はどこにもないからです。
工場の売却は、住宅やマンションの売却とは異なった売却のノウハウがあります。工場などの事業用不動産の取扱実績を豊富に有する不動産会社だと安心です。
媒介契約には、一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介契約の3種類がありますから、実情に合った契約方法を選択します。それぞれの特徴を紹介しましょう。
一般媒介契約
複数の不動産会社と媒介契約を結べ、自社で買手を探すこともできます。ただし、不動産会社としては自社で売却できる確約がないので、熱心な売却活動は期待できません。
専任媒介契約
他の不動産会社とは媒介契約を結べませんが、自社で買手を探すことはできます。業務の処理状況は2週間に1回の報告義務があります。買手がみつかれば、確実に不動産会社の利益になるため、熱心な売却活動が期待できます。
専属専任媒介契約
他の不動産会社とは媒介契約を結べません。また自社で買手を探すこともできせん。業務の処理状況は1週間に1回の報告義務があります。買手がみつかれば、確実に不動産会社の利益になるため、熱心な売却活動が期待できます。
3:売却活動~条件交渉
売却活動中は、物件に興味を持った人が内覧を希望することがあるので、来客を迎える体制や対応方針を検討しておきます。
購入希望者が具体的に購入の意向を示したら、不動産業者を介して価格等の売買条件を交渉します。話がまとまれば、売買契約締結の準備に入ります。
4:売買契約締結
不動産業者が重要事項説明書を作成して、売買取引の主要事項を売主と買主に説明をし、問題がなければ売買契約を締結します。
契約締結時には、買主から売却額の10%程度の手付金が支払われるのが一般的です。その後引渡時に残金を支払います。なお、物件の引き渡しまでの間に中間金を支払うことを申し合わせることもあります。
5:決済~引渡
手付金(中間金)を除いた取引額残金を受領し、登記識別情報通知書や鍵などを買主に渡します。同時に委任した司法書士が登記��手続きを行います。
併せて固定資産税・都市計画税の清算を行います。
不動産の固定資産税・都市計画税は、1月1日時点の所有者に対してその年1年分の税額が課されます。法的な納税義務者は、1年間固定されていますが、譲渡日を起点に日割り計算をして、買主が所有日数分相当の税額を分担するのが不動産取引の慣習となっています。
工場売却に必要な書類
工場売却に際しては、次の書類が必要になります。あらかじめ存在を確認して、内容を把握しておきましょう。
- 登記済権利証または登記識別情報通知書
- 登記事項証明書(登記簿謄本)
- 14条地図または公図
- 建築確認済書と検査済書
- 敷地の確定測量図
- 固定資産税納税通知書
それぞれどのような書類なのか説明します。
登記済権利証または登記識別情報通知書
所有権の移転登記のために登記済権利証が必要になります。
ただし、2005年からは、登記済権利証は登記識別情報へと移行し、オンライン上で管理されています。そのため、2005年以降は、従前の権利証に替わり登記識別情報通知書が発行されています。
登記事項証明書(登記簿謄本)
登記簿謄本は、法務局でデータ化されているため、現在は、紙の登記簿を謄写するのではなく、データの内容を証明した登記事項証明書が交付されます。不動産の所有者の氏名・住所や不動産の場所、大きさ、構造や地目などの情報が記載されています。
不動産の所有者名義や借地権等の権利の設定の有無を正しく把握するために、事前調査の段階で取得し、売却方針を定める基礎資料として��活用します。
14条地図または公図
土地がどのような位置に、どのような形状で存在しているのかを明らかにするために作成された地図が14条地図です。不動産登記法14条により作成されているため、通称として「14条地図」と呼ばれています。
しかし、地籍調査が進捗していない地域がまだ多く存在しています。そのため、法務局では、地図が備え付けられるまでの間、「地図に準ずる図面」として公図が備え付けられています。
公図とは土地の形状や地番、道路、水路などを図で表している図面のことです。登記事項証明書や公図は、法務局の窓口で取得することができますが、オンラインによる請求で郵送してもらうこともできます。
建築確認済書と検査済書
建築確認済証と検査済証は、不動産の売買が成立するか否かの大きな要因となります。工場が適法であることの証となるからです。明らかな違反物件だと、担保価値がないとして、買主が銀行からの融資を受けられないことがあります。
また購入希望者が、生産ラインや資材ストックの関係で、増築を念頭に置いて購入を検討することがあります。しかし、適法性が証明できない建物は、増築をすることができません。
この場合、単に書類が紛失しているのであれば、管轄の行政機関で証明書が取得できますので、それほど深刻な問題には発展しません。しかし、まったく建築確認済を取得していなかったり、完了検査を受検しないまま使用していたりしている建物の場合は、解決の糸口が見つからないこともあります。
敷地の確定測量図
確定測量図はすべての境界につ�いて、隣地所有者が同意している図面です。確定測量図があれば、境界に関する争いが生じることがありません。不動産の売買では買主が確定測量図を必須の条件としていることがあります。
固定資産税の納税通知書
不動産の所有者には、固定資産税の納税通知書が郵送されています。固定資産税の納付状況の確認や、固定資産税を買主と精算する際に用いられます。また不動産の移転登記の際に納める登録免許税の計算にも必要になります。
納税通知書は再発行できないので紛失しないよう注意が必要です。
工場売却の注意点
工場売却に際しては、持ち家やマンションにはない、工場特有の注意点がいくつかあります。内容を解説していきましょう。
解体が必要なことがある
買主が、工場の設備をそのまま使用するのであれば、解体をする必要はありません、しかし、そのまま利用できる買主は、かなり限定的です。また、規模の大きい工場の場合、更地にすると、分譲宅地やスーパーマーケット、病院といったように利用用途が拡大します。
工場のままだと購入希望者が現れないと判断される場合には、売却先を広げるために、工場の解体を実施した方が、売却に有利なことがあります。
売却に際しては、建物を残すのか解体するのかについて、総合的な検討が必要になります。
土壌の浄化義務がある
工場の製造過程で有害物質を使用していた場合は、土壌が汚染されている可能性があることから、有害物質を取扱う事業者は土壌調査が義務付けられています。調査の結果、土壌汚染が認められた場合には、土の入れ替えや中和などの対策を実施しなければなりません。
もし土地の浄化を十分に行わず、売却後に汚染が発覚した場合、売主は契約不適合責任が問われ、損害賠償を求められることもあります。
▼関連記事

境界確定をしないと売却できない
敷地境界が確定していない場合、適正な価格での売却は望めません。敷地境界が不安定な土地を相場どおりに購入する人は、ほとんどいないからです。売却できたとしても、相当の価格ダウンを覚悟しなければなりません。
売却に際しては、確定測量図の作成は必須です。
既存不適格台帳に登�載する
古くから操業している工場では、後で住宅系の用途地域に指定されて、用途不適格になっていることがあります。
用途不適格ではあるが、工場として買い取ってもらうのが最善だと考えられるのであれば、都道府県庁(一部市役所)の建築法規担当部署で既存不適格台帳に登載する方法が有効です。
これにより、買主も従前と同様に作業場や原動機を適法に使うことができます。何より、既存不適格台帳に登載することで、買主側からも根拠が確認できるので安心して購入することができます。
ただし、売却までの期間中に、一時的にでも店舗、倉庫、車庫などの他の用途に使用すると、その時点で既存不適格が適法になったと判断され、以降工場としての使用が不可能となるので注意が必要です。
違反状態があれば解消しておく
建築確認済証を取得しないまま増築している箇所があれば、事前に解体をしていた方が、売却がスムーズに進みます。
違反状態のままで売却をすれば、買主に責任が及ぶだけでなく、将来の適正な増築の可能性を消滅させるリスクがあります。また買主に対して、銀行からの融資が認められないことがあります。
工場を売却する方法
工場の売却は、戸建て住宅やマンションとは異なり、物件特有の売却方法が求められます。ここでは、工場の売却方法について解説をします。
仲介による売却
最も一般的な売却方法が、不動産会社に仲介依頼をする売却です。
工場の場合、業種によって使い勝手が大きく異なるので、売主の力だけで買主を探すのは困難です。しかし、仲介で売却活�動を進めた場合、広い範囲から購入希望者を探すことができるので、売却できる可能性が高くなります。
買取専門会社に売却
不動産の取引では、買取専門の不動産会社に売却するという方法があります。ただし、買取専門の不動産会社は、住宅を専門に扱っているところが多いため、工場を買い取ってくれる会社はかなり限定的になります。
また買取専門の会社は、その後の売却によって利益を上げる経営形態のため、相場よりも安い価格での売却は避けられません。
【成約実績 No.0415】
愛知県 蒲郡市
工場のような買い手が限定される物件だと、
買取業者の取扱いもかなり減ってしまいます。しかし、イエウリにはこのような物件を
買取る会社様がいらっしゃいます。どこに頼むべきか迷ったらイエウリへ#企業公式相互フォロー#イエウリ#工場売却pic.twitter.com/xYRRmYmGev
— イエウリ【公式】 (@ieuri_ieuri) October 6, 2024
「イエウリ」に登録している不動産会社は、工場の買取に対応しているところもあるため、売却を検討している方はお気軽にご相談ください。
信頼できる不動産会社をご紹介
イエウリ の不動産査定はこちら
買取保証による売却
買取保証とは、ある一定の期間までは、一般の仲介取引と同様に市場に出しますが、買主が見つからなかった場合、事前に決めておいた買取価格で不動産会社が物件を買い取るという仕組みになっています。
売却期限は、3ヶ月から6ヶ月としているのが一般的です。期限まで見つからなければ、保証が適用されて不動産会社が買い取りますが、相場よりも相当安い価格が設定されています。
リースバック前提の売却
リースバックとは、不動産を一度、資産家や不動産会社などに買い取ってもらい、その買主と賃貸借契約を結んで引き続き不動産を利用する方法です。
リースバックを行った場合、毎月建物の賃料を支払うことになりますが、固定資産税などを納める義務はありません。
賃料の負担が課題となりますが、現状維持のまま事業継続が行える点はコスト削減の点からメリットがあります。
不動産M&Aによる売却
会社の合併や事業の取得を目的として行う企業活動をM&Aといいますが、「不動産M&A」は、不動産の獲得を目的に行われます。
通常の不動産取引で行われる売却ではなく、不動産M&Aでは株式の売買によって、不動産の移動が譲渡会社と譲受会社の間で実施されます。
たとえばひとつの方法として、譲渡会社が会社分割により不動産のみを所有する会社を設立して、その会社の株式を譲渡するという形で行われます。
通常の不動産取引で工場を売却すると、売却益に対して約40%の法人税などや、法人税を控除した残額に最大50%の所得税などが課されます。しかし、不動産M&Aにおいては、株式が譲渡対象になるので、株式の譲渡益に対する20.315%の所得税となります。
また工場を譲り受ける会社の方も、通常の不動産の取得の際にかかる不動産取得税や登録免許税、印紙税などがかかりません。
まとめ
工場売却は、次のような流れで進めていきます。
- 事前調査~査定依頼
- 不動産業者との媒介契約
- 売却活動~条件交渉
- 売買契約締結
- 決済~引渡
契約締結時には、買主から売却額の10%程度の手付金が支払われるのが一般的です。その後引渡時に残金を支払います。
工場の売却に際しては、建物を残したまま売却するのか、更地にして売却するのかの検討が必要です。もし工場としての売却が期待できないようであれば、建物を解体して更地で売却した方が有利なこともあります。
工場の製造過程で有害物質を使用していた場合は、有害物質を取扱う事業者は土壌調査が義務付けられています。しっかりと調査��の上対策を講じなければなりません。
工場が適法に建てられていることも、売却するうえで大きな要素です。適法性が証明できなければ、買主の方でも銀行からの融資が受けられないことがあります。