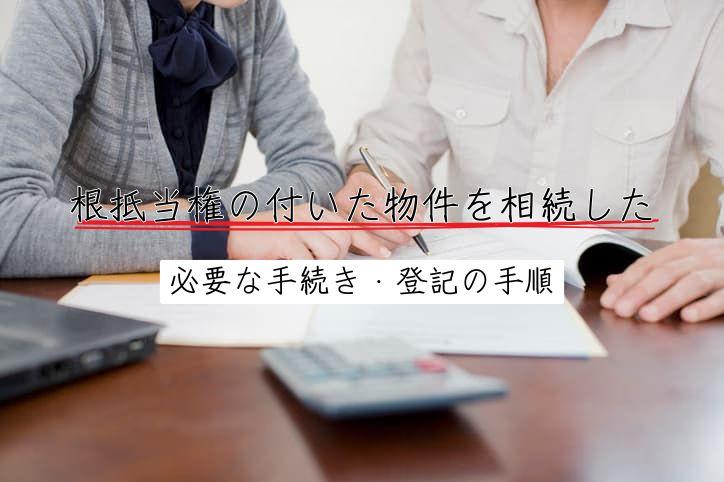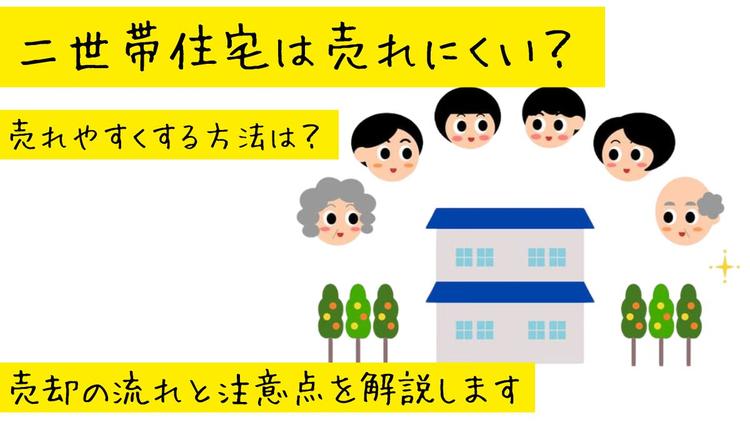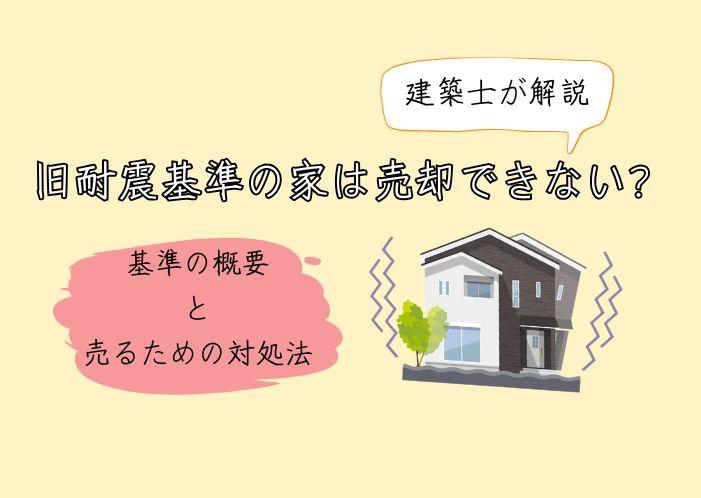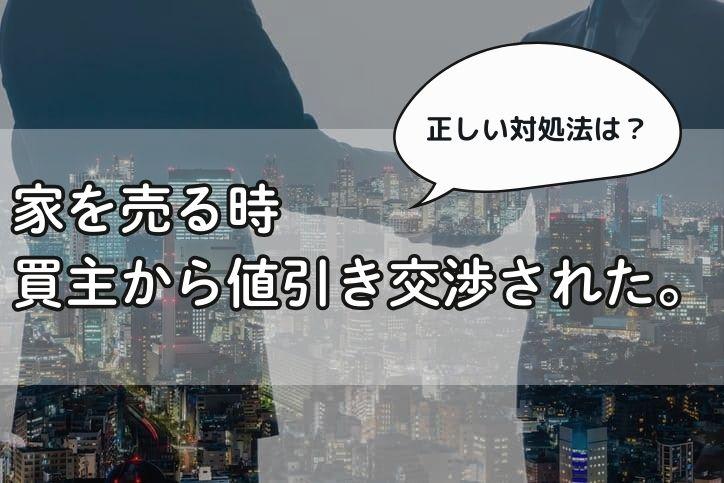根抵当権は主に事業者が利用する権利ですが、個人の方でも相続した不動産に根抵当権がかけられている可能性があります。事業を営んでいないと馴染みがないため、どのように対処すればよいか分かりません。
そこで今回は、根抵当権の付いた物件をどのように相続すべきか、根抵当権の抹消方法や登記手順、必要書類などについて解説していきます。
根抵当権とは?
Question paper.
抵当権は、住宅の購入経験や融資を受けた経験があれば馴染みのある権利でしょう。
では「根抵当権」とはそもそもどのような権利でしょうか。
まずは根抵当権の特徴や抵当権との違いについて確認していきましょう。
根抵当権の特徴
根抵当権は「抵当権」とよく似ている言葉ですが、大きな違いが2つあります。
極度額の範囲内で何度でも借り入れ可能
根抵当権の設定契約時に「極度額」が設定されます。
これは、根抵当権を設定した不動産を担保とした融資の担保上限額であり、この金額に達するまでは何度でも借り入れや返済が可能です。
根抵当権は主に企業が利用する権利で、運転資金が必要な際に企業名義の建物を担保し、スムーズに融資を受けるために利用します。
登記費用や手続きが省ける
個人では、住宅等の金額の大きな買い物をする場合を除き、融資を受ける機会はそれほど多くありません。しかし、企業は運転資金を調達するために何度も融資を受けます。
抵当権は、債務の返済を完了すると消滅するため、新たに融資を受ける場合には改めて抵当権を設定しなければなりません。
この抵当権の設定には、「抵当権設定登記」が必要なため、登記の手間と費用が発生します。
企業の運転資金を調達する際、抵当権ではなく根抵当権を使って融資を受けるのが一般的かつ効率的です。
抵当権との違い
| 根抵当権 | 抵当権 | |
| 借入額 | 極度額(上限金額)に応じて、その範囲内なら繰り返し借り入れが可能 | 決まっている |
| 債権 | 特定されていない ⇒返済額や返済日が決まっていない | 特定されている ⇒返済額や返済日が決まっている |
| 移転 | お金を借りた人の承諾が必要 ⇒借入額や返済日が決まっていない | お金を借りた人の承諾は不要 ⇒借入額や�返済日が決まっている |
| 連帯債務者 | 一般的に認められない ⇒貸与額や返済日が決まっていない | 認められる ⇒貸与額や返済日が決まっている |
抵当権は一般の方でも住宅ローンを契約する場面などで幅広く利用されています。
一方、根抵当権は主に企業などの事業者が利用するケースが大半です。
また、債権者が債権を別の人に譲渡した場合、抵当権は自動的に新たな債権者に移る「随伴性」があります。
しかし、元本確定前の根抵当権は、債権者が別の債権者に移ったとしても、根抵当権がただちに行使される事はありません。
元本確定については次の章で解説していきましょう。
その他、抵当権と根抵当権の違いに「付従性の否定」があります。
抵当権は返済が完了すると自動的に消滅しますが、根抵当権は返済が完了してもその権利は消滅しません。
これは根抵当権が、企業のような定期的に融資を受けたいと考える債務者に対し、何度も登記を行う手間を軽減する制度だからです。
元本確定とは
元本確定とは、根抵当権をやめるときの手続きのことです。
極度額の範囲内で可能であった借り入れと返済を終了し、終了した時点での借入金を確定します。
元本確定をすると、抵当権と同じ扱いとなり、以降は新たな借り入れができません�。
元本確定を行う場合には、以下のいずれかの事由に該当している必要があります。
- 元本確定期日が設定されていた
- 元本確定期日が設定されておらず、抵当権設定の時から3年を経過し、根抵当権設定者(借入人など)が元本確定請求した
- 元本確定期日が設定されておらず、根抵当権者(銀行など)が元本確定請求した
- 合併または会社分割により根抵当権設定者が確定請求した
- 根抵当権者や債務者の相続開始後6カ月以内に相続人を定める合意の登記をしなかった
- 根抵当権者が競売若しくは担保不動産収益執行、または差し押さえを申し立てたとき
- 根抵当権者が抵当不動産に対して滞納処分による差し押さえをしたとき
- 根抵当権者が抵当不動産に対する競売手続の開始又は滞納処分による差押えがあったことを知った時から二週間を経過したとき
- 債務者または根抵当権設定者の破産手続開始決定があったとき
根抵当権の相続を行う場合にはとくに「債権者や債務者の死亡後6カ月以内に合意の登記をしなかった」という事由によって根抵当権の効力が消滅してしまうため注意してください。
信頼できる不動産会社をご紹介
イエウリ の不動産査定はこちら
根抵当権の相続を急ぐ必要がある理由
根抵当権が設定された不動産を相続した場合、相続を急ぐ必要があります。
相続開始から6ヶ月をすぎると元本が確定する
根抵当権の元本確定事由には「相続の開始後6カ月以内に登記をしないときは、担保すべき元本は、相続開始の時に確定したものとみなす」があります。
したがって、相続開始から6カ月以内に新たな指定債務者の登記をしないと元本確定され、根抵当権としての効果が失われてしまうのです。
引き続き根抵当権を利用したい場合には、相続開始から6カ月以内に債務者変更登記の必要があるため相続を急ぐ必要があります。
相続放棄をする場合、相続開始から3ヶ月以内にする必要がある
相続放棄をする場合はさらに急ぐ必要があります。
相続では債権だけでなく債務を相続する可能性もあります。
相続する財産が債権より債務の方が多ければ相続放棄を検討する必要が出てくるでしょう。
相続放棄を行う場合、相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に相続放棄の申述をすることが定められているため、相続するよりも迅速な対応が求められます。
事業継続のために根抵当権をそのまま相続したい
根抵当権は主に企業向けの権利と説明しましたが、事業継続のために根抵当権が設定されたままの不動産を相続したいと考えることもあるでしょう。
そこで、根抵当権をそのまま設定した状態で不動産を相続する場合の流れについて解説していきます。
所有者と債務者が同じケース
根抵当権を設定した不動産の所有者と債務者が同じ被相続人であった場合、不動産・債務相続は比較的スムーズです。
この場合は、不動産の相続人を所有者名義とする相続登記と、債務者の名義を変更する「指定債務者登記」を行うことで根抵当権の相続が完了します。
所有者と債務者が異なるケース
根抵当権の設定された不動産は、不動産所有者と債務者が異なる場合があります。
この場合、不動産の所有者を変更しませんが、債務者の相続人が引き続き根抵当権設定者の地位を相続して利用する場合には、「指定債務者登記」が必要です。
この場合、指定債務者の決定は債務の相続人と根抵当権者で行いますが、指定債務者の変更登記は不動産の所有者と根抵当権者で行います。
根抵当権の相続の流れ
根抵当関係の相続を行う場合のプロセスは以下の通りです。
1:債権者である銀行などの金融機関に連絡を取る
根抵当権関係相続登記には、債権者が発行した書類が必要です。
金融機関に相続を開始した旨を伝え、必要書類の準備を依頼しましょう。
2:遺産分割協議により根抵当権の設定された不動産の相続人を決定
相続人が複数いる場合、遺産分割協議によって根抵当権の設定された不動産を誰が相続するかを決定します。
会社などで事業を営んでいる場合には、相続によって新たに代表者となる人が相続するのが一般的です。
また、不動産の所有者と債務者が異なる場合にも、この段階で一本化しておく方が後の手続きがスムーズになります。
3:根抵当権の設定された不動産を相続するための登記を行う
根抵当権の設定された不動産の相続には以下の3つの登記手続きが必要です。
- 所有権移転登記(所有権者が変わる場合)
- 根抵当権の債務者変更登記
- 指定債務者の合意の登記
手続きの方法については後ほど解説します。
4:債権の範囲の変更を行う
「3:根抵当関係を相続するための登記を行う」で指定債務者を決定し、登記を行います。
指定債務者を決定したとしても相続以前の債務は指定債務者だけが負うことになるとは限りません。
2の遺産分割協議によって決まった相続人全員に分割して債務が相続されます。
相続開始後に発生した債務は指定債務者が負いますが、指定債務者の登記をしたからといって、他の相続人が負うこととなった債務を指定債務者が負うのではありません。
このとき、指定債務者以外の相続人が免責的に債務を引き受けて、根抵当権の被担保債権の範囲に含める際には「特定の債権」として追加する債権の範囲の変更登記も行います。
信頼できる不動産会社をご紹介
イエウリ の不動産査定はこちら
根抵当権を抹消したい
根抵当権を相続せず、抹消したいと考える場合、どのような手続きが必要でしょうか。
ここでは、抵当権を抹消する場合の流れを解説していきましょう。
債務が残っている場合
根抵当権を利用した借金(債務)が残っている場合、一般的には不動産を売却することで返済を完了し、根抵当権を抹消する手続きに進みます。
不動産の売却価格が債務を上回っている場合は不動産を売却。
その売却益で債務を完済して抵当権の抹消登記を行うか、元本確定によって抵当権として相続するかのいずれかを選択します。
しかし、不動産を売却しても債務が残る場合には、相続放棄を検討するのも1つの方法です。
相続放棄をする場合には、相続開始から3ヶ月以内に手続きを行う必要があるため、不動産売却価格の査定等の手続きを早めに進めていきましょう。
債務が残っていない場合
根抵当権により担保される債務が残っていない場合は、根抵当権を設定している金融機関等と交渉し、合意を得られれば抹消登記が可能です。
不動産ではなく現金での相続を考えることもあるでしょう。この場合は根抵当権の抹消登記を行い、不動産を売却して相続します。
不動産として相続する場合も、事業を営んでいない限りは根抵当権を設定しておくメリットは少なく、将来的に発生する手間を考えると、相続時に根抵当権の抹消登記を行う事がお勧めです。
根抵当権抹消登記で気をつけること
根抵当権の抹消には根抵当権者である金融機関等の同意が必要です。
金融機関等は、一般的な抵当権よりも取引額が大きくなる根抵当権を抹消することに反対する場合がありますので、相続を理由に抹消登記の合意を得ることが重要です。
根抵当権者の合意がなければ根抵当権抹消登記に必要な書類を作成してもらえないため、確実に合意を得て書類を入手しましょう。
信頼できる不動産会社をご紹介
イエウリ の不動産査定はこちら
根抵当関係の登記に必要な書類は?
根抵当権を相続する場合「所有権移転登記」「根抵当権の債務者変更登記」「指定債務者の合意の登記」の3つの登記手続きが必要です。
また、根抵当権を抹消する場合には「根抵当権抹消登記」を行います。
それぞれの登記に必要な書類を紹介していきましょう。
所有権移転登記の必要書類
相続による所有権移転登記には、以下の書類が必要です。
- 登記申請書
- 被相続人の除票(または戸籍の附票)
- 相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)
- 相続人の住民票
- 資産評価証明書
- 相続関係説明図
また、司法書士など代理人に依頼する場合には委任状も必要です。
根抵当権の債務者変更登記
相続にともなう根抵当権の債務者変更登記を行う場合には、債務者と根抵当権者である金融機関等のそれぞれが書類を集める必要があります。
債務者の必要書類
- 権利証(又は登記識別情報)
- 印鑑証明書
- 資格証明書又は会社謄本(所有者が会社の場合)
- 委任状(司法書士などに依頼する場合)
根抵当権者の必要書類(金融機関等)
- 変更契約書(又は登記原因証明情報)
- 委任状
- 資格証明書又は会社謄本
根抵当権者の委任状は債務者が手続きを行う場合も、司法書士に依頼する場合も必要です。
債権の範囲の変更登記
債権の範囲の変更登記を行う場合には、以下の書類が必要です
- 登記申請書
- 登記原因証明情報
- 登記識別情報
- 印鑑証明書
- 委任状(司法書士などに依頼する場合)
指定債務者の合意の登記
相続によ�って指定債務者の合意の登記を行う場合には、以下の書類が必要です
- 登記申請書
- 登記原因証明情報
- 委任状(司法書士などに依頼する場合)
根抵当権抹消登記
相続による根抵当権抹消登記では、以下の書類が必要です。
なお、根抵当権を抹消する場合は事前に根抵当権者である金融機関等の合意を得て書類を入手する必要があります。
債務者の必要書類
- 登記申請書
- 資格証明書又は会社謄本(所有者が会社の場合)
- 委任状(司法書士などに依頼する場合)
根抵当権者(金融機関等)の必要書類
- 登記原因証明情報(弁済証書など)
- 根抵当権設定契約証書(登記済証)
- 資格証明書または登記事項証明書(会社法人番号や代表者の記載が必要)
- 委任状
根抵当権の抹消登記手続きを債務者本人が行う場合は本人の委任状は必要ありません。
しかし、根抵当権者の委任状は本人が手続きを行う場合でも、司法書士などの専門家に依頼する場合でも必要です。
信頼できる不動産会社をご紹介
イエウリ の不動産査定はこちら
根抵当権の登記に必要な費用は?
根抵当権の登記を行う場合、司法書士に依頼するのが一般的です。
司法書士は登記に関する専門家なので、相続に関する複雑な根抵当権の抹消登記や債務者変更登記、所有者移転等をスムーズに進められます。
根抵当権の登記に関する費用は司法書士事務所によって様々ですが、一般的な相場としては以下の通りです。
- 所有権移転登記…3〜5万円
- 根抵当権変更登記…1〜3万円
- 指定債務者の変更登記…1〜3万円
- 根抵当権抹消登記…1〜3万円
専門的な知識を覚え、書類を集めて手続きを行うことを考えると、司法書士に依頼するメリットが大きいといえるでしょう。