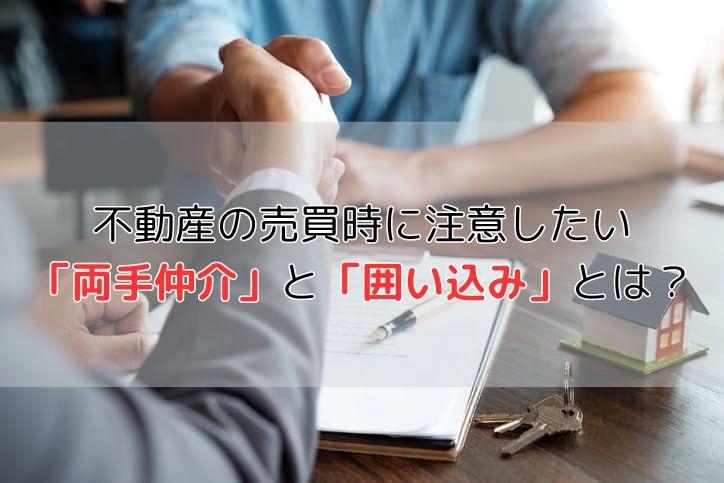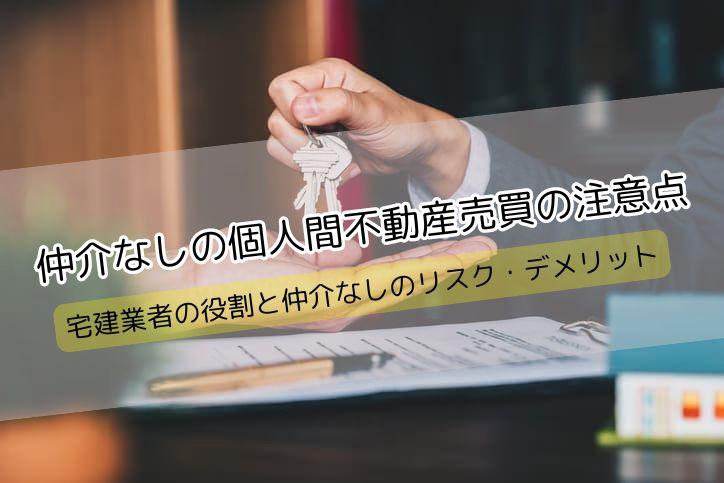不動産の売却時に、不動産会社とのトラブルが発生するケースがあることをご存じでしょうか?
特に、仲介手数料が収益の中心となる不動産仲介会社において、手数料を得ることを優先した営業活動が原因で、売主に不利益を与える事例が報告されています。
その中でも注意したいのが「両手仲介を狙った囲い込み」です。
この仕組みによって売主が不利な状況に置かれることがあるため、事前に正しい知識を持つことが重要です。
本記事では、まず「不動産売買の仲介手数料の仕組み」を解説し、その後、売主がトラブルを未然に防ぐための具体的な対策について紹介します。
不動産取引を成功させるためのポイントをしっかり押さえ、安心して売却を進めていきましょう。
まずは不動産売買の仲介手数料の仕組みを理解しよう
売買仲介手数料の金額
不動産の売買取引には、売主、代理、仲介(または媒介)があります。
そのうち仲介によって契約する際に、仲介手数料が発生することになります。
不動産の仲介手数料は宅建業法で決められており、「ここまでもらっても良い」という上限額が定められています。
売買価格が800万円を超える場合
この金額が売主、買主双方にかかります。
売買価格が800万円以下の場合
※社会問題化している空き家問題などで、低廉な不動産物件の売却に際し、修繕・清掃など実務上かかる費用を想定して、売主・買主に事前告知した上で30万円(税別)を上限額とできるように変更されました(2024年7月より)1。
800万円以下の物件取引で、売買主の承認が無い場合は以下の計算式で求められる金額が上限となりますが、実際のところは媒介契約時の締結時に説明を行った上で30万円+税の請求とする方針の不動産会社が多いです。
| 売買価格 | 計算 |
| 200万円以下 | 売買価格×5%+消費税 |
| 200~400万円 | 売買価格×4%+2万円+消費税 |
| 400万円以上 | 売買価格×3%+6万円+消費税 |
仲介手数料の上限額は、上記計算ツールに任意の金額(単位は万円)を入力して確認可能です。
不動産売買における仲介のしくみ
不動産取引が成立した場合は、仲介業者に売主も買主もそれぞれ最大3%+6万円を支払うことになります。
売主側の仲介業者と買主側の仲介業者がそれぞれ仲介手数料をもらう取引を、業界では「片手仲介」「片手取引」「共同仲介」「別れ」などと呼び、ごく一般的に行われています。
売主側の仲介会社は売主から販売を依頼されると、自ら買主をみつけることもあれば、不動産業者間のネットワーク(代表的なものがREINS)に公開し、他の不動産会社の力を借りながら買主を見つけることになります。
より早く、高く売りたいというのが売主の一番のニーズだからです。
一方、不動産仲介会社が一社で売主も買主も見つけた場合は、双方より仲介手数料をもらうことになり、これを「両手仲介」「両手取引」などと呼びます。
片手仲介(片手取引)
仲介会社Aと仲介会社Bがそれぞれ片手仲介となり、取引は共同仲介となる2。
A社、B社がそれぞれ受け取る手数料の上限は3%+6万円+消費税。
両手仲介(両手取引)
仲介会社Aが売主・買主の双方から手数料をもらい、両手仲介となる。
両手仲介となった場合、仲介会社が受け取る報酬の上限は6%+12万円+消費税。
信頼できる不動産会社をご紹介
イエウリ の不動産査定はこちら
両手仲介が悪いわけではない
問題の少ない両手仲介とは
不動産仲介会社が営業努力で売主から物件の販売依頼を受け、さらに努力をして直接買主を見つけて取引に結び付けると、両手仲介となり仲介手数料は最大、3%+6万円(税別)を双方から収受することとなるので、仲介会社としては大きな収益になります。
このことは営業活動や、重要事項説明のための物件調査、お客様へのご案内業務がありますし、売主側、買主側へ行う業務はそれぞれ別のものです。
両手取引で収益が上がること自体は問題ではありません。
買いと売りの仲介の仕事は別
買い側仲介の仕事
- 購入希望者の要望ヒアリング
- 物件情報収集
- 現地案内
- 契約手続き
- ローン手続き
- 司法書士の手配 など
売り側仲介の仕事
- 査定価格の提案
- 販売までの物件情報調査
- 媒介契約
- 広告宣伝活動(現地案内、広告媒体への掲載など)
- 売買契約書、重要事項説明書の作成 など
買い側にも売り側にも、上記の仕事に入る前に、お客様にお会いするまでの広告宣伝活動も必要です。
これらすべての費用の対価が、不動産業界では仲介手数料という「成功報酬」型の収益体系なので、契約まで至らなかった場合は無収入となります。
このように、買い側の仕事と売り側の仕事は、業務の内容は基本的に別物なので、ひとつの取引に手数料をそれぞれ収受して両手仲介となったとしても、その分業務も増えているので妥当な費用です。
また、取引金額が小さい場合は、両手仲介で契約しないと収益となる仲介手数料が小さくなってしまい、取引自体を受けつけてもらえないケースも耳にします。
両手仲介の場合は、売主の要望も買主の要望も一人(または一社)で聞くこととなるので、どちらかに偏りが出てきてしまう場合が考えられます。
不動産会社は契約をまとめるのも仕事なので、要望を十分伝えることも必要です。
信頼できる不動産会社をご紹介
イエウリ の不動産査定はこちら
悪いのは両手仲介のための囲い込み
それでは両手仲介がなぜ問題視されるのでしょうか。
それは、両手仲介を目的とした囲い込みが行われるケースです。
囲い込みとは?
「申し込み(買い付け」が入ってしまっている」「清掃してから内覧を受け付けたい」「売主から鍵を受け取っていない」「図面を作成中」など、囲い込みの口実にされる理由はさまざまですが、売主の意思に反して他社からの買主を受け付けない行為は悪質です。
不動産仲介会社は、売主から販売の委託を受けて、自ら買主を見つければ両手仲介となり仲介手数料の3%+6万円を双方から収受することができます。
両手仲介は業務量が増えるのでそれ自体は問題ではありません。
「大手は両手取引の比率が高いから囲い込みがまん延している」と指摘されることもありますが、自社で抱える顧客が多い場合に両手仲介となるケースもあり、両手仲介自体が違法で悪質というわけではありません。
しかしながら、売主から販売委託を受けたあと、両手仲介とするために情報を広く公開せず、自社のお客様だけに紹介することがあり、これが囲い込みです。
物件の売却依頼を受けた不動産業者は公的なデータベース「レインズ」に物件情報を載せ、取引状況を公表しなければならない。取引状況は「公開中」「書面による購入申し込みあり」など3段階で表示でき、囲い込む場合は「申し込みあり」と偽るケースが多いという。
「申し込みあり」とした場合、物件の購入希望をもつ顧客をかかえる不動産業者を遠ざけることができる。売却依頼を受けた業者は自ら買い手を探して成約させることで、売買の両者から手数料を得られる。手数料は法律に基づく告示で「売買価格の3%プラス6万円」が上限の目安となっている。
2025年の宅建業法改正により、囲い込みは行政処分(是正の指示)の対象になります。
囲い込みが問題になるケース
宅建業法では、売主が不動産業者に仲介を依頼する際に3種類の媒介契約の様式があります。
売主自ら買主を探す ×
売主自ら買主を探す 〇
売主自ら買主を探す 〇
| 契約できる会社数 | 自分で見つけた買主との取引 | レインズへの登録 | 販売状況の報告頻度 | 契約期間 | |
| 一般媒介契約 | 複数 | 可能 | 任意 | なし | なし |
| 専任媒介契約 | 1社 | 可能 | 必須 | 2週間に一度 | 3ヶ月 |
| 専属専任媒介契約 | 1社 | 不可 | 必須 | 1週間に一度 | 3ヶ月 |
うち、囲い込みでとくに問題になるケースは専属専任媒介契約と専任媒介契約のケースです。
宅建業法では、専属専任媒介と専任媒介では、他の仲介会社へ依頼をしない分、指定流通機構(REINS)への登録義務、定期的な報告義務など活動内容が定められています。
売却を専任で依頼するからには広く募集をかけてより早く、より高く売りたい方が多いと思いますし、そのための積極的な営業活動を宅建業法で定めています。
しかしながら、両手仲介をするために他の不動産業者に売り物件情報を公開しなかったり、公開していても他の業者から問い合わせがあったときに「買付申し込みがあったため売り止めです」などと伝えていたりする場合は、売却までに時間がかかり、その結果として成約価格が下がってしまうこともあります。
例)3,000万円で販売中の物件が囲い込みによって売れず、2,800万円に値下げして両手取引が決まった。
3,000万円のまま片手仲介→仲介会社が受け取る手数料報酬�→片手:105.6万円
2,800万円で両手仲介→売主・買主の両方から手数料を受け取れる→両手:99万円x2=198万円
このように、囲い込みを行って値下げしなければいけないようになると、売主の手取りは減少する。一方で、仲介会社が受け取る手数料は増加する。
これが「囲い込み」の弊害です。
(なお、中には売却情報をあまり公開したくない売主もいるでしょうし、一般媒介契約は他社にも依頼できるのでどこまで公開するかは売主と話し合いになります。)
- 囲い込みとは、両手仲介をするために他社に物件を紹介しないこと
- 囲い込みの弊害は、他社に情報が公開されず売主の不利益になること
囲い込みが行われると、購入希望者も希望物件にうまく巡り合えないという間接的な不利益や、取引情報がオープンにならないため、不動産市場価格が形成されにくくなるという市場全体に及ぶ弊害もあります。
囲い込みの実態
囲い込みは両手仲介のために実施しますので、他業者に紹介するように見せかけておきながら、実際にはそうしないことを言います。
売主にはほかの業者に紹介するように見せかけ、自社のお客に優先的に紹介するのです。
不動産業者の間の確認作業は、最終的には電話確認です。
REINSに掲載されていても問い合わせがあった時に「決まっている」「契約予定」と言われてしまうとそれ以上のことは確認ができません。
また、囲い��込みを行って意図的に長期間物件が売れない状態にすることは「干す・干し行為」と呼ばれ、「専任返し」を狙って買取再販業者を紹介されるようなケースも存在します3。
信頼できる不動産会社をご紹介
イエウリ の不動産査定はこちら
囲い込みの有無で成約日数の差をシミュレーション
囲い込みによって、成約までの期間がどれぐらい延びてしまうかのリスクを確認するために、以下のような条件でシミュレーションを行ってみます。
囲い込みシミュレーション条件
不動産会社はA, B, C, Dの4社存在します。
売主XはA社と専任媒介契約を締結しました。
売主Xの物件に興味を持つ見込み客は、不動産会社A, B, C, Dによってそれぞれ毎月1名を獲得することができ、そのうち金額に合意して家の成約が決まるのは10%です。
A社が囲い込みをする場合としない場合で、成約日数と商談(見込み客とのマッチング、買い付け交渉)の発生回数にどれぐらいの差が生まれるのかを検証していきます。
囲い込みをしない場合
囲い込みをしない場合、A社と専任媒介契約を結んでいても、他の不動産会社(B社、C社、D社)からの見込み客が申し込み可能です。
- 1ヶ月ごとに各社から見込み客1名が来る→月あたり合計4名の見込み客
- 成約確率10%→10人に1人が成約
ここから、月に4人の見込み客がいるため、1ヶ月ごとに4人×10%=0.4件の成約期待値になります。
成約に至るまでの期間は期待値で約2.93ヶ月と算出できます。
囲い込みされた場合
囲い込みが発生すると、A社のみが見込み客を連れて来て、他社(B, C, D)の見込み客はA社によって無視されます。
- 1ヶ月ごとにA社から見込み客1名が来る →月あたり1名の見込み客
- 成約確率10%→10人に1人が成約
この場合、1ヶ月に1人の見込み客が来るため、1ヶ月ごとに1人×10% = 0.1件の成約期待値になります。
成約までにかかる期間は約9.96ヶ月(期待値)です。
囲い込みの有無による成約日数のシミュレーション結果(期待値)
| 囲い込み | 成約までの日数 | 商談回数/月 | 合計商談回数 |
| なし | 2.93カ月 | 4回 | 12回 |
| あり | 9.96カ月 | 1回 | 10回 |
上記は個別の会社の客付け状況、物件の売れ行き等を無視した期待値シミュレーションですが、囲い込みのリスクの大きさはお分かりいただけるでしょう。
信頼できる不動産会社をご紹介
イエウリ の不動産査定はこちら
囲い込みをされないためのチェックポイント3つ
①REINS登録状況の確認
専属専任媒介と専任媒介では、不動産指定流通機構(REINS)への登録義務があります。
不動産業者はREINSに登録すると証明書をもらいます。
証明書には登録番号とその確認サイトのアドレスが記載されていて、登録番号を入力すると売主はREINSへの掲載内容を確認できる仕組みです。
これは、囲い込みをしていないか確認するために用意されているシステムです。
売主は、登録証明書に記載されているURL、ID、パスワードを利用して、自分の物件情報が正しく登録されているか確認することができます。
2025年1月からは「売主が登録情報にアクセスしやすくする」という目的で、登録証明書にQRコードも記載されるようになりました。
なお、一般媒介の場合には、不動産業者はREINSの登録義務はありませんが、登録する場合もありますので担当者に確認してみましょう。
②定期的な報告をもらう
営業活動が具体的にどのように行われているか報告を受け、確認をするようにしましょう。
③信頼できる担当者を探す
仲介において一番大切なのは、募集方法について具体的な話を聞ける、信頼できる担当者を探すことです。
仲介会社をどこにするか、最初は査定額や付帯サービス、会社への信頼性を含めて決めることになると思いますが、売却活動が開始された後は担当者との二人三脚の活動になります。
信頼できる不動産会社をご紹介
イエウリ の不動産査定はこちら
▼関連記事:囲い込みを通報する窓口は?

まとめ
両手仲介になると不動産業者の手数料が最大2倍になりますが、結果的に両手仲介になったのか、または両手仲介を目指して情報を囲い込んだかで売主の利益は大きく変わることになります。
売り手としては一般的にはなるべく早く、より高い売却価格で売る事が利益になりますので、信�頼できる不動産業者を見つけられるかが、不動産売却成功の大きなポイントになるでしょう。
国交省は取引の透明性を高めるため、宅建業法の解釈や運用に関する通達を6月末に改正し、囲い込みは処分対象だという見解を明確にした。レインズへの登録内容に虚偽があるとわかれば処分する方針だ。
こうした取り決めを25年1月に施行する。発覚した場合は宅建業法に基づく是正や再発防止の指示処分の対象となる。従来は発覚時の罰則が明確でなく、囲い込みを許すもとになっていた。
なお、2025年1月からはこうした囲い込み行為に対して是正の指示処分がなされるように、改正された宅建業法が施行されています。
信頼できる不動産会社をご紹介
イエウリ の不動産査定はこちら
▼関連記事