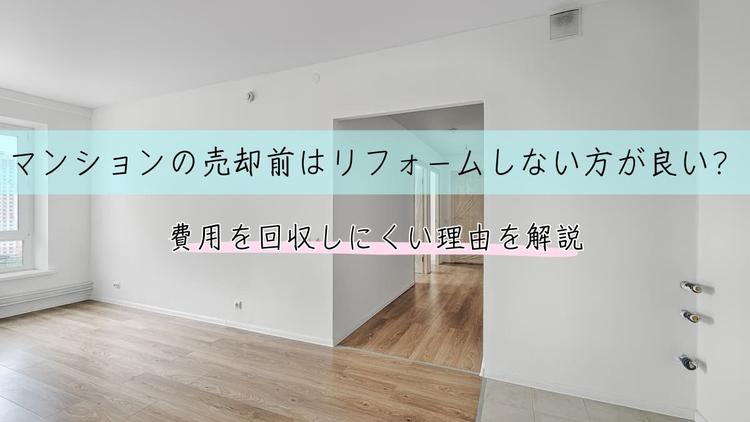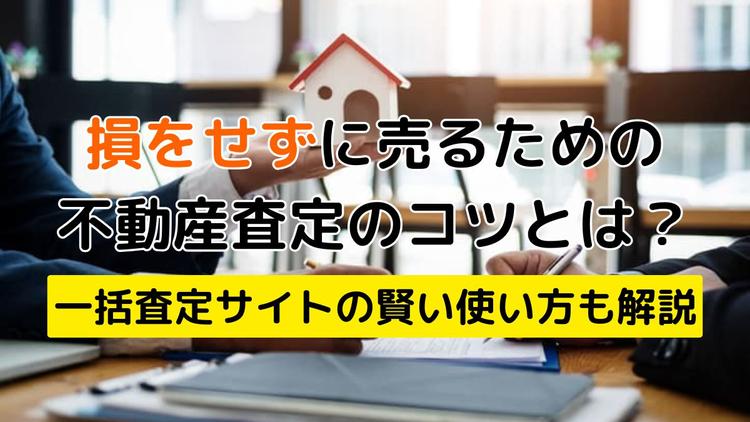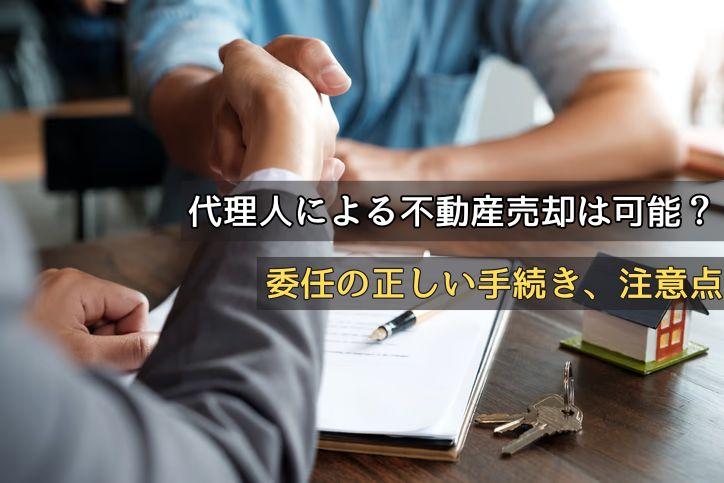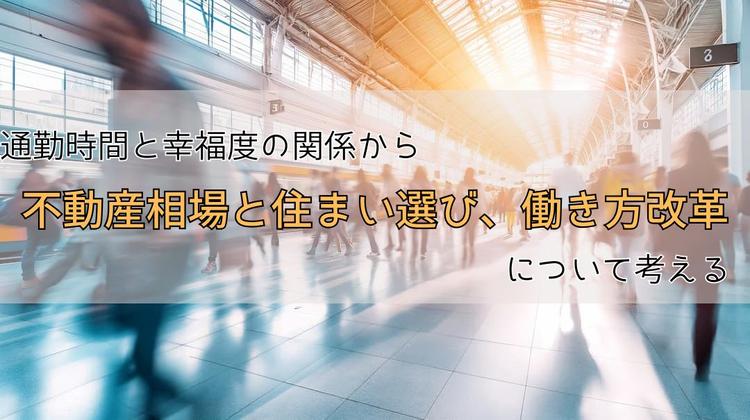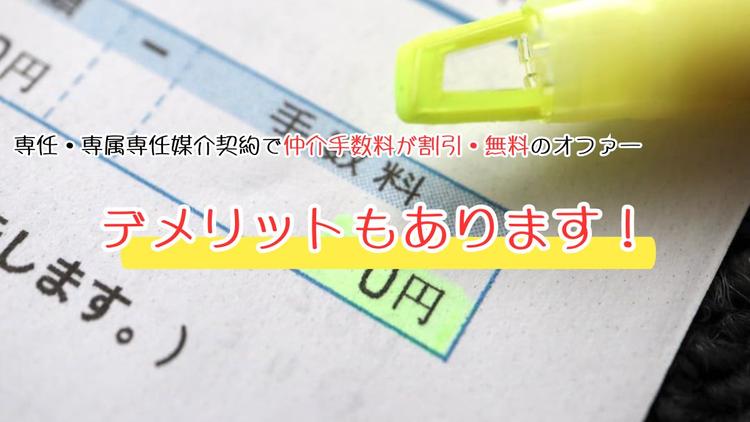家の売り出しがスタートすると内覧が行われ、建物内を確認した後に売買契約に進むのが一般的です。
売り出しをスタートしたのにも関わらず、内覧の申し込みが来ないと、売れないのではと不安に感じる売主もいるでしょう。
売却活動を開始したのにも関わらず、内覧の申し込みがないのには、何らかの理由がある可能性があります。
家の売却を成功させるには、そうした理由をしっかりと調査し、適切な対策を立てることが重要です。
この記事では、内覧が来ない理由や対策から内覧後に売れないケースの対処法まで詳しく解説します。
売却開始後1ヶ月内覧が来ないよくある原因
一般的に売却開始後1ヵ月目は注目度が高く、内覧も多く入る時期です。
この時期に内覧がスムーズにいかないと売却にも響きかねないので注意しましょう。
注目度の高い1ヶ月目にもかかわらず内覧が来ないのには、それなりに理由があるものです。
ここでは、内覧が来ないよくある原因として以下の3つを解説します。
- 価格が相場より高い
- 不動産会社が積極的でない
- インターネットに掲載している写真の質が悪い
価格が相場より高い
売り出し価格が相場よりもあまりに高い物件は、よほどの魅力がない限り買い手から避けられます。
とくに、周辺の競合物件よりも価格が高いと候補から外されやすくなるので注意しましょう。
また、多くの買主はインターネットでの物件を検索時に「価格」を条件に入れているものです。
相場よりも高い価格は検索時点で除外されてしまい、そもそも候補にすら上がっていない可能性もあるでしょう。
不動産会社が積極的でない
広告頻度や媒体が適切ではない・問い合わせに積極的に応えていないなど、不動産会社の対応が原因で内覧が来ないケースもあります。
価格が適切でも、買主も目に留まらなければ意味がありません。
専任媒介契約・専属専任媒介契約では、売却活動の報告義務があるので、どのような活動が行われているかチェックしてみましょう。
インターネットに掲載している写真の質が低い
買主の関心を引くうえではインターネットや広告にされている写真の印象も大切です。
買主の立場で考えれば、同じような条件の物件で写真の見た目がきれいな物件とそうでない物件なら、見た目がきれいな物件を選ぶのは当然といえるでしょう。
写真が暗かったり構図が悪かったりすると印象が悪くなります。
写真が悪くてもしっかり文面でアピールしているから大丈夫と考える方もいるでしょうが、広告のアピール文面は意外に買主はチェックしていません。
たとえば、インターネットなら間取りや価格・エリアで検索し、表示された物件の写真を真っ先に見る人も多いでしょう。
そのうえで、気になった物件の詳細まで進んでようやくアピールポイントなど細かい文章をチェックするものです。
このように、写真の見た目が悪いと候補から外されやすくなります。
掲載されている写真が魅力的に見えるか客観的にチェックしてみるとよいでしょう。
▼関連記事

家の売却は何カ月かかる?
そもそも1ヵ月目で内覧が来ないのは、心配になる方も多いでしょう。
ここでは、一般的な家の売却期間について詳しく解説します。
3ヵ月~半年程度が一般的
仲介の売却では、3ヵ月~半年ほど時間がかかるのが一般的です。
東日本流通機構の首都圏不�動産流通市場の動向 によると、物件登録から成約までの平均期間は中古マンションで85.3日、中古戸建で97.3日となっています1。
大まかな売却までのプロセスは以下のとおりです。
- 不動産査定
- 不動産会社と媒介契約
- 売却活動
- 売買契約
- 決済・引き渡し
このように売却までにいくつかのプロセスをふみ、その間に各種契約手続きやローン審査を行っていくため、ある程度時間が必要になります。
なかでも、時間がかかるのが売却活動期間となり、この期間によってトータルの期間は大きく変わってくるものです。
築年数が古い・価格が高いなど条件が悪いと買主がなかなか現れず、半年以上時間がかかるケースもあるので注意しましょう。
売却開始から1カ月内覧が来ない場合は見直しを検討しよう
売却開始から最初の1ヵ月目は、広告の露出度も多く買主からの注目度も高い時期です。
また、物件にもよりますが、売却までの内覧数は5~10件くらいが目安となり、例えば3ヵ月で売却し6件内覧するなら1ヵ月に2件の内覧が入る計算です。
1ヵ月目であればそれより多いことは期待できるので、少なくともゼロにはならないでしょう。
そのため、注目度の高い時期に内�覧が来ないなら早急な対策が必要です。
まずは、内覧が来ない原因を把握し適切に対処できるようにしましょう。
▼関連記事

売却開始から3ヵ月で不動産会社を変更することもできる
不動産会社との媒介契約のうち、専任媒介契約・専属専任媒介契約の契約期間は最長3ヵ月と定められています。
契約期間終了後は自動更新できず、更新手続きが必要です。
そのため、3ヵ月の契約終了のタイミングで更新せずに解約し、別の不動産会社を探すこともできます。
内覧が入らない理由としては、不動産会社の売却活動が適切でないケースだけでなく、囲い込みされている可能性もあります。
囲い込みとは、不動産会社が自社の買主で売却するために他社からの問い合わせを断ってしまう状況です。
この状況になると、他社の買い手が制限されるので売却が長期化する恐れがあります。
このような不動産会社が原因で内覧が入らない場合は、不動産会社の変更を視野に入れるとよいでしょう。
なお、契約期間中に契約解除すると違約金が発生する恐れがあります。
不動産会社に契約違反がないのであれば、契約更新のタイミングまで待つことをおすすめします。
▼関連記事

内覧がこないときの対策
内覧が来ないときは、来ない理由に合わせた対策が必要です。
ここでは、理由別に検討できる対策として以下の3つを紹介します。
- 価格を見直す
- 写真を撮り直す
- 不動産会社の活動状況を小まめに報告してもらう
それぞれ見ていきましょう。
価格を見直す
相場よりも高いなら、価格を下げることで内覧が入る可能性があります。
まずは、相場を調べ売り出し価格が適切かをチェックしましょう。
相場の調べ方としては以下の方法があります。
- 国土交通省の不動産情報ライブラリで過去の成約価格をチェックする
- レインズマーケットインフォメーションで過去の成約価格をチェックする
- 不動産ポータルなどで類似物件の売り出し価格をチェックする
類似物件の成約価格や売り出し価格を調べるとおおよその相場がつかめるでしょう。
ただし、成約価格や売出価格は、売主や買主の事情も反映されるので必ずしも自分の不動産と一致するわけではない点は覚えておくことが重要です。
そのうえで、どれくらい下げた方がいいかは不動産会社と相談しながら決めましょう。
▼関連記事

写真を撮り直す
広告に掲載する写真は、基本的に明るく清潔感があり広く見えることが重要です。
また、おしゃれな小物や家具の配置で空間を演出するのもよいでしょう。
写真を見た時に買主がこの家に住んでみたいと思われるように、意識して写真を撮ると印象アップにつながります。
自分で演出や撮影が難しいならプロの手を借りるのもおすすめです。
不動産会社によってはプロによる写真撮影やホームステージングのサービスを行っているケースもあるので、相談するとよいでしょう。
▼関連記事

不動産会社の活動状況を小まめに報告してもらう
専任媒介契約では2週間に1回以上、専属専任媒介契約で1週間に1回以上の売却活動の報告義務があります。
報告内容な不動産会社によって異なりますが、一般的には以下の項目が報告されます。
- 行った販売活動
- 問い合わせ件数と内容
- 内覧件数
- 問い合わせや内覧時の所感 など
報告をチェックすると販売活動の内容や問い合わせの有無などが分かるので、内覧が入らない理由や対策も立てやすくなるでしょう。
なお、一般媒介契約では活動報告の義務はありません。
また、専任媒介契約や専属専任媒介契約であっても報告しない不動産会社もいる点に注意が必要です。
反対に、義務に関わらず小まめに報告してくれる不動産会社は信頼できるといえます。
▼関連記事

内覧後に成約が決まらないときの対処法
内覧対策し、内覧が入ったからといって売却まで進むとは限りません。
せっかく内覧が入っても売却が成立しなければ意味がないため、対策が必要です。
内覧後に成約がなかなか決まらない大きな理由も、内覧対応に失敗していることにあります。
ここでは、内覧後に成約が決まらないときの対処法として以下の3つを解説します。
- 内覧前に徹底的に掃除する
- 部屋の中を明るくする
- 臭いにも気を配る
それぞれ見ていきましょう。
内覧前に徹底的に掃除する
内覧で買主にいい印象を与えるには、部屋をきれいに・広く・明るく見せることが欠かせません。
そのため、内覧前の徹底的な清掃・整理整頓が重要です。
部屋全体きれいにするのが望ましいですが、とくに以下のような部分は入念に清掃することをおすすめします。
- 玄関
- リビング
- 水回り
- ベランダ
- 押し入れ・クローゼット
なかでも内覧時に重点的にチェックされやすいのが水回りです。
トイレやお風呂・キッチンはピカピカにしておくことで印象ア�ップを狙いやすいでしょう。
売却すれば引っ越しになるので、内覧を機に不要な荷物を片付け室内をスッキリさせましょう。
自分での掃除だけではきれいにならないときは、ハウスクリーニングの検討をおすすめします。
費用はかかりますが、水回りだけなど部分的でも印象アップ効果を得やすく売却につながりやすくなるでしょう。
▼関連記事

部屋の中を明るくする
買主は採光や部屋の明るさを気にするので、明るい室内のほうが印象は良くなります。
内覧前に部屋の照明をつけておくだけでなく、窓やカーテンの掃除も行っておきましょう。
窓がピカピカになると印象がよくなるだけでなく、室内に光が入りやすく明るさの演出にもつながります。
カーテンが黒ずんでいると印象が悪くなりやすいので、洗濯するか撤去してしまうのもおすすめです。
また、窓際に光を遮るようなものは置かないようにすることも大切です。
臭いにも気を配る
盲点になりやすいのが室内の臭いです。
とくに、ペットを飼っている家庭や喫煙者がいる場合は、徹底的に消臭しておきましょう。
内覧前に換気するだけでなく、消臭スプレーや芳香剤の活用もおすすめです。
カーテンやソファーなど布製品も臭いが染みついている可能性あるので、気になる場合は事前に選択しておくとよいでしょう。
臭いはその家に住んでいる人は気づきにくい、反面、第三者は気になりやすいものです。
不動産会社の担当者に臭いをチェックしてもらうのもよいでしょう。
▼関連記事

売却が決まらないときは買取を検討するのもおすすめ
対策したからといって必ず売却できるとは限りません。
なかなか売却が決まらないと、売れ残り感が出て買主から避けられやすくなり悪循環に陥りかねないので注意しましょう。
売却が決まらないときは、仲介ではなく買取での売却を視野に入れるのも1つの方法です。
買取なら条件がまとまればすぐに売却できる
買取とは、不動産会社に直接家を買ってもらう売却方法です。
ここまで解説してきた売却方法は、不動産会社が売主と買主の間に入る仲介になります。
仲介の場合、広告活動などで買主を探す必要があるので売却までに時間がかかるだけでなく、そもそも買主が見つからなければいつまでも売却できません。
一方、買取であれば不動産会社との交渉に合意できればそのまま売却できるので、1ヵ月ほどの短期間での売却が可能です。
また、買取には以下のようなメリットもあります。
- 仲介手数料が不要
- 売却前にリフォームが必要ない
- 内覧対応不要
買取は仲介ではないので仲介手数料は発生しません。
仲介手数料は売却にかかる諸経費の中でも高額になるため、不要になるメリットは大きいものです。
買取後は不動産会社がリフォームするので、売主が事前にリフォームする必要もありません。
買取は仲介よりも価格が下がるというデメリットはありますが、仲介手数料やリフォーム費用が不要になることから、物件によってはトータルでそこまで大きな価格差が生じないケースもあります。
とくに、内覧が入らずずっと売れ残るリスクを抱えるよりも、買取で早期に売却した方がメリットが大きい場合もあります。
売却額が落ちてもすぐに売却したいケースでは買取が適しているでしょう。
イエウリなら仲介と買取両方検討できる
買取か仲介かで悩む際は、まずは両方の査定結果を比較して売却方法を検討するのもおすすめです。
この際、査定はできるだけ複数の不動産会社に依頼するようにしましょう。
不動産会社によって得意・不得意な不動産種類・エリアは異なり、査定方法も独自の基準ため査定額は大きく異なります。
とくに、買取は査定額がほぼ売却額になるので、少しでも高値を付ける不動産会社を見つけることが重要です。
ただし、仲介・買取にしても査定額だけでなく、実績や評判・担当者との相性など総合的に判断して信頼できるかで見極める必要があります。
イエウリなら、買取・仲介両方の査定に対応し、数多くの不動産会社を簡単に比較できるのでよりあなたに不動産にぴったりな信頼できる不動産会社と出会えるでしょう。
まとめ
売り出しをスタートし1ヵ月目に内覧が来ない状態を放置していると、売却の長期化につながりかねません。
内覧が来ないときは、原因を探し早めに対応することが重要です。
内覧が来ない主な原因には、価格の高さや写真の悪さ・不動産会社の問題が挙げられるので、原因をチェックし適切に対処し、早期の成約を目指しましょう。
対策してもなかなか売れない場合は、買取を視野に入れるのも1つの手です。
まずは、買取・仲介の査定額を比較し売却方針を決定するとよいでしょう。