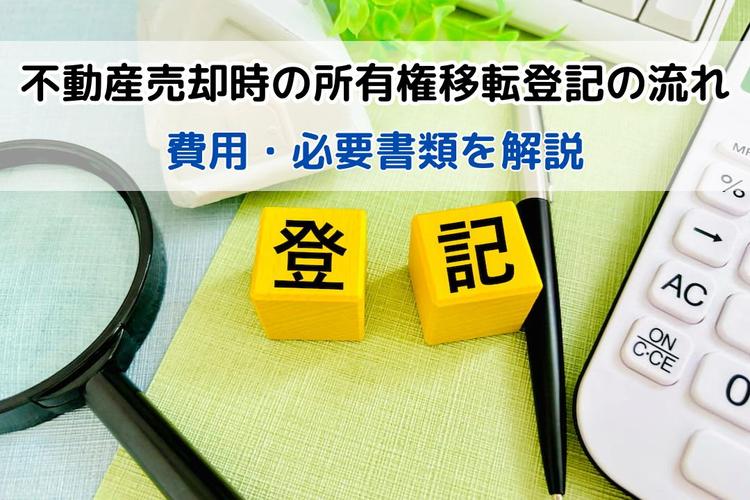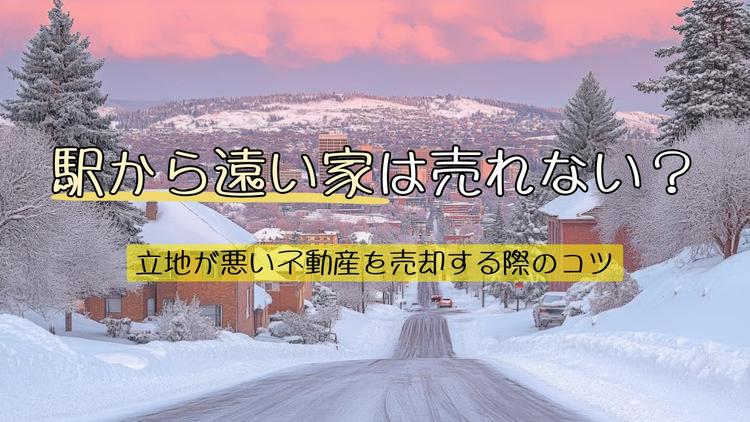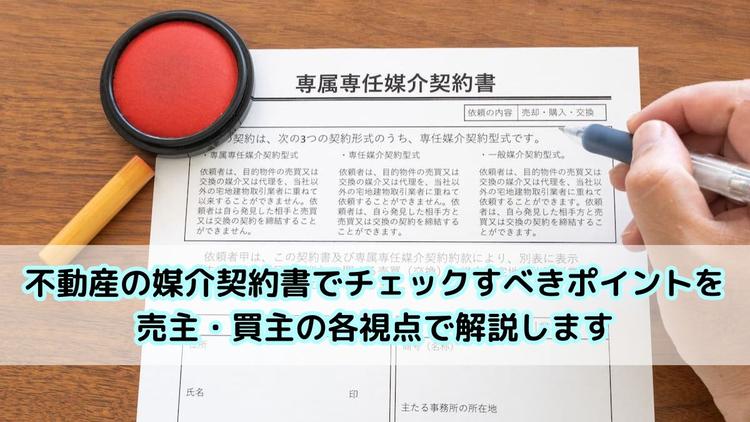不動産が売買されると、所有権移転登記が必要になります。所有権移転登記は、法律で定められた手順に沿って進められるので、費用や書類を準備しておく必要があります。
この記事では、不動産売却後の所有権移転登記がどのような流れで進められるのかを明らかにしたうえで、登記にかかる費用や必要書類について解説します。
所有権移転登記とは?
所有権移転登記とは、土地や建物の所有権が移った際に、その所有権を明白にするために行う登記です。たとえば不動産を売却した場合、所有者を買主の名義に登録することで、売主から所有権が移ったことを公示します。
不動産の所有権を登記することで、その不動産の所有者が誰なのかが分かり、安心して売買ができるのです。
不動産の売却で登記はいつ行う
不動産の売却では、所有権が売主から買主に移ったときに、共同で所有権移転登記を行います。
ただし実務上は、物件引渡しの場に立ち会った司法書士が、売主と買主の代理人として法務局に出向き、申請を行うのが一般的です。
なぜ所有権移転登記を行うのか
所有権移転登記を行うことで、権利が誰にあるのかを証明することができます。
登記を行わなかった場合、詐欺被害に遭うなどのトラブルに巻き込まれる可能性があります。たとえば、不動産を購入したのに、売主が他の買主にも売却していて、そちらが先に登記したために所有権が認められなかったといった事例も発生しています。
「第三者のためにする契約(三為契約)」など、所有権移転登記がされないケースもありますが、一般的な住宅の売買時は、残代金決済・引き渡しと同日に所有権移転登記を実施するのが一般的です。
高額の価値である不動産の所有権を巡るトラブルは、決して珍しいことではありません。トラブルを避けるためにも、売買による所有権移転登記は速やかに行うことが重要です。
不動産を売却した後の所有権移転登記の流れ
不動産を売却した場合の所有権移転登記は、次のような流れで進められます。
- 売買契約
- 決済・引渡し
- 所有権移転登記の申請
- 登記完了
段階ごとに具体的な流れを紹介していきましょう。
売買契約
不動産の売却では、まず不動産会社と媒介契約を結び販売活動を行います。販売活動を通じて、買主と条件が折り合えば、売買契約を締結することになります。
このとき、買主が手付金を支払います。
決済・引き渡し
決済は、引渡しと同時進行で行われます。
この決済時に、買主が残金を支払います。買主が住宅ローンを利用する場合は、融資を行う銀行の個室で決済が進められるのが一般的です。
会場が銀行であることや、同日に所有権移転登記申請をするため、決済は平日に行われます。この場には、売主、買主、不動産会社の営業担当者、司法書士、銀行の住宅ローン担当者が一堂に会します。
所有権移転登記の費用は買主が負担
司法書士は、当事者が選任することができますが、不動産売買の実務上は不動産会社か��ら紹介されるのが一般的です。
所有権移転登記の費用は原則として買主が負担し、抵当権抹消登記(金融機関が不動産を担保にする、抵当権という権利を抹消する手続き)が必要な場合は、売主がその費用を負担します。
司法書士による本人確認
司法書士は、売主と買主の本人確認をしたうえで、売買に関する意思確認をします。これは、なりすましや認知症によるトラブルを防ぐため、会話を通じて確認が行われます。
なお、代理人による意思表示は原則として認められないため、当事者(特に売主)は必ずこの場に立ち会わなければなりません。
その後、書類確認が行われます。必要な書類が不足していると引渡しができないので、当日、本人確認書類などの忘れ物がないか、しっかりと確認しておくことが重要です。
司法書士による必要事項の確認が完了後、売主が買主に鍵を渡します。これで引渡しが完了したことになります。
所有権移転登記の申請
所有権移転登記は、当事者本人が手続きをすることもできますが、司法書士に依頼するのが一般的です。
特に、
- 売主の住宅ローンが残っていて、抵当権抹消登記の必要がある
- 買主が住宅ローンを利用するため、抵当権設定登記の必要がある
といったケースでは、金融機関から司法書士を通じて手続きを行うよう求められることが多いため、所有権移転登記の部分も司法書士に委任して対応してもらうのが一般的です。
基本的に登記は、引渡しと同日に申請します。そのため、書類の作成ミスや必要書類の不足により、登記所に書類の受領を拒��絶されることがないようにするという意味でも、専門家に依頼するのが安心でしょう。
所有権移転登記の完了
申請してから完了までは、7日〜10日程度の日数を要します。
買主(登記権利者)と売主(登記義務者)が共同で申請した場合、登記が完了した時点で、法務局から登記完了証がそれぞれに交付されます。
この時、法務局でこれまでのすべての登記事項が記載されている「全部事項証明書」を入手し、名義が変更されていることを確認します。
なお、売主が司法書士に引き渡した登記識別情報通知(権利書)は、所有権移転登記のために法務局に持ち込まれた後処分され、返却はされません。
不動産売却後にかかる費用
不動産売却後には、次のような費用が必要になります。
- 登録免許税
- 必要書類を入手するための費用
- 司法書士への報酬
- その他の費用
それぞれ具体的に紹介していきましょう。
登録免許税
登録免許税は、法務局で名義変更を申請する際に課せられる税金で、収入印紙を購入して申請書に貼ることで納税したことになります。
不動産売買の登録免許税の税率は次のように定められています。
- 土地:不動産価格の1.5%
- 建物:不動産価格の2%
たとえば、土地の価格が2,000万円で建物の価格が1,000万円だった場合、登録免許税は50万円になります。
必要書類を入手するための費用
不動産売買後には、所有権移転登記のためにさまざまな書類を用意しなければならず、そのための費用が発生します。具体的には、次のような費用です。
- 住民票:300円
- 印鑑証明書:300円
- 固定資産税評価証明書:300円
なお、登録免許税を算出する際の根拠となる固定資産税評価証明書は、もし手元に「固定資産税・都市計画税納税通知書」に同封された課税明細書があれば、不要となります。
また、所有権移転登記が完了した際は、登記識別情報通知の交付に300円が必要です(買主が取得する)。
戸建ての場合は、土地と建物で2つの登記識別情報通知が発行されます。
登記識別情報通知は再発行されない書類で、取引した物件の買主が後にそれを売ろうとするとき、本人確認のために必要になります。
紛失してしまった場合は、代替手段による本人確認が必要になるなど、追加の費用がかかるため、買主は大切に保管しておきましょう。
司法書士への報酬
不動産売買では、司法書士に支払う報酬も必要になります。
法的には、名義変更の手続きを自ら行うことも可能です。しかし、手続きでミスが起こった場合に引渡しに影響が出たり、書類の作成に手間がかかることから、司法書士に依頼をするのが一般的です。
司法書士に支払う報酬額は、自由競争なので司法書士によって異なりますが、5~8万円程度が相場です。
複数の司法書士から見積書を発行してもらい、比較検討する方法もあります。
その他の費用
不動産売却後も様々な費用がかかります。
まず、不動産売却により譲渡所得が発生した場合、譲渡所得税を支払う必要があります。
また、不動産会社に仲介を依頼した場合には、仲介手数料を支払う必要があります。仲介手数��料の多くは、法律で定めた基準の上限としており、その場合「(売却金額×3%+6万円)×消費税」で算出されます。
たとえば、3,000万円の不動産を売却した場合には約105万円の仲介手数を支払うことになります。
さらに、自宅を売却したのであれば、転居費用なども発生します。新居が建築中であれば、それまでの仮住まいの賃貸に関する費用も必要です。
不動産売却後の所有権移転に必要な書類
不動産の売主は、所有権移転で次のような書類が必要になります。
- 不動産登記申請書
- 登記識別情報(権利書)
- 委任状
- 登記原因証明情報
- 住民票
- 固定資産税評価証明書
- 本人確認書類
それぞれの書類について紹介していきましょう。
不動産登記申請書
所有権移転登記を申請するための書類です。手続きを司法書士に依頼する場合は、司法書士が書類を用意し、売主は認印を押印します。
委任状
売主が所有権移転登記を司法書士に依頼する場合、委任状が必要になります。売主は実印で押印します。
登記原因証明情報
所有権移転登記の原因を証明する書類のことで、売却による場合は、売買契約書が証明の書類になります。領収書も合わせて用意してください。
登記識別情報
不動産売却では、登記識別情報が必要となります。
登記識別情報とは、不動産の名義が変更された際に、登記所から新たな名義人に通知されるもので、従来の権利書に代わる書類です。
- 不動産番号
- 受付年月日、受付番号
- 登記の目的(抵当権設定、所有権移転など)
- 登録名義人の住所
- 登録��名義人
- 登記識別情報(12桁の英数字)
登記識別情報通知には上記が記載されています。
権利書との違い
平成17年3月施行の法改正によって、従来の紙の権利書から、電子の登記識別情報へと移行しました。
登記事務のオンライン化に伴い権利書は廃止されましたが、当初オンライン化できていない法務局もあったため、すべての法務局で登記識別情報が交付できるようになったのは、平成20年7月以降です。
つまり、平成17年3月~20年6月に登記した人は土地の権利書か登記識別情報のいずれかを所持し、平成20年7月以降に登記した人は、登記識別情報のみを所持していることになります。
登記識別情報は、所有権移転登記の手続きの際に登記所へ提出し、その不動産の所有権を取得した本人であることを証明します。再発行はできないため、予め存在を確認しておくことが重要です。
登記識別情報通知を紛失した場合の対応
仮に登記識別情報を紛失しても、事前通知や他の本人確認情報によって、所有権移転登記の手続きは可能です。
ただし、事前通知や他の本人確認の手続きによる費用や時間を要することになるので、登記識別情報を紛失している場合は、仲介をしている不動産会社への事前の連絡が不可欠です。
印鑑証明書
押印した印鑑が実印であることを証明するための書類です。
住民票
売主は、登記名義人の表示変更登記が必要な場合に住民票を用意します。たとえば、登記上の住所と現住所が一致しない場合に必要になります。その際、本籍地やマイナンバーは省略してください。
また、住民票で現住所と登記簿上の住所・氏名との繋がりが確認できない場合は、住民票の除票か戸籍の附票、戸籍謄本が必要になります。
固定資産税評価証明書
固定資産税評価証明書は、土地や建物など、固定資産税の課税対象となる資産を所有している場合に、その対象物の課税評価額を証明する書類のことです。
自宅に配達される課税明細書が手元にあれば不要ですが、紛失している場合は、市区町村役場の固定資産税課で入手が可能です。
本人確認書類
所有権移転登記をする本人であることを証明するために用います。
マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなどが有効です。顔写真付きの書類がない場合には、保険証など2種類の書類を準備する必要があります。
実印・認印
各種書類に必要に応じて押印します。
所有権移転登記後の注意点
家の売却ができたからといって、売却した不動産に関することから縁が切れたわけではありません。いくつかの残された注意点を解説します。
契約書や領収書を整理する
売却が完了すると、安心して売買関係の書類をそのままにする売主もいるかもしれません。しかし、将来的に売却した不動産に関して、買主から契約不適合を指摘される可能性があります。また、売却によって高額の収入を得た場合、税務署から連絡が来る可能性もあります。
こうした事態に備えて、契約書や領収書などの売買に関する書類は、きちんと整理をし、保管しておくことが大切です。
税務署からの申告案内に返信する
売却して利益が出ると、売主は譲渡所得税を納めなければなりません。売却後、しばらくすると税務署から「譲渡所得税等の申告の案内」が送付されてきます。
計算上譲渡所得税がかからないのであれば、案内の中にある返信欄に計算根拠を記入し、利益が発生しないことを明記して返信すれば、申告は不要になることがあります。
売って利益が出たら譲渡所得税を納付する
譲渡所得税は、家を売って利益が出た場合に、売主に対して課税される税金です。
ただし、自らが居住用として利用した家なら「居住用財産の3000万円特別控除」を利用できます。この特別控除により、利益から3,000万円まで差し引き、納める税額を軽減��することができます。
なお、譲渡所得税の申告は売買した翌年の2月16日から3月15日までに行います。特別控除を利用する場合でも、申告をする必要があります。
申告に必要な確定申告書と譲渡所得税の内訳書は、インターネットでダウンロードできます。忘れないように準備を進めてください。
まとめ
不動産売買後の所有権移転登記は、法的には重要な意味を持ちますが、実際は司法書士がほとんど対応します。
売買の当事者である売主・買主は必要書類を揃えた上で司法書士に任せておけば、難しい作業などは発生しませんが、実施される登記の意味を知っておくことで、安心して取引に臨めるでしょう。
買主側は自身がその家を売ることがあれば、売主の立場として所有権移転登記を再度経験することになります。
登記識別情報は再発行されず、売却時に必要な書類になりますので、大切に保管しておきましょう。