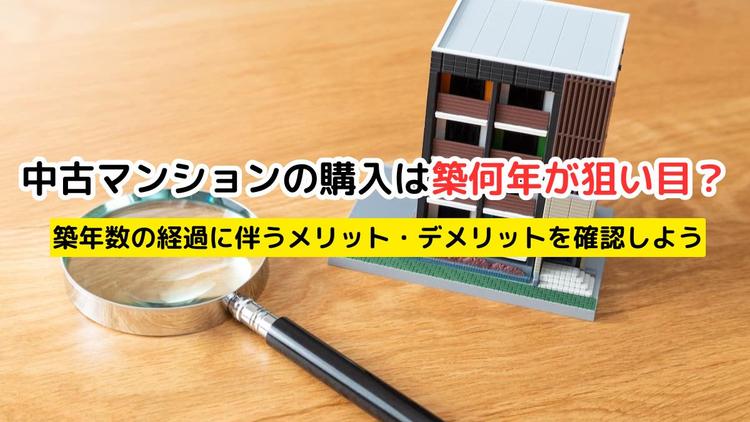家を買う人の多い年代といえば、20代や30代を思い浮かべる方も多いでしょう。
数十年に及ぶ住宅ローンを組むことが多い住宅購入ですが、50代でも家を買うことはできるのでしょうか。
本記事では、50代でも家を買えるかどうかや、ローン審査のポイント・注意点など解説していきます。
50代で家は買える?
50代でも家を購入することは可能なのでしょうか?
結論からいうと、もちろん50代でも家を買うことはできます。
実際、50代で子育てが落ち着き、初めて家を購入するといった方や、子供が巣立った後の終の棲家を購入するといった方は以外と多いものです。
子供の教育費の負担がなくなり、ある程度貯蓄があり、また将来的には退職金を受けられるなど、50代は以外と家を買うための条件は揃っているといえます。
一方で、数年後~十数年後にはほとんどの方が退職するといった問題から、住宅ローンの審査に通りにくい点に注意しなければなりません。

50代で家を買う際のローン審査のポイント
冒頭でお伝えしたとおり、50代で家を購入することは十分可能ですが、住宅ローンを組むときは問題となりやすいです。
このため、あらかじめローン審査のポイントを押さえておくことが大切だといえるでしょう。
団体信用生命保険に注意
50代で�住宅ローンを組むとなると団体信用生命保険が問題となりやすいです。
団体信用生命保険とは、住宅ローン返済中に債務者が死亡した場合、残債をゼロにしてくれる保険のこと。
民間の住宅ローンでは、住宅ローンを借りるときに団体信用生命保険への加入を必須としていることがほとんどです。
特に民間金融機関の住宅ローンでは、多くが団信への加入を求められます。
万が一債務者が死亡してしまった場合、その後返済が滞ってしまう可能性が高いことから、このような保険があると考えるとよいでしょう。
団体信用生命保険は保険ですから、健康上の問題がある場合には加入できないことがあります。
団体信用生命保険に加入できないと、住宅ローン自体が利用できませんから、この点が問題となりやすいのです。
解決策としては、
- 団信への加入が必須でない住宅ローン(フラット35など)を利用する
- ワイド団信や、基準が緩和されている団信に加入する(保険料が高め)
といったものが挙げられますので、金融機関の担当者に相談してみましょう。
ワイド団信は取り扱っている金融機関が限られているため、民間の生命保険を利用して、万が一の際に保険金が下りるように準備しておく対策も有効です。
借入期間は30年以下
また、50代で住宅ローンを組むとなると、借入期間は30年以下にしなければなりません。
住宅ローンには完済時年齢が設定されており、一般的には80歳前後で完済するよう借入期間を設定しなければならないからです。
仮に完済時年齢の上限が80歳に設定されている場合、50歳で借りれば29年、54歳で25年、59歳で20年など、年齢に応じて設定できる借入期間が短くなってしまいます。
もちろん、借入期間が短くなれば毎月返済額が大きくなります。
あらかじめ、ご自分の年齢と金融機関の完済時年齢をチェックしておくことが大切です。
上記のローンシミュレーターでは、家の購入金額、頭金、金利、借入期間を設定することで、月々の返済額と総支払額を計算可能です(元利均等返済で計算)。
退職金があるとローン審査に通りやすい
50代の住宅購入だと、数年で退職となってしまう方もいらっしゃるでしょう。
こうしたケースでも、退職時年齢を超えた借入期間を設定すること自体は可能ですが、審査ではどのように住宅ローンを返済していくのか、厳しくみられやすくなっています。
ただし、まとまった額の退職金を得られるのであれば、それが審査にプラスに働きます。
親子リレーローンで問題解決
50代での住宅購入で、子供が成人している場合には、親子リレーローンの利用を検討するのも一つの方法です。
親子リレーローンとはその名の通り、親子で住宅ローンを組むもの。
単に2人で住宅ローンを組むのと違う点は、親子で年収を合算できるのに加え、借入期間などは子供の年齢を見てくれるということです。
親子リレーローンを利用すれば、50代の住宅ローン審査の問題のほとんどを解決できるでしょう。
ただし、新居には親子ともに住むことが条件となります。

50代で家を買う際の3つの注意点
住宅ローン審査の問題以外にも、50代で家を買う際には気を付けないといけないことがあります。
具体的には以下のようなものです。
- 老後のためのお金は残しておこう
- いつまで働けるか現実的に考えよう
- 相続も考えた計画を立てよう
それぞれ見ていきましょう。
老後のためのお金は残しておこう
50代での住宅購入は住宅ローン審査が問題となりやすいですが、仮に審査に通らない、あるいは満額融資を受けられないといったケースでも、貯蓄を大きく切り崩したり、退職金のほとんどを購入資金に充てたりするのには慎重になるべきです。
老後に仕事を退職した後、年金で毎月の生活費の全てを賄えるとは限りません。
日本年金機構のデータによると、平均的な収入における夫婦2人分の厚生年金の支給額は約22万円となっています1。
一方で、総務省の調査によると夫婦2人が生活していくのに必要な平均額は約29万円となっており、平均的な水準で生活していくだけで毎月5万円ほど切り崩していかなければならない計算です2。
同調査では、「ゆとりある老後」を送るのに必要な金額は1カ月で約36万円としている他、自営業の方などは国民年金しか受け取れないため、支給額が少なくなってしまいます。
また、昨今の物価上昇により、あらゆる商品・サービスの値段が上がっており、想定しているよりも多くの生活費がかかる可能性も十分考えられるでしょう。
50代で家を買う際には、こうしたことを踏まえて、ある程度老後にお金を残すよう計画を立てることが大切です。
いつまで働けるか現実的に考えよう
50代の住宅購入でもう一つ考えておかなければならないのが、いつまで働けるかという問題です。
50代であればまだまだ元気で、現役を少しでも長く続けたいと考えている方も多いのではないでしょうか。
2024年現在、多くの企業では60歳、遅くとも65歳に定年を設定しており、そこから働き続けたければ給料を下げて再雇用といった道が設けられていることもあるでしょう。
ニッセイ基礎研究所のデータによると、2018年の平均退職年齢は69.9歳3。
ご自分の勤め先がどのような制度を取っており、いつまで働き続けることができるのか事前に確認しておくことが大切だといえます。
相続も考えた計画を立てよう
50代の住宅購入でもう一つ考えなければならないのが、相続の問題です。
住宅を購入すると、将来、自分が亡くなったときに誰に相続されるのかという問題が生じます。
住宅などの不動産は、現金のようにきれいに分割することができません。
また、多くの場合個人の資産の中で住宅は大きな割合を占めることが多く、相続人間で不公平が生じることになりやすく、最終的に争族となってしまう可能性もあるのです。
例えば、子供3人がいる家庭で、5,000万円の住宅と1,000万円の現金、合計6,000万円の金融資産があるケースを見てみましょう。
上記の場合、子供3人に仲良く2,000万円ずつ配分できたら一番よいのですが、不動産は現金のように簡単に分けることができません。
共有持ち分を持つという方法もありますが、住宅を3人で共有しても活用法が限られてしまいます。
例えば、子供Aが5,000万円分の住宅を、子供BとCがそれぞれ500万円ずつ現金を相続する
といったことになると、子供BとCはAと比べて相続財産が少なくなってしまいます。
こうしたことから、相続人間で争いが生じてしまうことがあるのです。
争族の��問題は、被相続人が生前に遺言書を残しておけば解決できることが多いです。
50代で住宅を購入するのであれば、相続の問題を考えて遺言書を作成しておくこともセットで考えてみてはいかがでしょうか。

まとめ
50代で家を買う場合の住宅ローン審査のポイントや審査以外の注意点についてお伝えしました。
50代でも家を購入することはもちろん可能ですが、住宅ローンの問題や相続の問題など、50代での住宅購入ならではの問題があります。
これらは、事前に準備しておけば解決できることがほとんどです。
50代での住宅購入を考えている方は、購入前に本記事の内容を参考に準備をを進めることをおすすめします。