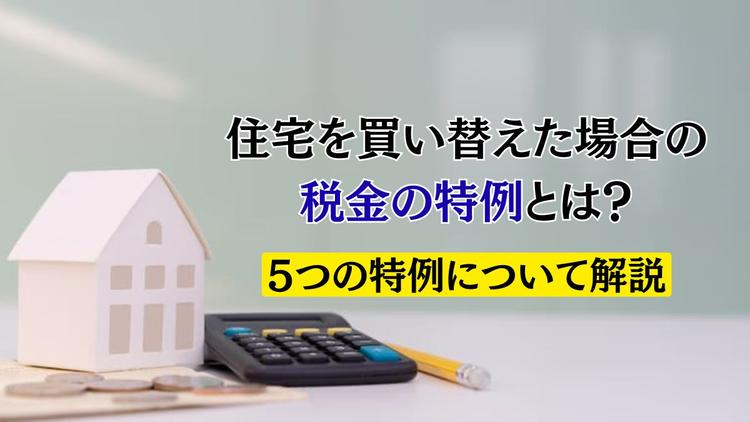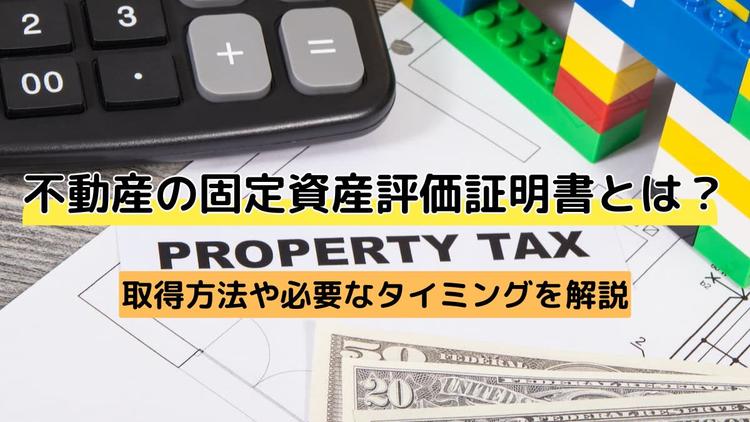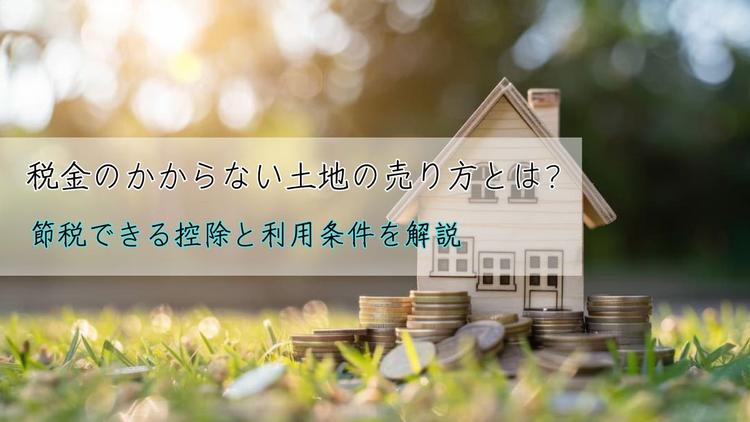住宅の買い替えの際には、多額の金銭が移動するため、なかなか税金のことまで気が回りません。しかし、住宅の売買においては、いろいろな種類の税金が課せられることをご存知でしょうか。
その中には、本来の納税額を大幅に減額できる特例が設けられているものもあります。きちんと情報を把握して節税に努めましょう。この記事では、住宅を買い替えた場合の税金の5つの特例について解説をします。
住宅を買い替えるときにかかる税金は?
住宅を買い替えた場合、どのような税金の特例があるのかを知るために、まず住み替えをすると、どのような税金を納める必要があるのかを押さえておきましょう。
住宅の売却時にかかる税金
住宅を売却した際には、次のような税金がかかります。
- 印紙税……売却の契約を交わす際に必要になります。
- 登録免許税……所有権移転登記や抵当権解除をする際に納めます。
- 譲渡所得税……売却によって得た利益に対する所得税と住民税です。
所有権移転登記にかかる登録免許税は、登録免許税法で、「登記等を受ける者が二人以上あるときはこれらの者は連帯して納付する義務を負う(3条)」と定められています。したがって、売主、買主が共同で納付するのが原則ですが、多くの取引において買主が負担しています。
住宅の購入時にかかる税金
住宅を購入した際には、次のような税金がかかります。
- 印紙税……購入の契約を交わす際に必要になります。
- 登録免許税……所有権移転登記や抵当権設定をする際に納めます。
- 不動産取得税……家や土地を購入した後に納めます。
譲渡所得の計算方法
住宅を売却して買い替える場合、譲渡所得税に対する特例制度が設けられています。この特例制度については後述しますので、こ��こでは譲渡所得税の基本的な計算方法を押さえてきましょう。
まず課税譲渡所得金額を、次のように算出します。
- 譲渡価額とは、土地や建物の売却代金などをいいます。
- 取得費とは、売った土地や建物を買い入れたときの購入代金や、購入手数料などの資産の取得に要した金額に、その後支出した改良費、設備費などの額を加えた合計額をいいます。
- 譲渡費用とは、土地や建物を売るために支出した費用をいい、仲介手数料、測量費、売買契約書の印紙代、売却するときに借家人などに支払った立退料、建物を取り壊して土地を売るときの取壊し費用などです。
課税譲渡所得金額に応じて、次のような税額がかかります。
長期譲渡所得税額=課税譲渡所得金額×20.315%(所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%)
ただし、売却した不動産の所有期間が5年以内の場合は短期譲渡所得に該当するので、税率は39.63%になります。
参考:国税庁|「長期譲渡所得の税額の計算」「短期譲渡所得の税額の計算」
住宅を買い替えるときに受けられる税金の特例5つ
ここでは、住宅を買い替えるときにかかる税金のうち、税額の控除等が受けられる5つの特例を紹介していきます。
このうち買い替えで利益が出たときに適用される特例が「3,000万円の特別控除�の特例」「マイホームを売ったときの軽減税率の特例」「特定の居住用財産の買い替えの特例」です。
反対に買い替えで損失が出たときに適用される特例が「マイホームを買い替えた場合の譲渡損失及び繰越控除の特例」です。
さらに住宅ローンを利用した際に適用される「住宅ローン控除」があります。
それぞれどのような特例なのかを解説していきましょう。
3,000万円の特別控除の特例
「3,000万円の特別控除の特例」は、住宅を売却したとき、譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる制度です。たとえば、5,000万円の売却益があった場合、3,000万円を差し引いた2,000万円に対して課税されます。
したがって、売却益が3,000万円以下であれば、非課税になります。
特例が受けられる要件は次のとおりです。
- 自分が住んでいる家屋を売ること。
- 居住しなくなって3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。
- 建物を解体した場合は、解体から1年以内に土地の売買契約を締結すること。
- 解体した日から売買契約を締結するまでの期間、貸駐車場として利用していないこと。
- 売主と買主が、親子や夫婦など特別な関係でないこと。
- 前年、前々年にこの特例や「マイホームを買い替えた場合の譲渡損失及び繰越控除の特例」の特例を受けていないこと。
- 売った年、その前年及び前々年に「特定の居住用財産の買い替えの特例」の適用を受けていないこと。
上記の条件に適合する場合にあっても、次のような物件については適用除外となります。
- こ��の特例を受けることだけを目的として入居したと認められる家屋
- 居住用家屋を新築する期間中だけ仮住まいとして使った家屋
- 別荘
この特例は、自分が住んでいる家屋を売った際に適用される制度です。そのため、家を売った人の住民票に記載されていた住所とその家の所在地とが異なる場合には、戸籍の附票の写し、消除された戸籍の附票の写しその他これらに類する書類でその家を売った人がその家に居住していたことを明らかにする書類の提出が求められます。
マイホームを売ったときの軽減税率の特例
「マイホームを売ったときの軽減税率の特例」は、土地、建物の所有期間が10年以上ある場合に利用できます。
譲渡所得に対する所得税と住民税(譲渡所得税)の税率は通常、20.315%ですが、特例を利用することで、税率が14.21%に引き下がります。
この特例が適用される要件は次のとおりです。
- 売った年の1月1日において、売った土地や建物の所有期間がともに10年を超えていること。
- 自分が住んでいる家屋を売ること。
- 居住しなくなって3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。
- 建物を解体した場合は、解体から1年以内に土地の売買契約を締結すること。
- 解体した日から売買契約を締結するまでの期間、貸駐車場として利用していないこと。
- 売った年、その前年及び前々年にこの特例の適用を受けていないこと。
- 「特定の居住用財産の買い替えの特例」の適用を受けていないこと。
- 売主と買主が、親子や夫婦など特別な関係でないこと。
住民票と物件の所在地が異なる場合は、その家に住んでいたという証明書の提出を求められます。
この特例を受けた場合、長期譲渡所得税20.315%(所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%)のうち、所得税+復興特別所得税が10.21%に軽減されるので、税率は、14.21%になります。
特定の居住用財産の買い替えの特例
「特定の居住用財産の買い替えの特例」は、譲渡益に対する課税を将来に繰り延べることができる制度です。
譲渡所得税は、本来であれば買い替えのときに課せられますが、自宅を令和3年12月31日までに売って、代わりの家を買い換えたときは、次の購入した家を売却するときまで、その譲渡所得を持ち越すことができます。
気をつけたいのは、この特例は、課税するタイミングが将来になるだけで、免除や減額されるものではない点です。
この制度が適用されるための要件は次のとおりです。
- 自分が住んでいる自宅を売却すること。
- 売った人の居住期間が10年以上で、かつ、売った年の1月1日において、売った土地や建物の所有期間がともに10年を超えていること。
- 居住しなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すること。
- 建物を解体した場合は、解体から1年以内に土地の売買契約を締結すること。
- 解体した日から�売買契約を締結するまでの期間、貸駐車場として利用していないこと。
- 売主と買主が、親子や夫婦など特別な関係でないこと。
- 買い換える建物の床面積が50平方メートル以上のものであり、買い換える土地の面積が500平方メートル以下のものであること。
- 住宅を売った年の前年から翌年までの3年の間に住宅を買い換えること。また、買い換えた住宅には、「売った年かその前年に取得したときは、売った年の翌年12月31日まで」「売った年の翌年に取得したときは、取得した年の翌年12月31日まで」に住むこと。
- 売却代金が1億円以下であること。
- 売った年、その前年及び前々年に「3,000万円の特別控除の特例」「マイホームを売ったときの軽減税率の特例」「マイホームの譲渡損失についての損益通算及び繰越控除の特例の適用」を受けていないこと
- 買い換える建物が、中古住宅である場合には、取得の日以前25年以内に建築されたものであること、または一定の耐震基準を満たすものであること。
マイホームを買い替えた場合の譲渡損失及び繰越控除の特例
土地建物等を譲渡して譲渡損失の金額が生じた場合、「マイホームを買い替えた場合の譲渡損失及び繰越控除の特例」を使うことで、所得税や住民税が軽減されます。さらに、この特例を適用しても、なお控除しきれない損失の金額は、その譲渡の年の翌年以後3年間にわたり繰り越して控除することができます。
この特例が�適用される要件は次のとおりです。
- 売った年の1月1日において、売った建物の所有期間が5年を超えていること。
- 自分が住んでいる家屋を売ること。
- 居住しなくなって3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。
- 建物を解体した場合は、解体から1年以内に土地の売買契約を締結すること。
- 解体した日から売買契約を締結するまでの期間、貸駐車場として利用していないこと。
- 売主と買主が、親子や夫婦など特別な関係でないこと。
- 新しく購入した建物の面積が50平方メートル以上であること。
- 建物を購入とした年の翌年12月31日までの間に居住の用に供すること。
- 自宅を買った年の12月31日時点で、期間10年以上の住宅ローンがあること。
参考:国税庁|マイホームを買い換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
住宅ローン控除
「住宅ローン控除」は、住宅ローンを借入れて新居を購入する場合に利用できる特例です。返済期間が10年以上の住宅ローン残高の0.7%が13年間(一部条件で10年間)にわたり所得税の額から控除されます。
また、所得税からは控除しきれない額は、住民税からも一部控除されます。控除額の限度は、長期優良住宅で409.5万円です。
適用されるための要件は、次のとおりです。
- 新居取得の日から6カ月内に自らが居住し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること。
- 住宅の床面積が50平方メ��ートル以上(合計所得金額1000万円以下の場合は40㎡以上)であること。
- 住宅が一定の省エネ基準に適合していること。
- 借入期間が10年以上あること。
- 控除を受ける年分の合計所得金額が2,000万円以下であること。
耐震基準については、1982年1月1日以前に建築された住宅を取得した場合、耐震基準適合証明書が必要になります。
買い替えに伴う特例は併用できる?
ここまで、買い替えに伴う5つの特例を紹介してきましたが、これらの特例を併用して使用する場合には注意が必要です。特例の組み合わせ方によっては、どちらかひとつしか利用できないことがあるからです。
ここでは、特例の併用の可否について解説をしていきましょう。
住宅ローン控除と併用することができない特例
次の特例は、住宅ローン控除と併用することはできません。
- 3,000万円の特別控除の特例
- マイホームを売ったときの軽減税率の特例
- 特定の居住用財産の買換えの特例
それぞれ節税効果の大きい特例なので、どれを選択するかは、慎重に検討する必要があります。
併用が可能な特例
次のような特例は併用が可能です
- 3,000万円の特別控除の特例+マイホームを売ったときの軽減税率の特例
- マイホームを買い替えた場合の譲渡損失及び繰越控除の特例+住宅ローン控除
たとえば、4,000万円の譲渡益があった場合、「3,000万円の特別控除�の特例」を使うことで、1,000万円が譲渡所得税額になります。これに「マイホームを売ったときの軽減税率の特例」を併用することで、1,000万円に対して14.21%の税率が適用されることになります。
特例を申請するためには確定申告が必要
これまで紹介した5つの特例制度を使用するためには、確定申告を行う必要があります。
たとえば、譲渡益が2,500万円だった場合、「3,000万円特別控除」を使うことで非課税となりますが、この場合でも、確定申告をしなければ特例の適用は認められません。
各特例については、売却の翌年の2月中旬〜3月の中旬までの確定申告期間中に申告する必要があります。
住宅ローン控除は、最長で10年間にわたり控除を受けることができますが、申告をするのは初年度のみで、翌年以降は勤務先に書類を提出することで、控除が行われるようになります。
確定申告の方法
確定申告は、税務署の窓口へ直接提出する方法のほかに、郵送やオンラインによる申告もできます。申告書の仕上げに自信がない場合は、書類の不備などを指摘してもらえる窓口への提出した方がいいでしょう。
住宅の買い替えで使う特例は、種類が多いため、どの特例を使えばいいのか迷うことがあります。税務に関して報酬を伴う相談は税理士以外の者が行うことはできません。特例の利用について相談したいときには、税理士か税務署に相談しましょう。
確定申告を税理士に依頼した場合、一定の報酬が伴いますが、不動産の状況によっては、税理士に依頼したことで、思わぬ節税効果が生じることがあります。どのような方法で確定申告をすればいいのか、じっくりと状況を見極めて判断をしましょう。

まとめ
住宅を買い替えるときに受けられる税金の特例は、次の5つがあります。
- 3,000万円の特別控除の特例
- マイホームを売ったときの軽減税率の特例
- 特定の居住用財産の買い替えの特例
- マイホームを買い替えた場合の譲渡損失及び繰越控除の特例
- 住宅ローン控除
「3,000万円の特別控除の特例」と「住宅ロ�ーン控除」は、いずれも節税効果の高い特例ですが、この2つの特例は併用することができません。どちらを使うのかについては、節税効果を総合的に考慮したうえで、選択をする必要があります。
特例は、確定申告をすることで、初めて適用されることになります。確定申告は自分でも手続きをすることは可能ですが、自信がない場合は税理士に依頼するという方法があります。