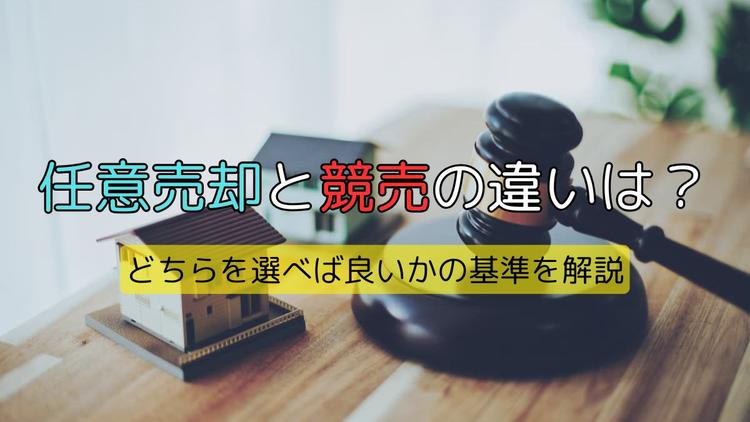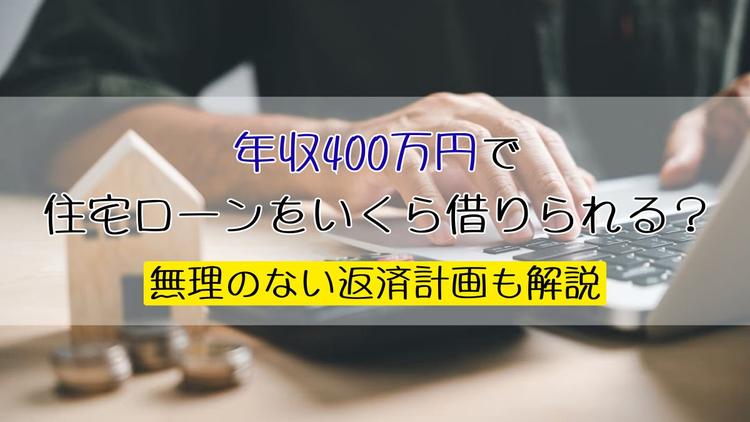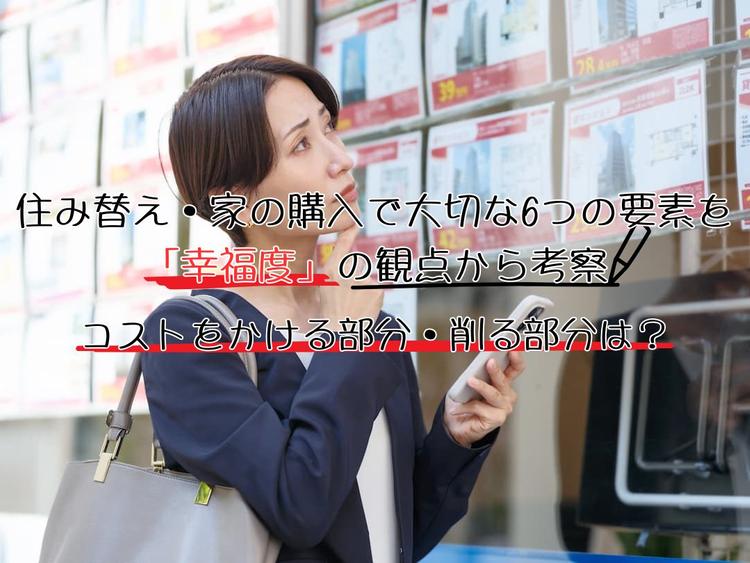脱炭素の機運が高まるなか、「遊休農地を活用して太陽光発電をしたい」という相談が増えています。しかし農地は農地法の規制下にあり、宅地や雑種地とはまったく違う手続きと制限が課されます。
この記事では 農地で太陽光発電を行う二つの方式(①野立て型 ②営農型=ソーラーシェアリング)を区別しながら、許可要件・手続きの流れや費用について解説します。
農地で太陽光発電は大きく二つの方式
農地で太陽光発電を行う場合、大きく分けて「野立て型」と「営農型(ソーラーシェアリング)」という二つの方式があります。それぞれ、目的や許可の必要性、農地の使い方において大きな違いがあります。
野立て型太陽光発電
野立て型とは、農地を完全に発電用地に転用し、農作物を育てることをやめてパネルを設置する方式です。農地を本来の用途である「耕作のための土地」から外してしまうため、農地法に基づく「転用許可」が必要になります。
この転用は、農地法第4条(自己所有地の転用)または第5条(売買・賃貸など第三者による転用)の対象となり、許可には厳格な基準が設けられています。特に、市街化調整区域や青地(農業振興地域内の農用地区域)では、許可が下りないケースも多く、実現のハードルが高い方式といえます。
ただし、一度許可を得てしまえば、発電に専念でき、管理も比較的容易です。また、20年間の固定価格買取制度(FIT)を利用すれば、収益性が比較的読みやすいのも特徴です。
営農型太陽光発電(ソーラーシェアリング)
一方の営農型は、農地での耕作を継続しながら、その上空を活用して太陽光パネルを農地上空に設置する方式です。農業と発電を両立させることから「ソーラーシェアリング」とも呼ばれます。
営農型は農地としての利用を維持するため、農地法上は「一時転用」として扱われ、比較的許可が得やすい傾向があります。ただし、2024年の制度改正により、実際に農作物の栽培を継続していることの証明(営農実績報告)が厳格に求められるようになりました。
パネル設置には、高さ・間隔・支柱の構造に制限があり、耕作や農業機械の使用を妨げない設計が必須です。さらに、遮光率にも上限が設けられており、作物の種類や栽培方法にも工夫が必要です。
営農型は、農地としての税制優遇を維持しつつ、農業収入と売電収入を組み合わせることができるため、経営安定化の手段として注目されています。
法的枠組みと最新の改正ポイント
農地で太陽光発電を行うには、農地法を中心に�複数の法令の規制を受けます。特に、農地を発電用に使うには「農地転用」の許可が必要となり、その可否や手続きの内容は、農地の種類や利用方法によって大きく異なります。
農地法4条・5条
農地法では、自己所有の農地を転用する場合は第4条、他人から取得・賃借して転用する場合は第5条の許可が必要です。営農を継続しながら太陽光パネルを設置する「営農型」の場合は、一時的な転用として扱われます。
しかし、野立て型は農地としての機能を完全に失うため、原則として恒久的な転用が求められます。
農地の区分
農地の区分にも注意が必要で、農業振興地域内の「第1種農地(青地)」では、野立て型の転用は原則認められません。比較的許可が得やすいのは「第3種農地」など、周辺が市街化している地域です。
ただし、営農型であれば青地でも一定の条件下で一時転用が認められることがあります。
必要な手続きや義務について
営農型に関しては、2024年4月に農林水産省が許可基準を省令として明文化しました1。改正では、転用期間は原則3年以内(最長10年)、設備は容易に撤去できる構造とし、作物の種類や収量見込みを記した営農計画書の提出が義務化されました。
加え�て、年次報告で営農実績を確認し、不履行があれば撤去命令や許可取消の対象となります。発電目的だけの事業者を排除し、農業と共生する再エネ活用が重視されています。
また、農地法のほかにも、電気事業法(高圧設備の基準)、経済産業省による固定価格買取制度(FIT)やFIP制度、さらに大規模設備では環境アセスメント法なども関係します。各制度を正しく理解し、必要な手続きを漏れなく行うことが、太陽光発電事業の成否を左右します。
許可取得に必要な手続き
農地で太陽光発電を行うには、農地法を中心とした関係法令に基づいて、所定の許可を取得する必要があります。特に農地転用は、適切な手続きなしに行うと違法行為とみなされ、行政指導や撤去命令、さらには刑事罰の対象となる可能性もあります。
この章では、太陽光発電を目的とした農地転用に必要な主な手続きの流れを、野立て型と営農型の双方に共通する形で整理します。
現地調査と農地の区分確認
まず行うべきことは、対象農地の現況と法的区分の確認です。具体的には以下の点を調査します。
- 農地種別の確認:青地(農用地区域内農地)か白地(農用地区域外農地)か
- 地目:登記簿上の地目が「田」「畑」であるか
- 農業振興地域整備計画:農振除外の要否を確認
- 周辺環境:送電線や電柱の位置、接続可能性、日照条件など
- 地盤・排水状況:架台設置や営農の妨げになる地形でないか
この段階で、第1種農地や農振除外困難な地域であることが判明した場合、計画自体の�見直しが必要になります。
関係機関との事前相談
太陽光発電の導入は農業とエネルギーの交差点にあるため、複数の行政機関と連携が求められます。以下の窓口に早期に相談することが重要です。
- 市町村農業委員会(農地法の許可申請・営農型の可否)
- 都道府県農業振興課(農振除外・営農実績評価)
- 地域の電力会社(系統連系の可否・負担金見積)
- 農業協同組合(JA)や土地改良区(水利権や地役権の確認)
事前相談で方向性を明確にしておくことで、書類作成や許可申請後のトラブルを最小限に抑えることができます。
許可申請に必要な書類の準備
農地転用の許可申請や一時転用の届け出には、以下のような書類が必要です(自治体により若干異なります)。
- 転用許可申請書(4条・5条または一時転用)
- 土地登記簿謄本・公図・地積測量図
- 現況写真(全景、周辺、耕作状況など)
- 太陽光発電設備の配置図・構造図
- 営農型の場合:営農計画書・作付予定表・遮光率計算書
- 事業計画書(設備概要、収支計画など)
- 系統連系予定表・電力会社からの接続回答書
- 委任状(代理申請の場合)
特に営農型では、作物の選定理由や収量見込みを記した「営農計画書」が審査の鍵を握ります。これが曖昧または現実味のない内容であれば、許可が下りないこともあります。
申請と審査の流れ
農地法に基づく許可申請は、原則として毎月1回の締切日(例:毎月10日など)が設けられており、その後以下の流れで審査が進みます(自治�体によって若干異なります)。
- 農業委員会への提出(市町村)
- 現地調査・審査会による確認
- 県(または政令市)による最終審査・知事許可
- 許可証交付・通知(通常1〜3か月)
なお、営農型の場合は「一時転用許可」として扱われますが、手続きの大枠は同様です。事業規模が大きい場合や他の法令(都市計画法・環境保全条例等)に抵触する恐れがある場合は、さらに追加の手続きが求められることもあります。
経済産業省への手続き(FIT/FIP申請)
農地転用許可の取得と並行して、「固定価格買取制度(FIT)」または「フィードインプレミアム制度(FIP)」の認定申請を、経済産業省へ提出します。申請には以下の情報が必要です。
- 設備認定申請書(再生可能エネルギー発電設備)
- 売電契約予定書類
- 電力会社からの接続承諾書
- 設備仕様書・構成図
- 資金調達計画(融資申請書類含む)
これらの申請が承認されることで、発電開始後に固定価格で電力を買い取ってもらう権利が確定します。
なお、FIP制度では売電価格が市場価格と連動するため、FITと比べて収益に変動リスクがあります。
工事着手と完了報告
農地転用許可やFIT認定を取得した後、ようやく工事に着手できます。工事期間中は以下の点に注意が必要です。
- 許可内容に反しない設計・施工を行うこと
- 営農型の場合、農作物の作付や準備を同時進行で進めること
- 関係機関への着工届・完了届の提出を忘れずに行うこと
完了後は、発電設備の連系(電��力系統への接続)とともに、発電量の測定が開始され、売電収入が得られるようになります。
初期費用の目安
農地に太陽光発電設備を導入するには、許可取得から設計・施工、電力会社との連系に至るまで、さまざまな初期費用がかかります。発電方式(野立て型 or 営農型)や発電容量、土地の条件によって金額には幅がありますが、ここでは一般的なモデルをもとに、初期費用の内訳と相場感を解説します。
許可申請および設計関連費用
- 農地転用許可申請:1万〜3万円……自治体によって異なる。代理申請の場合は別途報酬が発生
- 測量・設計図作成:50万〜100万円……土地形状や規模によって変動。営農型はさらに計画書作成が必要
- 営農計画書作成(営農型):20万〜50万円……作物選定、収量予測、遮光率計算など専門的な作業が必要
営農型では、「作物が育つ環境づくり」と「支柱とパネルの設計」の両立が求められるため、設計費用は野立て型よりやや高くなる傾向があります。
太陽光発電設備の設置費用
パネル・架台・パワコン(直流を交流に変換する機器)等機材費は、営農型の場合、架台が高さや耐久性が求められるため高額になります。
- 野立て型:20万〜23万円/kW
- 営農型:23万〜30万円/kW
工事費(造成・架台設置・電気配線)は、地形・地盤・施工難易度によって大きく変動します。
- 野立て型:200万〜500万円
- 営農型:300万〜600万円
系統連系・電力会社負担金は、配電盤からの距離や系統容量によって異なります。
- 野立て型:50万〜150万円
- 営農型:50万〜150万円
出力が50kW未満の発電設備を想定した場合、野立て型で総額約1,000万〜1,300万円、営農型では約1,200万〜1,500万円が目安となります。
解体・原状回復費用(将来分を事前に積立)
- 解体・撤去積立金:1万〜2万円/kW……自治体によっては義務付け(条例)されるケースもある
- 廃パネル処分費:0.5万〜1万円/kW……リサイクル費用・運搬費を含む
太陽光発電設備の撤去と原状回復は、農地法および一部自治体の条例により義務付けられる場合があります。特に農地の場合は、営農可能な状態に戻すことが求められるため、撤去費用の積立は事業計画段階から必須です。
その他の初期コスト
その他の費用として次のようなものが発生します。
- 土地の取得・借地料:地域により大きく異なる
- 行政書士・設計士等の専門家報酬:10万〜50万円
- 火災・自然災害保険:年間1万〜5万円程度
まとめ
農地での太陽光発電には、「野立て型」と「営農型(ソーラーシェアリング)」の二方式があり、それぞれに適用される法制度や許可手続き、コスト構造が大きく異なります。
特に営農型は、2024年の法改正により営農実績の報告義務が強化され、発電と農業の両立がより厳しく求められています。初期費用も1000万円以上と高額であり、地形や送電設備などの条件次第で変動します。
成功の鍵は、関係機関との綿密な事前調整と、現地に即した実現可能な計画づくりにあります。