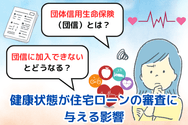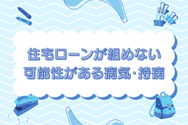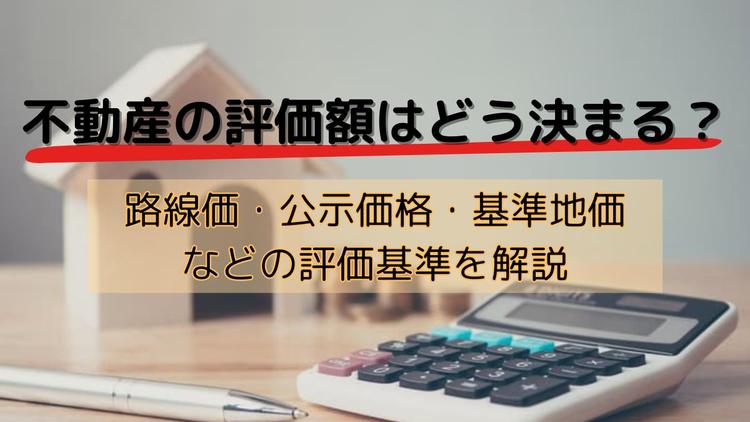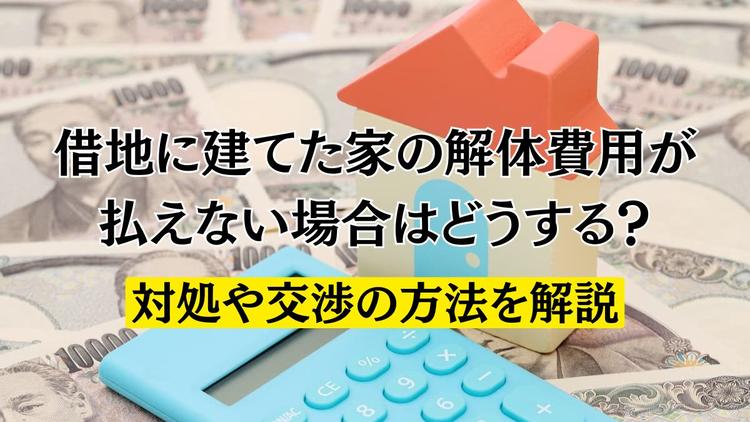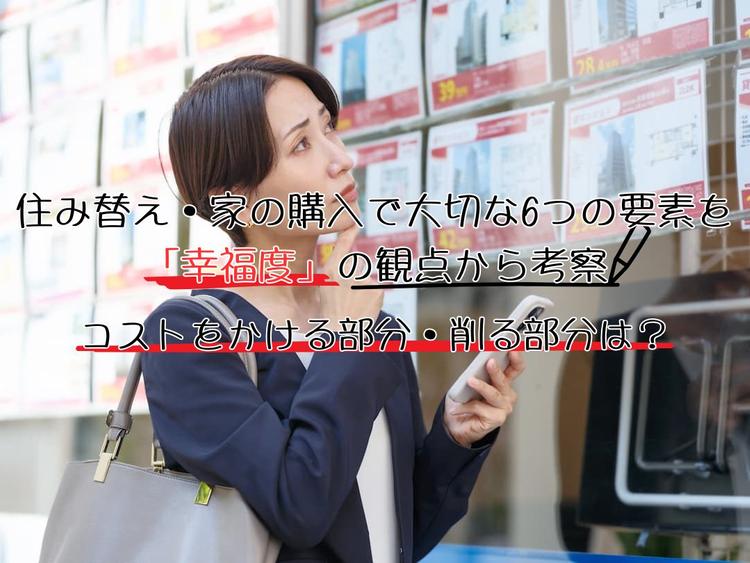住宅ローンの審査に、申込者の健康状態が大きく影響を与えることをご存じでしょうか?特に持病や過去の病歴があると、最悪の場合、住宅ローンが組めなくなる恐れもあるのです。
当記事では、病気や持病があると住宅ローンが組めない理由や団信の審査項目、そして持病があっても住宅ローンを組むための対策を分かりやすく解説していきます。
健康状態が住宅ローンの審査に与える影響
住宅ローンの審査では、申込者の収入や勤務先、他の借入状況などがチェックされますが、それと同じくらい重要視されるのが「健康状態」です。
住宅ローンは30年以上の長期で返済が続きます。そのため金融機関は、申込者が長い期間、無理なく返済を続けられるかどうかを見極める必要があります。
しかし、年収や勤続年数といった経済状況だけでは、確実に返済が続けられるかどうかを判断するのは困難です。なぜなら返済期間中に、病気や事故などで返済が滞るリスクは誰にでも起こり得るからです。
こうした貸し倒れのリスクを防ぐために、ほとんどの金融機関では「団体信用生命保険(団信)」への加入を住宅ローンの契約条件としています。
ただし、団信に加入するには、申込者が健康であることが前提となります。
つまり、住宅ローンを組むには経済的な条件だけでなく「健康であること」も審査を通過するカギになるのです。
団体信用生命保険(団信)とは?
民間の金融機関の住宅ローンでは、多くが団信への加入を求められる。
団体信用生命保険(通称:団信)は、住宅ローンの返済中に契約者が死亡または高度障害の状態になった場合に、残りのローンを保険金で完済してくれる生命保険のことをいいます。
住宅ローンを組む際に、金融機関は団信の加入を求めるケースがほとんどです。ただし、加入するには健康状態が良好でなければいけません。
もし、将来的に病気のリスクが高いと判断される場合、加入を断られる可能性があるため注意が必要です。
団信に加入できないとどうなる?
多くの金融機関で団信の加入を必須としている理由は、金融機関が貸し倒れを防ぐためです。
ローンの借主が返済期間中に万が一の事態に見舞われた時、団信に加入していればローンの残りを補償してもらえます。
一方、未加入の場合はローンがそのまま残ってしまうため、貸し倒れのリスクが発生します。これを避けるために、団信への加入を必須としているのです。
また、借主にとっても、病気や事故によって収入が減ってしまった場合に自宅を失うリスクを避けることにも繋がります。
こういった理由から、いくら年収が高くて正社員として働いていたとしても、団信への加入ができないと住宅ローンの審査に通らない可能性が高くなります。
ただし、団信に加入できなかったからといって、すぐに住宅ローンをあきらめる必要はありません。
昨今では持病がある人でも加入できる「ワイド団信」や、団信への加入が必須ではない「フラット35」�といった選択肢も増えています。
団信に加入できない事情がある場合は、団信を必要としない方法やローン商品を検討すると良いでしょう。
団信の審査で見られる主な項目
住宅ローンを利用する際「団体信用生命保険(団信)」の審査を受けることになります。団信の審査では、民間の生命保険と同様に厳しい審査が行われるため、健康状態や病歴によっては加入が難しくなるケースもあります。
団信の審査では、現在の健康状態だけでなく過去の病歴、診断の有無、服薬・通院状況などを総合的にチェックされます。
以下では、団信の審査でみられる主な項目について解説します。
健康状態
団信の加入時には、告知書と呼ばれる健康状態の申告書を提出します。告知書には主に、以下のような内容を記載することになります。
- 医師の診療・治療・検査を受けている最中か
- 常用している薬があるか
- 健康診断で異常を指摘されたことがあるか
- 手術歴や入院歴があるか
告知書を作成する際は、必ず正確な情報を記載してください。たとえ自分では問題ないと思っていても、後々のトラブルに繋がる恐れがあります。
▼関連記事:住宅ローンの利用時に健康診断は必須?告知書の内容・注意点を解説
既往歴
既往歴(きおうれき)とは、過去にかかった病気や怪我の記録のことです。
団信では現在の健康状態に加えて、過去の病歴や治療歴も重視されます。仮に完治しているかが分からない病気や、再発のリスクが高い病気があると審査が厳しくなりがちです。
例えば、過去にがん、心筋梗塞、脳卒中などにかかっていた事があり、現在も継続して通院している場合は加入を断られることがあります。
完治済みか進行中か
団信の審査では、申込者の現在の状態が判断材料になります。過去に病気にかかっていたとしても、すでに完治していて医師の診断書などでも「治癒済み」と証明できれば、審査に通過できる可能性は高くなります。
一方で、以下のような状態は「進行中」「リスクあり」と判断されやすくなるため注意が必要です。
- 現在も通院している
- 処方薬を服用し続けている
- 主治医から「寛解」「経過観察中」とされている
- 再発の恐れがある
例えば、病気の治療を終えて経過観察中だったとしても、症状が一時的に消えている寛解(かんかい)の状態では完治済みにならない可能性があります。
住宅ローンが組めない可能性がある病気・持病
団体信用生命保険(団信)の審査では、病気だからといって必ず団信に加入できないというわけではありません。
しかし、以下のような病気・持病があると、団信に加入することができず住宅ローンを組めない恐れがあります。
| カテゴリ | 代表的な病名 |
| 精神疾患 | うつ病 てんかん 統合失調症など |
| 循環器系疾患 | 狭心症 心筋梗塞 不整脈 高血圧症(重度の場合)など |
| 脳血管系疾患 | 脳卒中 脳梗塞 脳出血 くも膜下出血)など |
| 悪性新生物 | がん(悪性腫瘍) |
| 糖尿病 | 糖尿病 (合併症がある、服薬中など状況による) |
| 肝疾患 | 肝炎(B型、C型肝炎など) 肝硬変など |
| 腎疾患 | 慢性腎臓病 腎不全など |
| その他 | クローン病 潰瘍性大腸炎 全身性エリテマトーデス 関節リウマチなど |
虚偽の申告は告知��義務違反になる
団体信用生命保険(団信)に申し込む際には、必ず「告知書」という書類を提出する必要があります。
告知書は、申込者の健康状態を保険会社に申告することを目的としています。告知書の内容を材料として、申込者が団信に加入できるかを判断します。
団信の告知書では、以下のような質問が設けられているのが一般的です。
- 現在、医師の診察や治療を受けているか
- 過去〇年以内に手術や入院をしたことがあるか
- 常用している薬があるか
- 健康診断で異常を指摘されたことがあるか
これらの質問に対して嘘偽りを記載したり、症状が軽いからといって勝手に省略すると「告知義務違反」となる可能性があります。
虚偽申告の具体例
健康状態に問題があると、団信への加入は難しくなります。これを避けるために、次のような虚偽の申告をするケースは少なくありません。
- 持病があるにもかかわらず「通院なし」と記載した
- 薬を服用しているが薬の名前や治療内容を記載しなかった
- 精神疾患の診断を受けたが落ち着いているからと申告しなかった
- 健康診断で異常値を指摘されたが自覚症状がなかったため無視した
- 経過観察中なのに「完治」と判断して申告を省略した
こういった虚偽申告は、たとえ悪気がなかったとしても告知義務違反にあたります。後々のトラブルを避けるためにも、絶対に虚偽の申告はやめましょう。
告知義務違反が発覚すると
健康状態に問題があるからといって、告知書に嘘の情報を記載すると、以下のような重大な事態を引き起こす可能性があります。
- 団�信契約の解除や保険金の不払い
- 住宅ローンの一括返済を求められる
- 信用が失われてローンが組みづらくなる
告知義務違反が発覚した場合、保険会社は団信の契約を解除することができます。契約を解除されると、それまで支払った保険料は返還されず保険金も受け取れません。
さらに金融機関によっては、団信の解約を理由に住宅ローンの一括返済を求めてくる可能性があります。
借主に万が一の事態が起きた際に保険金が支払われないと、住宅ローンの残りを遺族が引き継ぐことになるでしょう。
もし、一括返済に応じられない場合、自宅を手放すことになるかもしれません。
虚偽の申告をして団信に加入できたとしても、家族に負担を強いる結果になるだけです。
故意に虚偽の申告をした場合はもちろんですが「うっかり忘れていた」「勘違いしていた」といった場合でも、告知義務違反とみなされかねません。
告知書は、自分の健康状態や病歴を正確に申告する書類です。虚偽の申告をすると、自分だけでなく家族にも悪影響を与えることを覚えておきましょう。
団信に入れない場合の対策
住宅ローンを契約する条件として、団体信用生命保険(団信)の加入を必須としている金融機関がほとんどです。病気や持病があると団信に加入できない可能性があります。
しかし、団信に入れないからといって、住宅ローンが組めないというわけではありません。
近年では、持病がある人や健康に不安がある人でも住宅ローンを組めるように、様々なローン商品が用意されています。
以下では、団信に加入できない場合の対策を紹介します。
金融機関や保険会社に相談する
健康状態に不安があると「団信に加入できないかも…」と不安に感じるもの。そこで申告書に虚偽の申告をすると、後々取り返しのつかないトラブルを引き起こすかもしれません。
住宅ローンや団信は、専門的な知識が必要不可欠です。だからこそ、団信の加入に不安がある場合は、まず専門の担当者に相談しましょう。
団信の審査基準は、金融機関や保険会社によって異なります。例えば、A銀行で団信に通らなかったとしても、B銀行なら通過するかもしれません。
自分だけでは判断が難しいことでも、専門家の目線で客観的に評価してもらうことで解決の糸口が見つかる可能性は高いのです。
団信の加入に不安を感じたら、早めの相談を心がけましょう。また、一社だけに絞らず、複数の金融機関に相談して内容を比較してください。
その中から、自分に最も適したローン商品を選ぶことをお勧めします。
ワイド団信を扱う銀行を探す
病気や持病で通常の団信に加入できない場合に、強い味方となるのが「ワイド団信」です。
ワイド団信(引受基準緩和型団体信用生命保険)には、以下のような特徴があります。
- 通常の団信よりも健康状態に関する審査が緩やか
- 高血圧、糖尿病、軽度のうつ病などがあっても加入できる可能性がある
- 保険金の保障範囲は通常の団信と同じ扱い
ただし、持病や病気のリスクがある人向けなので、金利は0.3%〜0.4%程度上乗せされる点がデメリットになります。
通常の住宅ローン金利が年1.0%だとすれば、ワイド団信を利用することで金利は年1.2%〜1.3%程度になります。
ワイド団信なら病気や持病があっても団信に加入できますが、返済総額に多少なりとも影響がある点を加味して慎重に検討しましょう。
団信が不要なローン商品を選ぶ
団信への加入が住宅ローン契約の必須条件となっている金融機関は多いものの、すべてではありません。中には団信への加入が任意となっている住宅ローン商品も存在します。
代表的なのが、住宅金融支援機構と民間金融機関が連携して提供する「フラット35」です。フラット35は団信の加入が任意なので、健康状態に不安がある人や、団信の審査に落ちた人でも住宅ローンを組むことができます。
しかし、借主の死亡や高度障害など万が一の事態が起きても、保険金が支払われることはありません。家族にローンが残ってしまうため、事前に他の生命保険などを契約しておきましょう。
▼関連記事:団信なしでフラット35を利用しても大丈夫?
収入合算の連帯保証型を活用する
団体信用生命保険(団信)の審査に通らなかったとしても「収入合算」という方法を活用すれば、住宅ローンを組むことが可能です。
収入合算には「連帯保証型」と「連帯債務型」の2つがあります。このうち連帯保証型は、配偶者のうち一方が主債務者となり、もう一方が連帯保証人として収入を合算する形になります。
連帯保証型の最大のメリットは、団信への加入が必要なのは主債務者のみという点です。
つまり、配偶者のうち団信の審査に通らなかった方が連帯保証人になり、健康状態に問題のない方が主債務者として団信に加入すれば、協力して返済を進めることができます。
まとめ
最後までお読みいただきありがとうございます。今回は、住宅ローンが組めない持病や病気について解説しました。
住宅ローンを組む際に欠かせない団体信用生命保険(団信)は、健康状態に不安のある人にとって高いハードルになることがあります。
持病や過去の病歴によっては団信の審査に通らず、結果として住宅ローンを組めないといった事態も起こり得ます。
ですが、団信の申し込みで虚偽の申告をするのは絶対に止めておきましょう。
虚偽の申告をすると保険金を支払ってもらえなかったり、ローンの一括返済を求められるといった深刻な事態を招く恐れがあります。
病気や持病があると団信の審査に通りづらくなるのは事実です。しかし、団信に加入できないからといって、マイホームの購入を諦める必要はありません。
近年では、ワイド団信や団信に加入しなくても組めるローン商品、収入合算の活用など、様々な選��択肢が用意されています。
健康上の理由で悩んでいる人は、まず専門の担当者に相談してみてください。プロの意見を参考にすることで、理想のマイホームを購入することは十分に可能です。