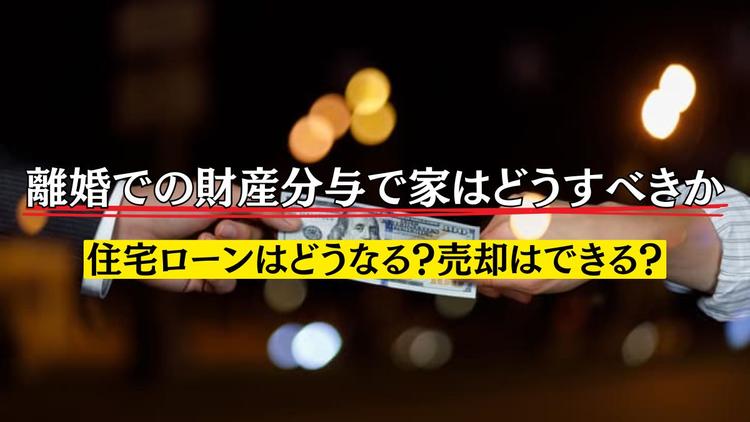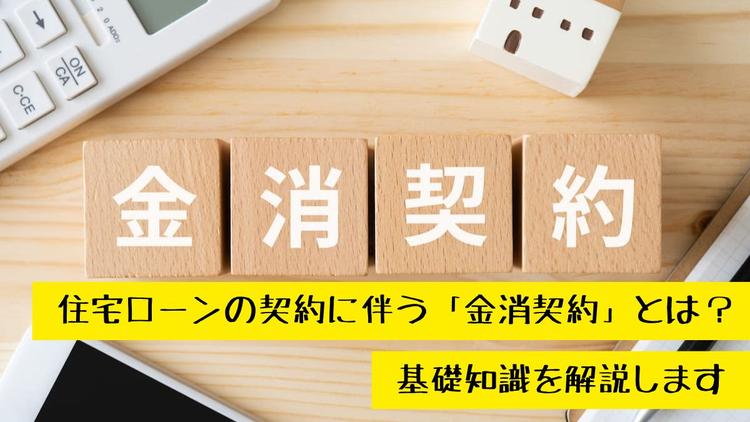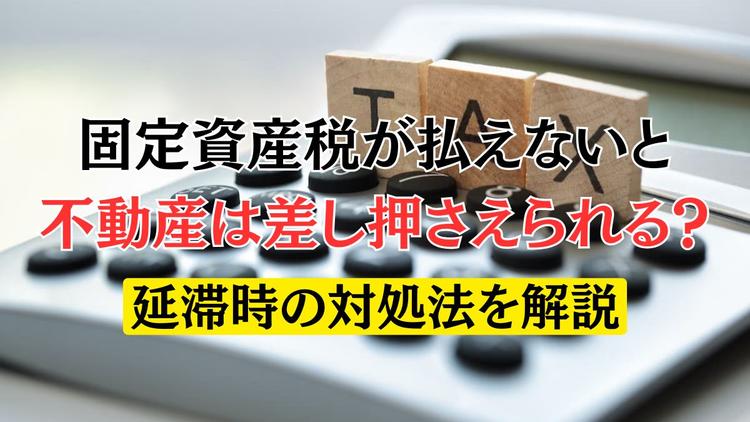新居を購入すると、家具や引越し費用、リフォーム費用、税金などお金がかかるものです。
これらの費用を住宅ローンに上乗せできれば資金に余裕ができますが、上乗せできるかは費用や金融機関によって異なります。
また、上乗せにはデメリットも生じるので慎重な判断が必要です。
この記事では、住宅ローンに上乗せできるものや上乗せするメリット・デメリットなどを分かりやすく解説します。
住宅ローンに本体価格以外で上乗せできる諸費用は?
住宅ローンは、家の購入や新築のために利用できるローンです。
基本的には購入・新築する家の本体価格や工事費に利用できますが、それ以外でも家を所有するための費用であれば住宅ローンに上乗せできる可能性があります。
ここでは、住宅ローンに上乗せできる主な諸費用と、上乗せできない諸費用について解説します。
なお、上乗せできる費用は金融機関やローン商品によって異なるので、実際に検討する際にはしっかり確認することが大切です。
上乗せできる諸費用
主な上乗せできる諸費用は以下のとおりです。
- 住宅ローン手数料・保証料
- 火災保険料
- 仲介手数料
- 印紙税
- 抵当権設定関連費用
住宅購入時には、本体価格以外にもさまざまな諸費用が発生します。
たとえば、住宅ローンを組むための事務手数料や保証料、保険料、家を所有したときの不動産取得税や登録免許税などです。
一般的に、住宅を所有する際の諸費用は、購入価格の5~10%ほどといわれているので、これらの費用をどう用意するかを事前に計画する必要があります。
住宅ローンに組み込めるかどうかによっても資金計画が大きく変わってくるので、事前に金融機関に確認しましょう。
リフォーム費用も上乗せできる
中古住宅を購入する際に、リフォームを検討する方もいるでしょう。
リフォーム費用に関しては、組み込める金融機関が多くあります。
ただし、住宅購入時やすでに住宅ローンを完済しているケースで組めるのが一般的です。
住宅ローン返済中の追加融資では利用できないケースがほとんどなので、注意しましょう。
住宅ローンにリフォーム費用を上乗せできない場合、以下の方法での対応が検討できます。
- 自己資金
- リフォーム一体型住宅ローン
- リフォームローン
自己資金で対応できない場合、物件の価格+リフォーム費用で借入できるリフォーム一体型住宅ローンか、住宅ローンとは別にリフォームローンを利用する方法があります。
なお、住宅ローンに上乗せする場合や別のローンを組む場合でも、基本的に申込時にリフォーム費用の見積もりが必要です。
物件購入から住宅ローンの申し込みまでに工事内容を決める必要があるので、スケジュール管理には気を付けましょう。
▼関連記事:住宅ローンの新規申し込み・借り換えでリフォーム行う際の流れ
上乗せできない諸費用
住宅購入に関係のない借金返済のための資金や、生活資金などは上乗せできません。
また、住宅購入に関する費用でも、不動産取得税や引越費用、家具購入費用は上乗せできない��金融機関が多いです。
ただし、近年は家具購入費用なども組み込める金融機関が増えています。
たとえば、みずほ銀行の住宅ローンでは、引越費用や修繕積立金、管理準備金、水道利用加入金の上乗せが可能です1。
金融機関によって対応が大きく異なるので、上乗せできる金融機関を探してみるのもよいでしょう。
住宅ローンに諸費用やリフォーム費用を上乗せするメリット
住宅ローンに諸費用やリフォーム費用を上乗せするメリットは、以下の3つです。
- 低金利で借りられる
- 住宅ローン控除の対象になる
- 手元に資金を残せる
それぞれ見ていきましょう。
低金利で借りられる
住宅ローンの金利は、他のローン商品に比べて低いのが特徴です。
例えば、フラット35の2025年2月最頻金利は1.890%で、変動金利の場合、0.3~0.5%前後の金融機関が多いでしょう2。
諸経費やリフォーム費用については、諸経費ローンやリフォームローンを検討する方法もありますが、これらは住宅ローンの金利より高いものがほとんどです。
個人向けのフリーローンともなれば、年利10%を超えるケースも珍しくありません。
諸経費を住宅ローンに上乗せすることで、別々のローンを組むよりも返済負担を抑えやすくなります。
また、返済の窓口を1本化できるため、口座残高が足りなくて引き落としされず、支払いが遅延してしまうなどのミスも防ぎやすいでしょう。
住宅ローン控除の対象になる
住宅ローン控除とは、住宅ローン残高に応じて一定額を所得税、住民税から控除できる税制優遇措置です。
住宅ローン控除は年末時点の残高で控除額が決まるので、諸経費まで組み込んで残高が多くなれば控除額も大きくなります。
控除額が大きくなることでより多くの所得税の還元が見込めるため、トータルの負担の軽減にもつながるでしょう。
手元に資金を残せる
諸費用の目安は購入額の5~10%となるので、自己資金で支払うと手元資金が大きく減ってしまうという方も多いでしょう。
たとえば、3,000万円で家を購入した際の諸費用の目安は150~300万円です。
これを住宅ローンに上乗せできるなら、その分自己資金を手元に残せます。
家は購入後にも修繕費や固定資産税などさまざまな費用が発生するものです。
また、病気やケガで急に収入が減少し、住宅ローンの支払いが厳しくなる事態に陥る可能性もあるでしょう。
ある程度まとまった資金を手元に残しておけば、新居購入後も安心して生活しやすくなります。
住宅ローンに諸費用やリフォーム費用を上乗せするデメリット
諸費用やリフォーム費用を住宅ローンに上乗せすると、返済額が大きくなるなどのデメリットも生じます。
そのため、デメリットまで理解したうえで、上乗せするかの判断が必要です。
上乗せするデメリットには以下の3つが挙げられます。
- 借入期間が長いと総返済額が大きくなる
- 借入額が大きくなると審査に落ちる可能性が高くなる
- すべての費用を上乗せできるわけではない
それぞれ見ていきましょう。
借入期間が長いと総返済額が大きくなる
諸費用やリフォーム費用を上乗せすれば、借入額がアップするため返済期間か毎月の返済額が増えます。
たとえば、以下のケースで返済額をシミュレーションしてみましょう。
- 住宅購入額:3,000万円
- 諸費用:300万円
- 住宅ローンの条件:金利1.0%
借入期間35年で組んだときの返済額は以下のようになります。
| 毎月の返済額 | 返済総額 | |
| 上乗せしない(借入額3,000万円) | 84,685円 | 35,567,700円 |
| 上乗せする(借入額3,300万円) | 93,154円 | 39,124,680円 |
また、返済期間を30年にしたときの返済額は以下のとおりです。
| 毎月の返済額 | 返済総額 | |
| 上乗せしない(借入額3,000万円) | 96,491円 | 34,736,760円 |
| 上乗せする(借��入額3,300万円) | 106,141円 | 38,210,760円 |
上記のように、借入額がアップすれば毎月の返済額や返済総額の負担は増えます。
一方で、300万円を上乗せしない場合、返済期間の短縮も検討しやすくなり、結果的に返済総額を軽減することも可能です。
借入額を検討する際には、長期的な返済シミュレーションを行い慎重に検討しましょう。
こちらのローンシミュレーターでは、借入額、頭金、金利、借入期間に任意の数値を入力して、月々の返済額と利息を含めた総返済額を簡単に確認できます。
シミュレーションの際に活用してみてくださいね。
借入額が大きくなると審査に落ちる可能性が高くなる
借入額が大きくなることで、審査に不利になりやすい点にも注意が必要です。
住宅ローンで借入できる金額は、年収に対する年間の返済額の割合である返済比率が大きく影響します。
一般的に、返済比率が30~35%以下であることが審査通過の目安です。
たとえば、年収400万円で年間の返済額が120万円の場合、返済比率は30%となり基準内に収まります。
一方、諸費用を含めて返済額が年間140万円にアップすると、返済比率は35%に達し、審査で不利になる恐れがあるのです。
全ての費用を上乗せできるわけではない
諸費用やリフォーム費用を上乗せしたい場合でも、すべての費用を上乗せできるわけではありません。
上乗せできる費用は、金融機関やローン商品ごとに異なります。
さらに、項目によっても条件があり、実際にかかった費用すべてを上乗せできないケースもあるでしょう。
まずは、金融機関の条件をチェックし、どこまで上乗せできるか確認したうえで資金計画を立てることが重要です。
家の購入で失敗しない資金計画を立てるためのポイント
家は人生で最も高い買い物といわれるように、購入に際して大きな資金が動きます。
資金計画で失敗してしまうと、希望の家が買えなかったり、返済できないなど大きなダメージになりかねないため、慎重な資金計画が求められます。
資金計画を立てる際には、以下の3つのポイントを意識しておきましょう。
- 借入可能額=安心して返済できる借入額ではない
- 住宅ローンの金利タイプ別の特徴を理解する
- 手元に現金を残すと安定しやすい
それぞれ解説します。
借入可能額=安心して返済できる借入額ではない
住宅ローンは年収などをもとに、金融機関が借入可能額を算出します。
ただし、借入可能額は借入できる額であり、返済しやすい額ではない点に注意が必要です。
たとえば、返済比率で借入可能額を見た場合を考えてみましょう。
返済比率の上限を35%とした場合、年収400万円であれば年間返済額が140万円まで借入可能です。
年間返済額140万円なら、毎月の返済額は約11.7万円となり、年収400万円なら月収約33.4万円となります。
しかし、年収400万円の手取りは約300~340万円程が目安になるため、手取り300万円であれば毎月の手取り収入は25万円になります。
25万円の手取りから11.7万円の住宅ローンの返済が厳しいかは他の支出にもよりますが、少なくない額であるため、慎重なシミュレーションが必要になるでしょう。
また、マンションの場合は管理費・修繕積立金の支出が毎月発生し、一定期間が経過するとこれらの�費用が増加する可能性がある点も考慮しなければいけません。
とはいえ、実際には借りる人のライフスタイルや家族構成、お金に対する考え方などによって理想の返済額は大きく異なります。
借入できる額ではなく、長期間無理なく返済できる額はいくらかを考えてみましょう。
必要に応じて、FPなどの専門家に相談するのもおすすめです。
▼関連記事:住宅ローンの返済が苦しくならないための確認事項
住宅ローンの金利タイプ別の特徴を理解する
住宅ローンの金利タイプは、以下の3つです。
- 全期間固定金利:借入れ時点で金利が決まり返済期間中ずっと変わらない
- 変動金利:定期的に金利が見直される
- 固定期間選択型金利:一定期間が固定期間となり以降は変動金利か固定金利になる
金利タイプごとにメリット・デメリットは異なり、返済額の大きな違いにもつながるので、特徴を踏まえて適切なタイプを選ぶ必要があります。
金利タイプ別のメリット・デメリットは以下のとおりです。
| 金利タイプ | メリット | デメリット |
| 全期間固定金利 | ・金利上昇リスクを避けられる ・返済計画が立てやすい | ・金利が高い ・金利が下がっても恩恵を受けられない |
| 変動金利 | ・金利が最も低い ・金利が下がれば返済額の軽減につながる | ・金利上昇リスクがある ・返済計画が立てにくい |
| 固定期間選択型金利 | ・一定期間の返済を安定させられる ・固定期間終了後に金利下がれば返済の負担を減らせる | ・固定期間終了後に返済額がアップするリスクがある ・変動金利になると金利上昇リスクがある |
固定金利は金利上昇のリスクを避けられますが、他の金利タイプよりも金利が高く、返済の負担が大きくなりがちです。
一方、変動金利は金利が低く返済の負担を軽減できる可能性が�ある反面、金利上昇リスクに備える必要があります。
2025年現在で金利は上昇傾向にあり、以降の金利がどうなるかの正確な見通しはできません。
一般的に変動金利の上昇より先に固定金利が上昇するため、「今は変動金利で住宅ローンを組み、金利が上がったら固定金利に借り換える」という計画では失敗しやすくなります。
どの金利プランが適しているかは、資金状況やリスクへの備え、希望の返済プランによって変わるものです。
長期的なシミュレーションをもとに、自分に合った金利プランの選択やリスク対策をするようにしましょう。
▼関連記事:変動金利は一気に上がる?
手元に現金を残すと安定しやすい
住宅購入後の急な支出や収入減少に備えて、手元にある程度現金を残すのも大切です。
生活防衛費として、月の支出の6倍ほどの現金があれば安心といわれています。
手元の現金をすべて頭金に回してしまうと、万が一の際に対応できないリスクがあるので注意しましょう。
ただし、頭金の額が少ないと借入額が大きくなり、返済の負担が増えるといったリスクもあります。
頭金と手元に残す現金のバランスは資金状況などによって異なるため、FPなどプロに相談するとよいでしょう。
住宅ローンに上乗せできる諸費用に関するよくある質問
最後に、住宅ローンに上乗せできる諸費用に関するよくある質問をみてきましょう。
借金500万を住宅ローンに上乗せできる?
基本的に住宅に関する費用以外は住宅ローンに上乗せできない�ため、借金の返済に充てることはできません。
ただし、ろうきんが提供する「住宅プラス500」であれば、住宅ローンの最高500万円まで上乗せでき、500万円を借金の返済に充てることが可能です。
また、他の金融機関でも借金返済に充てられるプランを提供している場合があるので、具体的なプランについては金融機関に確認するとよいでしょう。
家具代金で住宅ローンを多めに借りることはできる?
家具代金を住宅ローンに組み込めるかは金融機関、ローン商品によって異なります。
注文住宅で造作棚を設ける場合は組み込める可能性が高いですが、購入のケースでは購入できる種類や領収書の提出など制限が多いのが一般的です。
住宅ローンのオーバーローンがバレたらどうなる?
オーバーローンとは、住宅の価格以上に住宅ローンを借りることです。
着工後に工事費が減少したり、登記費用が安く収まった場合などでローンが余るケースがあります。
余ったお金を本来の目的以外に使うと、規約違反になる恐れがあるので注意しましょう。
規約違反になると一括返済を求められたり、金利の優遇が解除されるリスクがあります。
オーバーローンでお金が余った場合は、金融機関に正直に相談するようにしましょう。
なお、最初からお金を余らせる目的でオーバーローンを組むことは禁止されており、発覚すると一括返済を求められる可能性があります。
まとめ
住宅ローンには、住宅取得に関する諸費用やリフォーム費用を上乗せできる可能性があります。
諸費用を上乗せすることで、低金利が適用でき手元資金を減らすリスクも避けられます。
しかし、諸費用の上乗せは借入額アップによる、返済額増加、審査落ちのリスクもあるので、上乗せするかは慎重な判断が必要です。
返済シミュレーションは入念に行い、満足いく家の購入と無理のない返済ができるようにしましょう。