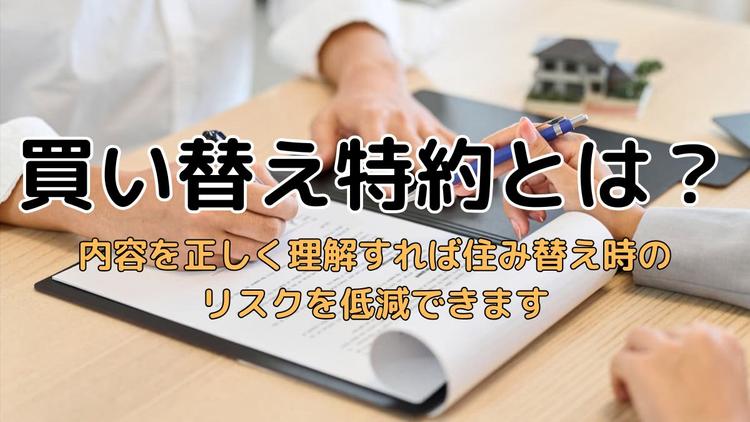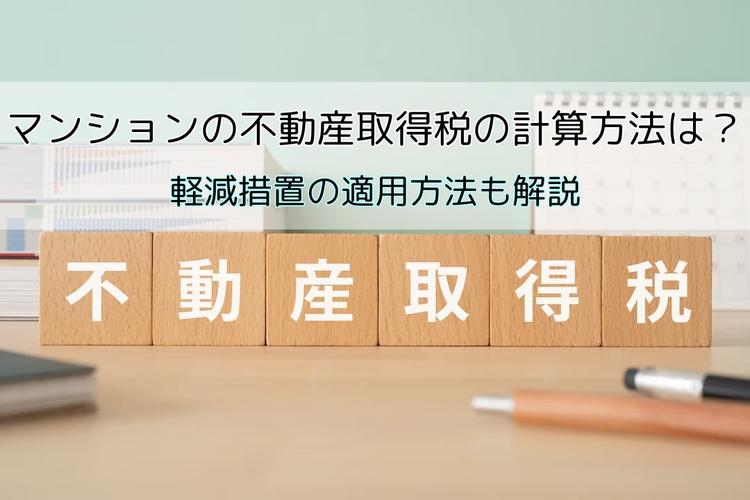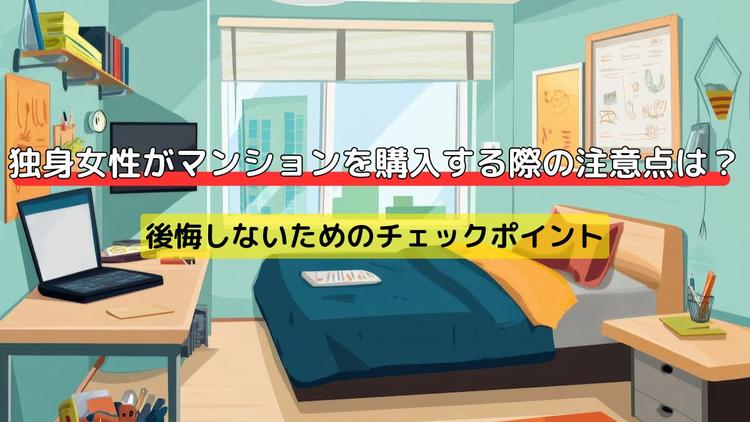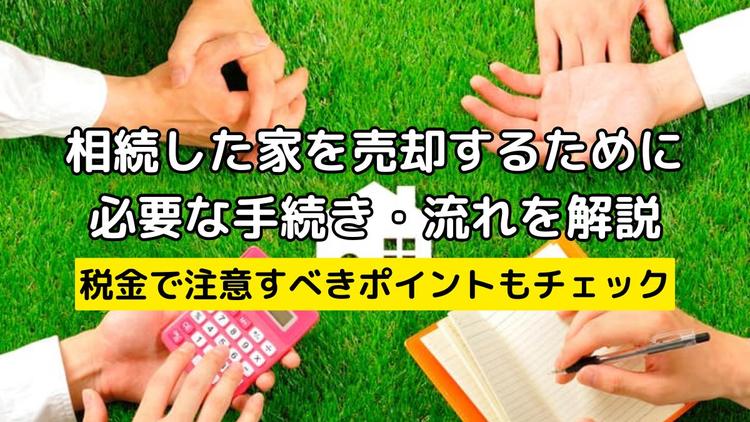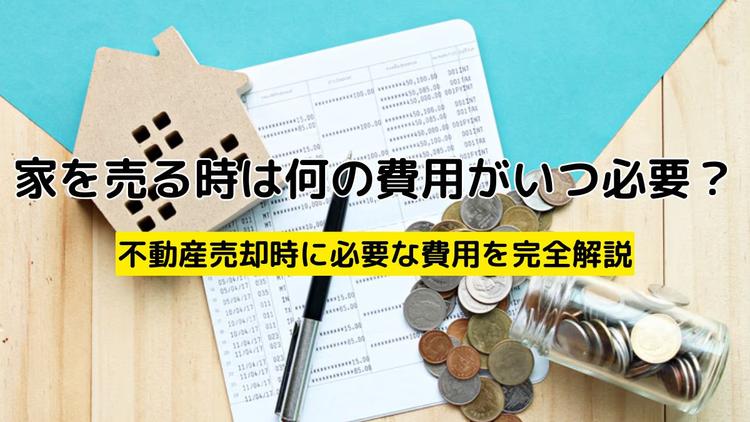「マンションに地震保険は必要?」「管理組合が加入しているからいらないのでは?」
マンションは地震に強いから保険は不要と考えている方もいるでしょうが、万が一に備えて地震保険への加入をおすすめします。
とはいえ、地震保険に加入するとなると毎月の保険料の負担が気になる方も多いでしょう。
そこで、この記事ではマンションの地震保険の補償内容や範囲・保険料相場などを分かりやすく解説します。
地震に備え安心して長くマンションで暮らすために、この記事を参考にしてください。
マンションに地震保険は必要?
日本の建物は耐震性が高く、とくに近年のマンションは耐震性に優れています。
そのため、マンションなら地震が来ても大丈夫と考えている方もいるでしょう。
しかし、いくら耐震性が高くても、地震による被害が絶対に出ないという保証はありません。
地震大国といわれる日本では、いつ・どこで大きな地震が起きても不思議ではない以上、マンションであっても地震への備えを万全にしておくことが大切です。
地震への備えの1つとなるのが、地震保険です。
まずは、マンションの地震保険の基本を確認していきましょう。
そもそも地震保険とは
地震保険とは、地震や噴火またこれらが原因で起こった津波による損害を補償する保険です。
具体的には、地震・噴火・津波による火災や損壊・埋没・流失による建物や家財の損害を補償します。
火災や風水害・落雷による損害は火災保険で補償されますが、火災保険では地震等による損害やこれらを原因とする火災の損害は補償されません。
そのため、地震の損害に備えるためには地震保険への加入が必要です。
なお、地震保険は火災保険とセットでしか加入できません。
地震保険単体では加入できないので、火災保険加入時に地震保険も付帯する必要があるのです。
ただ、火災保険に加入していれば後から地震保険を付帯することはできます。
すでに火災保険に加入していて地震保険を付帯していない場合でも、地震保険に新たに加入できます。備えに不安がある方はぜひ加入を検討してください。
共用部分は管理組合が加入するのが一般的
マンションで地震保険の対象となるのは、「専有部分」「共有部分」「家財」です。
このうち、入居者が加入しないといけないのは専有部分と家財になります。
専有部分と共有部分の違い
専有部分とは、入居者の住戸部分を指します。
一方、共有部分は入居者全員で利用するエレベーターやエントランス、建物全体を支える骨組みの躯体部分など、専有部分以外の場所です。
家財は、建物ではなく入居者が所有する家具などの動かせる財産を指します。
共有部分の保険は管理組合��が加入している
共有部分の火災保険・地震保険については管理組合が加入するのが一般的です。
共有部分については入居者個人で加入できないため、管理組合がどのような保険に加入しているかを把握するようにしましょう。
専有部分・家財については、入居者個人での加入が必要です。
地震保険に加入せずに専有部分に損害が発生しても、マンションが加入している保険で補償されることはありません。
さらに、専有部分(建物)の地震保険に加入していても家財の地震保険に加入していなければ、家財の保障は受けられないので注意しましょう。
専有部分の建物や家財の損害に備えるためには、自分で必要に応じて火災保険・地震保険に加入する必要があるのです。
マンション入居者の地震保険の加入率
財務省の報告によると、マンションの専有部分における地震保険付帯率は2021年度で74.9%です1。
2012年度の70.9%から横ばい・やや増加で推移しており、多くの入居者が加入していることが分かります。
一方、共有部分の地震保険付帯率は2012年度の35.4%から2021年度の49.0%と右肩上がりに上昇しています。
上昇しているとはいえ、まだ半数の共有部分で地震保険に加入していないことが分かります。
そのため、自分のマンションの共有部分の地震保険についてもしっかり確認しておくようにしましょう。
マンションの地震保険の支払い事例
ここでは、実際に発生したマンションの地震保険の支払い事例や未加入による事例をみていきましょう2。
【加入により補償を受けられたケース:仙台市のマンション】
東日本大震災では、マンションが「全壊」判定となる大きな被害を受けた例があります。
しかし、このマンションでは地震保険への加入と修繕積立金が十分にあったため、マンションの取り壊し費用の捻出ができ、さらに残額は全世帯に配布され、入居者の生活再建に大きく役立ちました。
【地震保険未加入による問題となったケース:神戸市のマンション】
1995年に発生した阪神淡路大震災でマンションが半壊したケースでは、地震保険未加入により損害の補償が受けられていません。
さらに、修繕積立金も不十分であったことから修繕資源が足りず、修繕するには1戸当たり数百万円の臨時徴収が必要になりました。
しかし、高齢者と若者世帯が混在していたことで修繕費徴収への意見がまとまらず、被災後何年にも渡って半壊状態で居住することになったのです。
マンションでは、専有部分の地震保�険加入だけでなく共有部分の加入状況・修繕積立金の徴収状況も再建に大きく関わってくる点は覚えておきましょう。
地震保険の補償内容と補償範囲
ここでは、地震保険の詳しい補償内容と補償範囲をみていきましょう。
マンションの地震保険の適用範囲は、以下の3つに分かれます。
- 共有部分:エントランスや共有施設・廊下・外壁・各住居の玄関ドアや窓など
- 専有部分:各住居の室内の壁や柱・床・間仕切壁など
- 家財:家具・家電など(30万円を超える貴金属や骨とう品などは除く)
上記のうち、入居者が加入するのは専有部分と家財です。
また、適用範囲は加入する火災保険の適用範囲内となります。
例えば、火災保険が専有部分のみであれば、地震保険で家財に加入することはできません。
一方、火災保険で専有部分・家財に加入していれば、地震保険ではどちらか一方を選ぶことが可能です。
地震保険の損害認定区分
地震保険では実際の損害額に対して補償を受けられるのではなく、地震の損害程度に応じて保険金が支払われる仕組みになっています。
損害程度は以下の4段階に分かれます。
| 損害程度 | 支払われる保険金 | 【建物】主要構造部の損害基準 | 【建物】消失・流出した床面積 | 家財 |
| 全壊 | 保険金額の100% | 時価の50%以上 | 延床面積の70%以上 | 時価の80%以上 |
| 大半壊 | 保険��金額の60% | 時価の40%以上 | 延床面積の50%以上 | 時価の60%以上 |
| 小半壊 | 保険金額の30% | 時価の20%以上 | 延床面積の20%以上 | 時価の30%以上 |
| 一部損 | 保険金額の5% | 時価の3%以上 | – | 時価の10%以上 |
仮に、建物の保険金額が3,000万円で大半壊の判定を受ければ、3,000万円×60%=1,800万円の保険金が支払われます。
一方、建物の被害が出ていても一部損以上と判定されなければ、保険金は支払われません。
なお、マンションの場合は1棟全体の損害程度で専有部分の損害程度も判断されます。
ただし、専有部分の損害が全体よりも大きい場合は、個別で判定されるのです。
例えば、全体が大半壊で専有部分が小半壊なら、専有部分も大半壊として保険金を受け取ることが可能です。
反対に、全体が小半壊でも専有部分が大半壊なら、大半壊の保険金を受け取れます。
地震保険金額は火災保険金額の50%まで
地震保険の金額には以下のような上限が設けられています。
- 火災保険金額の30~50%まで
- 上限:建物5,000万円・家財1,000万円
地震保険の保険金額は、火災保険の保険金額の30~50%までと決められています。
仮に、火災保険の保険金が4,000万円なら、地震保険の保険金は1,200万円~2,000万円の範囲でしか契約できません。
さらに、その範囲であっても建物なら5,000万円、家財は1,000万円が上限となるのです。
マンションの地震保険料の相場
地震保険に加入すると、当然ながら保険料の負担が必要になります。
災害への備えをしておきたいところですが、保険料の負担が大きくなると生活費の負担になってしまいます。
ここでは、地震保険料の相場についてみていきましょう。
どの保険会社でも保険料は同じ
地震保険は民間の保険会社が独自に運営しているのではなく、国と民間の保険会社による共同運営です。
公共性の高い保険であるため、どの保険会社で加入しても保険料は変わらないという特徴があります。
ただし、火災保険は保険会社によって補償内容や保険料が異なります。
地震保険は火災保険とセットで加入するため、トータルの保険料は火災保険料分変わってくる点は覚えておきましょう。
建物の所在地と構造で保険料が決まる
地震保険の保険料は、建物の所在地と構造によって以下のように決められています3。
- 所在地:地震発生リスクに応じて都道府県ごとに3区分に分かれる
- 構造:主に鉄骨・コンクリート造りの「イ構造」と木造物件の「ロ構造」の2種類に分かれる
例えば、東京都でイ構造の場合の保険金額1,000万円あたりの保険料は、年間27,500円です。
地震保険料の割引制度
上記を基本保険料として、耐震性能と長期契約による割引を受けることが可能です。
長期契約の保険料は、年間の基本保険料に以下の長期係数を乗じて算出します。
| 期間 | 係数 |
| 2年 | 1.90 |
| 3年 | 2.85 |
| 4年 | 3.75 |
| 5年 | 4.70 |
さらに、耐震性能による以下の割引が適用されます。
| 割引制度 | 割引率(他の割引との重複付加) |
| 免震建築物割引 | 50% |
| 耐震等級割引(耐震等級3) | 50% |
| 耐震等級割引(耐震等級2) | 30% |
| 耐震等級割引(耐震等級1) | 10% |
| 耐震診断割引 | 10% |
| 建築年割引 | 10% |
例えば、東京都のイ構造(年間保険料27,500円)で5年契約すると、保険料は以下のようになります。
さらに、耐震等級が2であれば保険料は以下のとおりです。
なお、上記はあくまで目安です。
具体的な保険料については、保険会社に確認するようにしてください。
結論、マンション入居者は地震保険に加入すべき?
基本的には、マンション入居者は地震保険に加入することをおすすめします。
どんなに耐震性の優れているマンションであっても、地震による被害を受けない保証はありません。
地震による被害を受ける可能性は高くはありませんが、一度でも地震の被害に遭えばその被害は甚大になりかねないものです。
その時に地震保険に加入していなければ、生活への影響は大きくなります。
仮に、建物に被害が出なくでも家財に大きな被害が出るケースもあるでしょう。
地震で火災が発生した場合、地震保険に加入していなければ保険金が下りない
地震で被害に遭わなくても、地震によって火災が起きると火災保険では保障されない点も注意が必要です。
実際、阪神淡路大震災では地震後に起きた火災での被害も甚大なものでした。
また、地震保険は保険金の使い道の用途に制限がないため、マンションの修繕だけでなく生活費や住宅ローン返済などに充てることも可能です。
地震によって住まいや生活に影響が出た際、使用用途の自由なまとまったお金があるのは、地震被害から生活を立て直すうえで大きな支えとなります。
地震保険に加入していなくても利用できる支援制度
なお、地震保険に加入していなくても地震などの自然災害で住宅に損害が出た場合、国による以下の支援を受けることが可能です。
| 制度名 | 被災者生活再建支援制度 |
| 支援金額 | 最大300万円 |
とはいえ、住居や家財に大きな被害が出ている場合、300万円では生活の再建には心もとないでしょう。
より安心して生活したいなら、万が一に備えて地震保険に加入することをおすすめします。
マンションの地震保険に加入すべき人の特徴
基本的には地震保険への加入をおすすめしますが、とくに以下のような人は地震保険に加入すべきといえます。
- もしものときの貯蓄がない人
- 自営業など大地震で仕事を失う可能性がある人
もしものときの貯蓄がない人
貯蓄がないなか地震で大きな被害を受けると、生活の再建が難しくなります。
さらに、住宅ローン残債が大きい場合は、家がない中住宅ローンは残り・貯蓄もないとかなり厳しい状況に陥りかねません。
とくに、マンションを購入した直後は住宅ローン残債が多いうえに頭金などの支出で貯蓄も大きく減少しているので、地震保険で備えておくことをおすすめします。
一般的に、生活防衛費は生活費の半年~1年ほどあれば安心といわれています。
大地震の被害に遭うことを考えれば、それよりも多く貯蓄があった方が安心でしょう。
反対に、それよりも貯蓄が低い場合は地震保険の加入を検討することをおすすめします。
自営業など大地震で仕事を失う可能性がある人
公務員や大企業の社員であれば、地震で会社に大きな被害が出ても給与がゼロになる可能性は低いでしょう。
一方、自営業や個人事業主・フリーランスなどは地震で仕事を失えば収入がゼロになりかねません。
その際、地震保険があれば建物の修繕だけでなく生�活費などにも充てられるため、生活の再建を図りやすくなります。
マンションの地震保険に関するよくある質問
最後に、マンションの地震保険に関するよくある質問をみていきましょう。
マンションの地震保険がいらないといわれる理由とは?
地震保険は住宅の建て直しではなく生活の再建を目的としているため、住宅を建て直せるほどの保険金はおりません。
また、マンションは耐震性が高い反面、損害判定で「一部損」と判定されやすいため、より保険金額が下がるのです。
一方、保険料は年々改定されており値上げ傾向が続いています。
今後も南海トラフ地震のリスクの高まりなどで値上げされる可能性があり、大きな負担となりかねません。
このような保険金の少なさや保険料の負担の大きさにより、マンションの地震保険がいらないといわれてしまうケースがあるのです。
ただし、地震保険が必要かどうかは住んでいるエリアや資産状況などによっても異なります。
プロなどに相談しながら自分のケースで判断するようにしましょう。
マンションで地震保険に加入するデメリット
マンションで地震保険に加入するデメリットしては、「保険料の負担がある」「火災保険への加入も必要」「保険金では建て直しは難しい」といった点が挙げられます。
しかし、地震への備えになる、安心感があるなどのメリットもあるので、両方を比較して検討することが大切です。
まとめ
地震保険に加入することで、万が一地震で建物・家財が損害しても生活再建を目指しやすくなります�。
地震がいつ起きるか分からない日本では、地震保険を検討することをおすすめします。
ただし、保険料は保険会社による違いはありませんが、火災保険とセットで契約する必要があるためトータルの保険料に違いが出る点には注意しましょう。
適切な地震保険に加入し、より安心してマンションでの生活ができるようにしてください。