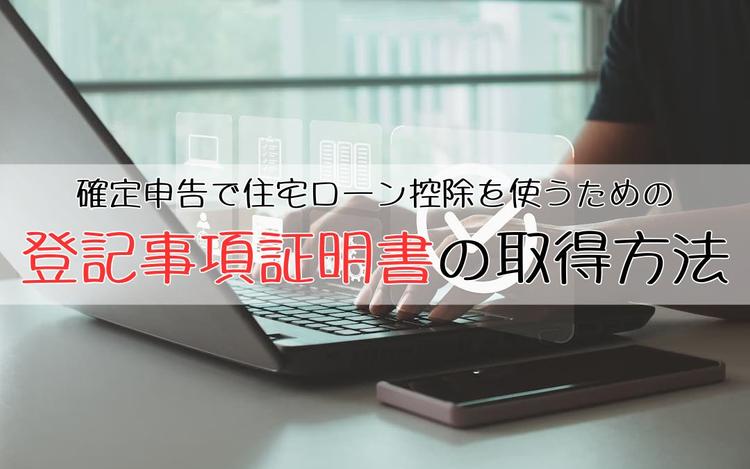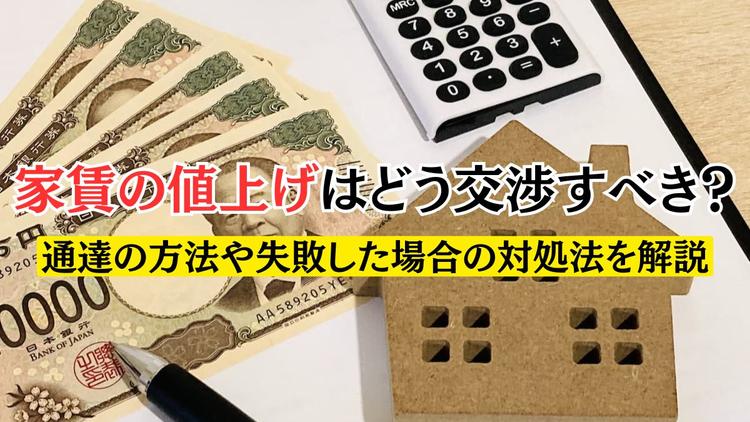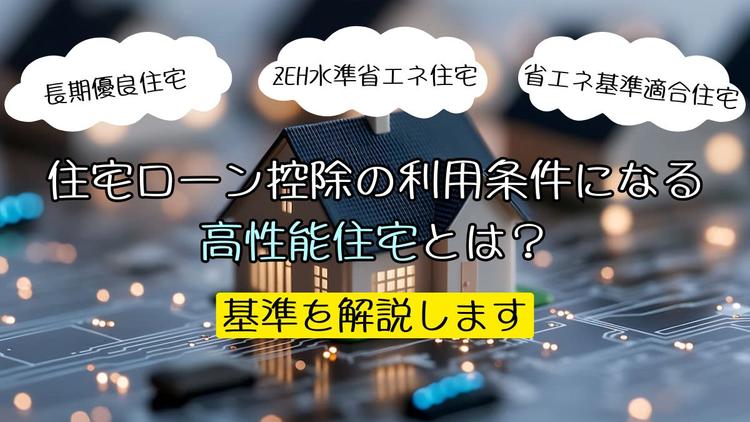住宅ローン控除を適用するためには、確定申告時に登記事項証明書を提出する必要があります。
また、登記事項証明書は、不動産の売買や相続など、さまざまな場面で必要になる書類でもあります。
この記事では、登記事項証明書の概要や種類、取得方法などを分かりやすく解説します。
▼確定申告で必要な登記事項証明書のまとめ
- 戸建ては全部事項証明書(土地・建物それぞれ)を取得する
- マンションは一部事項証明書を取得する
- コピーではなく原本を提出するのが無難
- e-Taxで電子申告する場合は、初年度の申告であっても不動産番号の入力で問題ないため、登記情報提供サービスが便利(平日日中に利用可能)
- 登記事項証明書の取得はオンライン、窓口、郵送で可能
- 2025年の確定申告は3月17日(月)までだが、還付申告となる場合は期間を過ぎても5年間は遡って請求できる(ただし、雑収入・事業収入等があって合算して納付となる場合は、延滞税が加算される可能性がある)
登記事項証明書とは
登記事項証明書とは、法務局の登記簿に記録されている内容を証明する書類です。
不動産に関する登記事項証明書には、以下のような項目が記載されています。
- 所在地・地番・地目
- 不動産の構造・床面積
- 所有者の氏名・住所
- 抵当権などの設定されている権利
- 過去の履歴
登記事項証明書を見れば、その不動産の概要、所有者、過去の取引履歴などがすべて分かります。
なお、登記簿の記録を証明する書類に、かつて「登記簿謄本」と呼ばれていた、登記簿を複写(コピー)したものがあります。
以前は紙で記録・管理されており、その写しを交付していたため登記簿謄本と呼ばれています。
しかし、現在の登記簿は電子データで管理されており、内容の証明書はデータを印刷して交付されるため、登記事項証明と呼ばれているのです。
登記事項証明と登記簿謄本は記載されている内容は同じですが、登記簿の管理方法や出力が異なってきます。
登記簿謄本が使用されていた時期が長いため、現在でも慣習的に登記簿謄本と呼ばれますが、登記事項証明書を指しているケースがほとんどです。
登記事項証明書の種類
登記事項証明書は、登記内容を証明した書類の総称であり、細かくは以下の4種類があります。
| 登記事項証明書の種類 | 概要 |
| 全部事項証明書 | 登記簿の記録がすべて記された書類 |
| 一部事項証明書 | 一部の記録のみが記された書類 |
| 現在事項証明書 | 現在の状況だけ記した書類 |
| 閉鎖事項証明書 | 閉鎖された登記簿の情報が記された書類 |
利用の目的によって取得すべき書類が異なるので、注意しましょう。
以下でそれぞれ詳しく解説します。
全部事項証明書
全部事項証明書は、登記簿に記録されている登記事項のすべてが記載された書類です。
それまでの所有権移転や抵当権設定・抹消など、その不動産の過去から現在までの情報がすべて網羅されています。
登記事項証明書が必要なケースでは、指定がない限り基本的には全部事項証明書を提出します。
一部事項証明書
一部事項証明書は、登記簿に記載されている内容の一部を抜粋した書類です。
全部事項証明書は過去から現在までのすべてが記載されているため、不動産によっては膨大な数になるケースがあります。
例えば分譲マンションの場合、所有者だけでも数百人に上るケースもあり、全部事情証明書ではページ数が多いだけでなく、必要な情報を読み取るのにも時間がかかります。
一部事項証明書であれば、所有者を自分1人に絞って交付してもらうことが可能です。
現在事項証明書
現在事項証明書は、現在効力がある情報のみを記載した証明書です。
全部事項証明書が、効力のあるなしにかかわらず過去から現在までのすべての登記事項が記載されているのに対して、現在事項証明書の場合、現在に効力がない過去の登記事項は記載されません。
例えば、過去に抵当権を設定していても現在はすでに抹消している場合、現在事項証明書には抵当権は記載されないのです。
過去の取引履歴を見たい場合は全部事項証明書、今誰が所有しているのかだけ知りたい場合は現在事項証明書、というように使い分けるとよいでしょう。
閉鎖事項証明書
閉鎖事項証明書とは、建物を解体したり土地を合筆したりして閉鎖された登記簿の内容を証明した書類です。
たとえば、複数の土地をまとめて1筆の土地にした場合、消滅した地番の登記簿の記録は閉鎖され、全部事項証明書にも記載されません。
そのため、閉鎖された登記簿の情報を見るためには、閉鎖事項証明書が必要になるのです。
過去の土地の利用履歴や所有者の権利関係などをさかのぼりたい、建物を取り壊した記録が欲しいといった場合に利用するケースが多いでしょう。
確定申告で登記事項証明書が必要になるケース
確定申告で登記事項証明書が必要になるのは、以下の3つのケースです。
- 所得税の申告で住宅ローン控除を適用する
- 贈与税を申告する
- 相続税を申告する
所得税の申告で住宅ローン控除を適用する
住宅ローン控除とは、住宅ローンを利用してマイホームを購入した際に、住宅ローン残高に応じた一定額を所得税から控除できる税制優遇措置です。
控除額は住宅を購入した年度や住宅性能によっ��ても異なりますが、年末時点の住宅ローン残高の0.7%を13年間控除できます。
控除適用の1年目に確定申告をする
住宅ローン控除を適用する場合、1年目は確定申告での申請が必要となり、その際に登記事項証明書が必要になります。
登記事項証明書は、住宅ローンを利用した際の抵当権の設定が記録されるため、住宅ローンを利用していることの証明になるのです。
そのため、一戸建であれば全部事項証明書、マンションでは一部事項証明書が必要になります。
なお、2年目以降は登記事項証明書の提出は不要です。
会社員の場合、2年目以降は年末調整で控除の申告が可能
さらに会社員であれば、2年目以降は年末調整で申告できるので、確定申告も必要ありません。
また、e-Taxでの確定申告であれば、初年度の申告であっても不動産番号の入力を登記事項証明書の貼付に代えることができます。
不動産番号とは、法務局が不動産を管理するために登記簿に付加している数字のことです。
不動産番号は登記事項証明書に記載されているだけでなく、法務局の登記情報提供サービスでも調べられます。
贈与税を申告する
贈与税とは、贈与を受けた人に課税される税金です。
贈与税は、1月1日から12月31日までの贈与額が110万円の基礎控除を超えた場合に課税されます。
不動産を贈与された場合も、不動産の評価額が贈与税の対象となるので、課税される場合は申告時に登記事項証明書が必要です。
また、贈与税には控除の特例がいくつか用意されており、不動産に関する特例を適用する際にも登記事項証明書を提出することになります。
その際、一部の特例は不動産番号の入力で対応可能です。
相続税を申告する
不動産を含めた正味の相続財産(プラスの財産からマイナス財産を差し引いた額)が、基礎控除額を超えると相続税が課税されます。
相続税の基礎控除額は、「3,000万円+600万円×法定相続人の人数」です。
相続税の申告をする際、相続財産に不動産が含まれるなら登記事項証明書の提出が必要です。
なお、不動産を相続した場合、相続税の発生に関わらず相続登記をしなければなりません。
相続登記とは、不動産の名義を被相続人(亡くなった人)から相続人に移転する登記手続きです。
この際にも登記事項証明書が必要になります。
登記事項証明書の取得方法
登記事項証明書は、以下の方法で取得できます。
| 取得方法 | 手数料 | 受付時間 |
| 法務局の窓口 | 1通600円 | 平日:8時30分~17時15分 |
| オンライン | 【郵送交付】1通500円 【窓口交付】1通480円 | 平日:8時30分~21時 ※17時15分以降の受付は翌営業日受付となる |
| 郵送 | 1通600円 | – |
法務局の窓口で取得する
まずは法務局の窓口で取得する方法です。
以前は不動産を管轄する法務局でしか取得できませんでしたが、現在は不動産の所在地に関わらずどの法務局でも取得可能です。
そのため、最寄りの法務局に出向いて申請すればその場で取得できます。
取得の際は、交付申請書に手数料分の収入印紙を貼付して申請するだけなので、申請手続きに不安がある方や、すぐに欲しい場合は窓口がおすすめです。
オンラインで取得する
「登記・供託オンライン申請システム」を利用してオンラインで申請することも可能です。
事前に利用者登録は必要ですが、インターネット環境があればいつでも申請できるので、法務局に出向く時間がない人でも気軽に申請できます。
また、他の取得方法に比べて手数料が割安な点もメリットといえます。
オンラインで取得する際の大まかな流れは、以下の通りです。
- 申請者情報登録
- 交付請求手続き
- 手数料の納付
- 受け取り方の選択
- 取得
オンラインで請求するためには、まず住所・氏名・パスワードなどを入力する申請者情報登録が必要です。
申請者を登録したら、交付請求の手続きを行います。
トップページの「かんたん証明書請求」で、不動産種別などの必要事項を入力して請求しましょう。
請求後は、電子決済で手数料の納付が必要です。
また、オンライン請求で発行された証明書は、窓口か郵送で交付を受けることになります。
オンラインで電子証明書が発行されるわけではないので、注意しましょう。
取得方法を選択したら、取得方法に合わせて交付を受けます。
窓口交付なら申請後3~4時間後、郵送では翌日~翌々日位に取得することが可能です。
郵送で取得する
申請書などを法務局に郵送して取得する方法です。
郵送時には、以下のような書類を送付します。
- 申請書
- 収入印紙
- 返信用封筒と切手
申請書は法務局のホームページで入手できるので、ダウンロードして必要事項を記入します。
申請書に収入印紙を貼付し、住所を記入し切手を貼った返信用封筒を同封して、最寄りの法務局に送付しましょう。
送付後問題がなければ、1~2週間で証明書が郵送されてきます。
郵送での申請は、他の申請方法に比べて取得までに時間がかかる点に注意しましょう。
急ぎで取得したい場合は、窓口取得をおすすめします。
住宅ローンの確定申告における登記事項証明書のよくある質問
最後に、住宅ローンの確定申告における登記事項証明書のよくある質問をみていきましょう。
住宅ローン控除の登記事項証明書はコピーでも大丈夫?
登記事項証明書の写しを提出することも可能ですが、基本的には原本を提出します。
コピーの場合、最新の情報ではない古い登記事項証明書の可能性を疑われたりと、信用性が低くなりかねないので注意が必要です。
確定申告では、原本が必要な書類とコピーで代用できる書類とで、必要書類が細かく決まっています。
添付書類にミスがあると再提出など時間がかかるため、問題がないのであれば原本を提出するほうがスムーズに確定申告を進められるでしょう。
なお、不動産番号を入力する場合は、登記事項証明書の添付は不要です。
住宅ローン控除の登記事項証明書は取得から何カ月以内のものが必要?
登記事項証明書に有効期限はないため、いつ取得したものでも提出することが可能です。
ただし、古い登記事項証明書の場合、最新の情報と記載内容が異なっている可能性があります。
申請に合わせて新しく取得したものを添付するほうが、確実に手続きを進められます。
住宅ローン控除の登記事項証明書は土地と建物どちらのものが必要?
借入した住宅ローンの対象となる不動産分の登記事項証明書が必要です。
住宅ローンに土地も含まれている場合は、建物だけでなく土地も提出するようにしましょう。
まとめ
土地や建物の情報を記載した登記事項証明書は、住宅ローン控除を申請する際に必要になる書類です。
登記事項証明書にはいくつか種類がありますが、住宅ローン控除の申請では一戸建てなら全部事項証明書、マンションなら一部事項証明書を取得すればよいでしょう。
法務局の窓口だけでなくオンライン申請、郵送申請での取得方法があるので、自身の都合のよい方法を選び、確定申告に合わせて早めに用意しておくことが大切です。