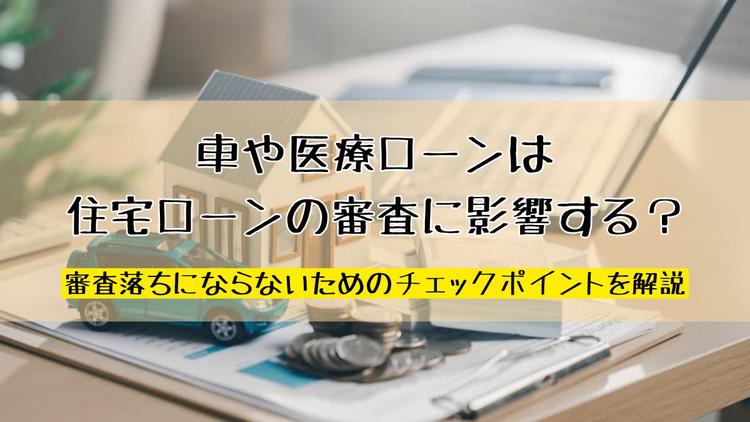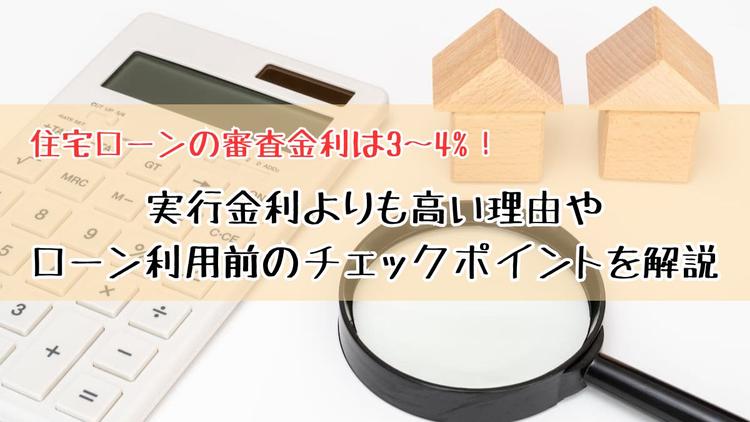マンションを購入した後は、管理費と修繕積立金を毎月納める必要があります。マンション全体を維持するための費用なので、すべての所有者に平等な負担が求められます。
でも、何らかの事情で収入が大幅に減ってしまい、管理費等を滞納せざるを得ない状況になったら、どのように対応すればいいのでしょうか。また、滞納がある状態でマンションを売却することは可能なのでしょうか?
マンションの管理費・修繕積立金とは
管理費とは、マンションの建物や敷地内を良好な状態に維持するための費用です。
分譲マンションには、必ず共用部分がありますが、共用部分の管理は、全所有者が平等に分担する必要があるため、管理費という形で積み立てをしています。
たとえば、共用部分の日常的な清掃を始め、照明設備の維持、エレベーターや防犯カメラの管理点検などに要する費用に充てられます。
修繕積立金は、外壁塗装や屋上防水といった、長期展望をすれば必然的に改修が必要になる費用を一定金額積み立てていくものです。
こうした改修工事は、高額の費用を要するために、長期間にわたり積立をして資金を蓄えていきます。
つまり、管理費と修繕積立金は、マンションを維持管理していくうえで欠かすことのできない費用なのです。
このため、管理費や修繕積立金を長期間にわたり滞納する人が出ると、建物や設備の維持管理・修繕に支障をきたし、他のマンション居住者は迷惑を被ってしまいます。
こうした事態を防ぐために、管理組合は滞納者に対して法的措置を含めた厳しい対処をせざるを得ないのです。
管理費・修繕積立金の滞納は意外と多い
管理費・修繕積立金の滞納と聞くと、特別な事情の有る特定少数の人だと考えがちですが、実際には意外と多く発生している問題です。
国土交通省の「令和5年度マンション総合調査結果」によれば、3カ月以上管理費や修繕積立金の滞納をしている人がいるマンションは、全体の29.2%です。
2018年の調査時点での同数値は24.4%でしたので「管理費や修繕積立金を滞納する人が増えている」という傾向があり、維持管理に少なからず影響が出ているケースもあるでしょう。
管理費・修繕積立金を滞納する背景
管理費・修繕積立金を滞納する背景には、昨今の景気後退が大きく影響していると考えられます。
当初、年齢と共に年収がアップすることを見込んで、住宅ローンを組んだのに、思いの外アップしないばかりか、反対に収入が減少してしまうことも。
管理費等の滞納者の多くが住宅ローンも滞りがちという事情もあり、この問題の解決を困難なものにしています。
住宅ローンの場合、1度でも滞納があると、金融機関の担当者から督促の連絡が入ります。
しかし、管理費等を滞納しても、ただちに管理組合から厳しい督促状が届くことがないため、 滞納していることにあまり罪悪感を抱かないままに、支払いを後回しにしてしまうケースがあるのです。
一方で管理費の滞納は、マンション運営に大きく支障をきたす問題として深刻化しており、管理組合が管理費の滞納者に対して 競売の申し立てをするケースが増えています。
マンションの管理費・修繕積立金を滞納したらどうなるのか
実際にマンションの管理費・修繕積立金を滞納したらどうなるのかをみていきましょう。
この場合、大きく次のような流れで進みます。
- 管理組合から滞納している住人へ電話や書面で督促がある
- 滞納が続く場合は、内容証明等で支払いを請求が届く
- それでも支払いがなされない場合は、口座の差し押さえや競売によって滞納分を回収といった法的措置がとられることもある
滞納後に取られる措置
管理費等を滞納が発生すると、管理組合では次のような流れで手続きを進めていきます。
①理事会での報告
管理費等を滞納すると、管理組合では理事会で滞納の事実を報告して、対応を協議します。
最初は、電話や書面で督促を行いますが、金額が膨らんだ場合や悪質と思われる滞納者には、法的な手続きを検討します。
理事会のメンバーは実際にマンション居住している人がほとんどなので、ここまでの事態になると、日常生活で顔を合わせる機会もあり、滞納者の家族は気まずい思いをしてしまうでしょう。
状況によっては、子どもにも何らかの影響が及ぶことがあるのです。
②総会での報告
年に1度開催される総会では、管理費等の滞納の件が報告事項として取り上げられます。
あるいは、法的手続きを進めることについて、出席している区分所有者に意見を求めることがあります。
③管理組合の法的な対応
滞納期間が長く、金額が膨らんだ場合や悪質だと思われる滞納者には、管理組合の判断で代理人弁護士を選任して、訴訟を起こします。
訴訟により、管理組合は債務名�義(債権の存在と範囲を証明する文書)を取って、それに基づき競売の申し立てをします。
請求額は、滞納管理費等の他に遅延損害金は当然ですが、訴訟や競売に要した費用も含まれることになるので、支払い額はさらに膨れ上がります。
滞納による法的措置(競売)は認められている
マンションの区分所有物件は、住宅ローンの担保としているケースがほとんどであるため、競売の後は金融機関が優先的に債務を回収します。
通常、こうした回収の見込みがないケースでは、競売自体が認められません。
このような事態に対応できるのが、区分所有法第59条の規定による競売です。
同条では
区分所有者の共同生活上の障害が著しく、他の方法によってはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもつて、当該行為に係る区分所有者の区分所有権及び敷地利用権の競売を請求することができる
と定められています。
つまり、管理費・修繕積立金の回収が極めて困難な場合には、管理組合は、その区分所有者が所有する区分所有建物の競売を請求できるとしているのです。
たとえ当該マンションに時価を超える抵当権が設定されていても、競売を実施することができます。
競売を実施後は、新しい区分所有者から管理費・修繕積立金を回収することになります。
区分所有法第8条では、旧所有者が負担していた管理費等の支払い義務を承継するとしており、管理組合は新しい所有者から滞納していた管理費等を回収することができるのです。
マンションの管理費・修繕積立金を滞納したまま売買はできるのか?
管理費等を滞納している区分所有者が、滞納を解消することなく、売却をすることはできるのでしょうか。
論点を絞るために、住宅ローンは完��済済の物件として考えていきましょう。
滞納した管理費・修繕積立金は買主が支払いの義務を負う
区分所有法第8条では
前条第一項に規定する債権は、債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行うことができる
とされています。
ここでいう債券の中には、管理費や修繕積立金も含まれます。
つまり、当該物件を購入した所有者には、前所有者が滞納した管理費等の滞納を支払う義務も付随するのです。
売却時は重要事項説明で滞納があることを告知する
このため、売却に際しては管理費等の滞納の事実を重要事項説明の中で、提示する必要があります。
もしこの事実を隠匿したままで売却をすると、契約不適合として、損害賠償などの法的措置がとられることになります。
また買主に管理費等の負担を強いるので、相場の価額から管理費等負担分を差し引いた額で売り出しを進めることになります。
売却することにより管理費等の滞納は解消できますが、そもそも滞納の負担分があまりにも大きいと、たとえ割り引いた金額で売り出しても、その金額の正当性が疑われることになります。
前所有者の滞納に絡んだ風評を新所有者が引き継ぐ形になるため、心理的圧迫感を敬遠して購入を見合わせる人もいます。
管理費等の滞納があっても売却自体は可能だとはいえ、買主の心理を鑑みれば、売却価額を大幅に引き下げざるを得ない状況に陥る可能性も視野に入れておく必要があります。
また買主側としても、中古マンションには、管理費滞納物件の可能性があることを念頭において、購入に際しては、引き継ぐべき債務の有無について、しっかりと確認をする必要があります。
管理費を滞納してしまった時の対処法
マンションの管理費等を滞納してしまった場合、再三の催促を無視していると、最悪の場合、突然競売にかけられるといった展開が待ち受けています。
こうした事態を回避するためには、どのように対処をすればいいのか解説をしていきましょう。
放置することは絶対に厳禁
再三の督促に対して、何のリアクションもない場合、理事会としては、次のステップに進めることしか選択肢は残されていません。
つまり、法的措置を粛々と進めることになりますから、知らない間に競売が決定されているという展開も十分にあり得ます。
督促に対して、「放置する」という手段は最悪の事態を招くことになりますから、絶対に慎みましょう。
返済の意思があることを伝える
管理費を滞納することになったのには、必ず何らかの事情があります。
滞納をした場合、理事会にまず謝罪をして、事情を説明したうえで、返済をする意思があることを伝えることが重要です。
住宅ローンの滞納と違い、債権者は同じ建物に住む近隣住民なのですから、返済する目途を伝えることで、突然の法的処置をとられるリスクは回避することができます。
可能な範囲で返済する
理事会に経済状況を理解してもらったうえで、全額は困難であっても、可能な範囲で返済を続けることで、理事会から返済を一定猶予してもらえる道筋が開かれます。
まったく返済をしないまま、返済期限の延長を懇願しても、そのうちに理事会の信頼を失うことになります。
たとえば2カ月に1回は払うという実績を積み上げることで、滞納を解�消する意思があることを示すことができます。
任意売却を検討する
管理費や修繕積立金の支払いが困難になると、いよいよマンションの売却も視野に入ってきます。
もし住宅ローンの返済が完了しているのであれば、自分の意思だけで売却することができますから、ためらうことなく決断ができます。
ところが、住宅ローンの返済中だと、抵当権が設定されているため、自由に売却することはできません。
しかし、このまま手をこまねいていると、管理組合が、競売の実施に踏み切る事態も想定できます。
競売は価格が安くなってしまう
競売は、一般の売却と比べて低い価格で落札されるので、マンションが他人の手に渡った後も、住宅ローンの返済だけが残るという事態も十分にあり得るのです。
住宅ローンの残債があるマンションを売却するには、任意売却という方法が適しています。
任意売却は、表面上は一般の売却とまったく変わりないので、相場の価格で売却できる可能性が高いのです。
ただし、金融機関に任意売却を許可してもらう交渉など、特有のテクニックを要するため、任意売却を扱っている不動産会社に依頼する必要があります。
任意売却後に残債を返済していく
売却額が住宅ローンの残債や管理費等の滞納金の合計額を上回れば、債務は解消されます。
売却額が債務を下回るオーバーローンになれば、残った債務について、債権者と協議をして、返済方法を調整します。
任意売却では、オーバーローンになった際の課題があるものの、競売よりも高く売却できるというメリットがあり��ます。
これを生かすためにも、可能な限り競売への道を避けて、任意売却を実施できる道を模索しましょう。
まとめ
マンションの管理費や修繕積立金を滞納しても、住宅ローンの滞納のように早い時期での督促はありません。それだけに、つい油断をして何カ月も滞納をして、債務が大きく膨らんでしまうことがあります。
管理費等を滞納して、管理組合からの請求を無視していると、最悪の場合、物件が突然競売にかけられるいう事態もあり得ます。
管理組合としても、同じ建物に居住する住民に対して、競売という強硬手段を実施するのは、けっして本意ではないはずです。
勤務先の事情などで、どうしても管理費当の支払いが困難になれば、とにかく理事会に相談をして、一定の猶予をもらえるよう交渉をしてみてください。
また、返せる範囲での返済を続けて、返済の意思があることを示すことで、競売を回避することが可能になります。