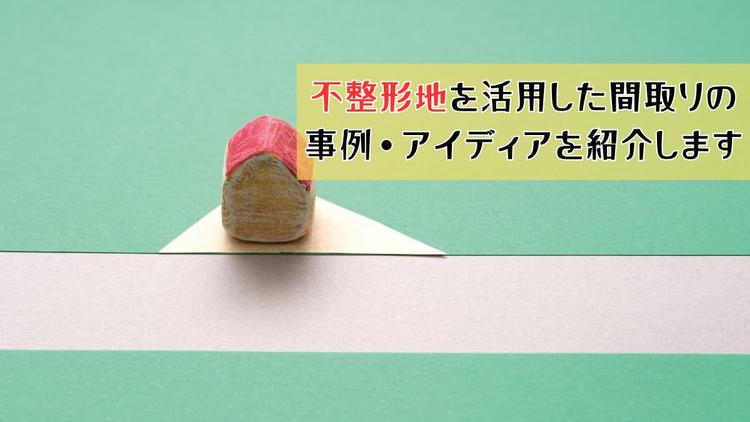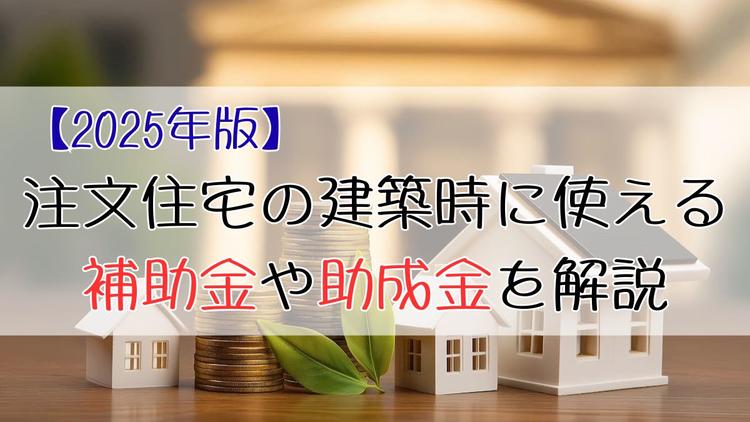築年数がかなり古い家を相続したのですが、再建築不可物件かもしれないという話を聞きました…。そもそも「再建築不可物件」とは何なのでしょう?
再建築不可物件とは、現在の家をすべて解体すると、二度とその敷地に家を建てられなくなる不動産物件のことです。
そもそも、どうしてこのような再建築不可物件が存在するのでしょうか?
過去に適用された法律がありますが、その前から既に存在していた物件に関しては規定を適用しないというルールが定められたことが要因なんです。
なるほど…。再建築不可物件を持っている場合、その物件を売却することも難しいのでしょうか?相続したものの、使わないので手放したいと考えています。
この記事では、どんな状態の敷地が再建築不可物件となるのか、また建て替えは本当にできないのか、さらには売却できるのかについて詳しく解説をしていきますね。
再建築不可物件とは?該当するケース4つ
建築基準法では、都市計画区域内にある建築物の敷地は道路に2m以上接していなければならない、と「接道義務」が定められています。
それでは、具体的にどのような状態の敷地が建て替えできない再建築不可物件に該当するのかをみていきましょう。
該当ケース①道路に接する長さが2m未満
路地状敷地とか旗竿状敷地と呼ばれる敷地は、道路に接する細い通路形状の敷地の奥に建物が建っている状態の土地をいいます。
通路状の敷地部分のどこか1カ所でも2mに満たない箇所があると、接道義務要件を満たしていないために、再建築不可物件になります。
該当ケース②袋地である
袋地とは、道路にも通路にも接していない敷地です。
日常の通行は、通行権1によって他人地を利用しているので支障はありませんが、自己敷地に接している道路が存在しないために再建築不可物件になります。
該当ケース③所有地は道路に接しているが直接行き来ができない
所有地が道路に接していても宅地が擁壁や法敷(盛り上がっている斜面部分)の上にある場合、あるいは反対に高架道路の下に敷地がある場合は、通常の方法では道路から宅地にたどり着くことができません。
このように直接道路からの通行が不可能なものは再建築不可物件になります。
ただし擁壁に階段を設けて容易に敷地から道路に通行できる場合は、接道していると見なされます。
該当ケース④敷地の接している通路が「道路」ではない
接道要件を満たすためには、幅員4m以上の建築基準法上の道路に接していなければなりません。
たとえ人が自由に通行できる幅員4m以上ある通路であっても、建築基準法上の道路でないケースは少なくありません。
たとえば長屋内の通路や農業用の通路、神社の参道等において、道路の扱いになっていないことがあります。
こうした建築基準法上の道路ではない、単なる通路のみに接している敷地は再建築不可物件です。
道路がなくても建てられる「ただし書き」規定
原則として建築基準法上の道路に接していなければ、再建築不可物件になりますが、前面の通路が広い空地であれば、合法的に建築できる可能性があります。
それが「43条ただし書き」規定です。
第43条第2項第2号では次のように規定されています。
その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものはこの限りでない。
つまり広い空地に接する敷地で防火性能が高い建築物を建てるのであれば、地方自治体(特定行政庁)が許可をすれば接道義務を求めないというものです。
この「ただし書き」規定が適用される敷地は再建築不可物件ではありませんが、建て替えをする際には改めて許可を得る必要があります。
注意が必要なのは、この制度は1999年に改正されたということです。
このため以前は建てられたのに、現在は建てられなくなったということもありえます。
▼関連記事

信頼できる不動産会社をご紹介
イエウリ の不動産査定はこちら
なぜ再建築不可物件でも建物が存在するのか
それでは、なぜ接道要件を満たしていない土地に現在建物が建っているのでしょうか。
その理由を解説していきます。
法の適用を猶予する規定がある
建築基準法は、建築物の現在あるべき状態を示した法律です。
たとえば接道義務を規定している第43条では「建築物の敷地は道路に2m以上接しなければならない」と記されていますから、本来はすべての建築敷地に接道義務があります。
ところが建築不可物件に古い住宅が今も建っているのは、例外規定があるからです。
それが第3条第2項です。
条文を要約すると「この法律を適用する際に現に存する建築物には、当該規定を適用しない」とされています。
つまり、接道義務条項が施行された1950年以前に建てられた建物には、接道義務規定は適用しないという意味です。
この条文を根拠に、再建築不可物件の建築物は既存不適格建築物と称される適合建築物として、現在も建っているのです。
再建築不可物件でもできる工事は?
それでは、再建築不可物件が老朽化してきたときには、どこまで手を加えることができるのでしょうか。
その点を理解していないと、再建築不可物件の売買は成立しません。
ここでは、再建築不可物件は何ができて何ができないのかを解説していきます。
住宅の工事には3段階ある
中古住宅を工事する場合、その規模と内容によって大きく次の3段階に分類できます。
- 修繕…主に内装材を新たにすることをいいます。柱や梁などの主要構造部を取り換える場合は、半数以下であれば修繕の範疇になります。
- 大規模の修繕・模様替…主要構造部の過半の修繕や模様替を指します。たとえば柱が21本あれば、11本以上取り換えれば「大規模の修繕」を行ったことになります。
- 新築……建物をすべて撤去して、一から建て直す場合を指します。
再建築不可物件はどの工事が可能か
それでは再建築不可物件はどこまで工事が可能なのでしょうか。
そして手続きは必要なのでしょうか。
まずは結論を一覧表にしてみましょう。
なお建物は、木造2階建ての住宅で延べ床面積が500平方メートル以下のものを想定しています。
| 工事内容 | 建築確認申請 | 工事の��適法性 |
| 修繕 | 不要 | 適法 〇 |
| 大規模の修繕・模様替2 | 不要 | 違法 × |
| 新築 | 要 | 違法 × |
再建築不可物件の新築ができないのは当然としても、ここで悩むのが大規模修繕の扱いです。
建築確認申請が不要であるにもかかわらず、工事自体は違法になるのはどういうことなのでしょうか。
実は「大規模修繕は建築確認申請が不要」という事実だけが先行するあまりに、「建築確認申請が不要なら、工事は自由にできる」と施工業者が勝手に判断をして工事を進め、役所から違反指導を受けるケースは全国で少なからず発生しています。
このあたりを勘違いしないためにも、法的根拠を押さえていきましょう。
大規模の修繕が建築確認申請不要の根拠
住宅で木造2階建て、500平方メートル以下の建築物は、第四号建築物と規定されており、建築をする場合のみ建築確認申請を要するとされています。
これを規定した第6条の要約は次のとおりです。
建築主は、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第四号に掲げる建築物を建築しようとする場合においては、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない。
この条文によって、特殊建築物や規模の大きい一号から三号建物は、大規模の修繕や模様替えでも建築確認申請が必要とされている一方で、第四号建築物は建築する場合に限って申請するよう規定しています。
このため小規模の木造住宅は、大規模の修繕をしても建築確認申請は不要となります。
ただし、工事ができるのは現行法に適合している建築物のみです。
再建築不可物件で大規模の修繕は不可
再建築不可物件の工事については、誤った工事をする事例が多いので詳しく解説をしていきましょう。
第3条第2項によって、法律施行以前に建っている建築物には現行法規の規定が適用されないことを説明しました。
ところがこの規定には、適用の猶予を解除する条文があります。
それが次に示す第3項です。
前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分に対しては、適用しない。
前項とは法の適用を猶予した第2項のことです。
これが次の各号に該当すれば「適用しない」としています。
つまり猶予が解除されるということです。
次の各号のうち第3号の要約をみてみましょう。
工事の着手がこの法律の施行後である増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替に係る建築物又はその敷地。
増築した場合はもちろんのこと、大規模の修繕や模様替も含まれています。
この規定によって大規模の修繕工事を行なった時点で、第3条第2項の例外規定が解除されるので、接道義務の規定が適用され、違反建築物になってしまうのです。
再建築不可物件は、近隣の物件も同じ状況であるため、近所の住民は、当該物件が再建築できないことを熟知しているケースが多いです。
このため何らかの工事が始まると、地方自治体の違反建築指導部署に問い合わせの電話が入ることがよくあります。
木造住宅は、大規模の修繕をしても建築確認申請は不要ですが、だからといって法の適用を受けないわけではありません。
工事内容が大規模の修繕となった時点でたちまち現行法規に適合させる義務が発生しますから、再建築不可物件における工事にしては必ず修繕の範囲で納める配慮が必要です。
信頼できる不動産会社をご紹介
イエウリ の不動産査定はこちら
再建築不可物件の建物はどこまでの工事ができるのか
それでは再建築不可物件に建つ住宅は、どこまでの工事が可能なのかを細かくみていきましょう。
主要構造部とは
修繕が大規模の修繕にならないためには、主要構造部の取り換えを半数以下に抑える必要があります。
主要構造に該当する部分
まずは主要構造にはどのようなものが該当するのかを次に示します。
- 壁
- 柱
- 床
- はり
- 屋根
- 階段
主要構造に該当しない部分
次に該当するものは主要構造部には含まれませんから、自由に取り換えることができます。
「建築物の構造上重要でない間仕切壁、間柱、付け柱、揚げ床、最下階の床、回り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段その他これらに類する建築物の部分」
部位別にどんな工事ができるのか
壁・屋根
壁や屋根は、表面の仕上げ材のみを指しているのではなく、壁や屋根を構成する下地を含めています。
たとえば外壁がモルタル壁であれば、下地の木摺り(きずり)を残していれば、モルタルをすべて落としても過半にはなりません。
また、既存の壁の上にサイディングボードを全面に張ることもできます。
内部の壁も仕上げ材の撤去は支障ありません。ただし、撤去の際には構造合板を取り付けて耐震性を高めることが重要です。
屋根は瓦をすべて取り換えたとしても、野地板や垂木を残しているのであれば過半の工事にはなりません。
床
床は「最下階の床」は主要構造部に含まれません。
このため、1階の床については大胆な工事が可能です。
再建築不可物件は、基礎構造が脆弱なことが多いので、1階の床を全面撤去することで、基礎の補強工事が施工できます。
柱や梁はそれぞれ本数を数えて、その半数以下であれば取り換えが可能です。
階段
気をつけたいのは階段です。
通常一カ所しかないために、これを取り換えるだけで過半どころが全取り換えという扱いになるので、踏板の修繕程度にとどめておくのが無難です。
ただし、伝統的な形式の町家を積極的に残すことを施策としている地方自治体においては、急こう配の梯子状の階段は、主要構造部ではない「局部的な小階段」と見なすこともありますので、この点は物件を管轄する地方自治体にご確認ください。
信頼できる不動産会社をご紹介
イエウリ の不動産査定はこちら
再建築不可物件の売却はできるのか
再建築不可物件では、建て替え工事はできません。
それでは、売却することはできるのでしょうか。
再建築不可物件の売却で注意すべきポイントをみていきましょう。
再建築不可物件であることを確実に伝える
再建築不可物件は、建て替えができないという特殊な事情や住宅ローンが使えないということから市場相場の60%~50%といった低い価格で取引されています。
だからといって、売却の際に再建築不可であることを隠すことは許されません。
再建築不可であることは重要事項で伝えるべき事項の最も重要なもののひとつであることから、不動産広告や重要事項説明書に記載する義務があります。
伝えなかった場合は、重大な契約違反として損害賠償の対象となります。
隣家に購入を打診する
再建築不可物件を売却する際、最も購入希望意欲が高いのが隣家の住民だったということはよくあります。
再建築不可であっても、解体をすることで駐車場として利用できたり、自家の日当たりが良くなったりすれば、資産価値のアップが期待できるからです。
もちろん買取の意志がまったくないこともありますが、もし購入意欲があれば、高値で買い取ってもらえる可能性がありますから、打診をしてみるのも一策です。
既存住宅状況調査(インスペクション)を実施する
大がかりなリフォームを実施しても、確実に買取希望者が現れる保証はありません。
また価格的にもリフォーム代金に見合うだけの効果が現れる保証はどこにも��ありません。
しかし、何年か前にリフォームを実施していて、耐震性に関わる構造や雨漏りの心配がない住宅であれば、インスペクションを実施することで、再建築不可物件であっても買取希望者が現れる可能性が高くなります。
さらに重要事項説明の際に「建物状況調査の結果の概要」を提示することができるので、買取希望者に安心を与えることができます。
信頼できる不動産会社をご紹介
イエウリ の不動産査定はこちら
まとめ
再建築不可物件が売却できるかどうかは、どれだけしっかりメンテナンスが行われているかにかかっています。
雨漏りやシロアリの被害がないかを確認したうえで、趣のある外観を生かしながら、美装をすることで、購入希望者の注目を集めることができます。
売却価格については、基本的には現金で購入する人が対象になりますから、どうしても販売価格は安くなってしまいますが、利点、欠点を堂々と明らかにしたうえで売却に臨みましょう。