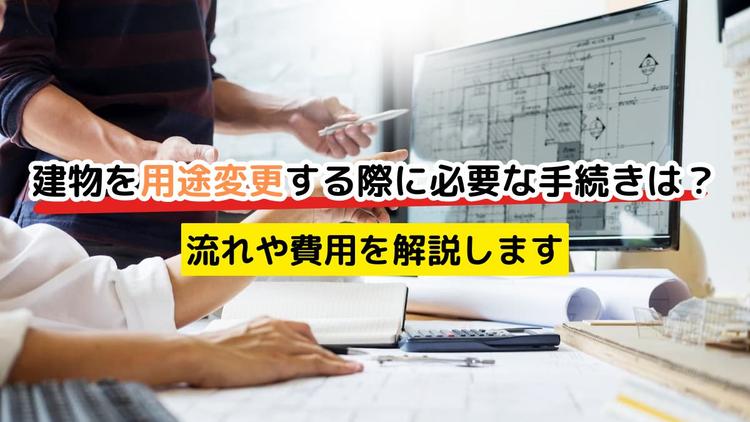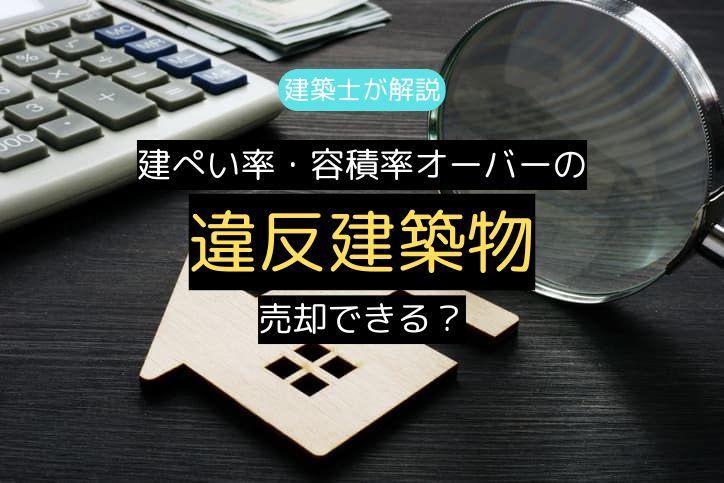住宅や店舗などの建築を計画する際に、「セットバック(道路後退)」という言葉を耳にすることがあります。
これは、都市計画区域内で新築や増築をする場合に、敷地の一部を道路として使えるようにしなければならないケースです。
本記事では、セットバックの定義や必要となる場面、費用負担の考え方、登記や税金上の扱いについて解説します。
セットバックとは何か
「セットバック」とは、建築物を建てる際に敷地の一部を道路として提供し、建築可能な範囲を後退させることをいいます。
建築基準法では、原則として「幅員4メートル以上の道路に敷地が2メートル以上接していなければ建物を建てられない」とされています。
この基準を満たすため、狭い道路に面する土地では、建築可能な敷地を道路から後退させる必要があるのです。
セットバックが問題になる2項道路とは
特に問題となるのは、いわゆる「2項道路」と呼ばれる、幅員4メートル未満の古い道路に面した土地です。
昭和25年11月23日以前から建物が立ち並び、実質的に道路として使われていた私道や里道などで、法的には一定の条件を満たすことで「道路」として扱われます。
しかし、そのままでは安全性に不安があるため、将来的な改良を見越して「道路の中心線から2メートルの範囲まで建築可能な敷地を後退させる」ことが義務づけられているのです。
これが、建築基準法第42条第2項に基づくセットバックの考え方です。
セットバックした部分は「みなし道路」になる
セットバックが求められるのは、新築、増築、大規模な修繕、大規模な模様替を行うときです。
後退した部分は、所有者の土地でありながら、建物の建築や付属する門・塀の設置が制限される「みなし道路」として取り扱われます。
つまり、物理的には私有地であっても、法律上は公道と同様の機能を期待されている空間なのです。
セットバックが必要なケースの具体的な対応
セットバックは、すべての建築計画に必要なわけではありませんが、特定の条件を満たす場合には法的に義務づけられます。
ここでは、代表的なケースについて、それぞれの対応方法と注意点を解説します。
「2項道路」に接した敷地で新築を行う場合
建築基準法では、建築物を建てるためには、その敷地が幅員4メートル以上の道路に2メートル以上接している必要があります。
しかし、都市部の古い住宅地などには、幅員4メートル未満の「2項道路」に接する土地が多数存在します。
これらの土地に建築する際には、将来的な安全性や防災性を確保するため、道路の中心線から水平に2メートルの位置まで敷地を後退させる「セットバック」が求められます。
新築を計画する際には、建築確認申請の段階で後退部分の境界を明確にし、建築物の配置計画の調整が必要です。
既存の塀や門などがある場合は撤去し、敷地の一部を「道路としてみなす空間」として扱うことが前提となります。
後退部分は建築物の敷地面積に算入されないため、容積率(敷地面積や建ぺい率の計算にも影響する点に注意が必要です。
- 建蔽率(けんぺいりつ):敷地面積に対して「建物が建てられる面積」の割合
- 容積率(ようせきりつ):敷地面積に対して「建物の延べ床面積」の割合
セットバック部分に既存建物がある場合の増築等
すでに建物が建っており、その一部がセットバックエリアにかかっている場合、建物の増築や大規模な修繕、大規模な模様替を行うことはできません。
たとえ増築範囲がセットバックの範囲外であっても、既存建物�がそのままの状態だと建築確認済証は交付されないのです。
建築確認済証が交付されないとどうなる?
建築確認済証は「新築や増改築、リフォームの計画が法律に適合していますよ」と行政などが認めた証明書です。
これがなければ工事を始めることができず、取得しないまま工事すると違反建築物とみなされる可能性もあります。
つまり「セットバックにかかる建物が残ったままだと、法律に適合しない」と判断され、建築確認がおりず、正規の工事ができない=工事そのものが許可されないということになります。
このような場合の対応としては、建築確認申請書の中で、セットバックに抵触する既存建物の部分を撤去する旨を明らかにする必要があります。
また、建築確認申請が不要な補修工事であっても、大規模の修繕や模様替えを行う場合は、セットバック部分にかかる建物を撤去しなければなりません。
▼関連記事:建築確認申請とは?手続きの流れや費用、増改築時の注意点を解説します
再建築不可物件を再建築可能にしたい場合
いわゆる「再建築不可物件」とは、建築基準法に定める接道義務(法第43条)を満たしておらず、新たな建築物を建てることができない土地のことです。
こうした物件の多くは、昭和25年の建築基準法施行前に建てられた建築物であり、現在の法基準に適合していない「既存不適格建築物」に該当します。
再建築不可物件で建築したい場合、ひとつの手がかりが建築基準法第43条に基づく許可や認定の活用です。
建築基準法第43条の許可・認定とは?
本来、建物を建てるには「幅4m以上の道路に2m以上接していること(接道義務)」が必要ですが、43条の規定により、やむを得ず接道義務を満たさない土地でも、一定の安全性が確保されると判断されれば、特例として建築が許可される場合があります。
この際には、「安全性確保のために将来的に前面の通路幅を確保すること」が条件として課されることがあり、セットバックが求められます。
たとえば、再建築不可とされている敷地が4メートル未満の通路に面している場合、特例許可や認定を受ける条件として「通路中心線から2メートルのセットバック」が求められることがあるのです。
ただし、第43条に基づく許可や認定は、自治体ごとに厳しい基準が定められているため、再建築を検討している土地については、まず所轄の建築指導課に相談し、43条許可や認定の対象かどうかを確認しましょう。
▼関連記事:43条但し書き道路とは?不動産の売買時に確認すべきことを解説します
セットバックで後退した部分の取扱い
セットバックにより敷地を後退させた場合、その部分は道路の一部としてみなされますが、所有権や登記、税務などの面では特有の取扱いがなされ�ます。
登記上は自分の土地であっても、建築基準法上は一般の敷地とは異なる制約が課されるため、適切な理解が不可欠です。
ここでは、セットバック部分の主な取扱いについて解説します。
所有権は原則としてそのまま
セットバックによって道路とみなされるようになった部分も、原則としては土地所有者の私有地です。
自治体に寄附を求められる場合もありますが、義務ではなく、寄附に応じなければならない法的根拠はありません。
ただし、建築基準法上はこの部分を「道路」として扱うため、建物や塀などの構造物を設置することはできず、利用に大きな制限がかかります。
そのため、「所有しているが自由に使えない土地」であることを認識する必要があるでしょう。
▼関連記事:私道負担とは?不動産の売買時にチェックすべきポイントを解説します
登記簿上の地積や地目は変わらない
セットバックをしても、通常は登記簿上の地積や地目(たとえば「宅地」など)は変更されません。建築基準法上の取り扱いとして「道路とみなされる」だけであり、登記情報に自動的に反映されるものではないからです。
一方で、自治体が将来的に公道化(道路整備)を計画している場合には、所有者に対して後退部分の寄附や移管(譲渡)を打診するケースがあります。寄附に応じた場合には、当該部分が分筆され、自治体名義で登記されることになります。
固定資産税が軽減・非課税になる場合がある
セットバック部分は建築物の建築が禁止されるなど、事実上��の利用制限があるため、多くの自治体では固定資産税の軽減や非課税措置を設けています。
具体的な扱いは自治体ごとに異なりますが、主に次のような対応がなされています。
- 「建築不可地」として評価額を減額
- 条件を満たせば当該部分のみ非課税
減免は自動的に適用されるわけではないので、個別に申請が必要です。固定資産税の納税通知書を確認し、減免が反映されていない場合は、市区町村の資産税課に相談してください。
セットバックにかかる費用負担と工事内容
セットバックを行う際には、単に敷地を後退させるだけでなく、付随するさまざまな工事や調整が必要です。
当然ながら、これらには一定の費用が発生し、場合によっては予想以上の出費となることもあります。
ここでは、セットバックに関連する主な工事内容と費用の目安について解説します。
撤去工事費(塀・門など)
セットバックにより道路とみなされる部分には、原則として建築物や構造物を設けることができません。
すでに塀や門柱、物置などが設置されている場合は、それらを撤去しなければなりません。
費用目安:10万円〜50万円程度(規模や構造による)
コンクリートブロック塀や鉄製門扉の撤去は費用が高めになります。
整地・舗装工事
後退した部分が未舗装である場合や、隣接する道路との段差が生じる場合には、整地や簡易舗装工事が必要になることがあります。
とくに、周囲がアスファルト舗装されている地域では、セットバック部分だけが未整備だと景観上も問題となるため、舗装を求められる��ケースも少なくありません。
費用目安:1平方メートルあたり5,000円〜1万円程度
なお、地盤改良や排水処理を伴うと、追加費用が発生します。
境界標の設置・測量費用
セットバックの位置を正確に確定するには、測量と境界標(鋲や杭)の設置が必要です。
とくに、複数の隣接地と共有する道路の場合、土地家屋調査士などの専門家による立会い測量が求められることもあります。
測量・境界標設置費用:10万円〜30万円程度
これらは、現地条件や筆数により変動します。
インフラの移設・調整費用
まれに、後退予定地に水道メーターや排水枡、ガス管の取り出し口が設置されている場合があります。
このような場合は、セットバックに伴って移設や保護工事を行わなければならず、費用がかさむ要因となるので注意が必要です。
水道・ガス・電気関連の移設費:5万円〜20万円程度(項目別)
なおこれらの工事は、自治体によっては助成制度が設けられています。
工事費用の総額イメージと注意点
セットバックにかかる費用は、規模・構造物の有無・地域差によって大きく変動しますが、一般的な住宅地では次のような費用感がひとつの目安になります。
- 小規模(塀の撤去+舗装のみ):10万円〜30万円程度
- 中規模(測量+舗装+撤去工事):30万円〜60万円程度
- 大規模(インフラ調整含む):70万円以上
また、隣接地との境界確定や道路形状の複雑さによっては、追加費用が発生することもあります。
そのため、設計者や施工業者に�事前に現地調査を依頼し、見積もりを取得することが非常に重要です。
セットバックを推進する自治体の主な取り組み
狭あい道路に面した敷地での安全な建築を促進し、災害に強い都市インフラを整備するため、各自治体ではセットバックの実施を後押しするさまざまな取り組みを行っています。
狭あい道路(きょうあいどうろ)とは、幅が4メートル未満の道路のことです。
ただし、建築基準法では「将来4メートルに広げることを前提に、道路とみなす(=みなし道路)」ことがあり、この場合はセットバックして建物を建てる必要があります。
とくに、古い住宅地や密集市街地では、火災や地震時の避難や救助の妨げとなる狭い道路の改善が喫緊の課題とされており、セットバックはその具体的な手段のひとつです。
ここでは、自治体が実施している代表的な取り組みについて紹介します。
撤去・舗装費用への補助金交付
多くの自治体では、建築に伴って敷地の一部を後退させる際に発生する費用を軽減するため、助成制度を設けています。
主な対象となるのは次のような費用です。
- セットバック部分にある塀・門・樹木等の撤去費用
- 簡易舗装や整地工事のための施工費用
- 境界標の設置や測量費用
たとえば、東京都内の一部の区では、1件につき上限30万円までの補助金を交付する制度があり、多くの場合、補助割合は2分の1〜3分の2程度となっています。
ただし、工事前の申請が必須である点には注意が必要です。
狭あい道路整備事業
狭あい道路の沿道にある老朽家屋や空き家、建替予定の建物を対象として、将来的な4メートル幅の確保を前提とした道路整備計画を策定している自治体もあります。
これは、自治体が主体となって次のような整備を進めるものです。
- セットバックにより確保された用地の舗装・排水整備の実施
- 公費による境界標設置や図面作成支援
- 寄附を受けたセットバック部分を公道として登記し管理する
このような制度を利用することで、建築主は自費負担を抑えながら、将来的な道路整備に協力する形となります。
寄附制度と公道認定の推進
後退部分を将来的に自治体管理の公道として扱うことを前提に、無償譲渡(寄附)を促進する制度を設けている自治体もあります。
これにより、セットバック部分は正式な「公道」として取り扱われるようになり、次のようなメリットが生じます。
- 所有者の維持管理義務からの解放
- インフラ整備(上下水道・街灯など)が行われやすくなる
- 隣地との境界トラブルの予防
なお、寄附にあたっては分筆や登記、測量が必要となることがあり、これらの費用についても助成の対象となる場合があるため、事前に確認しておくと安心です。
まとめ
セットバックは、建築物を新たに建てたり増改築したりする際に、安全で機能的な道路環境を整えるために必要となる制度です。特に、幅員4メートル未満のいわゆる「2項道路」に接する敷地では、道路の中心線から2メートルの範囲まで敷地を後退させることが求められます。
この後退部分は、所有者の私有地でありながら建築物の設置が制限される「みなし道路」として扱われ、法的・税務的にも特有の制約を受ける対象です。
セットバックには、塀や門の撤去、整地、舗装、測量、インフラの移設といった工事が伴い、数十万円以上の費用がかかることもありますが、自治体によっては補助金や助成制度が用意されていることもあります。
土地の有効利用や建築計画に影響するため、事前の調査や行政への相談が不可欠です。安全で適法な建築を実現するためにも、セットバックの意義と手続きを正しく理解しておきましょう。