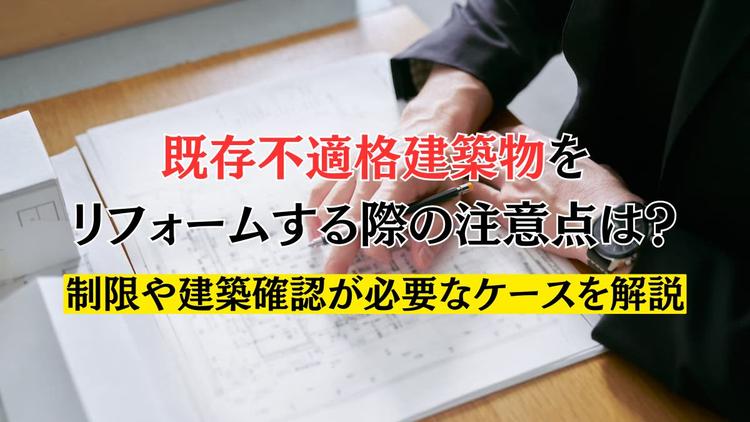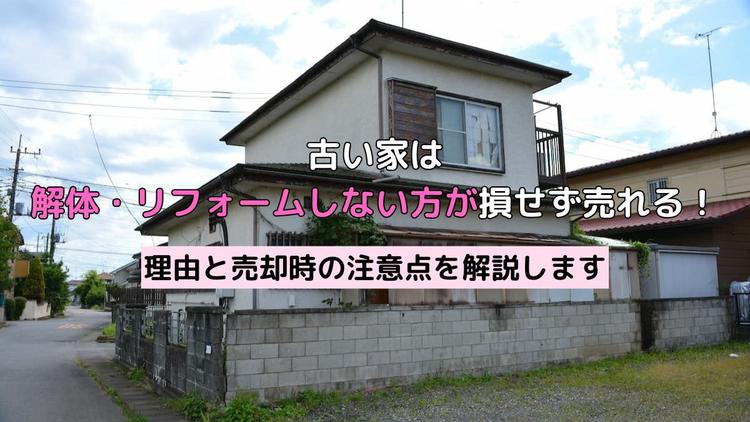中古住宅を購入して理想の住まいにリフォームしたい。
そんな希望を実現するには、物件が「既存不適格建築物」である可能性を考慮する必要があります。
既存不適格建築物は、建築当時は適法に建てられたものの、その後の法改正や都市計画の変更によって現行法規に適合しなくなった建物のことです。
違法建築物ではないので、そのまま住み続けること自体は問題ありませんが、リフォームを行う際には特有の制限を受けるため、事前の慎重な確認と計画が不可欠となります。
この記事では「既存不適格建築物とは何か」という基本的な知識から、リフォームを行う際にどのような制限や手続きが必要になるのか、そして特に注意すべきポイントについて、具体的な事例を交えながら解説します。
既存不適格建築物とは
既存不適格建築物とは、建築された時点では適法であったものの、その後の法令改正や都市計画の変更によって、現行の建築基準法や規制に適合しなくなった建物を指します。
既存不適格建築物は建築当時の基準に適合しており、いわゆる「違法建築物」ではなく、適法な建築物として存在しています。
しかし、リフォームをする場合には、その内容や規模によっては現行の法令が適用されるため、特別な注意が必要となるのです。
まず、具体的にどのようなケースが既存不適格建築物に該当するのか、いくつかの代表的な事例をみていきましょう。
接道義務の不適合
原則として、建築物の敷地は幅員4メートル以上の道路に2メートル以上接していなければならないと定められています(建築基準法第43条)。
しかし現実には、建築基準法が施行された昭和25年以前に建てられた建物や、行政の道路認定基準の変更によって接道義務を満たさなくなった地域では、既存不適格建築物が少なくありません。
たとえば、幅員が4メートル未満の個人所有の通路にしか接していない敷地に、80年以上前に建てられた木造住宅などがこれに該当します。
なお、接道義務に適合しない建築物は、いったん更地にするとその後新築ができなくなることから、「再建築不可物件」と呼ばれることもあります。
建ぺい率・容積率の超過
都市計画区域内では、用途地域ごとに建ぺい率(敷地面積に対する建築面積の割合)と容積率(敷地面積に対する延べ床面積の割合)の上限が定められています。
現行の都市計画法が1968年に施行されたことから、実際に各都市で建ぺい率や容積率が指定されたのは1970年頃からです。
その後も、都市の変貌に伴い、多くの地域で指定が変更されています。
そのため、建築当時は適法であった建物が、指定後に指定建ぺい率や容積率の制限を超えている状態となったものがあるのです。
防火規定の強化による不適合
都市計画区域で防火地域や準防火地域の指定が見直されたり、建築物の防火基準が強化されたりした場合、以前は防火規制の対象外であった建物が現行の基準に適合しなくなることがあります。
特に木造建築物においては、外壁の材質や開口部の防火設備(��防火戸など)の設置などが義務付けられることがあり、これらの基準を満たしていない既存の建物は既存不適格となります。
再開発によって、木造低層住宅が密集していたエリアに中高層のマンションや商業施設が建つようになると、火災時のリスクが増大します。
これに対応するため、防火地域や準防火地域の指定、あるいは防火性能の高い建物の建築義務が新たに課されたケースが考えられるでしょう。
用途の不適合
用途地域は全部で13種類あり、それぞれの地域で建築できる建物の高さや用途が定められている。
建築物の用途も、都市計画の変更や法改正によって制限を受けることがあります。
たとえば、古くから操業されていた工場や商店などが、その後住宅系の用途地域に指定されたことにより不適格となる場合があるのです。
耐震基準の不適合
建築物の耐震基準は、過去の地震災害の教訓を踏まえて強化されてきました。
特に、1981年(昭和56年)に大幅な改正が行われた「新耐震基準」以前に建てられた建物は、震度6強以上の地震に対して十分な耐震性能を有していない可能性があります。
これらの旧耐震基準に基づいて建てられた建物は既存不適格となり、リフォームの際に耐震補強を求められることがあるのです。
リフォームを行う際の制限
既存不適格建築物であっても、壁紙の張り替えや床材の交換、設備の更新などの小規模な修繕や模様替えであれば、原則として建築基準法上の制限を受けることはありません。
しかし、建物の構造、用途、面積に影響を与えるような一定規模を超えるリフォームを行う場合には、建築基準法をはじめとする関係法令への適合性が求められることがあります。
ここでは、既存不適格建築物のリフォームにおける制限について解説します。
現行法への適合が求められるケースとは
リフォーム工事が建築基準法上の「大規模の修繕」「大規模の模様替え」に該当する場合、工事完了後の建物全体の状態が現行の法規に適合してい�ることが原則として求められます(建築基準法第3条第3項第3号)。
つまり、工事完了後は不適格部分が解消された状態にする必要があるのです。
大規模の修繕・模様替えとは、建物の主要構造部(柱、梁、床、屋根、壁)のうち、いずれか一種類以上について過半を修繕または模様替えする工事を指します。
建物を既存不適格のまま維持したいのであれば、リフォームで老朽化した柱や梁を交換する際に、交換する箇所を厳選して過半の交換とならないように注意する必要があります。
特に、接道義務を満たしていない敷地では、主要構造部の過半を交換することで、建物の存在自体が認められなくなる可能性があるため、細心の注意が必要です。
増築をすると面積が減ることもある
増築とは、既存の建物の床面積を増加させる工事を指します。既存不適格建物は、増築をすると建物全体を現行法規に適合させなければなりません。
建ぺい率や容積率を超過している建物に増築を行うのであれば、既存の建物を一部解体し、現行の建ぺい率・容積率の範囲内に収める必要があります。
たとえば、指定建ぺい率が60%の地域に建ぺい率70%の建物がある場合、この建物を増築するには、増築部分の建築面積以上の規模で他の箇所を解体し、建ぺい率を60%以下に抑える必要があるのです。
こうした場合に注意したいのが、既存不適格建築物は現状維持が認められているだけで、いわゆる「既得権」ではないという点です。
すでに適法に70%で建っているからといって、70%まで建てる権利があるわけではなく、本来は60%に抑える必要があ�ります。「一定規模の工事」を行うまでは現状維持が認められているにすぎません。
内装工事だけでも制限はある
既存不適格建築物は「大規模の修繕」「大規模の模様替え」「増築」を行えば、現行の建築基準法が適用されると説明をしてきましたが、用途変更に関しては、取り扱いが異なります。
用途を変更する場合は、簡単な内装工事を行うだけでも、用途規制が適用されるのです。極端なケースだと、工事を一切行わなくても用途規制の対象になります。
昔から建つ機械製造工場の土地が、後に第一種低層住居専用地域に指定された場合、この工場は用途不適格の建築物になります。
指定後も引き続き機械製造工場としての使用は続けられますが、不適格という理由だけで物品販売店舗などの別用途に変更することは認められません。
用途変更をするのであれば、指定された用途地域に適合した建築物にする必要があるのです。
建築確認が必要となる主なケース
既存不適格建物においても、一定の規模の工事をする場合には、建築確認申請(行政や指定検査機関による審査)が必要な場合があります。
ここでは、どのような工事を行えば建築確認申請が必要なのかについて解説をします。
増築を伴う場合
既存の建物の床面積を増加させる行為は、増築の規模にかかわらず原則として建築確認が必要です。
たとえば、子ども部屋を増やす、2階の一部を増築する、屋根裏やバルコニーを居室化する行為などがこれに該当します。
ただし、防火地域・準防火地域の指定がない地域における10平方メートル未満の増��築は、建築確認申請は不要です。しかし、その場合でも工事が完成した時点では、都市計画で指定されている建ぺい率や容積率の制限内に収める必要があります。
建ぺい率や容積率の既存不適格建築物であっても、増築の確認申請は可能です。ただし、その場合は、既存の建物を一部解体し、完成後には適法な建築物となる計画であることを明確にする必要があります。
大規模の修繕・模様替えを行う場合
大規模な修繕や模様替えを行う場合は、建築確認申請が必要です。この場合、不適合項目も再度審査され、現行基準への適合が求められます。
特に耐力壁の位置や量の変更など、耐震基準への適合には注意が必要です。
ただし、平屋建て住宅で200平方メートル以下の場合は建築確認申請は不要です。
それでも現行の建築基準法に適合していることが求められ、不適格部分は解消しなければなりません。
200平方メートル以上の用途変更を伴う場合
建築物の用途を200平方メートル以上変更して、建築基準法上の特殊建築物(学校、病院、劇場、百貨店、ホテル、工場など)に変更する場合も、建築確認が必要です。
たとえば、300平方メートルの旅館を土産物屋や飲食店に変更する場合などが挙げられます。
用途の変更は周辺への影響が大きく、建物の構造や避難・安全性能にも大きく影響するため、工事を実施しない場合でも建築確認申請が必要となります。
用途変更の内容によっては、新たな構造基準(耐火性能、遮音性能、非常用出口の確保など)が適用される場合があり、工事の規模が大きくなる可能性もあるため、計画段階�で十分な確認が必要です。
リフォームをする際の注意点
リフォームは新築よりも安い工事費用で新しい環境を整えることができますが、対象の建物が既存不適格建築物の場合、法規制が複雑になり、予期しないトラブルに発展する可能性があります。
ここでは、既存不適格建物をリフォームする際の注意点について解説していきましょう。
建築確認申請が不要でも適法性が求められる
建築確認申請が必要となる工事や規模については前述しましたが、重要なのは、既存不適格建築物はたとえ建築確認申請が不要な工事でも、建築基準法への適合性が求められるということです。
建築確認申請が不要だからといって、接道義務不適合建物(再建築不可物件)の構造材を容易にすべて取り替えてしまった結果、行政から違反指導を受けるケースは決して少なくありません。
そのため、建築確認申請が不要な場合であっても、法への適合性をしっかりと確認することが不可欠です。
接道義務不適合でも大規模修繕の可能性はゼロではない
一方で、接道義務不適合建物であっても、大規模な修繕ができる可能性はゼロではありません。
建築基準法第86条の7では、「政令で定める範囲」において、既存不適格建築物の大規模な修繕については「接道義務」規定を適用しないとしています。
「政令で定める範囲」とは、「建築物の用途の変更を伴わない大規模の修繕または大規模の模様替であって、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものとする(同施行令137条の12第6項)」というものです。
つまり、特定行�政庁の43条認定または許可基準に適合する場合、接道義務に適合していない建築物であっても、大規模な修繕が施工できる可能性があるのです。
専門家との連携が重要
既存不適格建築物に関する法的判断や技術的判断は非常に複雑であり、一般的な個人が適正に判断することは困難です。
そのため、既存不適格建築物のリフォームを計画する際には、専門家との連携が重要になります。
既存不適格建築物を適正に扱うためには、建築基準法についての知見が必須となります。
したがって、相談先としては、建築士や建築士事務所を開設しているリフォーム会社を選択すると安心でしょう。
まとめ
既存不適格建築物は、建築当初は法令に適合していたにもかかわらず、後年の法改正や都市計画の変更により現行基準に適合しなくなった建物であり、違法建築物とは一線を画します。
しかし、リフォームを行う際には、接道義務、建ぺい率・容積率、防火・耐震性能、用途の適合など、さまざまな観点で制限や手続きが発生するため、慎重な検討が不可欠です。
特に、増築や用途変更、大規模な修繕を伴う場合には建築確認申請が必要となり、既存の不適合状態が再評価される可能性があります。安易な判断でリフォームを進めると、工事の中断や是正命令といった重大なトラブルにつながることがあります。
工事に際しては、ぜひ建築士あるいはリフォーム会社でも建築士事務所を開設している会社に相談をしてください。
一方で、既存不適格建築物であっても、適切な対応を行えば安全性と快適性を両立したリフォームは可能です。建築士や行政への早期相談を通じて法的なハードルを正確に把握し、無理のない設計計画を立てることが、満足度の高い住まいづくりの第一歩となります。
今後さらに厳格化される法規制や社会的要請を見据えたうえで、将来の居住環境を見据えた柔軟な視点を持つことが、建物の価値を長く保つ鍵となるでしょう。