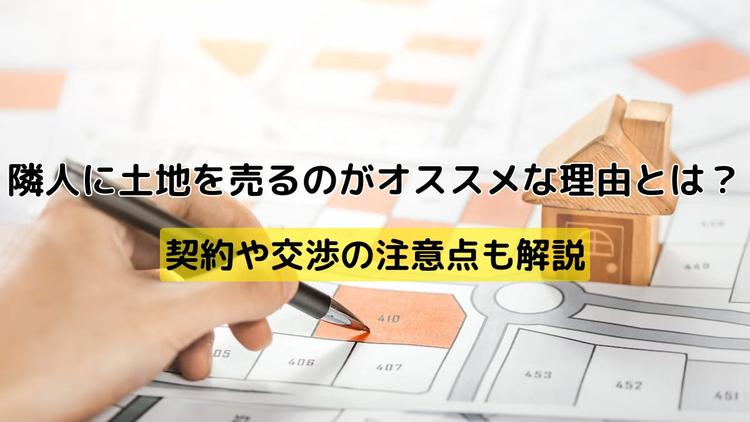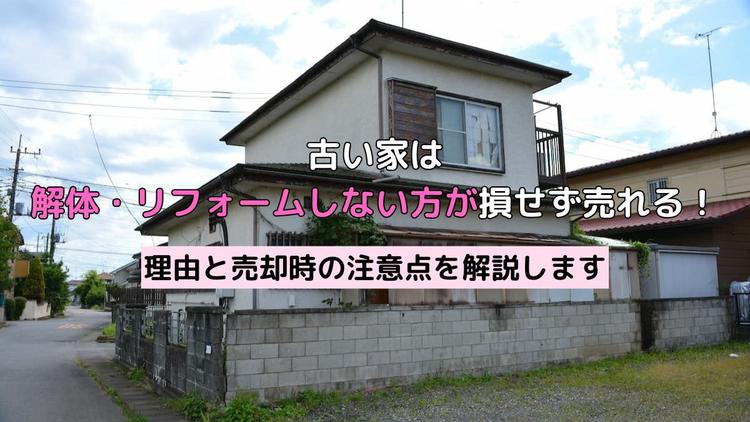境界確認書は、境界の位置について双方の所有者が合意したことを示す書面です。
作成に際しては、現地での立会いと書面への押印が必要ですが、隣地所有者の中には、立会いや押印を拒否する人もいます。
この記事では、境界確認の立会いや押印を拒否された場合の対策について解説します。
境界確認書とは
土地の境界を確定させるには、土地家屋調査士が境界確定測量を行い、その結果について双方の所有者が合意する必要があります。この合意内容を書面にしたものが境界確認書です。
境界確認をすることで、近隣トラブルを未然に防ぎ、安心して土地を売買することができます。
さらに、境界確認書が存在することで、境界争いのない土地であることが保証され、土地の価値を上げるひとつの要因にもなるのです。
境界確認書を作成する目的は
境界が確定していないまま土地を売却すると、将来境界に関するトラブルが発生する可能性があります。
境界確認書は、こうしたトラブルを未然に防ぐための書類です。
境界確認書が存在しない土地は、買主にとっても不安材料となることから、購入が敬遠される傾向にあります。
一方で、境界確認書が存在することで、買主が安心して購入できる要件を整えることができます。
また、登記を行う際に境界確認書を添付することで、隣接する土地の所有者同士が境界について同意していることを証明できます。
境界確認書の押印は実印が基本
境界確認書の作成は、法律で必須とされているものではありません。
そのため、押印する印鑑も「実印でなければならない」という決まりはありません。
実際のところ、認印だけで作成され、印鑑証明書が添付されていない境界確認書もあります。
ただし、認印による押印では「信頼性が低い」と見なされることが多いです。
境界確認書の役割を考えると、信頼性を高めるために実印で押印するのが理想的といえます。
もし、認印で作成された境界確認書しかない場合、実際の土地取引では、ほとんどの場合で「改めて実印で押印した境界確認書」を作成し直すことが求められます。
新規に確定測量を実施して境界確認書を用意する場合は、実印を押印したものを作成しましょう。
経験豊富な不動産会社をご紹介
イエウリ の不動産査定はこちら
境界確認書作成の流れ
境界確認書を作成する手順を知ることで、どのタイミングで隣地所有者に境界の立会いや境界確認書への押印を求めるのかが分かります。
なお、境界確認書を作成する場合、50~80万円が費用の相場です。
登記手続きまでを合わせた費用は、60万円~100万円程度です。
土地の大きさ・形状等によって金額は上下します。
ここからは、どのような流れで境界確認書を作成するのか紹介していきましょう。
①隣地所有者の了承を得る
境界確認書を作成することを決めたら、まず隣地所有者の了承を得ることから始めます。
境界確認書は、隣接する土地の所有者双方の同意によって成立します。
そのため、了承を得ずに準備を進めると、隣地所有者の気分を損ね、境界の立会いが困難になる恐れがあります。
測量で隣地に立ち入ることもあるので、境界確認書を作成する意義や事情をきちんと説明して、協力をお願いしましょう。
②土地家屋調査士に測量を依頼する
隣地所有者の同意を得た後、土地家屋調査士に確定測量を依頼します。
土地家屋調査士は、不動産の表示に関する登記の専門家です。
彼らは、土地や建物の場所や形状、利用状況を調査・測量し、図面を作成したり、登記の申請手続きを行ったりします。
なお、測量士という資格もありますが、登記を伴う測量は土地家屋調査士だけが行える専門業務です。
すでに土地の売却を進めていて測量が必要な場合、不動産会社に仲介を依頼していれば、土地家屋調査士を紹介してもらうのが一般的です。
③必要な資料を揃える
土地家屋調査士は、まず現況測量を行い、境界の概要を確認します。
そのため、現況測量に必要な次の資料を揃える必要があります(いずれも法務局で取得可能です)。
- 公図
- 登記簿謄本
- 共同担保目録
- 地積測量図
- 建物図面
④土地家屋調査士が現況測量を実施する
資料が揃ったら、土地家屋調査士が現況測量をし、仮の境界点を定め、仮杭を設置します。
現況測量とは、土地の現在の状態を正確に把握するための測量です。
具体的には、土地の形状や境界標(境界杭や塀など)の位置、隣接地との関係を確認します。
この段階では、あくまで「現状を確認して仮境界を定める」ことが目的で、隣地所有者の立ち合いは必要ありません。
⑤確定測量の立会いをする
立会いの当日は、土地家屋調査士により立会者が土地所有者本人であることの確認が行われます。
基本的には、マイナンバーカードや運転免許証などの身分証にて確認を行います。
代理人の立会いでも構いませんが、その場合は本人からの委任状が必要です。
ただし、土地所有者本人と境界の認識が異なるといった問題が生じる可能性があるため、可能な限り土地所有者本人の立会いが望ましいでしょう。
立ち合いでは、お互いの主張する境界点や境界線がすべて一致し、地積測量図などの内容と相違がないことを確認します。
現地に明示がない場合は、石杭、コンクリート杭、金属標、鉄鋲など耐久性があり移動しないものを目印として設置します。これで立会いは完了となります。
⑥境界確認書を作成(押印)
確定測量図をもとに境界点を示した境界確認書を作成し、依頼主と隣地所有者双方で押印します。
この際、できる限り実印を使用し、印鑑証明書を添付するのが望ましいでしょう。
境界確認書は2部作成し、依頼主と隣地所有者がそれぞれ1部ずつ保有します。
最初に隣地所有者の了解を得る段階から境界確認書作成までの期間は、概ね3カ月を見込んでおきましょう。
▼関連記事

経験豊富な不動産会社をご紹介
イエウリ の不動産査定はこちら
境界確認書の立会いや押印が拒否される原因
境界確認書は、隣地所有者の立会いのもと確定測量を行い作成します。
しかし、中には立会いや押印を拒否されるケースも少なくありません。
そもそも境界確認書の作成は、双方にとってメリットがあるはずですが、どうして拒否されるのでしょうか。
その要因について解説します。
立会いは義務ではない
境界確認書の立会いや押印に応じる法的義務はありません。
境界立会いは任意なので、多忙や体調不良を理由に断ることもでき、拒否してもペナルティはないのです。
隣地所有者に特段のメリットがない場合、立会いを断られる可能性は十分にあります。
そのため、境界確認をすることで生じるメリットや境界確認書を作成しなければならない事情を誠実に説明することが重要です。
土地の売却に際しては、境界が不明瞭なままでは買手が見つからないことが多いため、そうした事情を伝えた上で交渉を行うのが良いでしょう。
また、
- 当該の土地を隣地所有者や、その親族が購入する
- 隣地と合わせてその土地を売却する
といった事例が意外と多くあります。
隣地所有者が「隣の家を単独で売却されると、自分の土地の利用価値が下がり、処分する際に困る」と考えていることもあるので、売却に際して境界確認の立会・押印を拒否された場合は、不動産会社に相談して対応方法を検討することを推奨します。
慣習的に利用していた土地が減る
境界立会いをして境界線を確定することで、デメリットが発生することがあります。
たとえば、慣習的に利用していた土地が減って��しまうというケースです。
それまで何の問題もなく使用していた場所が使えなくなることで、境界確定をデメリットに感じる人も少なくありません。
隣地所有者が慣習的に利用していたエリアが、実は自分の土地ではなかったことが判明した場合、境界確認書の押印を拒否する可能性があるでしょう。
隣家と日常的なトラブルがある
日頃のコミュニケーションの有無が、境界確認書の作成では大きく影響します。
隣家と日常的な諍いが発生している場合、相手方の協力を得ることが難しい恐れがあります。
所有者が不明
境界確認書は隣地の所有者との合意で作成します。
隣家に住む人とは別に所有者がいる場合や空き家の場合、土地の所有者と連絡が取れないことがあります。
土地の所有者の所在が不明の場合、あらゆる手立てを講じて所有者を探し出さないと、境界確認書の作成が困難になります。
土地境界確定の立会いを拒否されたときの対策
隣地所有者に境界確認の立会いや押印を依頼しても、何らかの理由で拒否されることがあります。
ここでは、立会いや押印を拒否されてしまった場合の対策について解説をします。
土地家屋調査士に交渉を委ねる
境界確認書を作成する際には、土地家屋調査士に依頼します。土地家屋調査士は測量、境界杭の設置をしたうえで、確定測量図や境界確認書を作成します。
もし隣地所有者に立会いを拒否されてしまった場合は、土地家屋調査士に隣地所有者との交渉を委ねるという方法があります。
土地家屋調査士は、境界確定に関する専門家なので、相手方を納得させる説明のノウハウを有しています。
当事者同士だと感情のもつれが生じるようなことでも、第三者が立会いを依頼することで、スムーズに応じてもらえる可能性があります。
ただし、土地家屋調査士には、立会い時に相手方と交渉する権限は認められていないので、境界の合意をする際に相手方を説得するようなことはできません。
可能なのは、客観的に測量結果を示すことと、立会いへの協力をお願いすることという点は覚えておきましょう。
筆界特定制度を利用する
筆界とは不動産登記において、土地の範囲を示す境界のことです。例外もありますが、ほとんどの土地は筆界で所有地が分かれています。
筆界特定制度とは、筆界特定登記官が、外部専門家である筆界調査委員の意見を踏まえて、現地における土地の筆界の位置を特定する制度です。
新たに筆界を決めるのではなく、実地調査や測量を含む様々な調査を行ったうえで、もともとあった筆界を筆界特定登記官が明らかにします。
筆界特定制度を活用することで、公的な判断で筆界を明らかにできるため、裁判をしなくても筆界をめぐる問題の解決を図ることができます。
筆界特定制度の処理期間は、通常の案件で6カ月程度で、長くても1年程度が一般的です。
長いようにも思えますが、解決まで数年を要する訴訟と比較すれば、比較的早く解決できる方法だといえるでしょう。
▼関連記事:筆界特定制度とは
境界確定訴訟を行う
筆界特定制度でも境界を確定できない場合は、立会いを拒否された人が原告となり、拒否した人を被告として調停や裁判を起こし、裁判所に判断を委ねることになります。
境界確定訴訟を起こした場合は、判決によって境界線が決まります。判決後は、一切不服を申し立てることはできません。
これは紛争を解決する最も確実な手段ですが、必ずしも原告側の主張が通るわけではありません。また、判決が出るまでに長い期間と高額の費用を費やすことも考慮する必要があります。
経験豊富な不動産会社をご紹介
イエウリ の不動産査定はこちら
まとめ
境界確認書は、土地の境界を明確にすることで近隣トラブルを防ぎ、買主が安心して購入できる条件を整えるための重要な書類です。
この書類がない土地は、売却が困難になりやすく、売却価格にも影響を与える可能性があります。
しかし、境界確認書の作成には隣地所有者の協力が不可欠であり、場合によっては立会いや押印を拒否されることもあります。
こうした状況に直面した場合でも、土地家屋調査士に交渉を依頼したり、筆界特定制度を活用することで解決の道を探ることが可能で��す。
問題が長期化する場合は、最終手段として裁判による解決も視野に入れなければなりません。
ただし、裁判には時間や費用がかかるため、まずは誠実に隣地所有者と話し合い、信頼関係を築くことが成功への近道です。
境界確認書の作成は、土地の売却だけでなく将来的な安心を確保するためにも欠かせないステップです。
今回の記事を参考に、スムーズな境界確認書の作成を目指してみてください。