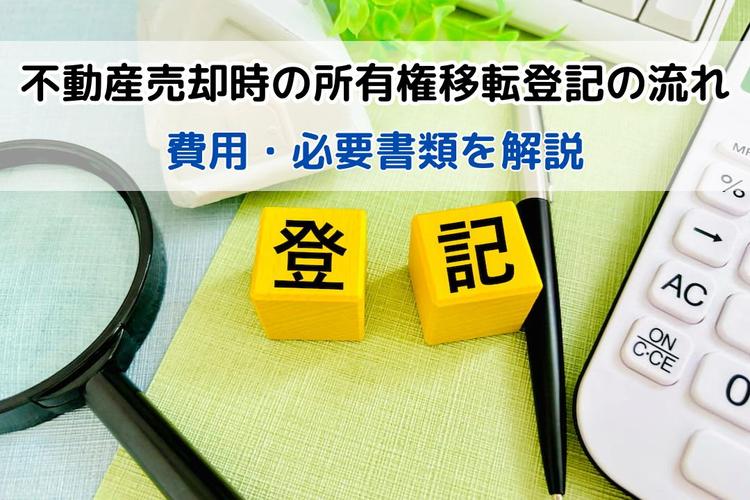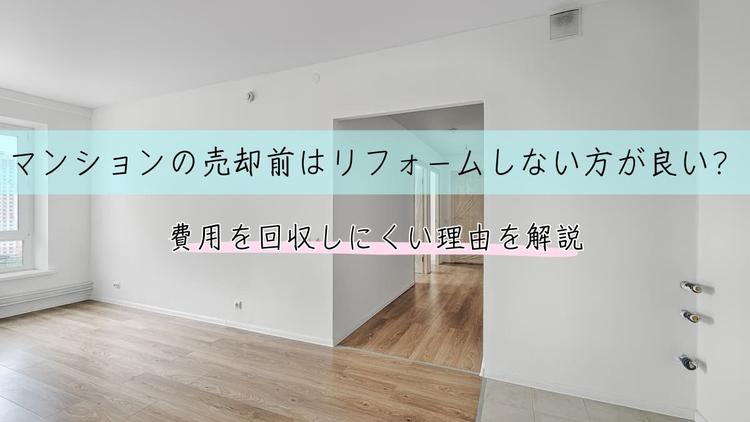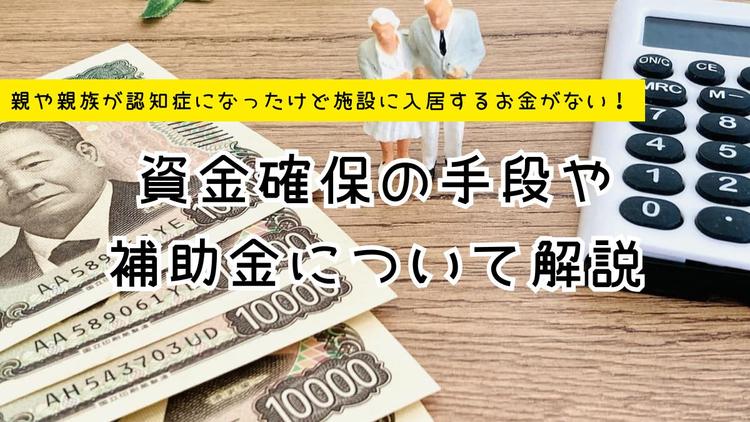介護リフォームとは、高齢者や介護が必要な人に適した住宅へのリフォームのことです。
快適に生活できるだけでなく、転倒やケガのリスクの低下や自分で生活する意欲の向上を期待できます。
しかし、介護リフォームを実施するにあたり、費用が気になるという方もいらっしゃるでしょう。
介護リフォームは一定の要件を満たすことで介護保険の適用を受けることが可能です。
この記事では、介護リフォームの費用相場や介護保険適用範囲などを解説していきます。
介護リフォームとは
介護リフォームとは、高齢者や介護が必要な人が快適に暮らせるようなリフォームのことです。
高齢になると身体機能が低下し、ちょっとした段差で転倒したり階段の上り下りが難しくなったりします。
また、車いすが必要になると、そのままの廊下や玄関では移動がしにくいケースもあるでしょう。
そのような不都合を解消し、暮らしやすい家に改修するのが介護リフォームです。
代表的な介護リフォームには、手すりを設ける・段差を解消する・引き戸にするといった工事が挙げられます。
また、一定の介護リフォームは介護保険の住宅改修費を利用して、補助を受けることも可能です。
介護保険の住宅改修とは
介護保険とは、介護を必要とする人を支える社会的保険制度1です。
この制度では、40歳から64歳の特定疾患などによる介護が必要になった人と65歳以上の介護認定を受けた人が対象となり、介護サービス費用の一部のサポートが受けられます。
なお、40歳以上は自動的に被保険者となり介護保険料の支払いが義務付けられています。
介護保険によるサポートの1つが、住宅改修費の支給です。
介護が必要な状態となった人が安全に生活できる環境に整えるための住宅改修を行う場合、保険から一定額が支給されます。
適用要件
介護保険の住宅改修費の対象となるのは以下の条件を満たす人です。
- 要支援1~2もしくは要介護1~5の認定を受けている人
- 介護保険被保険者証に記載されている住所の自宅に住んでいる人
- 自宅を改修する人
認定を受けている人でも施設に入居・病院に入院していると対象となりません。
ただし、施設や病院から自宅に戻ることが決まっている場合は、対象となる可能性があります。
介護リフォームへの適用範囲
住宅改修費の支給額と対象となる住宅改修の種類は以下のとおりです。
| 項目 | 内容 |
| 支給限度額 | 生涯20万円 |
| 住宅改修の種類 |
|
住宅改修費では、1人が生涯で20万円を上限として改修費用の9割が支給されます。
例えば、20万円の改修であれば、18万円が支給され自己負担は2万円で済むのです。
ただし、所得によっては支給割合が7~8割に減額されるので事前に要件を確認するようにしましょう。
1人20万円の枠は1回で使い切る必要はなく、20万円になるまで複数回分けて申請することが可能です。
また、介護度が3段階以上上昇などによって20万円申請後でも、再度申請もできます。
ただし、洋式トイレからグレードの高い洋式トイレへの変更は対象外となるように、対象となるリフォーム内容には細かな条件が設けられているので注意しましょう。
詳しくは、ケアマネージャーなどに相談することをおすすめします。
介護保険を適用した住宅改修の費用相場
ここでは、代表的な介護リフォームの種類別の費用相場と住宅改修費を申請した場合の自己負担額を紹介します。
なお、住宅改修費は1割負担として計算しています。
| 改修の種類 | 費用目安 | 住宅改修費の補助 | 自己負担額 |
| 浴室への手すりの取り付け | 3~5万円 | 2.7~4.5万円 | 3,000~5,000円 |
| 玄関スロープの設置 | 20万円~ | 18万円 | 2万円 |
| 和式→洋式便座への変更 | 18万円~ | 16.2万円 | 1.8万円 |
| 階段の段差を緩やかにする | 30万円~ | 18万円 | 12万円 |
| 階段への昇降機の設置 | 50万円~ | 18万円 | 32万円 |
| 階段への滑り止めシートの設置 | 8~10万円 | 7.2~9万円 | 8,000~1万円 |
上限額が20万円となるので、大規模な改修では自己負担も大きくなるので注意しましょう。
手すりを取り付けるなど小規模な改修であれば、他の改修工事と併せて上限内で複数回利用できます。
上記の費用はあくまで目安です。
希望する工事内容や家の状態・業者によっても費用は大きく異なるので注意しましょう。
改修工事を検討する際には、できるだけ複数の業者の見積もりを比較することで適切な価格での工事が行えます。
介護リフォームで介護保険を利用するメリット・デメリット
介護保険を適用することで自己費負担を押さえて自宅をすみやすく改修できるというメリットがある反面、上限額が大きくはなく希望の改修工事はしにくいなどのデメリットもあります。
以下では、介護保険を利用するメリット・デメリットを紹介するので、参考にしてください。
メリット:低コストで介護者の負担を軽減できる
バリアフリーに対応していない自宅で高齢者や介護者が生活するのは、生活しにくいだけでなくケガや事故のリスクも高くなります。
また、介護する側にとってもサポートがしにくいというデメリットもあるでしょう。
住宅改修費を利用することで、自己負担を押さえて家を生活しやすい環境に整えることが可能です。
生活しやすい環境を整えることで介護者側の負担の軽減が図れるだけでなく、被介護者が歩くなど自分で生活する意欲を高めやすくなり、身体機能の改善も期待できるでしょう。
デメリット:限度額が20万円のため改修内容が限られる
デメリットとしては、支給額がそれほど大きくない点が挙げられます。
上限が20万円であるため、大規模な改修など希望する改修工事の費用が高額になるとカバーしきれません。
上限を超えた分は全額自己負担となるので、あらかじめ改修工事費の相場を把握し必要に応じて予算計画を立てるようにしましょう。
また、改修工事の種類も限定されているので、希望する工事が対象外となる可能性もある点にも注意が必要です。
なお、改修工事費の支給方法は、「償還払い」と「受領委任払い」の2種類があります。
償還払い
償還払いは先に業者に自己資金で支払ってから支給を受ける方法です。
一方、受領委任払いは支給を前提に自己負担分のみ支払い、残りは自治体から業者に支払われる方法にな��ります。
償還払いは申請がスムーズに進みやすい反面、改修費はいったん全額自分で支払う必要がある点に注意が必要です。
受領委任払い
受領委任払いなら、自己負担での支出を押さえやすいですが、申請受理までに時間がかかる点に注意しましょう。
とはいえ、住宅改修費は支給を受けること自体にデメリットはありません。
必要なサポートはしっかり活用して住みやすく介護しやすい環境を整えられるようにしましょう。
介護保険の住宅改修でリフォームする流れ
ここでは、介護保険の住宅改修費を利用して介護リフォームする流れを解説します。
大まかな流れは以下のとおりです。
- ケアマネージャーに相談する
- 業者と工事内容を打ち合わせする
- 自治体の窓口で介護保険の住宅改修を事前申請する
- リフォーム工事の着工・完成
- 住宅改修費の支給申請~入金
住宅改修費を利用する場合、着工前に申請が必要な点には注意しましょう。
着工後の申請では受理されない可能性があるので、事前にケアマネージャーに相談し流れを把握することが大切です。
以下では、それぞれのステップを詳しく解説します。
ケアマネージャーに相談する
まずは、ケアマネージャーに相談し改修プランを検討していきます。
業者の選定の仕方や適切な改修プランなどのアドバイスが貰えるので、相談しながら今後の流れを確認していきましょう。
相談後、申請で進む場合はケアマネージャーが必要書類の準備をサポートしてくれます。
業者と工事内容を打ち合わせする
業者と工事内容を打ち合わせし住宅改修プランや見積書を作成してもらいます。
見積もりの段階では、できるだけ複数の業者を見比べることが大切です。
業者を比較することで、適正価格で施工できる信頼できる業者を見つけやすくなるでしょう。
ケアマネージャーへの相談段階でも複数の業者を比較することを進められるのが一般的です。
自治体の窓口で介護保険の住宅改修を事前申請する
必要書類を揃えて自治体の窓口に申請します。
主な必要書類は以下のとおりです。
- 支給申請書
- 改修費の見積書
- 住宅改修が必要な理由書
- 住宅改修後の完成予定の状況が分かる書類
住宅改修が必要な理由書は、ケアマネージャーや介護支援専門員・作業療法士など作成できる人が定められているので注意しましょう。
また、改修後の完成状況が変わる書類とは、日付入りの写真や間取り図などが該当します。
業者に依頼して用意してもらうようにしましょう。
必要書類は申請する自治体によっても異なるので、ケアマネージャーや自治体の窓口に確認することが大切です。
申請後は審査され、問題がなければ着工に進めます。
審査完了まで時間がかかるケースもあるので、工事時期に希望がある場合は余裕をもって申請するようにしましょう。
リフォーム工事の着工~完成
審査に通れば、改修工事の着工です。
改修工事中は適宜プラン通りに工事が進んでいるかをチェックしましょう。
住宅改修費の支給申請~入金
住宅改修費を支給��してもらうには、工事完了後に再度支給申請が必要です。
工事完了後に、以下の必要書類を窓口に提出しましょう。
- 住宅改修に要した費用に関わる領収書
- 工事費内訳
- 住宅改修完成後の状態が確認できる書類
- 住宅所有者の承諾書
申請後問題がなければ1~2ヵ月程で指定の口座に支給分が支払われます。
介護リフォームに介護保険の住宅改修を利用する人のよくある質問
最後に、介護リフォームに介護保険の住宅改修を利用する人のよくある質問をみていきましょう。
介護保険の住宅改修でできることは?
介護保険の住宅改修では、対象者が住む自宅の介護リフォーム費用の一部が介護保険から支給されます。
対象となる工事の種類は、以下の6種類です。
- 手すりの取り付け
- 段差の解消
- 滑り防止及び移動の円滑化などのための床又は通路面の材料の変更
- 引き戸などへの扉の取り替え
- 洋式便器などへの便器の取り替え
- その他上記の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
ただし、工事の種類ごとに細かい条件も定められているのでケアマネージャーに確認するようにしましょう。
介護保険の住宅改修は2回目も給付を受けられる?
住宅改修費は、1人生涯で20万円が上限となります。
回数制限はないため、1回の申請で20万円以下であれば20万円に達するまで複数回申請し支給を受けることは可能です。
しかし、上限20万を超えての申請はできません。
ただし、要介護度が3段階上昇、転居した場合は、20万円まで申請した後��でも再度申請することは可能です。
まとめ
介護リフォームすることで、介護が必要な人・介護する人の負担を減らし住みやすい環境づくりを実現できます。
また、介護リフォームの際には、介護保険の住宅改修費を申請することで自己負担の軽減が見込めます。
ただし、住宅改修費は上限が20万円となり工事の条件もあるので注意しましょう。
介護保険住宅改修費は着工前に申請しなければならないなどいくつかの注意点があるため、まずケアマネージャーに相談することをおすすめします。
介護リフォームの実施を検討されている方は、本記事の内容を参考になさってください。